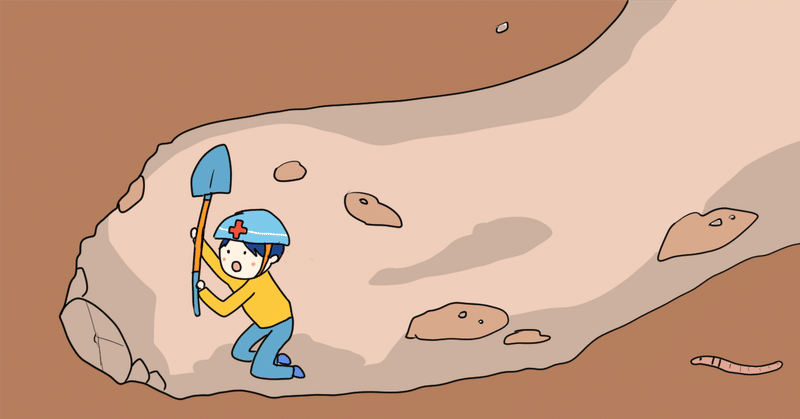
生成AI時代のツルハシとは?
みなさんは、ゴールドラッシュの逸話をご存知だろうか?
ゴールドラッシュとは、狭義では1848年にアメリカ・カリフォルニア州で、新しく金が発見され、金脈を探し当てて一攫千金を狙う者たちが殺到したことを指す言葉である。
さて、ゴールドラッシュについてあまりにも有名すぎる話として、
「一番儲かったのは、金を掘ろうとした人ではなく、その人々に対してツルハシやジーンズ、食事を提供した者である」
というものがある。
これは、日本だと「ツルハシビジネス」と呼ばれており、アメリカだと「Pick-and-Shovel Strategy」などと言われている。
理屈で言えば、非常にシンプルである。
・金を掘り当てれば、大きく儲かるのは誰でもわかるが、万が一掘り当てられなかった場合のリスクが大きい。
・それであれば、金を掘って潤った人に対してビジネスを展開すれば、儲かるのではないか?
と言った形で、伸びているマーケットに対して、低リスクで収益を上げる戦略であると説明できる。
ちなみに、儲かったのはツルハシばかりではなく、
・ジーンズ(リーバイス)
・手押し車
・金や人を運ぶ鉄道(スタンフォード大学創立者)
・金を安全に保管する銀行
なども大きく儲かったと言われている。
また、かつてアメリカで石油王と呼ばれた「ジョン・ロックフェラー」も似たような戦略を採用している。
1859年・ペンシルバニア州で油田が発見されたことを契機として、多くの者が石油を一発掘り当てようと考えて参入した。
この時、ロックフェラーは簡単に同じような参入方針を取ることはなかった。
そもそも、油田を当てられないリスクが非常に高い。
そのため、流通業から着手し、リスクなく収益を得ることに成功した。
また、その後は「精製」に参入し、「油田」を買収し、垂直統合を果たすことで、価格のコントロール権を得た。
ちなみに、このような事象は現代においても、かなり汎用的に言えるのではないかと思う。
・スマホゲームが流行った際にリスク低く儲かったのは、Unityなどのゲーム作成ソフト
・SaaSが流行って儲かったのは、月額決済サービス
・D2Cブームで儲かったのは、広告代理店
・YouTuberブームで儲かったのは、事務所やプラットフォーム
など、共通点を見出すことはそこまで難しくはない。
※もちろん、それでうまくいく人もいるので、あくまで傾向の話として。
序章が長くなったが、考えれば考えるほど、
この事象は「生成AIブーム(トレンド)」にも適用できるように思えてならない。
まず、生成AIを使ってアプリを構築しようとするプレイヤーは、金を掘る人と同様の立ち位置にいると考えて差し支えない。
当てれば大きいが、各社模索しており、変数も非常に多いため、容易ではないと想像できる。ちなみに、私の現状の立ち位置もここにいると客観視している。
では、どういった事業者が儲かるのか考えてみると、パッと思いつくのは下記のようなビジネスである。
・プロンプトの売買サイト
・OpenAIのAPIをラップしたサービス
・バックエンド処理をローコードで実装できるサービス
ただし、もしかしたらこうした領域はすぐにレッドオーシャンになるかもしれない。
そこで「風が吹いたら桶屋が儲かる」的な理論も忘れてはならない。
ゴールドラッシュの際には、副次的に様々なニーズが発生し、次々といろいろなビジネスが潤っていったと考えられる。
一番直接的なのは、ツルハシやスコップだが、ジーンズは意外性があるし、銀行についてもより概念的なニーズを満たしているものである。
こうした、今見えていないけど、実は副次的に広がりそうなビジネスが見つかれば、ブルーオーシャンの中でマーケットを独占していけないかと思っている。
実際に、石油における精製は意外性があり、ブルーオーシャンだったと言われている。
ただ、それを見つけるためにも、一定現場に入ってみないと分からない側面もありそうなので、しばらくは様子を見つつやっていきたいと思っている。
という浅い結論になったが、頑張っていきたい。
※ちなみに、日本だと意外と競合が出てこないなどの要因で、金を掘りに行ってもガンガン当てられる説も否定できない。
※あくまで思考メモであるので、他の人を攻撃する意図はないです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
