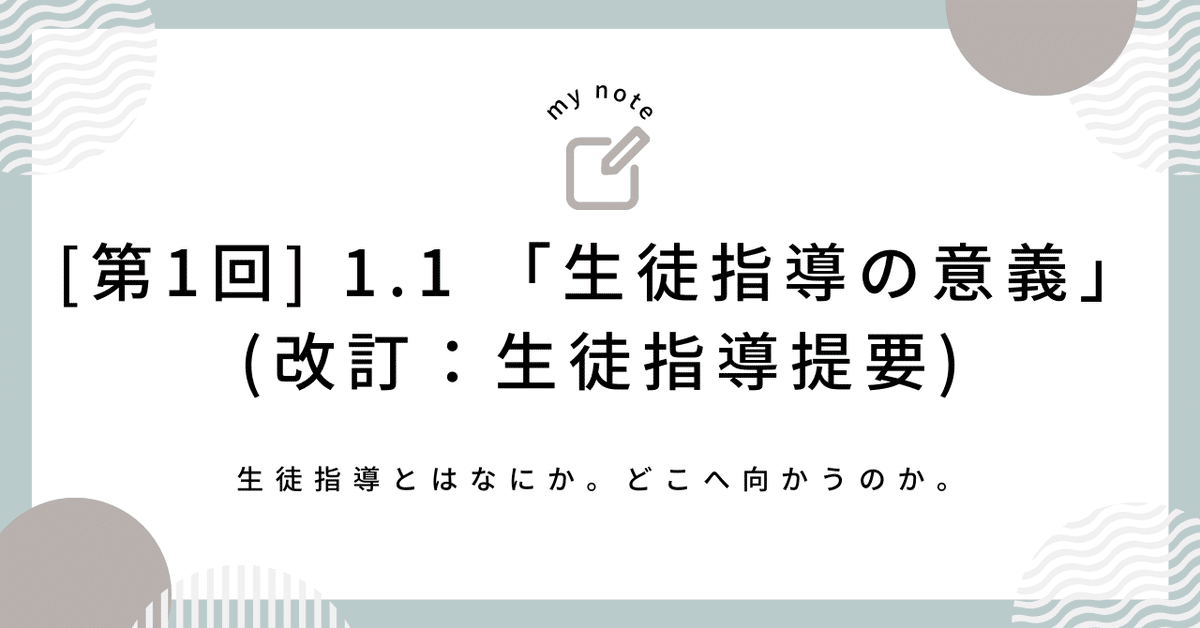
[第1回] 1.1 「生徒指導の意義」(改訂:生徒指導提要)
とぽます、です。
今回から改訂された生徒指導提要を読んでいきます。
改訂された生徒指導提要は大きく分けて、第Ⅰ部(はじめ~第4章)の「生徒指導の基本的な進め方」=総論と、第Ⅱ部(第5章~おわり)の「個別の課題に対する生徒指導」=各論に分かれています。
それでは、第1章1.1節「生徒指導の意義」を読んでいきましょう。
定義等が多く、やや冗長で退屈な文章となっていることを恐れます。(数学屋さんの性でしょうか。)
改訂版:生徒指導提要(R4.12)は、
こちらからダウンロードできます。
また、改訂前の生徒指導提要(H22.3)は、
こちらからダウンロードできます。
注意事項
内容の不確実性
私は、教育の専門家でない、ただの教職志望学生です。そのため、このマガジンに書く生徒指導提要の解釈や考察について、不確実・不正確な内容を含む可能性があります。
そのため、「生徒指導はかくあるべき」ということを言いたいのではなく、「とぽますは生徒指導提要を読んで、こう考えているのだな」と受け取っていただければ幸いです。
(コメントでの指摘・建設的意見はむしろ大変ありがたいです。)引用の禁止
1.の内容に関連して、本マガジンの内容をレポート・論文等に引用することはご遠慮ください。正確性を保証できないためです。
noteの記事を引用してレポート等を書く人はいないと思いますが、wikiコピペレポートなどもあると聞きますので、念のため明記しておきます。
1.1.1「生徒指導の定義と目的」
(1) 「生徒指導の定義」
1.1.1の冒頭では、生徒指導の定義が述べられています。
引用しましょう。
生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。
さて、学校教育の目的は、教育基本法にもあるように、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成(第1条)」を期することです。
目的を踏まえて、再び生徒指導の定義を見てみましょう。
「社会の形成者」を育成していくなかで、もちろんその能力を見極め、伸ばす助けをしていくこと(=学習指導)も大切ですが、社会の中で、自分自身のことについて、自ら決めて、実行する力を伸ばすことも必要です。
ところで、改訂前の生徒指導提要では、生徒指導はどのように定義されていたのでしょうか。引用します。
生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のことです。
社会において「生きる力」を高めることを言ってはいますが、「自発性・主体性」については触れられていませんね。
やはり、「自発・主体」は、学習指導要領にもみられるように、教育のトレンドワードなのでしょう。
*参考:「主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善の視点について(国立教育政策研究所)」
(2) 「生徒指導の目的」
続いて、生徒指導の目的を見ていきましょう。引用します。
生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的とする。
とくに、「発達を支える」ことについて、補足がされています。
生徒指導において発達を支えるとは、児童生徒の心理面(自信・自己肯定感等)の発達のみならず、学習面(興味・関心・学習意欲等)、社会面(人間関係・集団適応等)、進路面(進路意識・将来展望等)、健康面(生活習慣・メンタルヘルス等)の発達を含む包括的なものです。
さて、「生徒指導の目的」には2つの項目がありますね。
一人一人の「個性の発見」「よさや可能性の伸長」「社会的資質・能力」の発達についての総合的支援
「自己の幸福追求」と「社会に受け入れられる自己実現」への支援
どちらも、簡単には達成しうるものではないですし、また担任教員が一人で対応できるものでもなさそうです。
では、この目的の達成のための、重要なファクターは何でしょうか。
生徒指導提要では、「自己指導能力」という単語を挙げています。
自己指導能力とは、字のごとく、児童生徒が、「自分とは」を理解し(自己理解)、「自分は何をしたいのか・何をすべきか」を考え、自らの行動を判断・決定・実行することでしょう。
「自分が自分の師であり、相談者であり、責任者であるような態度が大切だ」ということだと私は考えます。
生徒指導提要では、児童生徒が、学校でのさまざまな場面において、他者との関わり合いや学び合いを経験し、主体的に自らの人生について決定する力をつけていくことを展望しています。
1.1.2「生徒指導の実践上の視点」
1.1.2では、生徒指導を実践するうえで、留意すべき視点について紹介しています。
(1) 「自己存在感の感受」
学校教育は、例えば全日制の普通科高校なら、一クラス当たり約40人のように、集団のなかで展開されます。
すると、児童生徒の中には「自分はone of themだ」と、個性が埋没するような感覚に陥る子が現れるかもしれません。
そういったことが無いように、一人一人に対して、「あなたは一人の人間として尊重されている」という態度で接し、また児童生徒自身がそのことを実感できなければなりません。
能力が高い・低いとは違う、「自分も他人のために役立つことができる。認められている。」というものさしを持つことが大切でしょう。生徒指導提要では、「自己有用感」という言葉が紹介されています。
閑話休題:「褒める」と「認める」の違い
上の「自己有用感」について、生徒指導提要の本文では、参考資料として『「自尊感情」?それとも、「自己有用感」?』というリーフレットが掲載されています。
このリーフレットの末尾に『「褒めること」と「認めること」の違いは?』というコラムがあります。このコラムが気に入ったので紹介しますね。
教職課程の経験がある人は、教科教育法など、いくつかの場面において「生徒を褒めて、やる気を引き出そう」という話を聞いたことがあるでしょう。
私もあります。
しかし、褒める「だけ」でいいのでしょうか?
褒めるということは、すなわち生徒が「教師の考える基準を超えた事実」を必要とします。
例えば、授業中に指名した問題を答えられたときに教員は褒めるでしょうし、テストでクラス上位をとれば保護者から褒められることもあると思います。
ここに、「褒める」ことの危うさがあります。
「基準を超えられない子」は褒められないことになってしまうのです。
授業中に出したどんな簡単な問題にも答えられない子、テストでどの教科も散々な結果となる子は褒められる経験がなくなってしまいます。
そこで「認める」ことの必要性が出てきます。
他者の挑戦を「認める」ことにおいて、その結果の如何は関係ありません。
とんちんかんな答えを言っていようが、的外れな解法を答案に書いていても「挑戦したこと」そのこと自体に価値があると考えるのです。
生徒に、「うまくいったら褒められる」という意識よりも、「どんなチャレンジも認めてもらえる」という意識が生まれるような接し方をしたいと私は思います。
(2) 「共感的な人間関係の育成」
前述した通り、学校教育は集団のなかで進んでいきますが、子どもたちは自らが属する集団を、本質的には選ぶことができません。(受験を経ているのなら進路を選ぶ余地はあったことになりますが、それはあくまでも「どの学校に行くのか」を選ぶだけで、自分の身を置く人間集団は入ってみるまで分からないはずです。)
この、「所属する人間集団の選択不可能性」は社会に出たら当たり前に存在します。職場の人達、引っ越し先のご近所さん…気が合わない人ともどうにかうまくやっていくことは、社会生活を円滑に回していくうえで大切です。
この視点は、学校ではその練習ができる、という見方です。
ただし、学校は(生徒たちにとっては)職場や居住地域ではないですから、目指すところはただの「うまくやっていける集団」ではなく、「学習集団」という性質を有する人間集団であることには注意しておきます。
(1) に関連しますが、「自分という存在が認められている」という実感はとても大切です。(1) では主に教員からの目線でしたが、(2) では学校での生活集団全体からも同じように感じられることが大切だと書かれています。
例えば、授業中に発言して、それが間違っていても笑われたり、馬鹿にされたりしない、そういう雰囲気つくりが大切だということですね。
とくに、課題探求型の授業も増えていくでしょうから、それぞれが意見を持って発表できる空気感は尊いものです。たとえ間違ったことを言っていても、「なぜその答えにたどり着いたのか」をまじめに議論してみるくらいでちょうどいいかもしれません。
(3) 「自己決定の場の提供」
教員やクラスの仲間が受け入れてくれる空気感のみがあっても、意思決定をする機会がなければ、自己指導に関する資質・能力は伸びにくいでしょう。
(3) では、そのような自己決定の場の提供が必要だと述べられています。
この視点については、指導提要本文で、
児童生徒の自己決定の場を広げていくために、学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進めていくことが求められます。
とも述べられており、「自発的・主体的な」授業の充実が求められていると解することができます。
(4) 「安全・安心な風土の醸成」
この視点については、少し注意が必要でしょう。本文では、
児童生徒一人一人が、個性的な存在として尊重され、学級・ホームルームで安全かつ安心して教育を受けられるように配慮する必要があります。
とあり、一見すると「肯定的な雰囲気つくり」だと思われ、(2) と同様のものに思われるかもしれません。
しかし、ここではむしろ「有害な環境の予防・改善」が主体だと考えるべきでしょう。
たとえクラスの大半から認められ、自分を表現する機会があったとしても、いじめや暴力の被害にあっていれば、健全な発達にはつながらないでしょう。
互いの個性を認め合い、安心して学校生活が送れるような風土であることがあたりまえでなければなりません。
(言うまでもなく、教職員による体罰、いじめへの加担・見過ごし、人権意識に欠けた言動は許されません。)
1.1.3「生徒指導の関連性」
1.1.3では、生徒指導とその他の教育活動との関係について述べられています。
具体的には、「キャリア教育」と「教育相談」の2点です。
もちろん、既に触れた通り、生徒指導は学校のあらゆる場面と関わる概念ですから、この2点以外の教育活動とも当然関わってくることは、注意しなければなりません。
(1) 「生徒指導とキャリア教育」
本文ではまず、キャリア教育とは何か、進路指導との包含関係を踏まえながら、説明されています。
生徒指導とキャリア教育は、相互に関わり合うものであり、一体となった取り組みがなされることが大切だと書かれています。
具体的には、いじめ等の課題への対応が書かれています。
児童生徒の反省によってのみでは再発防止力が弱いとされています。その行動が自他の人生にどんな影響を与えるのか想像させること、反省の過程で自己の内面の変化を振り返ることなどが重要です。
たしかに、問題行動をしなくなるだけでは不十分でしょう。
適切な指導と支援の結果、児童生徒が自身の人生を生きていくための成長をしていかなければなりません。
もちろん、いじめ等の被害生徒のケアに期待することも同様です。心のケアをして、安心・安全な環境で学べるようになることはもちろんですが、辛い経験を前向きなエネルギーへと転化できるよう、支えていくことも必要でしょう。
(2) 「生徒指導と教育相談」
一方で、教育相談は生徒指導から独立したものでなく、むしろその中心的役割を担うものだとされています。
本文では、教育相談の様態によって生徒指導との関係が2通りに述べられています。
①個別性・多様性に対応する教育相談
LGBTや発達障害、その他個別の課題など、集団と対象とした一斉の指導ではカバーしきれない事案が多くなってきています。
そこで、生徒と個別または少人数で対することで、個別的な配慮や支援を実施していくための教育相談、という側面があります。
②生徒指導と教育相談が一体となったチーム支援
教育相談は元来、不登校やいじめなどに対して事後の個別対応が重要視されてきたそうです。しかし、生徒指導と教育相談を一体化することで、「未然防止、早期発見・対応、改善、再発防止」を「チーム学校」の考え方のもと、一貫して行う必要があります。
