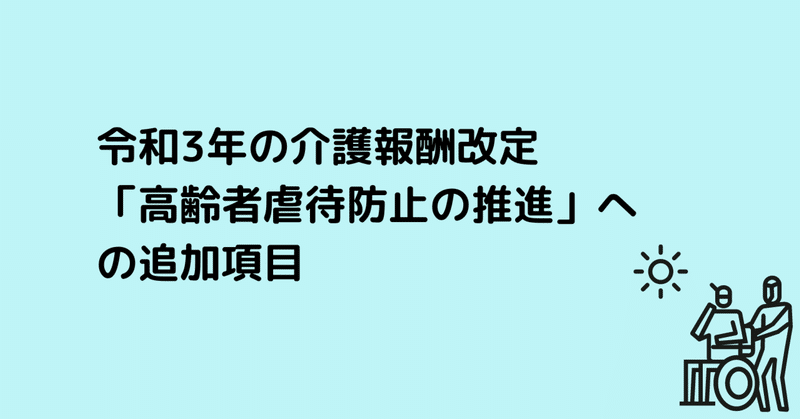
令和3年の介護報酬改定「高齢者虐待防止の推進」への追加項目
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。
私は作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長をしています。
介護施設管理職の仕事とは、職員のマネジメントをしながら研修や訓練を実施し、また基準を満たすよう帳票類を整備すること。
そして「知らなかった」、「忘れていた」では済まされません。
日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、管理職に必要な知識と情報をシェアしていきたいと思います。
今回は、「令和3年の介護報酬改定で高齢者虐待防止の推進への追加項目」について書いていきます。
追加項目

すべての介護サービスについて、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備等を行うことが義務付けられました。
また、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」として、すべての介護サービス事業者が定めておく必要があります。
虐待の発生又はその再発を防止するために、次のとおり必要な措置を講じる必要があります。
【1】虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護従業者に周知徹底を図ること
【2】虐待の防止のための指針を整備していること
【3】虐待の防止のための従業者に対する研修を行っていること
【4】虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置いていること
管理者が行わなければならない虐待防止の取り組み
従来管理者が行わなければならなかった虐待防止の取り組みを確認しておきます。
虐待防止の基本として実施すべきこととして、厚生労働省は「管理者においては、日ごろから事業所職員の状況、職場環境の問題などを把握するとともに、必要に応じ養介護施設などを運営する法人の業務管理責任者に対し、報告などを適切に行う必要がある」としております。
さらに「こうした取り組みが十分でなく、養介護施設従業者などの一人ひとりの努力のみに任せていると職員のストレスが溜まりやすくなり、不適切なケアにつながるなど、高齢者虐待を引き起こす要因となる可能性がある」と示しています。
虐待の発生要因として「教育・知識・介護技術等に関する問題」や「職員のストレスや感情コントロールの問題」が上位に挙がっていることから、今までは研修機会の確保や定期的なメンタルヘルスに配慮した面談などを行う必要がありました。
今回の改定でこれらに加え、上記の事項が加えられた形となります。
高齢者虐待防止法に規定されている事業所・職員の義務
高齢者虐待防止法に定められている介護施設の職員が行うべきことをまとめておきます。
虐待防止のための措置(第20条)
(1)事業所が自ら企画した研修を定期的に実施すること
(2)苦情処理体制が管理者などの責任の下、運用されること
(3)メンタルヘルスに配慮した職員面談などに組織的に対応すること
(4)業務管理体制を常に自主的に点検し、必要に応じ、体制の見直しや運用の改善に努めること
(5)地域住民との交流など、外部に開かれた施設づくり
早期発見(第5条)と通報(第21条)の義務
高齢者虐待防止法第5条には、虐待の早期発見に努め、虐待を発見した場合は速やかに通報しなければならないと規定されています。
研修マニュアルの作成
事業所に合ったマニュアルを作成しておきます。
研修の際、マニュアルに沿って「普段の業務でどんなことが不適切なケアか、虐待につながる可能性があるか」など具体例を示すことで日ごろの業務を振り返ることが大切です。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は「令和3年の介護報酬改定で高齢者虐待防止の推進への追加項目」についてお伝えしました。
介護保険の基準は「知らなかった…」では済まされません。
虚偽・偽装は指定取消しにつながリます。
これを機に、もう一度確認してみてはいかがでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後も、管理職又はリーダーであるあなたにお役立てできる記事を投稿していきますので、スキ・コメント・フォローなどいただけると大変嬉しいです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
