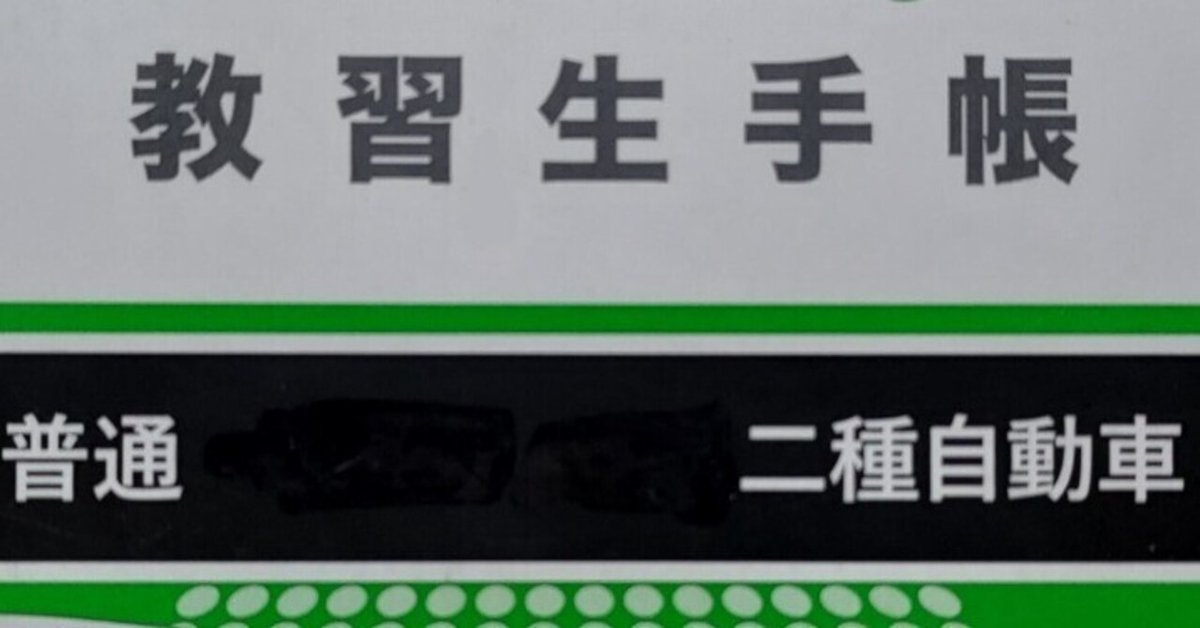
教習所に通っていたお話。普通2種免許取りました。
某タクシー会社から内定、乗務職を選んだ理由とか
長らく職を失っていた私ですが、6月に某タクシー会社から内定を頂きました。
大手転職サイトなどいろいろ利用しましたが、結局ハローワーク経由で応募するという(笑)
職員さんもすごく丁寧でした。失業手当や受給期間延長申請などお世話になりました。
タクシー乗務職を選んだ理由は
運行管理者の勉強や試験を通じて面白そうだと思った。
自動車運転者の改善基準告示の改正(いわゆる2024年問題)の影響が貨物に比べて旅客は少なくなりそうだと感じた。
管理者としてしか仕事をしてこなかったので、乗務職でさらに視野を広げることができそうだと思った。
学歴も職歴も大したことがないのでとりあえず食いっぱぐれのない資格が欲しかった。
などの理由が挙げられます。
資格取得支援制度を使う
とにもかくにも私には普通2種免許はありません。
当然取得してからの乗務となるのですが、内定を頂いたタクシー会社には資格取得支援制度なるものがありまして、自己負担なしで教習所に入所できる神制度があります。
多くのタクシー会社にこの制度があります。それだけタクシー業界に人がいないということなのでしょうが、得体の知れないほぼ4年無職の私に投資できるのは純粋にすごいと思いました。
デメリットは2年以内に退職すると、教習所代金を請求されるところでしょうか。(いわゆる2年縛り)
携帯業界とタクシー業界、どちらがこの制度の元祖なんでしょう(笑)
会社から2つの教習所の入所の提案があり、阪神圏か丹波か提案されました。
どちらも通学に1時間半ほどかかるのですが、阪神圏の某所の教習所にしました。車が多いほうが練習になるかなと思いましてね。
ただ、通勤ラッシュと被るとマジで車が動かなくなって悲惨な目にあいましたが…
教習所入所手続き。深視力とかいう運ゲ
費用面は会社が手配してくれていたのですが、入所前手続きがあるとのことで、6月末に入所手続きに行きました。
普通2種取得希望者がこの数か月すごく多いらしく、入所まで2週間ぐらい待ちました。長い時だと1か月待つこともあるのだとか。
大阪市内の教習所はそもそも入所できないなんてこともあるようです。
入所手続きは現免許証の確認と書類記入ぐらいなものですが、問題は視力検査です。
1種免許は準中型(5t限定除く)以上、2種免許はもれなく全部測られる深視力。
これが初めてやると本当に難しい。三桿法(さんかんほう)と呼ばれる測定方法で、横並びに立っている3本の棒が真ん中の1本だけ前後に動きます。
その真ん中の棒が横並びになったと思うタイミングでボタンを3回押し、平均誤差が2cm以内なら合格…というやつなのですが。
職員さん「真ん中の棒が動いているの見えます?」
私 「これほんまに動いてます???」
15回ぐらいチャレンジさせてもらい、なんとか合格。
ネット上を見てみると結構苦労されている方が多いようで、それも納得の測定でした。
教習スケジュール
教習内容を全部書くと文字数がえらいことになりそうなので、印象に残ったことを書いていきます。
まずスケジュールですが、会社にお任せしてたので過密スケジュールになりました。
1日目 入所式+適正診断+学科5時間+技能2時間
2日目 学科2時間+学科測定+技能3時間
3日目 学科3時間+技能3時間
4日目 学科2時間+技能3時間
5日目 応急救護6時間+技能3時間
6日目 学科測定+技能3時間
7日目 技能2時間+卒業検定
間の土日が休みで計9日間でした。
2種の場合、2段階に入れば技能教習が3時間連続で行えるようで、5日目の応急救護6時間の後の技能3時間合計9時間連続が辛かったです。
通学なのに合宿みたいなスケジュールですね(笑)
同時入所は私合わせて10名でした。もちろん違う会社の人ですが。
1段階 技能教習 MT or AT どっち??
入所手続きの際見落としていたこと…そうです、MTかATか。
実は1種免許はATで取得してから後にAT限定を解除したクチでして、人よりもMT車に乗っていた時間が少ないのです。
バイクはともかく車のMTはとてつもなく不安だったのですが…
問題なく(?)AT限定コースでした。
指導員の方にお聞きすると、現在は2種取得者もほとんどはATだそうです。
MTは代行運転業の方が取得されるだとか。
ともかく半クラエンストの達人にならなくて済んだわけですね。
技能教習は普通に自動車を運転するのですが、1種と違う課題は主に
鋭角
転回
目標停止
の3点です。軽く解説します。
鋭角(左旋回・右旋回)
一度では曲がり切れないコースで、必ず後退を必要とします。
3回まで切り返しがOKで、4回目を切り返した時点でアウトとなります。
卒業検定でも必ず行う課題で、3回目までは減点がありません。
車両感覚を養うために非常によくできている課題だと感じました。
転回
いわゆるUターンです。
車道のみを使ってUターンします。歩道や路側帯に入ってはいけません。
安全確認をしっかりと行うことが重要でそこまで難しい課題ではありません。
目標停止
車体を左に寄せ、左後部ドアを電柱や目印に合わせて停車の措置をする。
ご乗車を想定した課題です。
左後部ばっかり見ているとよそ見として取られるので、前も見ながら合わせる必要があります。
この他に、1種でもありました方向変換または縦列駐車が卒業検定の課題となります。
1時間目から鋭角コースに挑戦して難なくクリア。
しかし別の時間にコンフォートに乗ってやると感覚がおかしくなって4回目切り替えしても通過できないことがありました。
「縁石にぶつかるまで前に進んでみて?」
「な?案外余裕あるやろ?そんなに早く切り返しせんでも大丈夫やで!」
などわかりやすいアドバイスのおかげで、鋭角の苦手意識は多少和らぎました。
空いた時間があれば鋭角の練習もさせてもらいました。
1段階 学科教習
1種所持での学科免除はなく、2種は2種で学科教習を受けなくてはなりません。(全19時間)
1種内容のおさらい、道路交通法のおさらいがメインなので特に印象に残ったことを書いていきます。
身体障害者等への対応
ご乗車される方が身体障害者等であった場合を想定した学科教習。
車いすの方への対応を映像で学習し、視覚障害者の方の対応を実際にアイマスクをして疑似体験する…というものでした。
2人1組になって誘導する側とされる側になって行うのですが、視覚情報を言語で伝えるのはすごく難しい。
3階の教室から1回のロビーまで実際に誘導したりされたりしたのですが、
「ここで90度右に向きます」
「ここに手すりがあるのでつかまってください」(実際に左手を取って)
「一歩先に階段があります。ゆっくり下っていきますよー」
「この段が最後の段です」
着席する段階になって、座面をどうやってお伝えするのか。
実際に手を取って座面を確認してもらう際も、中腰になってしまうので転倒しないかなど非常に注意を払う必要がありました。
改めて普段の視覚情報を言語化して注意を促すのはこれほど大変なのかと実感することができました。
2段階 技能教習
仮免許は必要ないので、1段階のみきわめが終われば即路上です。
基本的な運転と課題
交差点の右左折時の速度、カーブを曲がる際の速度、制動の仕方など、旅客の乗車を想定した運転を指導されました。
あとは1段階で行った、展開と目標停止をひたすら練習します。
時期的なもので路上に草が多く生えており、目標停止が非常にやりにくかったです。
左側30cm以内に寄せて止めなければならないのですが、草に当たれば接触扱いで検定中止だとか。厳しい(笑)
ちなみに卒業検定では目標停止は4回指示されます。うち1回は駐停車禁止場所付近を指定されるので数値はしっかり覚える必要があります。
大型車と自転車が多い地域だったので非常に練習になりました。
所内で指導員に急かされ、先急ぎの危険を理解した運転なんて教習もありました。やはり急ぎの運転は怖いものです。
シミュレーター
なんと3時間もシミュレーターの時間があります。
危険予測、夜間の運転、悪条件下での運転にそれぞれ1時間です。
実際にエンジンの振動は再現されているのですが、制動時のGはもちろんかからない為かすぐに酔ってしまいました。
2人もしくは3人同時教習だったので時間にして15分ほどでしたが、1人だと1時間やるらしい…恐ろしい
ちなみにシミュレーター機は1台1,000万円ほどするのだとか。
コメンタリー
「前方信号青。左右確認よし」
「後方確認。右合図。右後方確認よし」
「横断歩道あり。歩行者あり。停止」
状況を逐一声に出して危険予測、危険回避を行うという教習。
イギリスの警察なんかでも採用されている指導方法だそうです。
普段無意識でやっていることも多く、何を言語化すればいいのかわからなくなります。
声を出すことに意識を取られてしまうので、慣れてきてからでないと効果が薄そうだなと感じました。
2段階 学科教習
応急救護
1段階でもやったあれです。
あなたは救急車を!あなたはAEDを持ってきてください!も実際にやります。
三角巾の使い方を実際に体験したのですが、不器用すぎてなかなかうまくいきませんでした。
止血等さまざまな使い方ができるので、非常に勉強になりました。
実際に使えと言われると不安は残りますが…
胸骨圧迫はなかなかに体力を使うので今の季節だと汗だくになりそうです。
知識としては覚えておきたいものですが、実際にそういった場面に遭遇しない運転を心がけていきたいものです。
卒業検定
100点満点の減点方式で、終了時に2種は80点以上で合格です。
まず所内で課題(鋭角+縦列駐車or方向変換)を行い、路上での検定でした。
経路は全て指示してくれる素敵仕様。
私は3人班で2番手、ただし所内課題は1番最初に行うという謎仕様でした。
所内課題(縦列駐車+右旋回鋭角)
縦列駐車と右旋回鋭角が課題でした。
縦列駐車失敗したことがなかったので難なくクリア。
右旋回の鋭角は左に比べて簡単(運転席側なのでよく見える)なので1回の切り替えしでクリア。
所内で1番手の人と交代しました。
路上課題(転回+目標停止4回)
1番手の人の走行を見ていたので、カンニングしたような気持ちからスタート(笑)
目標停止は
車が汚れそうな草と土が多かったトラックの前
バス停付近(駐停車禁止場所付近)
指示された電柱に右後部ドア合わせ
発着点付近
でした。
バス停の駐停車禁止場所は停留所表示から半径10mです。
乗用車約2台分あけてギリギリで停車する感じです。
半径なので対向車線のバス停の停留所表示も対象です。
片側1車線の場合は対向車線も注意しておく必要があります。
今回は2車線だったので特に意識はしませんでした。
転回も片側2車線だったので、安全確認をしっかり行い切り返しなし。
交通量が比較的少ない時間帯だったので落ち着いてできました。
無事合格!お疲れさまでした。

自分では気になる点が2点ほどあったのですが、特に減点されることもなく合格しました。
教習所で卒業証明書を受け取るのは5回目ですが嬉しいものですね。

明石試験場 深視力と学科試験
卒業の翌日、10年ぶりに訪れた明石試験場。
運転免許申請書に貼る写真がなかったので、試験場内の写真屋さんに撮ってもらい、各種書類の提出と適性検査を受けていざ深視力!!
思いのほかちゃんと三桿棒が動いてるのが見えて拍子抜け。
一発で合格しました、よかったよかった。
学科試験室はやっぱり異様な雰囲気。
高校生の頃、原付学科で一度落ちているのでトラウマになってるだけなのかもしれませんが(笑)
今回はしっかり勉強した、かつ運行管理者試験からそこまで日が空いていないので結構自信をもって挑むことができました。
教習所で頂いた問題集(6回分)と満点様(WEBサイト)で合格点出るまでやりました。
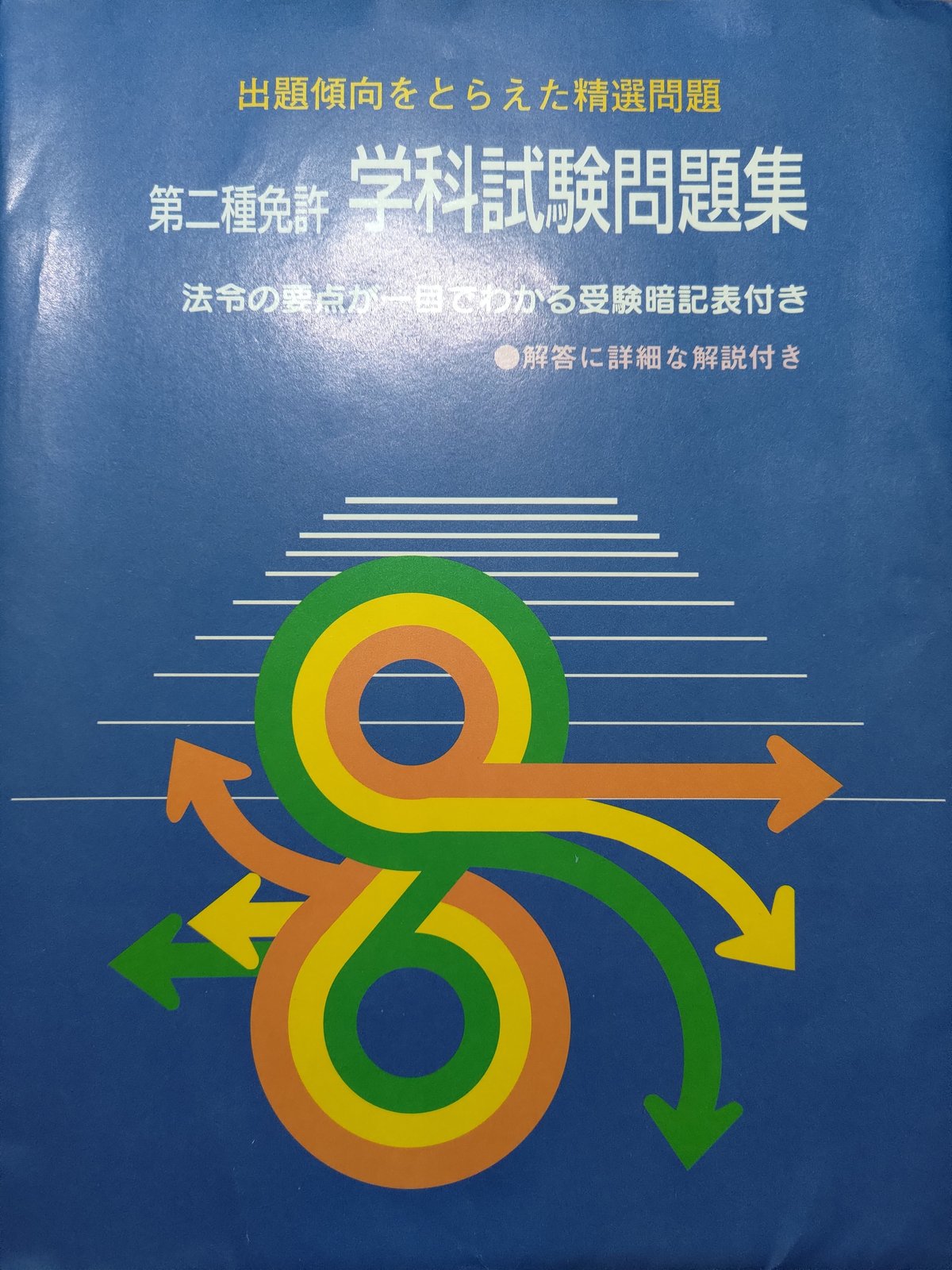
無事免許を手に入れました!!!

ちなみに学科試験は96点でした。
2種教習は自分の運転を見つめなおす良い機会になりました
普段の自分の運転が評価や指導されることがなかったので、非常に良い機会になったのではないかと思います。
改めて車の運転というものは非常に難しく、1tを超える鉄の塊を操作しているとも認識できました。
左の感覚がまだ甘い自覚があるので、これからも運転技術を磨いていく必要があると思いました。
安全第一に乗務員生活、頑張ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
