
松前町立大島小学校だより【2月号】
『言葉の力』(前)
―言葉には創造する力がある―
校長 神 龍 治
〈人生とは言葉そのもの〉〈言葉は自分そのもの〉…読み手を挑発するかのようなこの言葉は、中学3年国語教科書に掲載されている、『言葉の力』の一節です。筆者は、かつて『14歳からの哲学』で話題を呼んだ、池田晶子氏です。
『言葉の力』で池田氏はまず、人間が当たり前に言葉を話すことを、「本当に不思議なことだ」と断言します。なぜなら、

からです。言葉には、人間を超えた何かがあるのです。
次に池田氏は、新約聖書を引用します。

言葉の謎の絶対性を知っていた昔の人が、言葉を「神」と呼んだことを指摘します。そして、
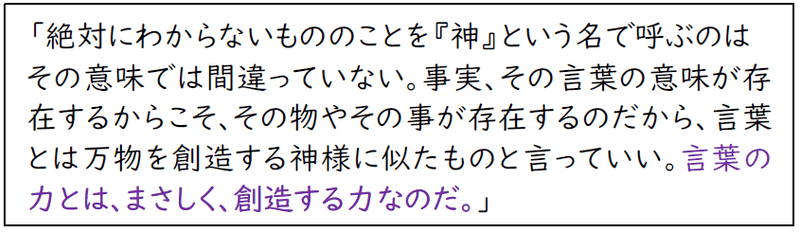
と、一言たりともおろそかにせず述べています。神が〈いる〉とも〈いない〉とも述べません。わからないということからわかること=「言葉の創造力」に読み手を導きます。
人間は、新たに登場したものに、名前を付けてきました。しかし、〈もとからあるもの〉には、ぴったりのふさわしい名前があります。例えば、〈とり〉という音の響きは、鳥のしなやかな流線型を示し、〈bird〉からは、羽ばたくさまが伝わります。〈あ・た・ま〉の〈あ〉母音の連続は、万物の真実が受け止められるよう、世界に開かれているさまを、〈head〉はひらめきを、〈kopf(コップフ)〉(ドイツ語)は、脳をがっちりと守る頭蓋骨の様子をとらえています。いずれも本質を言い当てる言葉です。
〈とり〉や〈あたま〉といった言葉の向こうには、ものごとの本当の姿、〈現像〉があります。〈とり〉と言うだけで、言葉は目の前にいない「鳥」を創造できます。言葉には、創造する力があるのです。それにしても池田氏の、〈言葉は自分そのもの〉とは、一体どういうことなのでしょうか。(来月号に続きます)
◎本校の教育目標
考える子 明るい子 強い子 助け合う子
◎本校のめざす姿
信頼と安心のある学校
◎重点教育目標
基礎的知識や技能を生かし、豊かに表現できる子
昔の話・祇園囃子体験【1月30日(火)】
本校と小島小学校の3・4年生を対象に、CS委員の門脇静男さんと秋本コウさんを講師とした体験授業を、小島小学校で行いました。
秋本さんは、祇園囃子を紹介された後、三味線を演奏してくださいました。また、子どもたち一人一人に寄り添って、楽器を体験できるように指導してくださいました。とくに篠笛は音を出すのが難しく、子どもたちは苦労していましたが、コツをつかんだ子ども同士が教え合う様子が見られました。
門脇さんは、写真をもとに、昔の子どもたちの遊びやくらしについてお話をしてくださいました。「かんじき」など、旧白神小学校で見学した実物なども交えたお話に、子どもたちは興味津々でした。

魚介調理体験【2月6日(火)】
本校3・4年生と小島小学校、松城小学校の4年生を対象に、水産技術指導普及所、松前さくら漁協の方々を講師として、松城小学校で行いました。
最初に「松前の漁業」について、スライドや漁船の模型をもとに、ヤリイカ漁のお話を聞きました。夜に出港し、魚群探知機を操作する様子や漁獲したヤリイカを仕分ける様子などを学びました。
次に、「調理体験」として、漁協女性部の方の指導のもと、子どもたち2人で1杯のヤリイカを捌き、刺身をつくりました。包丁捌きが心配でしたが、親切に教えてくださったおかげで、ケガもなく、上手にできました。
給食と一緒に自分たちで捌いたヤリイカを食べ、満足な表情でした。ご家庭でもお手伝いできることと思います。

◇◇さよなら集会◇◇
2月22日(木)に『さよなら集会』を行いました。
当日、1・ 2年生は、学習発表会での高学年の劇を見事に再演した上でクイズを行い、6年生へのメッセージを贈ってくれました。3~5年生は、トーナメント制で6年生と対決できる手押し相撲を行い、大盛況となりました。
6年生から「挑戦状」として出題されたクイズは高度で、どの学年も回答に苦戦しました。これまでお世話になった方々への感謝の気持ちを伝える発表もありました。
最後に、全校児童で「いすとりゲーム」を行いました。どの学級の発表も充実していて楽しく、卒業生にとっても在校生にとっても、思い出に残る温かな会になりました。

おめでとうございます!
<冬休み作品展の結果>
〈よく調べたで賞〉 4年 斉藤 揚羽さん
〈アイディア賞〉 6年 高橋 悠馬さん
〈ていねい賞〉 3年 上原まるいさん
5年 村本 翔音さん
6年 東舘 望愛さん


本校のいじめ認知事案について
今年度、本校では、いじめ認知事案はありませんでした。これからも小規模校の特性を生かし、子どもたち一人一人のよさを大切にした教育を進めてまいります。学校評価へのご協力もありがとうございました。結果は次号の学校通信にてお知らせいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
