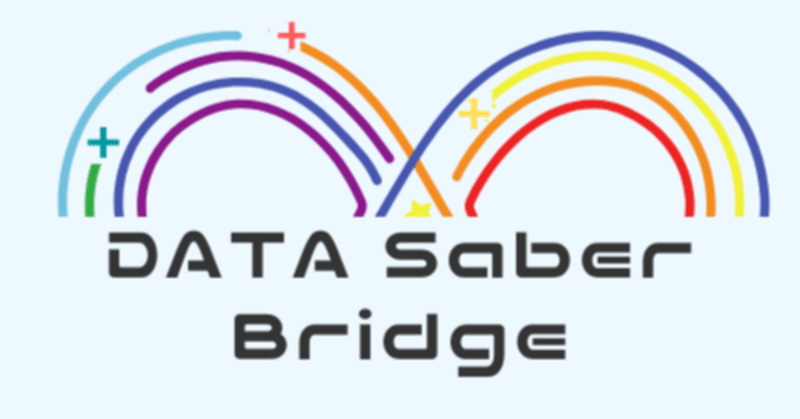
タスクのすり合わせがめちゃくちゃ大事で、これがすぐできる環境は貴重_DATASaberBridge [Ordeal 1-2]
解釈に揺れる
Ord1、2に取り組んでまず思ったのが「この問いの意味はどういうことだろう」「実務ならすぐ擦り合わせにいけるのに」ということ。
Ordで言えば、この問いの前提になっている基準点はどこだろうかとか、この問いの意図することってこれでいいのだろうかとか、そうした逡巡が起こる。
実務に置き換えると、この集計・分析依頼で何を知りたいのだろうか、この依頼の前提になっている仮説はどんなものだろうか(仮説を共有してもらえることが意外と少ない!)という感じで、ただ、これらは直接依頼者に訊きにいけるのでそれほど長くとらわれない。
しかし、実務でハードル低く依頼者とのすり合わせができる環境は貴重なのだとも思う。
物理的なハードル…同じフロアに出社しているとすぐに声をかけにいける(強制的に相手の時間に食い込むことでもあるけど)。
時間的なハードル…メール多用文化だとやりとりにタイムラグが発生するし、その間に刻々と状況が変化しタスクが変容し、ということがありそう。熱量の低下みたいなものもあるかも。
心理的なハードル…これが一番大きいかも。心理的安全性の文脈で言われる対人関係の4つのリスクに関係している。

ディスカッションが推奨される意味
試練では同期Apprenticeとのディスカッションが推奨されている。
これには、同じ課題に取り組む者同士でもさまざまな捉え方があることを実感させるねらいがあるのではないか。
同じSaberを目指す者同士でも認識の違いがある。依頼をする側と受ける側であれば尚更だろう。
解釈の幅を広げ、認識の枠組みを広げ、決めつけず、思い込みで進めない、都度方向と座標を確認して微修正を繰り返していく擦り合わせの作業を怠ってはいけない。という戒めを体感させる仕組みになっている。(と思う)
ということで、なんとか心理的なハードルを乗り越えてBridgeコミュニティでもディスカッションの機会を広げていきたい。
引用した本
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
