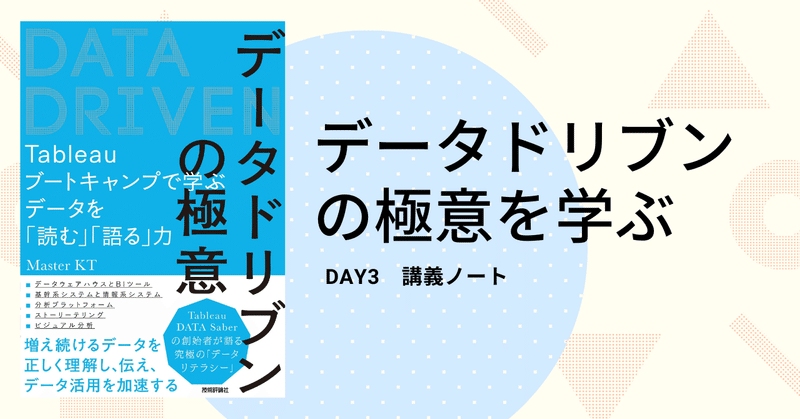
『データドリブンの極意』DAY3_講義ノート
分析プラットフォーム
データドリブン文化を組織に浸透させていくには、共有の分析プラットフォームを整える必要がある。
分析プラットフォームは、これを土台としてすべての人とデータを乗せるのが理想だ。そこで重要になるのがデータソースの信頼性だ。
最新のデータか? あるいは、いつの時点のデータか明示されているか?
正しい値が入っているか? あるいは、値の定義が合意されたものか?
最新か? あるいはいつのデータか
当然だが、データがいつまで経っても更新されていなければ、それを見る人はいなくなる。それどころか「必要な時に、その時点での最新データにこそ価値がある」場合にそれを得られなければ、データを見る動機は劇的に低下する。
たとえば、9時の朝礼で前日の実績を共有したいのに、データ更新が10時だったら、朝礼の時点で公式には二日前のデータが最新となる。これでは打つ手が変わってくる。
こうした事情があるから、自前の集計作業が現場仕事として定着し、Shadow ITを育てることとなる。
正しいか? あるいは合意されているか
値の正しさという観点では、指標として日々見る数値が組織全体で合意されているものなのかという点は重要だ。
KPI項目と実績数値の算出定義が定まっており、同一業務で統一されていることが理想だ。しかし社会の変化の激しい時に迅速な経営判断のもとで運用の変更が先立つこともありうる。大きな組織のこうした方針変更を受けて、下部の小さな組織で追うべき指標の設定がぐらつくこともあるだろう。
また個別の部署、チームに最適化して指標設定しようとすると、必要なデータを取るために大きな労力がかかることが想定される。
こうした難しさを乗り越えなければならない。
Tableau Serverの真価は信頼感を醸成するところ
ExcelであろうとTableauであろうと、確かなデータを出せる者が常に最新を、とファイルのコピーを都度共有していく方法にはいくつもの弊害がある。
・手元にあるファイルが最新とは限らない。
Tableauであれば、やはりTableau Serverを利用し更新を自動化していくことが答えになるだろう。
カスタムビューやアラートなど、ユーザーの労力を極力無くしていくための機能が備わっているところは、空いたメモリを思考や発想に振り向けるというデータドリブン文化の基本姿勢にかなっている。
・手元で加工したものが全体に共有・反映されない。
例えば、コピーされ手元で加工・分析されたものは、時には部門や部署に共有され、組織内の限られた場所での公式データとして使われることもある。その結果、ある部門ではコスト削減に非常に効果がある施策が、別の部門では特定のステーホルダーに過度な負担を強いるものとなっているといったことが起こりうる。全体感(全体観)を見失い個別最適に陥ってしまう危険を助長することにもなる。
Tableau Serverで、そこにあるものが最新で正しいデータであるという、データに対する信頼が浸透すれば、人と対する時に相手がどのようなデータをもとに現状を認識し発言しているのかという土台への疑念を持たずに済む。
このことは非常に重要で、相手が立っている土台を見定める必要があるのか、土台は共通として信頼できている上で、相手の価値観や判断軸に注意を向けることから始めれば良いのかでは大きな違いがある。
相手が立っている土台を信頼できないと、相手の言動を信頼できない。
相手が立っている土台への信頼、自分と同じ土台に立っているという信頼、この信頼のもとでこそ、本質的な議論が進められると思う。
だから、信頼できる土台が提供するのはその上に立つ人と人との信頼感だと思うのだ。
データを整えること
データはわかるように見せたら人を動かすことができる
一度見たデータはその後もずっと同じ、あるいはより高いクオリティで見続けたいという要求が出てくる
「わかるように見せる」ことは、データドリブン文化を浸透させる上で最低限必要なことで、DAY1もDAY2もこのことのために語られてきたものだ。
DAY2が「このように見せる」を扱っていたとすれば、DAY3では「何を(どんなデータを)見せるべきか」が語られている。
それは見せる価値があるデータなのか…。人の行動の土台となるにふさわしい確かなデータなのか…。鮮度を保つための労力が、得られるものに見合っているか…。
このような問いを思うと、次の記述の重みがより鮮明になる。
「この内容が有用であることは間違いないが、毎回目視で見て集計・メンテナンスする時間ほどの価値は、ここから得られるインサイトにはないと思う」と助言があり、そこで初めて、データをメンテナンスすることそのものにこだわっていた自分に気づいたのです。
ここは結構な感動ポイントだったりする。
自分の役割が何なのか
分析プラットフォームに乗っている人々の3つの役割が次のように整理されている。
・クリエイター=データ準備・初期分析設計者
・エクスプローラー=ダッシュボード作成者・データ探索者
・ビューアー=閲覧者・実行者(クリエイターとエクスプローラ以外のすべての人)
そしてマスターは、「データドリブン文化醸成においてこのビューアーがどういう振る舞いをするかが最も重要であると考えています」という。
ビューアーは「最低限データを見て理解できる能力が必要であり、何よりその理解した結果を使って新しいビジネスを生み出していく実行力が大きく求められる役割」だからだ(275)。
自分自身の役割を振り返れば、ビューアーが見てわかる、行動の基礎となるデータを見せること、となる。それにはやはりTaskを共有し、Actを把握することが必要だ。データを取得する部分が非常に重く、それ以外のことにまで目を向けられなかったりしているけれど、それではいけない。

DAY3には「常に思考のよりどころである文化」(230)という表現があり、これはデータドリブン文化を組織に浸透させると言った時の「文化」というもののイメージをはっきり示していると感じる。
文化は思考のよりどころ。
文化をデータドリブンにしていくことは思考のよりどころが変化していくこと。
思考のよりどころが変わると行動も変わる。
19世紀フランスの哲学者・ラヴェッソンは、「獲得された習慣とは一つの変化の結果として生じた習慣である」(『習慣論』p.7)という。そして生物は恒常的で変わらないことと変化することを同時に求めるものであると。
組織という人工物の中で、しかし生物として生き、振る舞う私たちには変化を求めることが本能として備わっているという言葉は、勇気の源泉とならないだろうか。
引用した本など
・自分宛のメモ
生物としての習慣と組織についてはもっと深めて考えたい。
信頼について、複雑性の縮減(ルーマン)という観点からも考えたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
