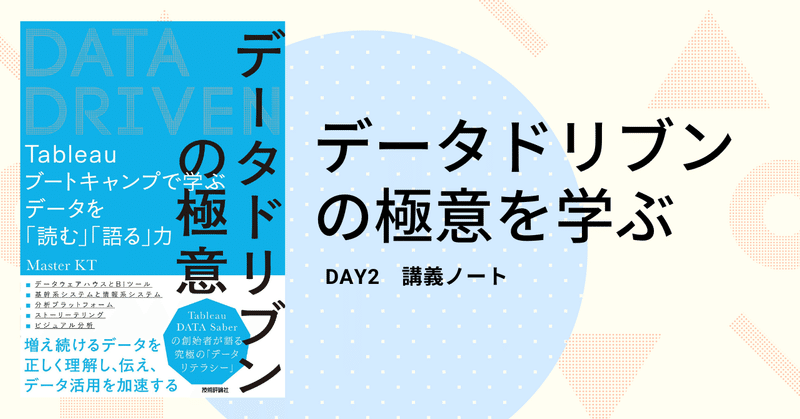
『データドリブンの極意』DAY2_講義ノート
かんたんに目的を果たせること
タスク(お題)とビジュアルの効果が完璧に一致していることで、私たちは目的を果たしやすくなります。
データをビジュアル化する理由がこれだ。
ビジュアル化されていなくても目的は果たせるだろう。
ただビジュアルの力をうまく使えば、より少ない労力で目的を果たすことができる。
この「より少ない労力で」ということが、時間をはじめとする資源が有限な世界では非常に重要な意味を持つ。
(そしてTableauをはじめとするツールはビジュアル化自体もより少ない労力で行うことができる、ということ)
ビジュアル化の目的とビジュアル分析のサイクル
そもそも、データをビジュアル化する目的は何だったか。
それは会社や部署が存在意義を全うしたり、成果を上げることだ。
それこそがTaskなのであり、データのビジュアル化はそのTaskを完遂していくために有効な手法ということだ。

この図はYouTubeでも詳しく説明されている。
思考のフローを邪魔するものを徹底的に排除する
では、より少ない労力で目的を果たしやすくするために、具体的に注意すべきことは何か。

形状に目を向けると、赤い円と青い円、赤い四角形と青い四角形がどちらも存在しています。結局、形状ごとのパターンを見つけられないので、イライラ度が増します。このイライラの感情は、思考のフローを遮断してしまいます。色相しか見ていないのであれば、余計な思考を誘発する形状を削除するべきです。
人の脳の特性と限界を知り、理解には極力負担をかけず、WhyやHowを考えることに最大限の時間と労力をとっておくこと。
つまり「覚えなくていいものを覚えさせないことによって脳の力を思索に振り向ける、これが重要」(221)。
この、思考のためのリソース確保を徹底的に行うから、Preattentive Attributeとデータタイプの相性やTableau上での表現技術を学んでおいた方が良いのだ。

メモリは大切に使っていきたい。
色覚多様性について
ここに言及されていたのは驚いた。
一般的にデザインの勉強をしていくと触れられるものなのかもしれないが、「赤と緑の識別がしづらい」当事者として、なんだか嬉しくなった。
厳密にはオレンジと黄緑が単独であると同定しづらい。二つが隣接していればどちらがオレンジでどちらが黄緑か識別はできる。
「それ取って、そこの…オレンジの…」
「は?」
てことがたまにある。
会社の同僚にも色の識別がしづらい人がいて、部内で展開される資料で色味が悪かったりすると毒づいていた。
作っている側からすると、「見やすいから」「綺麗だから」「この色好きだから」なので、決して悪気があるわけではないのだ。
ダッシュボードの2つのタイプ
これまでのHOMEWORKでオープンデータを使ってきたが、自分が何をやりたいのか、どうにもしっくり来なかった。
以下の2つは、改めて頭の中と表現したいことの整理に役立った。
● 探索型:現状を伝えて相手に考えさせるダッシュボード
● 説明型:現状を伝えるビジュアルに自分の意見を載せて伝えるダッシュボード
会社の業務では進捗管理のために作るものがほとんどであるため、探索型のビジュアル表現を身につけていくべきだ。
個人的に関心のある社会課題へのアプローチでは説明型がメインになるだろう。
さらに対象者が誰なのか(誰に見せる/見てほしいのか)、見た人にどう使ってほしいのかをイメージしながら作っていく必要がある。
ここを意識しながら、具体的な技術を身につけていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
