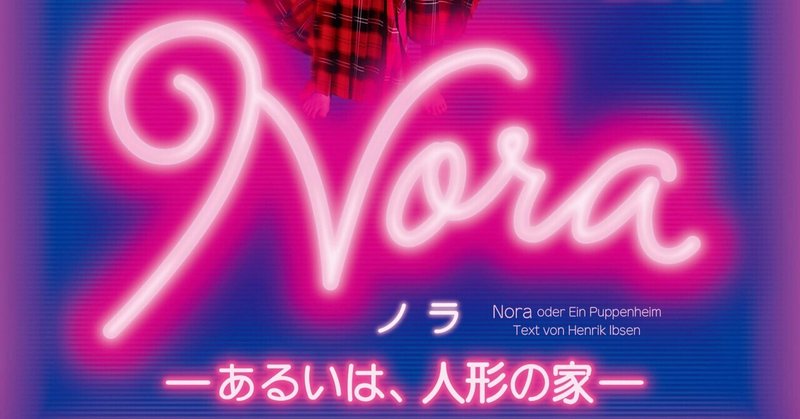
『ノラ-あるいは、人形の家-』のすすめ
深作組ドイツ・ヒロイン三部作第一弾!
〈近代演劇の父〉と称されるイプセン(Henrik Johan Ibsen, 1828 - 1906)の代表作『人形の家』が拙訳にて上演されます。原文は当然ノルウェー語ですから、当時の翻訳家マリー・フォン・ボルヒのドイツ語訳を通して新しく翻訳しました。今回の上演では、演出深作健太さんの意図により、舞台が19世紀末のノルウェーから現代のベルリンに移されています。過去6作と同様、テキレジ、構成、改訂は、全訳後に深作さんと共に進めました。キャストが決定してから、また稽古が進む中で変えた言葉も多々あります。この上演のためだけの言葉を楽しんでいただけたなら幸いです。
ノルウェー語の原題は Et dukkehjem で、直訳するならば「人形家庭」となるそうです。ドイツでは翻訳初版ランゲ訳のタイトルが Nora oder ein Puppenheim だったため、『ノラ、あるいは人形の家』で定着しているようです。わたしが今回底本とした〈イプセンのお墨付き〉であるボルヒ訳のタイトルは Ein Puppenheimとなっています。


注)以下、作品内容を含みます。
あらすじ
ノラとトルヴァルは結婚8年目の夫婦。一人娘エミーの世話や家事の多くを、家事代行サービスの派遣であるヘレーネに任せ、ベルリンの中心部で豊かな暮らしをしている。年明けからトルヴァルの銀行頭取就任が決まっていることもあり、一家は明るいクリスマス・シーズンを迎えていた。
そんな2023年12月24日、ノラがクリスマスの買い物から帰ってくる。ノラは、結婚して以来初めての節約しなくても良いクリスマスなんだと喜び、買ってきたものを広げてみせる。トルヴァルはいつも年下の妻ノラを嗜めつつ可愛がっているが、ペットや人形のように扱うばかりで彼女の話を真剣に取り合わない。そこにノラの旧友クリスティーネが訪ねてくる。10年ぶりに再会した二人は、その間に起こったことを披露しあう。苦労続きだったクリスティーネは、ついに決心し、今朝の電車でベルリンへ出てきたと言うのだ。一方ノラも、かつてある重大な決心をしていた。ずっと隠してきた〈秘密〉とは――
中心となるノラを担うのは、ご一緒するのが三度目となる信頼と期待の夏川椎菜さん。『ノラ』は今までに夏川さんが主演してくださった『オルレアンの少女』や『未婚の女』とは趣が大きく異なり、
・クリスマス前後の3日間
・ほぼヘルメル家のリビングルーム
・独白ほぼ無し
と、非常にオーソドックスな構造の会話劇です。タイトルが個人名であるのも、注目すべき点です。
登場人物たちの愛と思惑が絡み合い、145年前の初演時には一大センセーションを巻き起こした、ある結末を迎えます。
『人形の家』執筆までのイプセンのあゆみ
1828年、ノルウェーの港湾都市シーエンでイプセン誕生。父親は評判の成功した商人。両親、兄弟姉妹、使用人達とともに立派な家に住んでいた。
1835年、父親の商売が傾き、破産。社会的地位が下がるという経験が、イプセンの創作に影響を与えた。
1850年、48年のフランス二月革命に影響を受けた詩と風刺文学を執筆、『カテリーナ』の私家版を出版。現在のオスロに移住。この頃ノルウェーでも革命の気運が高まっており、イプセンも関わり始める。「普通選挙」「法の下の平等」などを求めた。
1951年、政治活動のため逮捕されそうになるが、すんでの所で逃れる。パウル・ボッテン=ハンセンの知的活動グループの会員になる。以降、執筆活動に勤しむ。
1852年、奨学金を得ると、演劇都市コペンハーゲンとドレスデンを訪ねる。リアリズム演劇を学ぶ。
1857年、芸術監督としてオスロの劇場に就任。
1858年、スザンナ・トレセンと結婚。
1862年秋、芸術監督を務めるオスロの劇場が破産。『愛の悲劇』が酷評される。
1863年、ノルウェー議会で奨学金が認可、家族揃ってのイタリア行きが決定。
1864年4月より1891年まで、イタリアとドイツに滞在。
1868年より7年間ドレスデン居住。
1870年-71年冬、ドレスデンで女権拡大活動家Camilla Collett カミラ・コレット(1854/55に小説『郡長の娘たち』出版。ノルウェーで初めて女性の地位について議論が生まれた)と知り合う。イプセンの妻も友人になる。
1875年、ミュンヘン居住。
1877年、ノルウェーのウプサラへ移り住む。
1878年、ローマ滞在。10月よりアマルフィで『人形の家』執筆開始。
1879年8月、『人形の家』完成。その後ウプサラに定住。
1879年12月4日、『人形の家』出版。12月21日、ストックホルム王立劇場で初演。
1880年2月6日、『人形の家』結末改訂版がフレンスブルクでドイツ初演。
各国初演
1879年12月21日、コペンハーゲンの王立劇場で初演。
1880年2月6日、フレンスブルクで結末改訂版のドイツ初演。
3月、ミュンヘンでオリジナル結末のドイツ初演。
1911年9月22日~24日、文芸協会演劇研究所試演場、坪内逍遥訳、第二幕省略
11月28日~12月5日、帝国劇場、島村抱月訳、全三幕上演
ドイツでの受容
1879年、『人形の家』戯曲がノルウェーと同じ時期に初版3,000部出版。翻訳家のヴィルヘルム・ランゲによって、タイトルが『ノラ、あるいは人形の家』に、登場人物の名前がドイツ風に変更されていた。また結末も、初演の女優へドヴィグ・ニーマン-ラーべの意向に添い、イプセンが書き直したものだった(レクラム国際図書)。続く第二版が6,000部。その後1880-90年の10年間で53,000部を発行。毎年のように売上が伸びていった。
1880年2月6日にフレンスブルクで結末改訂版が初演されると、そのままキール、ノイミュンスターでもこの結末での上演が続く。ベルリン・レジデンツテアター初演も同じく改訂版であった。1880年3月ミュンヘン・レジデンツテアター、遂にオリジナルの結末がドイツで初演されると、新聞などで盛んに議論が行われた。「〈ノラ問題〉には協調も妥協もない!」や「観客はこの作品に熱く味方し、ミュンヘンでは演劇作品に対してこれほど生き生きと議論が盛り上がったことは未だかつてない」などと、ドイツ中で激論が交わされた。
レクラム文庫(日本の岩波文庫はレクラムを参考に創刊)から中高生のための副読本 Lektürschlüssel XL Henrik Ibsen Nora (Ein Puppenheim)が出版されているように、ドイツにおいては今でも基礎教養的な作品である。
劇場でお会いしましょう!
わたしがこんなにも深く長くドイツ語圏演劇と関わることになったきっかけの一つが、2005年の夏、ベルリン・シャウビューネ来日公演で観たトーマス・オスターマイアー演出の『ノラ』と『火の顔』でした。この上演でも演出の意向により舞台が同時期のベルリンに移し替えられ、「ノラが夫を撃ち殺し家を出るが、家の外壁でへたり込み、呆然とする」という結末に変更されていました。演劇を専攻し始めた一年目に観た上演ということもあり、わたしの心に深く刻まれています。
また、2024年3月にベルリンで観劇した『人形の家』の改作『Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert』は、この家で働く者たちの視点から作品を問い直し、階級や貧富の差を考えさせるものでした。例えば冒頭で二言のみ発する配達人を、若者ではなく老齢の男性が演じており、年金減額、受給年齢引き上げを連想させます。配達人は「たった二言、数ユーロの仕事のために、俺はカーテンコールまで残るべきか?」と毒づくのです。また乳母のアンネ-マリーは「ドイツ初演では、ノラを演じる女優が〈子どもを捨てる母親はいない〉と結末を変えさせた。ノラの結末については145年間ずっと検討されてきた。でもわたしは? 貧困を抜け出す為、小さいノラの世話をすることに決めたわたしは、自分の子どもを諦めなければならなかった。彼女は今わたしの上司で、その子どもたちのお世話をしている。子どもを捨てる母親はいない、だって?ふざけるな!この145年間、乳母の人生は問題にさえならなかった」と怒りをあらわにします。
145年経ち法整備は進んだものの、個々の身体的精神的環境的な差異を是正するには至らず、システムや先入観が必ずしも刷新されたとはいえず、大くの問題をはらんだまま共同親権が可決された今の日本。そんな今を生きる皆さんには、ノラの考えや行動が〈軽率〉で〈バカ〉に見えるでしょうか?トルヴァルやランクの〈ハラスメント〉をどう感じるでしょうか?エミーの気持ちは?ヘレーネとノラの違いは?ランクはこの家族にとってどんな存在だと感じる?クリスティーネは、クログスタは、このあと?それぞれの愛の実践とは?
わたし自身、オスターマイアー演出の『ノラ』を観た時、翻訳戯曲を初めて読んだ時、ボルヒ訳のドイツ語で戯曲を読んだ時、稽古が始まってから……常に読み方が変わっています。みなさんも観劇しながら、観劇後に、一人で、みんなで、たくさん考えて、激論を交わしてください。
わたし達のための新しい『ノラ』を、青山・銕仙会能楽研修所、水戸芸術館ACM劇場の特設能舞台にて、皆様と共に体感できる日を楽しみにしております。ぜひ、観にいらしてください!
ぴあ
https://l-tike.com/play/mevent/?mid=716919
ローソンチケット
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2409897
e+
参考資料
・Lektürschlüssel XL Henrik Ibsen Nora (Ein Puppenheim) , 2022,Philipp Reclam jun. Verlag GmbH.
・『新訳版 愛するということ』(エーリッヒ・フロム、鈴木晶訳、紀伊國屋書店)
・『男性学基本論文集』(編・平山亮, 佐藤文香, 兼子歩, 訳・海妻径子, 本山央子, 下地ローレンス吉孝, 濱田すみれ, 比嘉麻里, 竹田安裕子, 高内悠貴, 鹿野美枝, 勁草書房)
・『マスキュリニティーズ -男性性の社会学-』(レイウィン・コンネル, 伊藤公雄訳, 新曜社)
・『男が男を解放するために -非モテの品格 大増補・改訂版- 』(杉田俊介, ele-king books)
・『近代家族とフェミニズム【増補新版】』(落合恵美子, 勁草書房)
・『わたしたちは無痛恋愛がしたい』(瀧波ユカリ、講談社)
・『ウーマン・イン・バトル -自由・平等・シスターフッド!-』(マルタ・プレーン著, イェニー・ヨルダン絵, 枇谷玲子訳)
・『悲劇喜劇2023年11月号』(早川書房)
・『物語 北欧の歴史 -モデル国家の生成-』(武田龍夫, 中公新書)
・『人形の家批評』(『青鞜』1912年1月号)
・『人形の家論(序)』(毛利三彌)
・『人形の家 再考』(土屋康範)
・『人形の家 解説』(島村抱月)
・『人形の家』(イプセン, 矢崎源九郎訳, 新潮社)
・『人形の家』(ヘンリック・イプセン, 毛利三彌訳, 論創社)
・『北欧演劇論 -ホルベア、イプセン、ストリンドベリ、そして現代-』(毛利三彌, 東海大学出版会)
・『イプセンの劇的否定性-前期作品の研究-』(毛利三彌, 白鳳社)
ドイツで観られるお芝居の本数が増えたり、資料を購入し易くなったり、作業をしに行くカフェでコーヒーをお代わりできたりします!
