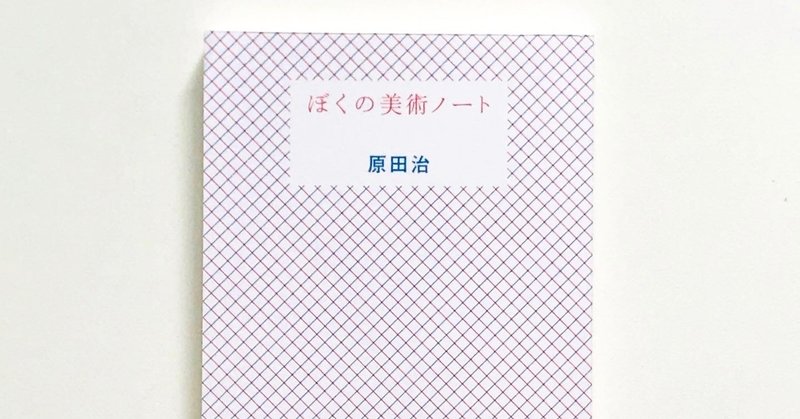
原田治「ぼくの美術ノート」
原田治の『ぼくの美術帖』を何度か読み返した後、その続編として亡くなられた後に出版された『ぼくの美術ノート』を読み終えた。芸術新潮の連載をまとめたものなので、美術帖の時よりもそれぞれ短めだし文章も柔らかだ。それでもどの項目も面白く、原田さんが好きなものに対しての愛が感じられるのは前書と同じである。
川端実のコラージュ作品、ビル・オーウェンスの『サバービア』、島根の船木さんのスリップウェアなどに関して自身の体験を通して書かれているが、この本の一番最後に「犬を負う子供たち」と題した林忠彦が撮った戦争で孤児となった兄弟と犬の写真でこう結んでいる。そしてこれが生前最後となるものだったのが少し物悲しい。
ぼくがこの写真に、強く惹かれるもうひとつの理由は、ぼく自身が、この昭和二十一年の生まれであるからだと思います。記憶もなく、想像することもできない時代であるはずなのに、一実の写真が、生々しくその時代の空気をリアルに掌握させてくれる。《犬を負う子供たち》と同じ空の下に、確かに生まれたばかりの自分が存在していたのだと。
林忠彦は、撮影時に、犬と食べ物を分かち合っていた少年たちを見て、「将来に希望をつないだ」と語っていたそうです。現代かどんなにひどくても、戦争の時代に比べたら良い時代だと、この写真は教えてくれているような気がします。
・
そして、以下はこの本の前書きから
三十四年間の拙著『ぼくの美術帖』(PARCO 出版)には、その扉に詩人・北園克衛のこの言葉を引用しました。そしていつか知らず、ぼくの座右の銘となっていました。
・
「美」とは本来無価値なものである
風景や空の雲が無価値であるというような意味において
「美術」は、ぼくにとって永年の友であり、見上げる目標であり、自然と身についた習世のようでもあります。空気のように美術を呼吸していたので、アカデミックな芸術論やクリティック、相場価格にも、およそ興味を惹かれることがありませんでした。世俗を離れたところでストレートに「美」と対峙することが好きなのは、これは単に性分というものかもしれません。青空の下、行雲を眺めるように、ひとり「美術」を楽しみなから歳をかさねてきました。
