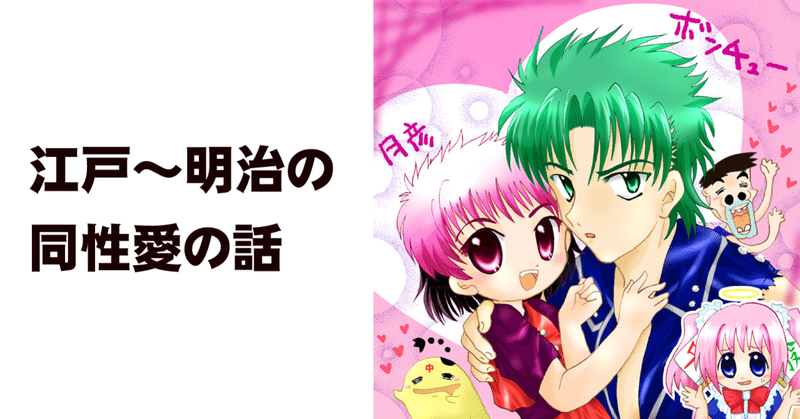
江戸~明治の同性愛の話
4/23~4/30まで毎日更新中……なのですが、大変申し訳ございません。
もろもろの事情により、本日も過去に雑誌に書いた記事の再掲載となってしまいました。
明日以降は、基本的に新規記事で更新したいです。(別に、新規記事の方が再掲載より質が良いわけでもないのですけど)
以下は、2002年10月の『二次元ドリームマガジン』vol.7に書いた文章の再掲載となります。
こういう話、なんていうか、あんましオリジナリティもなくて、内容も色々と微妙なのですけど、おおむねそのまま再掲載させていただきます。
元が10月の記事なので、書き出しが秋になっています。
前置き
菊薫る秋、展覧会などにも自然と足を運んでみたくなる季節です。
と、適当な文例集から丸写しの書き出しで雑誌の品位を上げてみようと画策したのですが……。
この『二次元ドリームマガジン』を読まれる方ともなれば、「菊薫る」と聞くと、自然にケツの穴の匂いが連想されることと思います。
さて、古代ギリシアの哲学者・プラトンによると、人間はもともと「頭が2つ、手足が4本ずつで、回転して移動する生き物」で、ゼウスの怒りに触れて2つに割られたのだそうです。
そして、その失われた半身を求めるのが恋愛なのだとかで……。
てことは、二次元にお嫁さんを求める人は、昔は「半身は三次元、半身は二次元で、回転して移動する生き物」だったのでしょうか。
とにかく、プラトンによると、なんか回転していた時代に男と男がくっついた生き物だった人が、現在の同性愛者なのだそうです。
そんなこんなで、今日は同性愛についてのお話をしてみます。
江戸時代
井原西鶴の小説に『男色大鏡』があります。
その中で、
「若道のふかき事、倭漢にその類友あり」
(男色の歴史は長く広く、日本と中国にその同類が多い)
として、中国の衛の霊公、漢の高祖、武帝など、歴史に名を残した男好きの皆さんの名前が列挙されています。
日本からは、在原業平のエピソードを紹介。
「元来は美少年好きであったのに、世間で陰陽の神などと言われるのは、さぞ草葉の陰で悔しがっていることであろう」
などと西鶴が同情していました。
「玉章は鱸に通はす」
『男色大鏡』は、ざっくりいうと江戸時代のゲイ小説です。
数十個のエピソードが紹介され、なんとなく当時の同性愛概念が感じられます。
たとえば、『男色大鏡』のエピソードの1つ「玉章は鱸に通はす」は、次のようなお話でした。
出雲大社の神々に噂されるほど美しい、甚之介という少年がいました。
甚之介が13歳になった頃。
ある28歳の侍が甚之介にあこがれて、鱸の口の中に忍ばせてラブレターを送ります。
そうして、甚之介が16歳になるまで、2人の交際は誰にも知られずに続きました。
しかし、その3年の交際のあいだ、
「会いに行った帰りに見送ってくれない」
「袴の後ろに土がついているのに教えてくれなかった」
など、甚之介の恨みはつもっていました。
そんなとき、もう1人、別の侍が甚之介に恋をして、三角関係になります。
それから、現代人の私たちにはよく分からない武士ならではの思考が色々あって、3人とその取り巻きで、切腹覚悟の果し合いをします。
その後、甚之介も切腹しようとしますが、喧嘩の経緯をお上に説明したところ、その行為が武士らしかったということで許されました。
そして、彼ら同性愛者たちの立派な振る舞いが有名になり、国中の者が同性愛を大事にするようになったそうです。

諸人の言の葉にかかりぬ。
よき事を見習い、国中の武士たる人の子はさもあるべし。秤なやむ町人の倅子、竜骨車にたよる里童子、塩焼く浜の黒太郎までも、形こそその所作にいやしけれ、この道に一命をしまず。
念友のなき前髪は、縁夫もたぬ女のごとく思はれて、時のすがたとて恋は闇、若道は昼になりぬ。
【訳】
このことが人々の噂になりました。
これを手本にして、国中の侍の子はもちろん、町人や百姓の息子、塩を焼く浜の黒太郎まで、見た目や動作は卑しくても、同性愛に命を惜しまないようになりました。
年上のカレのいない若者は夫をもたない女のように思われ、時勢とはいいながら、男女の恋は闇、同性愛は昼になりました。
この世界観を信じるなら、武士の世界の同姓愛は気持ち悪いものではなく、むしろ憧れの対象だったらしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
