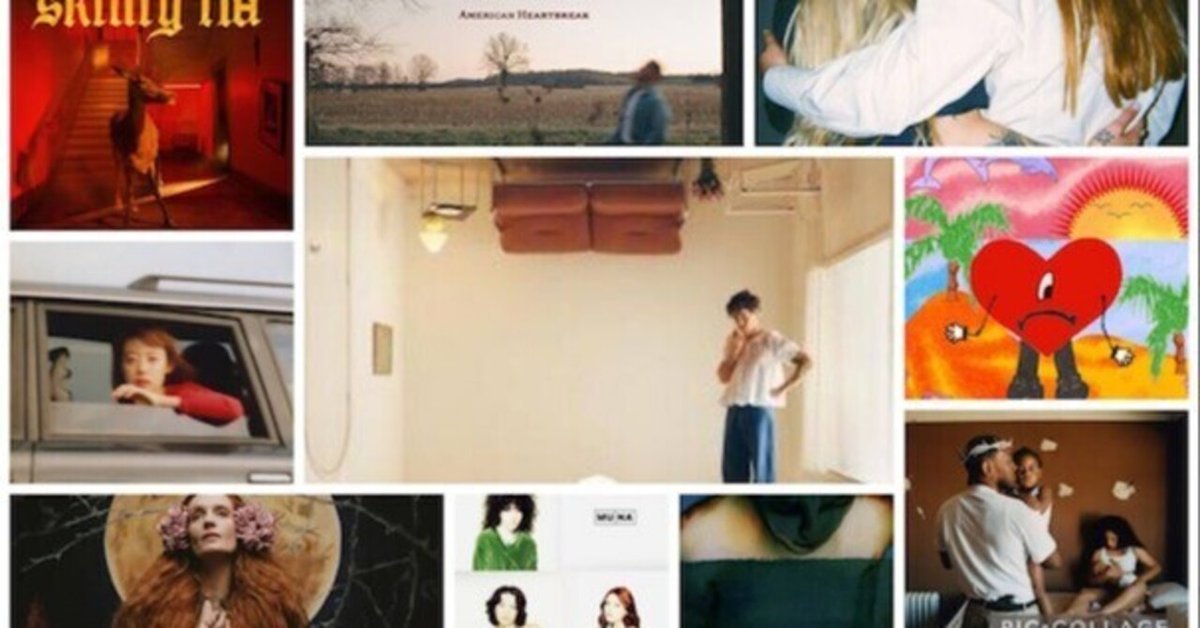
沢田太陽の2022年4〜6月のアルバム10選
どうも。
では、お待ちかね、3ヶ月に1度の恒例企画、アルバム10選、行きましょう。今回は2022年4〜6月のアルバム10選。
こうなりました!
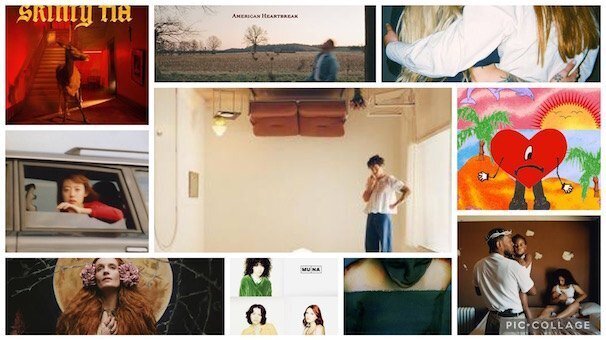
はい。これがこの3ヶ月の10枚です。どれもすごく素敵な、今回も非常にハイレベルのアルバムでしたけど、早速、ランダムに紹介していきましょう。

まず最初はザック・ブライアン。これ、あんまりレビュー媒体に出なかったのでマークしてない人、多いと思うんですが、ビルボードのアルバム・チャートで5位まで上がって長く売れそうです。彼、カントリーにカウントされてますけどどちかというとオルタナティヴ・フォークで、スカスカのサウンドにキレのあるディストーションの効いたギター聞くと、ライアン・アダムスやジェイソン・イゾベルの直系だとすぐわかり、いわゆる「アメリカーナ」と言われる類の玄人好みのサウンドを愛する人ならハマりますよ。あと、家は軍人の家系のようですが右翼的イデオロギーもほとんどない人なので、そのあたりでも問題ないです。「アメリカの失恋」と題した通り、基本、恋に破れた男のことを実に34曲もここで歌ってますが、疲れますが聴きごたえは保証しますよ。

続いてはジャスト・マスタード。アイルランドを拠点としたバンドです。不思議な名前のセンスですが、ヴォーカルを女性が務めるいわゆるシューゲイザーのバンドです。それ系のバンドの中では儚げな感じよりは、ヘヴィで沈鬱なイメージを強く押し出しているので、巷では「シューゲイザーmeetsインダストリアル」なんて呼ぶ人もいるんですけど、そんな堅苦しい感じでもなく、そのどうしようもない暗さの中に、すごくわかりやすい曲構成が隠されていて、そこに気がつくとすごく聴きやすいバンドです。それがあるからこそ、外面上のヘヴィさがむしろフックになっているというか。これが2枚目のアルバムなんですが、全英チャート入りこそ逃したもののバズはすごく立ってて本国でもトップ20に入ったくらいですから、次作以降の展開が楽しみです。カリスマ化する可能性秘めてます。

これも、まだこれからの人たちですね。MUNA。ロサンゼルスを拠点としたガールズ・バンド。こないだ上半期のシングルのところでも紹介しましたけど、今の僕のオススメです。彼女たち、元々はゴス系エレクトロのバンドで、その赤毛のヴォーカルの子なんて今と全然ルックス違うんですよね。前はメジャーで契約しててこれまでTHE1975、ケイシー・マスグレイヴス、ハリー・スタイルズと錚々たるメンツのツアーの前座までやってたのに目が出てなかったんですが、そこをフィービー・ブリッジャーズがフックアップして彼女のレーベル「サッデスト・ファクトリー」から出直したわけです。彼女との共演曲の「Silk Chiffon」は20年前のアヴリル・ラヴィーンやその頃の懐かしい女性SSWのポップを思わせる感じでフォーキーな曲も増えたんですけど、シンセポップ的要素はしっかり残っていて、そういう曲でもソングライティングがしっかりブラッシュアップされているところがすごく好感持てます。時間かけたら結構モノになる気がしてます。

続いてフローレンス&ザ・マシーンの「Dance Fever」。このインディ・ポップ寄りの女性アーティスト大全盛の昨今において、クイーンの存在になれる器なのにどこかコンフォート・ゾーン(「このくらいでいいか」の意)にとどまった表現をしがちだったフローレンスが大胆に力強い表現に踏み切った力作ですね。上半期のシングルのとこでも言及した「King」の力強さに、彼女本来のロック・オペラ的なシアトリカルな表現を全開にしたドラマティックなサウンドを余すところなく展開しているのがすごく嬉しいですね。こじんまりとしたシンガーソングライター的な表現では彼女の場合、やっぱり物足らないんですよね。プロデュースにあたったジャック・アントノフが彼女の表現をアッパーに高めて行ったことが実感できます。前半部の一部で見られる、ちょっとクラウト・ロック的な初期エレクトロ的なアプローチも思い切りの良さを表していると思います。遠慮なく、ガンガン攻めて欲しいものです。
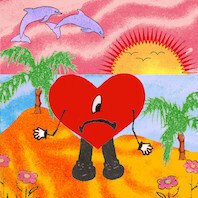
これは今年屈指のヒット・アルバムですね。バッドバニーの「Un Verano Sin Ti」。少し前の僕が、彼の作品をこういうレゲトンの作品をリストに入れることは自分でも考えにくかったんですけど、そんな僕でさえ、これはすぐにグッときたアルバムです。もともとドップリとトラップだった人が売れれば売れていくほどトラップから離れていき、エモい方に行くんですけど、曲の内向性が強まって、ただ単に「ラテン系エモ・ラップ」とも呼べないセンシティヴな表現へと深みを増していって。アメリカ進出を果たしたばかりの頃はカーディBやドレイクと組んでいたところが、このアルバムだとラウ・アレハンドロ、ザ・マリアス、ブスカブラ、ボンバ・エステレオといったラテン・ミュージック界でも有数のオルタナティヴなアーティストと組んで、スペイン語圏でのより挑戦的なサウンドにアプローチしようとしてね。しかも、このコライト(共作)全盛の昨今、フィーチャリング曲を除いて本人単独のソングライティングも貫いて。そういう作品がSpotifyのストリーミングの新記録作るくらいに売れるんですから理想的ですよね。

邦楽からも前回の宇多田に引き続いて選んでます。今回は羊文学の「Our Hope」。彼女たちのことは2020年の年間ベストの際にもランクインさせたくらいにお気に入りなんですが、リリース時から「自己ベスト更新」と方々で言われてたのも、これ納得の出来ですね。「光るとき」「ラッキー」「OOPARTS」といった、今後の彼女たちにとっての代表曲となりそうなキラーチューンのアンセムとしての完成度の高さと、とりわけ前半部で聞かれる、これまでになかった曲調やコードでの実験性にトライして表現の幅を広げている様とか。モエカの作詞家、ヴォーカリスト、ギタリストとしての可能性の高まりはもちろんのこと、バッキング・ヴォーカリストとしてのゆりかの非凡な才能が曲の彩りをより鮮やかにする瞬間がしばしば訪れるのも、このアルバムの持ち味でもあります。昨今のシューゲイザーのバンドとして、ここまで楽曲センスやアンサンブル、世界観の個性が完成された存在も世界的に珍しいです。そこいらの欧米圏の期待の注目株なんて言われるバンドよりは断然上だとさえ思いますね。

フォンテーンズDCのこのアルバム「Skinty Fia」も力作でしたね。2019年にデビュー・アルバム「Dogrel」でアイルランドからUK圏でのロックンロール復興を高らかに宣言するようにシーンに登場したときは戦慄が走ったものです。実際にあの後、UKやアイルランドでのロックシーンを再び活性化されたわけですけど、火付け役のひとつとなったフォンテーンズは4年で3作とハイペースで作品を発表し続け、今や全英初登場1位を余裕で獲得する大物バンドにはなったものの、シーンを牽引するというよりは、むしろその中で特異なポジションでカリスマ化し始めていますね。どんどんダークになっているんですけど、このアルバムでは、ポストパンク色をより濃くしているのはわかるんですけど、かなりヘヴィかつスロー、ストーナーに進化し、現在のシーンのみならず、歴史の縦軸で見ても稀有なサウンドを鳴らすようになりましたね。ただ、とっつきにくくはありながらも決して難解なわけではなく、一度聞いたら忘れないグリアン・チャッテンの強いアイリッシュ訛りの棒読みヴォーカルがフックとなり、強い説得力が付与されています。シーン復興の中での唯我独尊のロックンロール。今後がさらに楽しみです。

ただ、ちょっと気が早いかもしれませんが、2022年を象徴するロックで象徴する存在なら彼女たち、Wet Legになるのは決定的なんじゃないかと思ってます。ストロークスみたいなインディ・ギターロックを女性でここまでカッコよく決めた例というのは90s前半のブリーダーズの頃でもそうはなかったから、そういう意味で男性が飛びつきやすかったのもあるんですけど、「かわいらしさ」を売りにするにはそういう年齢でなくなった、あるいはそんなもの最初から眼中になく育ってきた30手前の女子たちが自虐的な本音をユーモアたっぷり(あと、エロネタも少なくない、笑)に聞かせる語りがそれ以上に人気あるように思いますね。そうじゃないと、このサウンドで世界的にあそこまでウケる理由、説明できないですからね。あと、それプラス、シングル曲のMVもことごとく傑作です。レズ・カップル風に一見見せつつ、ヴォーカルのリアンばかりが女王みたいに目立って、ブロンド美人のヘスターがほとんど映像に映してもらえない影の薄さを意図的に演出して楽しんでるのとか、見ていていちいち可笑しいです。

そして、もちろんこれを忘れるわけにはいきません。ケンドリック・ラマー。今やラッパーにしてピューリッツアー章まで受賞するヒップホップにおけるボブ・ディランみたいな存在にまでなった彼が、BLMやコロナの後に何を表現してくるか。これは全世界の人が見守っていましたね。当然、リリックの方も、思った以上に多かったパンデミックの話や、ポリコレ、LGBTなど興味深いトピックが多かったのもたしかなんですけど、僕自身は今回、リリックよりも音楽面の方にすごく惹かれたんですよね。アプローチとしては前作の「DAMN」でのコンテンポラリーな感じより名作「To Pimp A Buttefly」でのジャズ、ソウル・アプローチに近い感じで、「いかに話題作とはいえ、ここまで媚びないトラックでよく売れるな、この人」とも思ったんですが、もうなんというか、トラックとかビートの次元超えて「楽曲」としての完成度がとにかく高い。それは編曲者にジャズ・ミュージシャンやマルチ・プレイヤーが名を連ねていることもあるんですけど、シンガーソングライターの曲みたいな歌心が全体に感じられるというか。その意味でもヒップホップの次元、超えてる気がしましたね。さすがです。

そして締めはやっぱりハリー・スタイルズ。もう、これしかないですね。もう、このアルバムに関しては何度も書いたので書くネタがだいぶ尽きてるところもあるんですけど、「アイドルなのに、ロックをサウンドとして勝負できた」ことってやっぱり画期的で、これからのアイドル・ポップを本気で変えうるよなというワクワク感が本当にあるんですよね。それも徐々にいい意味で肩の力が抜けて軽くなってね。2017年のファースト・ソロであまりにも親父ロックを真正面にやりすぎてたところから、2年後の「Fine Line」でワン・ダイレクションのときに見せていた「アイドルだからできる軽み」で緩急つけることを覚えて本人なりに自信ができたからなのか、今回のアルバムではTHE 1975以降のソフィスティ・ポップと、フィービー・ブリッジャーズあたりに通じる今時のフォーク・サウンドを巧みにつなげて、これを未曾有の数のリスナーに聞かせたわけですからね。それって、それこそ昔のデヴィッド・ボウイとかマドンナがやってきてたことで、そういう「インディのシーンでの流行りをわかりやすく噛み砕いて伝えて自身がスターとしてカリスマになる」ということをできるようになっているんだなあと、1Dでデビューした頃を遠い目で思い出しちゃうんですよね。こういう痛快な逆転劇は大好きですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
