
シャード・オブ・マッポーカリプス(冬):ネオサイタマ・コン
ネオサイタマ沿岸部に広大な面積を占めるコンベンションセンター「オオキイ・ゲンバ」。その敷地には、早朝にもかかわらず入場待ちの行列が形成されている。単純な直方体の建物であることを執拗に拒絶するトラペゾへドロンじみたメインホールへと歩を進めていたシキベの足が、突如止まった。そして、前方に見える待機列を半ば虚脱した状態で見つめた。直前までシキベに並んで進んでいたオレンジ色の髪の少女が振り返った。
「驚きましたか? 大きな会場にとてもたくさんの人がいますが、わたしがシキベ=サンをガイドします。安心してください」
しかし、その声はシキベのサイバネ耳を素通りした。彼女は、数奇極まるその人生の中でも、とりわけ信じがたい事実を目の当たりにしていたのだ。
シキベの眼前の待機列に並ぶ来場客のほぼ半分は何らかのコスプレイ者である。そして、コスプレイ者たちの中には、彼女の視界に入っただけでも優に両手に余る数の、キョート風探偵装束を身に纏った者たちがいた。彼らの性別も肌の色も様々。
実際のところ、彼女はその事実を既に情報としては知っていた。だが、知識としてただ知ってることと、確たる事実として認識するのは全く別だ……彼女は「事実」を前にして、感激よりも畏怖に近い感情に打たれ、立ち尽くした。彼女のサイバネアイが捉えたキョート風探偵装束は、紛れもなく、彼女がかつて自分の手で描写した人物たちの姿。
「ゲーッ!」
シキベの肩に止まった三本足のカラスが一声啼いて、翼を大きく広げた。その声でシキベは我に返って、肩のカラスを見た。カラスは静かな眼差しを彼女に返す。眼差しを受け止めた彼女は、深呼吸とともに再びコスプレイ者たちを見た。その意味を噛みしめた。
シキベが創造した「サムライ探偵サイゴ」は、今や世界的なコンテンツとなっていた。

ニンジャの陰謀の犠牲となり一度は死んだはずのシキベ・タカコ。だが彼女は、マシンのボディを伴ってマッポーカリプスの世に突如として蘇り、そして自らが復活した理由も現在の状況も分からぬまま奇怪な事件と激しいイクサに巻き込まれることとなった。多くの人々の助けもあって奇跡的に事件を解決し、関係者の墓参も済ませた後にやっと迎えた「ガンドー探偵事務所」の本格的な再開の初日、彼女は早速、自分自身の復活を超える驚愕に見舞われることとなった。
「まあ、私もこの事務所のコンセプトはリスペクトしてるんで、貧乏暮らしは覚悟の上で、謹んで所長代行を正式に引き受けますけど……」
いつの間にかすっかり体に馴染んだダスターコートをまとったシキベは、深々と推理チェアに身を沈め、眼前のデスクに向かって軽口を叩いた。
「……最低でも、私のメンテナンス代くらいは払ってくださいよ、所長?」
「ゲーッ」
デスクの上の「所長」――三本足のカラス――が啼いた。シキベは笑って、ことさら大げさに息を吸い込んでから、口座管理UNIXに積もった数年分の埃に向かって吹きかけた。口座管理UNIXの電源を入れる。数十秒かけて起動した後、大型赤色LEDに表示された金額を見て、彼女はしばし絶句した。質問をする相手が存在することを思い出し、彼女はLEDを指さしてカラスに尋ねた。
「なンスか、これ……」
表示された口座残高は、五万十万といった金額とは桁がいくつか違っている。カラスは彼女をからかうかのように首を小刻みに左右に振りつつ、漆黒の眼球で彼女を見つめた。そしてカラスは、妙にもったいぶった仕草でデスクトップUNIXに近付き、嘴で電源ボタンを突いた。
再び数十秒かけてデスクトップが起動すると、カラスは更にデッキのキーボードを嘴でつついた。ブラウン管ディスプレイに、事務所口座の履歴が表示される。カラスは履歴を二十数年前まで遡ってスクロールさせた。シキベは無言のまま、表示された振り込み明細情報と金額の推移を読んでいった。
シキベは、かつて所長と断片的ながら共有した記憶を通じて、自分が死後に「サムライ探偵サイゴ」で商業出版デビューをしたことや印税等々が事務所の口座に振り込まれたこと、「サイゴ」がマンガ化やアニメ化まで果たしたことを一応、知っている。だがその情報は、結局のところ他人の――所長の記憶を通じて知った、垣間見た他人の夢のようなものでしかない。彼女自身は、自分の出版デビューを喜んだ体験すらしていないのだ。
だが今、「サイゴ」の出版と商業的な成功の結果がどういうものなのかが、具体的な出版社からの振り込み額という姿をとって眼前のディスプレイに表示されている。それは、かつてデビュー前に彼女が期待し、あるいは妄想した金額すら上回っていた。シキベはこの時はじめて、自らのこととして自身のデビューに驚愕した。実感が、シキベの目から涙を溢れさせた。
シキベは読み進める。年を経るにつれ、シトネ出版社から定期的に振り込まれる金額は徐々に減ってゆく。印税率が年々低下するというネオサイタマ式契約の影響だろう。もし自分が生きていたら、こんな契約内容に同意しただろうか?……それでも、マンガ化やアニメ化のタイミングで振込額は大幅に回復していた。原作小説の重版の効果のほかに、マンガの原作者印税、アニメ放映に際しての原作ロイヤリティ、さらにはビデオソフトやフィギュア等の関連グッズのロイヤリティが支払われたのだ。
結果として、所長が一時不在となる2037年までの振込総額は、アッパーガイオンのカチグミサラリマンの生涯賃金をも軽く凌駕している。もし自分が生きてこの金額を手にしていたら、仕事も何もかも放り出してオキナワにでも移住して、遊んで余生を送るかどうかしたのではないか。少なくともその衝動には駆られたはずだ。だが所長は私立探偵として戦い続けた。シキベは、あらためて敬意とともにカラスを見た。カラスは誇らしげにゲーゲー鳴いた。だが再びディスプレイに視線を戻したシキベは、疑念の声を漏らした。
「ア……?」
軽く眉根を寄せて、口座の履歴を自分の手で過去にスクロールさせる。今まで入金額ばかりに注目していたが、ふと、出費の項目に目を奪われたのだ。明らかとなった所長のカネの使い方は、シキベのおかげで転がり込んだ収入を受けて、時に度を過ぎて派手だった。一方2030年代に入ると、「サイゴ」関連の振込額はますます先細り、口座残高は減るばかり。
「所長、この500万もポンと払ってる『プーレク宿原』って、一体何買ったンスか?」
カラスはそっぽを向き、嘴で毛繕いした。
所長不在となる数ヶ月前に大口の探偵契約をした形跡はあるものの、総じて、まるでシキベが食わせてやっていたに等しい経営状況。しかも、ずいぶんと目減りした出版社からの振り込み額の大半は、マンガ・アニメ関連のロイヤリティが大半を占めている。シキベが数年にわたって書きためていた長大な原作小説は、巻を重ねるにつれて初版部数が減少し、重版の回数も減っていた。実際、シキベ自身が復活後にキョートで耳にした「サイゴ」の評判も、現在では下火がいいところだ。
つい先程の感動も今や消え失せ、シキベはうら寂しい気分となった。一度は成功を手にした(手にはしていないが)ものの、カネの形で見える成功の行き着く先は結局のところ……と考えたところで、あらためて赤色LEDに表示された金額を見て真顔になった。計算が合わない。
「所長、これおかしいっスよ。シトネ出版からの振り込みが今まで続いても、こんなに凄い残高にはならないスよ?」
問われたカラスも首を傾げた。所長不在の時期に彼も知らない何かがあったのか。シキベは所長不在期の口座を読み進める。口座上では、所長不在となってから現在まで二度、振込額の大幅回復イベントがあった。振り込み明細の情報によると、それぞれ「海外配信」と「リブート」。その直前には、振り込み名義もシトネ出版から別のメガコーポらしき社名へと変更されている。
「海外……」
シキベは呆然とつぶやいた。シキベが知る世界は、キョート共和国がそのほとんど全てだ。シキベがかつて生きた、日本が磁気嵐によって電子的鎖国状態となっていた時代、海外などというのは彼女の想像の埒外の存在であった。「サイゴ」の海外進出など妄想したこともない。
「これってつまり、『サイゴ』が海外で人気……ってことなンスかね」
言いながらもシキベ自身が半信半疑である。彼女は、肌で感じたキョートのアトモスフィアを、そこに生きる探偵の生き様と矜持を、文字通り叩きつけるようにキーボードを打鍵して執筆した。そうして生み出されたた作品が、ネオサイタマならともかく、海外で果たして理解されるのだろうか。キョート独特の用語も多用されているので、海外向けローカライズを試みても海外の言語でフルサポートされないようにも思える。カラスが嘴でキーボード入力した。
『多分そうなんだろ 知らねえけど』
シキベは吹き出した。所長は相変わらずだ。思わず、かつての彼がこの椅子に座っていた様をニューロンに思い描く。シトネ出版から出版オファーの連絡を受けた彼は、そのとき、一体どんな表情を見せたのだろう……と、突然、彼女はある可能性に思い至った。恐れの表情を浮かべ、シキベはカラスに尋ねた。
「あの……シトネ出版に原稿データを送ってくれたのは、所長ですよね?」
『そりゃそうだ』
みるみるうちに、シキベの顔面オモチシリコン皮膚が朱に染まる。
「……もしかして、私の原稿……読んだんスか?」
カラスは返答のかわりにシキベを見つめた。そこに、ニヤリと笑う彼の顔が確かに見えた。カラスはキーボードをゴツゴツつついた。
『熱かったぜ』
シキベは硬直した。数秒の沈黙の後、シキベは絶叫とともに推理チェアから転落し、顔を両手で覆った。そしてそのまま、奇声を上げつつ床の上でランダムなワーム・ムーブメントを続けた。

オオキイ・ゲンバで年末に開催される「ネオサイタマ・タノシイ・コンベンション」、通称ネオサイタマ・コンは、電子戦争以前からの伝統を誇るポップカルチャーの祭典である。のみならず、磁気嵐消失後の世界をネオサイタマ文化が浸食し席巻した結果、ネオサイタマ・コンは世界で最も注目を集めるコンへと成長した。三日間の開催期間の来場者数は120万人にも達し、その約半数を海外からの来場者が占める。
そのような巨大イベントに出かけるなど、もとよりシキベの趣味ではない。だが、前方を進むオレンジ色の髪の少女――コトブキ――を巻き込んだ、中国地方の秘境を舞台にしたイクサが悲劇的な結末を迎えた後、ようやく昨日の夜に一同がネオサイタマに帰還したところで、他ならぬコトブキがシキベをこのコンに誘ったのだ。コトブキがねぐらとしている「ピザ・タキ」の二階でベッドに並んで腰掛け、先のイクサで心に深い傷を負ったに違いないコトブキをシキベが気遣うのに答えて、コトブキは気丈に宣言した。
「尊い犠牲を無駄にしないために、そして約束を果たすために、わたしは『自分のなにか素敵なもの』を探します。優先順位です」
「ウェー……ちなみに優先順位だと、次には何が来るんスか?」
「悪の成敗ですね」
こうして、シキベはキョートに向けた出発を一日先延ばしにして、タイミング良く開催されていたこのコンにやって来た。「サイゴ」関連のもろもろを目で追うシキベの内心を知らぬコトブキは、遠慮なく会場内を早足で進む。
コトブキの背を追いながら、シキベはメインホール内の雑踏をかき分けた。目に入る大小様々なブースの配置にはおよそ規則性がない。Tシャツその他のアパレル、フィギュアやスタチューの展示販売やヴィデオゲームパブリッシャー、映画配給会社といった定番のブース以外にも、ポップカルチャーとの関連が今ひとつ分からない様々な企業が出展している。黒いラインの入った黄色いカンフートラックスーツを着たコトブキは、時折見知らぬ来場客からの撮影依頼に気さくに応じつつ、優雅なほどの足取りで雑踏をすり抜けてゆく。
やがてコトブキは絶えず銃声を轟かせる巨大ブースにたどりついた。シキベは雑踏から押し出されるかのようにしてコトブキに追いついた。コトブキは言った。
「まずは、ここをチェックします」
コトブキが指し示したのは、試射シューティングレンジを備えた、オムラ社が出展する銃火器及びパワードスーツ等の歩兵装備展示ブースだ。
「今後のイクサに備えて、事前にいろいろ試射するのが大事です。シキベ=サンもいっしょにどうですか?」
「アー……多分私は、使い慣れてるの以外は撃つことないんで……」
「では、ちょっと待っていてくださいね」
そう言い残してコトブキは試射の順番を待つ列に並んだ。すぐさまオムラ社員らしきスーツ姿の男が目ざとくコトブキを誘導し、列の先頭に割り込ませた。割り込まれた男は怒るどころか、目尻を下げて端末を取り出しコトブキの撮影を始めた。
コトブキは多種多様な銃の中からガトリングガンを選ぶと、腰だめで構えて銃口をシューティングレンジ奥の標的に向け、そのままフルオート射撃を開始した。5000rpmに迫る連射速度により三秒で給弾ベルトの全弾を撃ち尽くす。コトブキは銃口を上に向け、振り向いて、順番待ちの客に向かってポーズをとった。列が崩れ、コトブキを撮影する囲みが出来た。オムラの男は笑顔だ。宣伝効果があるのだろう。
偶発的撮影会を短時間で終え、満足げな笑みとともにコトブキが戻ってきた。
「期待通りの火力でした。でも新品はわたしの給料では買えないので、IRCオークションなどで中古品を探すことにします」
「ウェー」
「さあ、次は……」
「コトブキ=サン」シキベは遮った。「その前に、少し自分でも色々見て回って良いスか?」
「もちろんです。シキベ=サンの近くに居るようにしますから、何かあったら声をかけてください」
シキベは首だけの小さなオジギで謝意を伝えると、会場内を見渡しながら、さりげない足取りで逆方向に引き返した。つい先程から尾行の気配があった。彼女とコトブキのどちらが尾行の標的なのかをまず確かめる必要がある。そのためには、コトブキとは適度に距離を置いたほうがよい。
所長が会場内に同行していないことが悔やまれる。彼がいれば頭上から即座に尾行者を特定できただろう。いつものようにダスターコートの肩に彼を止まらせていては、ペット同伴者扱いされて入場を断られるのが目に見えていたので、やむなく今の彼は会場外だ。
シキベは落ち着いて歩みつつも、時折いかにも会場のアトモスフィアに圧倒されたかのような360度回転を交え、後方を確認する。その度に尾行者の候補を絞る。先程から端末を手に撮影を続けている男に目星を付けたところで前に向いたシキベを待っていたのは、大手フィギュアメーカーのブースだった。目立つところに精巧な6分の1スケールのサイゴとクロコ探偵のスタチュー見本品が展示されている。設置ベースの脇には「リブート後シリーズ準拠バージョン」の説明書き。
海外で人気と推理した「リブート後シリーズ」は、キョートが配信対象地域外のためシキベは未見だ。それどころか、「サイゴ」の配信権が独占されたことで、キョートでは過去作の「サイゴ」アニメシリーズまでまとめて視聴できなくなっている。シキベは背後警戒を続けつつも、結局スタチューを納めたガラスケースに近寄った。
ガラスケースの中のサイゴとクロコ探偵は、服装こそ自分の原稿での描写に忠実だが、妙に体型がスリムだ。その上クロコ探偵スタチューの顔は、イムラドリスに隠れ住むエルフのごとき美形。シキベは、自分が創造したキャラクターに加えられた他者による解釈を前に、不思議な感慨にとらわれた。「サイゴ」のキャラクターたちは、既にシキベの想像力の外に生きる存在なのだ。普段は皆無に等しい物欲をにわかに掻立てられたシキベは、スタチューの値札を確認し、怯んだ。その時。
後方でどよめきが上がり、シキベの意識が背後に引き戻された。振り返ると、リクエストに応じてヌンチャクワークを行っていたコトブキも手を止めて、騒ぎの方向を見つめはじめた。やや離れた場所で起こったどよめきが徐々に近づいてくる。浮かれ騒ぎがどよめきの後に続く。
「エジャナイザ! エジャナイザ!」
モーゼを先頭に紅海を割る出エジプト民めいて群衆の中から現れたのは、神輿を担いだ法被姿の者たち。神輿を露払い役にして、初老の男を乗せた車椅子が、そしてその車椅子を押す、スター俳優然としたスーツ姿の男が続いた。コトブキが絶叫した。
「ジェット・ヤマガタ=サン!」
周囲の来場者も口々に叫んだ。にこやかな表情で車椅子の男と何事かを話していたスターが、顔を上げてコトブキに軽く手を振った。コトブキは雄叫びとともに借り物のヌンチャクで天を衝いた。神輿を先頭にしたスペシャルゲスト会場入りダイミョ行列は、そのまま群衆に阻まれることなく会場内を進み、やがてシキベの視界から消えた。
スターが去っても、来場者たちは誰もが上気した笑顔でたった今の体験を語り合っている。中にはキョート風探偵装束の者も。シキベは会場内のアトモスフィアを出来る限りニューロンに、心に刻みつけた。そして決断的に二体セットでスタチューを購入した。懐は急激に軽くなったが、二体のスタチューが設置された推理デスクを思い浮かべただけで、思わず下膨れ気味の頬が緩んだ。シキベに続いて別の女性客がクロコ探偵単体を購入した。クロコだけが真っ先に売り切れとなった。
笑顔でスタチューの箱を受け取ったシキベは、突如として尾行者の問題を思い出し愕然となった。箱を両脇に抱えたまま慌てて周囲を見渡すと、展示品のハーレーにまたがってポーズをとるコトブキの姿がすぐ見つかった。またもやコトブキを撮影する囲みが出来ている。撮影者の一人が囲みを離れてドーナツ状空白地帯を進み、コトブキの後方から徐々にコトブキに接近している。既にシキベが尾行者として目星をつけていた男だ。シキベは咄嗟にコトブキに駆け寄ろうとしてから、考え直した。
尾行者は結局、コトブキの過剰に熱心な即製ファンに過ぎなかったようだ。特に害意があるようには見えぬ。シキベは緊張を解いて、一応見守った。興奮のあまり我を忘れているのか、尾行撮影者は臆面もなく手にした端末をコトブキの尻に近づけて撮影している。その余りの奥ゆかしさの欠如に、シキベは介入を決意した。
だがシキベが撮影者の囲みに達しようとした時には既に、尾行撮影者の背後に地味なフーディーを着た青年が立っていた。彼は尾行撮影者に声をかけた。
「おい」
尾行撮影者が振り向くと、青年は無言で撮影者の端末を取り上げて片手で握りつぶし、残骸を撮影者の手に返した。尾行撮影者が這々の体で退散するのを青年は無表情に眺めた。青年の異様なアトモスフィアを受けて、囲みの半径が広がり密度が下がる。コトブキはキョロキョロと左右を確認し、次いで背後の青年に目をとめた。そしてハーレーにまたがったまま青年に声をかけた。
「貴方も来ていたんですね、ニンジャスレイヤー=サン!」
囲みを抜けてコトブキに接近していたシキベは思わず立ち止まり、再び青年を見た。その視線を受けた青年はシキベを見返し、言った。
「何だ。まだおれに付きまとうのか?」そしてシキベが抱えたスタチューの箱を見て、付け加えた。「それともお前、フジョッシュとかいう、あれか」
「違いまス! てかアンタ誰!」
コトブキは今度はシキベに気づいて振り返った。そして再び青年のほうを向いて、笑顔で青年に言い添えた。
「わたしがシキベ=サンを誘ったんです」
「いやちょっと、それよりもまず」シキベの視線が青年の頭と足先とを往復した。「アンタが? ニンジャスレイヤー=サン?」
青年は訝しむ表情で問い返した。
「何を言っている?」
そう言った後、青年は何か思い当たった様子を見せた。青年は無愛想に言った。
「……別に四六時中あの格好をしているわけじゃない」
「アー、いいでスもう。納得しました」
シキベは諦めにも似た気分に襲われた。普段着姿でもこの調子とは、この青年――ニンジャスレイヤーには、ニンジャソウルの影響以前にもっと根本的なところで問題があるのではないか。社会人として。シキベの懸念をよそに、展示ハーレーから降りたコトブキが無邪気に訪ねた。
「ニンジャスレイヤー=サンは、どのコンテンツが目当てなのですか?」
「コンテンツ?……いや、サンズ・オブ・ケオスの連中に用があって来た」
コトブキが口を両手で覆い、凍り付いた。数秒の間の後、コトブキは悲痛な表情で訴えた。
「考え直してください。この会場のラブとリスペクトに満ちたアトモスフィアをイクサで破壊する権利は、誰にも……」
「誤解するな。イクサになるかどうかは相手の出方次第だ」そう言ってから、ニンジャスレイヤーは不服げに続けた。「おれも空気くらい読める」
「……分かりました」コトブキに笑顔はない。「わたしもついて行きます。展開によっては、たとえニンジャスレイヤー=サンと対立してでも、わたしはこの会場のラブとリスペクトを守ると誓います」
「勝手にしろ」
「アー、ちょっといいですか」
シキベは遠慮がちに割り込んだ。二人がシキベに向けたシリアスそのものの視線に鼻白みつつも、シキベは探偵としてなすべき質問をした。
「そのサンズ・オブ・ケオスっていう連中、そもそもここで何してるンスか?」
ニンジャスレイヤーはシリアスそのものの口調で答えた。
「タキ=サンがIRCで得た情報によると、奴らの一人がこの会場に個人ブースで参加している」

乱立するブースで遮られていた前方が不意に開け、多数の折り畳み式横長会議テーブルが整然と並べられたエリアがシキベの眼前に現れた。テーブルごとに、パイプ椅子に座った者と来場客が交流し談笑している。個人及び小規模クリエイターのブースの密集区域である。シキベは思わず眉根を寄せた。
「ウェー……ここってアレですよね。ヘンタイとかのジン(訳注:ファンジンの短縮形。ドージンとほぼ同義)を売ってるっていう……」
ニンジャスレイヤーは怪訝な表情で振り返った。
「キョートではそんなモノを売っているのか?」
「エ? ネオサイタマはその手の違法ジン多いんじゃないんスか?」
「聞いたことがない」ニンジャスレイヤーは答えた。「メガコーポの著作権を侵害するジンを作るような馬鹿が仮に居れば、企業傭兵あたりに殺されるのがオチだ」
シキベは暗黒メガコーポに対して生まれて初めて敬意を覚えた。コトブキが補足した。
「ここはアーティストアレイです。健全ですよ。安心してください」
ニンジャスレイヤーは、来場者に強制的に配布されるフライヤー入りPVC手提げ袋から会場案内図を取り出して確認した後、前方を見て呟いた。
「あそこか」
その視線をシキベも追った。画家ベレーを被ったニンジャ装束姿の男が、「サークル・サンズ・オブ・ケオス」とショドーされたノボリを背に、ぽつねんとパイプ椅子に座っている。薄いジンを空しく積み上げた会議テーブルに寄りつく様子を見せる来場者は皆無。不人気だ。ニンジャスレイヤーは、決断的な足取りで画家ベレーニンジャの真正面に進み出てアイサツした。
「ドーモ、ニンジャスレイヤーです」
俯いていたニンジャはたちまち目を輝かせて立ち上がり、両手でニンジャスレイヤーの右手を掴んで激しく上下させながらアイサツを返した。
「ドーモ! ようこそ! ようこそニンジャスレイヤー=サン! 僕はウインドトーカーです!」
ニンジャスレイヤーはまばたきした。次の瞬間、その目に殺意が燃えるのがシキベにも分かった。コトブキがニンジャスレイヤーに駆け寄って彼の肘に触れ、囁いた。
「ラブ、リスペクト……ラブです」
ニンジャスレイヤーはしばらく目線を左右に泳がせた後、頬を震わせながら左右非対称の笑みを作った。
「サ……サツガイ=サンを知って、いるかな?」
「もちろん! ニンジャスレイヤー=サンはまだサツガイ=サンに会ってないの?」
「……探しているところだ」
「気にしなくてもいいですって! そういう人も多いですから。なにせ最近サツガイ=サンのことがちょくちょく噂になり始めてるから、サツガイ=サンを探して僕らのところに来る人も多いんですよ」
シキベは会議テーブルに積まれたジンを見た。「多い」は明らかに見栄だろう。ウインドトーカーはまくし立てた。
「そういうみんなのために! 僕は、お役立ち情報をまとめました!」
「アー……試し読み良いスか?」
「ドーゾドーゾ!」
シキベはジンを一冊手に取り、不規則なフォントサイズのミンチョ文字で「ほのぼの」「サツガイ情報満載!」などの文言が埋め尽くす表紙を開いた。頭身が極端に低く描写された「サークル・オブ・ケオス」のニンジャとおぼしきニンジャたちが、他愛のない日常生活を送りながら時折サツガイについて議論するという内容の4コママンガ。数ページおきに、内輪ネタらしき内容がびっしりと書かれたコラムが挿入されている。意外にも絵柄はこなれており、紙質と印刷は無駄に高品質だ。上から紙面を覗きこんでいたニンジャスレイヤーが小さくため息をついた。
「……一冊もらおう」
「アリガトゴザイマス!」
ウインドトーカーは右手でニンジャスレイヤーの右手を掴んで再び激しく上下させつつ、空いた手でジンを差し出した。シキベは、身につまされる思いがした。
「私も貰っときます」
そう言って試し読みしていたジンをそのまま脇に挟んだシキベの手を、やはりウインドトーカーは握手した。代金を払った二人にウインドトーカーが言った。
「サインとかは良かったですか?」
シキベはニンジャスレイヤーを見た。ニンジャスレイヤーは黙ってジンをウインドトーカーに渡した。シキベもそれに倣った。ウインドトーカーは表紙裏に笑顔でショドーした。
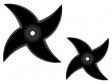
会場内のフードエリアでは、スシを筆頭に多種多様な料理の出店が設置され、イベント価格で販売されている。シキベとコトブキはスシを入手して立食テーブルの一つに陣取った。そこに、ピタでラップしたケバブとクラフトビールの小瓶を持ったニンジャスレイヤーが合流した。コトブキが目を丸くするのを見たニンジャスレイヤーが先んじて言った。
「イクサでもないのに、いつもスシばかり食う必要はない」
ニンジャスレイヤーは瓶から一口飲んで喉を潤すと、ジンを開いてページをめくり始めた。時折ケバブを頬張りつつも5分とたたずに読み終わり、彼は再度のため息とともにジンをPVC手提げ袋に戻した。やはり目新しい情報はなかったようだ。彼は憮然とした表情でメインホールの巨大空間を見渡した。海外から来たとおぼしき、キョート風探偵装束姿の二人連れが通りかかり、シキベに向かって親指を立てて見せた。テーブルの上に置いたスタチューの箱が目にとまったのだろう。
「不思議なものだな」ニンジャスレイヤーはまた一口飲んで、しげしげとスタチューの箱を眺めた。「そんなモノのために今でも大枚をはたく奴が、世界中からわざわざネオサイタマにやって来る」
シキベは思わず電子のニューロンの速度で反応した。
「そんなモノ呼ばわりは無いッスよ!」
「……やけに熱心だな」
「そりゃ……」シキベは言いかけた言葉を飲み込んだ。「……ファンっていうのはそういうもんなんデス!」
「それだ。不思議なのが」ニンジャスレイヤーはシキベを見た。「『サイゴ』だったか? おれがガキの頃にやっていたアニメだ。再放送で。何で今更海外からファンが来るんだ?」
シキベは有頂天になりかけている自分を抑えた。
「磁気嵐が無くなってから海外配信されたりリブートしたんで、海外では今まさに大人気っスよ!」
「初耳だ」
「ニンジャスレイヤー=サンにも、アニメを観てヒーローを応援する子供時代があったのですね」コトブキが腕組みをして満足そうにうなずいた。「そういう初心を忘れてはなりません」
「おれは付き合いで観てただけだ」ニンジャスレイヤーは瓶を見つめた。「だがあいつは、そういえば、随分とサイゴのことを気に入っていた」
「素敵な家族です」
コトブキの何気ない一言に、ニンジャスレイヤーは顔を上げた。そして再び目を伏せた。
「家族か……そうだな」
ニンジャスレイヤーは沈黙した。シキベがふと気づくと、周囲の観客の移動は徐々に一つの大きな流れに合流しようとしている。喧噪が巨大化しつつある。ニンジャスレイヤーはその騒ぎにまるで無反応だ。
「シキベ=サン」スタチューの箱の一つを抱え、コトブキが静かにシキベの手をとった。「彼は、時折あの状態になります。わたしたちは移動しましょう。もうすぐメインステージにジェット・ヤマガタ=サンが出演する時間です」
「ちょっとコトブキ=サン」もう一つの箱を抱えたシキベは手を引かれつつも、ニンジャスレイヤーを振り返った。「あれほっといて良いンスか?」
コトブキが立ち止まり、シキベに正対した。そしてシキベの瞳を見据えた。
「こういう時には、そっとしておいてあげることが大事です」そう言ってコトブキは小さく微笑んだ。「それが今では分かるようになりました」
シキベは虚を突かれた。コトブキは構わず再びシキベの手を引いて前進する。メインステージへと向かう巨大な人の流れが目前に迫る。雑踏に飲まれる直前、シキベはもう一度振り返った。
【終】
Photo by Anthony Ginsbrook on Unsplash
