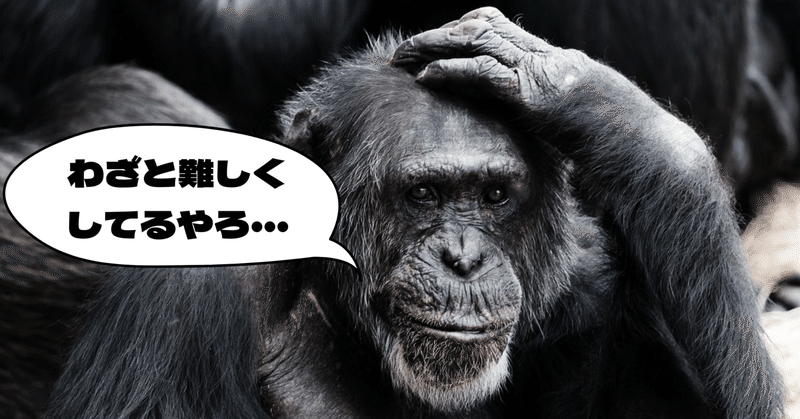
哲学が難解なのは何故か?
こんにちは。哲学チャンネルです。
普段、YouTubeやTwitterに出没しております。
落合陽一氏の「デジタルネイチャー」
— 哲学チャンネル (@tetsugaku_ch) February 4, 2022
すごく良い本だった。
サイエンス寄りではあるんだけど、哲学要素も満載で、まさに文理両立のとてもバランスの良い思想。
特に、事事無礙法界の概念を機械学習のブラックボックスと対比させて紐解く方向性はとても面白いと思った。
こういう活動をしていることもあって、視聴者様やフォロワー様から色々とご質問をいただくこともあります。
今回はそんなご質問の中でもわりと頻出する
「哲学はどうしてあんなに難しいのか?」
について個人的意見を書いてみようと思っています。
こんな活動をしているぐらいですから、私は哲学が好きです。
それと同じかそれ以上に哲学者を尊敬しています。
「哲学が何故難しいか?」への私の回答は、それがそのまま哲学者を尊敬している理由にもなります。
少し長くなりますが、ぜひ最後までお読みください。
多分ほんのちょっとだけ哲学が愛おしいものに思えるはずです。
哲学は難しい!!
繰り返しになりますが、哲学は難しいです。
私は中学生のとき「存在と時間」によってはじめて哲学の世界に触れました。なぜ「存在と時間」を読もうと思ったのかは不明です。当然、なんの収穫もなく見事に弾き返されました。
当時は多分、人生においての何かの答えを探していたのでしょう。その後もなんやかんや難しい哲学書を読んでは挫折するということを繰り返してきました。しかし思春期を抜けるとそのような欲望はだんだん弱くなり、そこから25歳になるぐらいまでは哲学とはほとんど無縁の生活をしていました。
(本は好きだったので小説などは恒常的に読んでいた)
25歳ごろに人生の大きな転機があってそこからまた哲学に興味が湧くわけですが、その際に読んだ哲学書も過去と変わらずとても難しい。今ではその「難しいこと」自体が「ありがたいこと」に変容しているので難しさに対してフラストレーションを感じることはありません。しかし、当時は間違いなく「なんでこんなに難しく書くんだよ」と憤っていました。
ということで、まずはじめに「哲学が難しい理由」を検討してみたいと思います。
言葉が難しい
まず、「言葉」が難しいですよね。
ハイデガーの用語に「現存在(Dasein)」というものがあります。
簡単に表現するならば「自己を人間として理解している存在者としての人間」となるのですが、これって「人間」または「人間存在」と表現しても良くないか?
またハイデガーには他にも「世人(Das Man)」という用語もあります。
これは公共的な世界に際して、世俗的な生き方をする人間のことを指した言葉ですが、これも「普通の人」とか「一般的な人生」と表現して良くないか?
このように哲学にはただでさえ難しい用語が現れるのに、さらに追加でその哲学者が造った新しい語まで現れます。
定義に厳しすぎる
哲学者は定義に厳しいです。
先程の「現存在(Dasein)」でいえば、その定義は「人間」や「人間存在」と同等なのではないか?と普通だったら感じてしまいます。
しかし彼らはそう考えません。
「人間存在」の定義は、話を進めるためには曖昧すぎる。より厳密に定義を絞り込んで「紛れ」が入り込まないようにしなければならない。そうやって定義を精査していくと「現存在(Dasein)」と定義するのが最適になる。
哲学者には「これぐらいで良いか」が希薄なんですよね。
彼らは言葉にとことん拘って、それを先鋭化させる。
定義が厳しいことで使用する言語量が増え、それが哲学の難しさを彩っています。
回りくどすぎる
みなさんも哲学書を読んだ後「結局何が言いたかったんだろう?」「結論はなんだったのだろう?」と感じたことがありませんか?
世に数多ある自己啓発本のように、章ごとにまず明確な結論が記載されていて、時に目次を読むだけでその本の主張がまるっと想像できてしまう。哲学書がそんな構成だったらどんなに読むのが楽でしょうか。
しかし、そういう哲学書は希少です。
ほとんどの場合、著者の主張や結論は分かりにくく提示されており、多くの場合は著作全体を通して読者が解釈をしないとその主張が見えてこなかったりします。
このような傾向が生まれる背景には、哲学者のどのような姿勢が影響しているのでしょうか?
きっとそうする必要があった
とはいえ、哲学者、とくに現代までその名が残っている大哲学者はいわゆる天才中の天才です。彼らが考えなしに哲学を難しくするわけないですし、その必要がないのにあえて難しくしているとも考え難い。
(ショーペンハウアーなどはフィヒテやヘーゲルを揶揄して「彼らはわざと哲学を難しくしている」と言っています。いや、あなたの思想も相当むずいぞ)
つまり『なんらかの理由』があってそのように表現するしかなかったと考えるのが妥当です。
では、その『なんらかの理由』とはなんでしょうか?
考察1
言語で表現できないことをそれでも言語で表現しようとするから
私たちは日常的に言語を使います。
そして世の中で『正しい』とされているものの全ては、その論拠を言語に頼っています。
『科学的に正しい』に関しても、その結論は言語を経由しないと導出されないし、『論理的に正しい』に関しても同様です。
そもそも、思考すら言語で行う私たちにおいて認識や判断すらも言語の影響を受けないはずがないのです。
私は言語に対して一定の不信感を持っています。
言語は完全に万能なツールではなく、私たちが受け取る入力のほんの一部分を表現することしかできない。(もちろんそこに多大な価値があります)
言語で表現できない事柄は未だいくらでも存在していて、その意味で言語に対して一定の不信感を抱くことが人生を歩む上で必要な姿勢なのではないか?勝手にそう考えています。
しかし、哲学者はそれでも言語によって真理を解き明かそうとします。
一方で真理を言語以外の部分で暴き出そうとするのが仏教をはじめとした宗教ですよね。少なくとも私はそう考えているし、その文脈で宗教を尊敬しています。
しかし、哲学者はそれでも言語によって真理を解き明かそうとします。
例えば仏教では真理に到達するためにはさまざまなアプローチが提案されています。『さまざまなアプローチが提案されている』ということは、アプローチ経由でないと真理に到達できないのであり、それは徹頭徹尾『個人的体験』に収束することをあらわしています。言語化できるギリギリのところが『アプローチ』であり、それ以上は『個人的体験』に任せるしかない。なぜなら真理は言語の外にあるからだ。そのように考えるわけです。
しかし、哲学者はそれでも言語によって真理を解き明かそうとします。
『個人的体験』ではなく『普遍』としての真理を提示するためには『普遍的』なツールによってその結論を提示しなければなりません。そしてそうした『普遍的』なデータは人間にとって言語ぐらいしかないのです。
(芸術なども可能性を内包していますが、どうしても『個人的体験』の要素が含まれてしまいます)
言語で表現できない(かもしれない)ものを、それでも言語で表現する。
当然求められる言語の操作能力は限界に達し、そこから現れる言語はとても難しいものになるのです。
カントは言った
人間には先験的な認識機能が備わっていて『物自体』をその認識方法であるフィルターを通して表象させている。だから、その根本となる『物自体』をありのままに認識することは不可能である。私たちが理性的に判断できる事柄は私たちの認識の内部にあるものに限定され『物自体』の領域に関しては信仰によって解決するしかない。
カントはこのようなことを言っています。
(つまりカントは私たちの認識の範囲内を主に哲学としてあらわしたのですが、そのキワキワの部分を攻めているので、当然超絶難しい)
カントのこの主張によって、人間の意識は『形而上学』的なものを捨て、認識の中にある現実的な世界に向かうことになった。つまり、昨今の社会の進化の原因はカントに求められる。と主張する識者もいます。
言語を超えた世界、つまり『形而上学』の(ひとまずの)終焉がカントにありました。
ウィトゲンシュタインは言った
カントから100年以上後、ウィトゲンシュタインが現れます。
彼は『論理哲学論考』の中で
「語りえないことについては人は沈黙せねばならない」
( Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.)
と述べました。
言語には限界があり、言語がたどり着ける真理は言語の表現能力の中のものに限られる。だから、それを超えた問題については沈黙するほかない。
ウィトゲンシュタインの登場によって言語に対する哲学の姿勢が大きく変化します。以後、哲学の多くの部分は『言語の研究』に興味を移行させていくのです。
「以前」と「以後」
カントーウィトゲンシュタインを一つの分岐点と考えたときに、哲学の難しさには以前と以後で二種類の性質が考えられます。
カントーウィトゲンシュタイン以前は『言語で表現することが無理かもしれない事柄をそれでもなんとか言語で表現する』難しさがありました。
一番分かりやすいのが神についてです。
神の存在の是非は置いておいて、神を表現するためにいくら言語を尽くしてもその姿を正しく捉えることはできません。
しかし過去の哲学者(とくに中世の哲学者)は言語を駆使してどうにかして神の存在とその意味を提示しようと苦心したのです。
そうして言語は極限状態で進化を続け、より難しくよりややこしくなっていったのです。
カントーウィトゲンシュタイン以後は『言語でできることとできないことをより鮮明にする』ことに主眼が置かれます。主に分析哲学と呼ばれる潮流です。
ウィトゲンシュタインを起点とし、ゴットロープ・フレーゲとバートランド・ラッセルがその方向性を定めたこの哲学は、それまでの哲学が文系の性質を持っていたとしたら(完全に文系というわけではない、もちろん)そこに大きく理系の概念が注入された傾向を持ちます。
言語を分析しより論理的に考察を繰り返していくと、最終的にはいわゆる一般言語と呼ばれる言葉は必要なくなり数式だけが残るのです。
つまり、以前と以後の哲学は似ているようで異質の学問であり、以前は言語の限界的な難しさがあり、以後には理系方向の難しさがあるのです。その転換点がウィトゲンシュタインであり、比較的文系の多い哲学界隈においてウィトゲンシュタインが忌避されるのにはこのような理由が隠されていると思っています。
ですから
どっちにしたって難しい!!!
わけですね。
考察2
普遍とは何か?
いつの時代も哲学者が暴こうとするのは『普遍的な真理』です。
誰それにとっての真理ではなく『普遍的な』真理なのです。
個人的には、この『普遍的』という概念が厄介で、それを追い求めるがために哲学は難しくならざるを得ないのではないか?と考えています。
その前提には私自身の『正しさ』に対する思想が強く絡みますので、癖が強めですが少しだけお付き合いください。
()はあらゆるところに存在する
私はあらゆる『正しいこと』の前に()が存在していると認識します。
それこそ()はどんな場所にも含まれています。
初音ミクが至高である。
という命題に関してはその前提に何かしらの()が隠されています。
()がないとしたらそれは『普遍的な真理』となるからです。
(私にとって)初音ミクが至高である。
こう表現すればそれは(私にとって)の真理です。その真偽を疑うことはできません。しかし()の内容が変われば真理値は一転します。
(あなたにとって)初音ミクが至高である。
は、多くの場合偽となるでしょう。
では真理っぽいもの。例えば
地球は太陽の周りを公転している
はどうでしょうか?
実はこれにも前提条件となる()が隠されています。
(科学的には)地球は太陽の周りを公転している
と表現することも可能ではないでしょうか?地球が太陽の周りを公転しているという結論は、科学的な思考により判明したものであり、それを目視したという人はそうそういないはずです。つまり、前提条件として(科学的には)が含まれてしまうのです。(一応補足です。私は天動説論者ではありません)
また、
(人間にとっては)地球は太陽の周りを公転している
と表現することも可能です。人間以外の生き物にとって、彼らの認識方法によっては太陽が地球の周りを回っている可能性があります。また、地球とか太陽とかの概念すら人間が勝手に認識している個別の方法かもしれません。
少し無理矢理かもしれませんが、上記のような明らかに真理っぽく思われていることにも前提条件の()を想定することができるのです。
私はこのように()を意識すること(メタ認知と呼んでも良いかもしれない)はとても大事なことだと感じています。
地動説を疑え。と言いたいわけではありません。
地動説も一つの立場から導き出された限定付きの結論だ。と認識することが重要だと言いたいのです。それを認識できると、世の中が少しだけ平和になるのではないかと考えています。
コロナはただの風邪だ。経済を止めるな。
コロナは殺人ウィルスだ。自粛しろ。
例えば昨今大きく議論になっているこの二つの意見。どちらの立場もそれぞれが『正しい』と思って主張をしており、だからこそ二つの意見は平行線をたどり、なかなか着地点が見えてきません。
しかし、この二つの主張の前提にも()が隠されています。
(何かの視点、集合、立場において)コロナはただの風邪だ。経済を止めるな。
(何かの視点、集合、立場において)コロナは殺人ウィルスだ。自粛しろ。
こうして捉え直してみると、少しだけ議論の余地が見えてくるような気がします。もしくは、両者の議論が果たして生産的なものになるのか?というそもそもの命題を考えるきっかけにもなるのではないでしょうか?
同様に、何かの主張をする際にも
(私にとっては少なくとも)〇〇である
という意識を持っていると、わりと話がスムーズに纏まりやすい印象があります。
主張とは「(私における)真理を共有したい」あらわれであり、「普遍的な真理を押し付けたい」わけではありません。
これをあたかも普遍的な真理のように主張してしまうから余計な棘が立ち、対立を生み出していることって少なくない気がします。
こうして()について考えていくと『教育』についてもいくつかの主張が得られるのですが、それに関してはまた機会がありましたら詳しく書きたいと思います。
相対主義と小さな物語
実はこの()をめぐる議論は、長い哲学史の中で連綿と紡がれてきています。
古くは古代ギリシア。
ソフィストと呼ばれる職業に就いていた賢人たちは「真理は人の数だけある」と考えました。代表的な論者はプロタゴラスやゴルギアスですね。
(近代哲学においてはロックやヒュームなどもこの思想に近い)
これはまさに()の存在を明らかにして、それを尊重しようとした動きだと解釈できます。
相対主義と相反するのが絶対主義です。
絶対主義においては普遍的な真理は存在するはずだと考えます。
カントーウィトゲンシュタインまでの哲学の大部分は絶対主義的な前提を含んでいました。
しかし現代になると、再度相対主義に光が当たります。
フランスの哲学者であるリオタールは、それまでの哲学が追い求めてきた大きな物語(普遍的な真理)は終焉し、小さな物語(多様性におけるさまざまな価値観)の世の中がやってきたと宣言しました。いわゆる『ポストモダン』のはじまりです。
その50年少し後の時代が、我々の生きる現代です。
私たちの世界は、多様性に溢れていてそれぞれの価値観がぶつかり合う、まさに小さな物語の様相を呈しています。
もちろん、そんな中でも普遍的な真理を追い求める動きは枯れていません。例えば新実在論で有名なマルクス・ガブリエルなどは「世界は存在しない」というテーゼを根底に、ポストモダン的な相対主義を超克しようと活動しています。
()は「信仰」ともリンクしている
話は逸れますが()は信仰ともリンクしています。
ここでは信仰の対象を宗教だけではなく、さまざまなものに広げて考えてみましょう。
まずは宗教。
(ある教えでは)〇〇が真理である
または国家。
(その国にとって)〇〇が真理である
または共同体
(ある共同体にとって)〇〇は真理である
こう考えてみると()の中に入る存在を『何かに紐づいて同様の信念を信仰する集合』と定義することができそうです。
世の中で起こる争いの多くは()に含まれる集合同士が、対抗する主張の()を認められないから起こっているのかもしれません。
フランスの哲学者であるエマニュエル・レヴィナスは「顔」の概念を提唱しました。人は自分の思い通りにならないものを「他者」と定義して、その「顔」を見ようとしない。全体主義とはそのような閉塞感が引き起こした「他者排除」の暴走だろうと。
『他者の顔と向き合う』(異質な存在を認める)ことによって全体主義のような悲劇を回避することができるのではないか?少し安易にまとめすぎましたが、彼は概ねこのような主張をしました。
『他者の顔と向き合う』とはつまり、自分が含まれない(集合)に対して、それでも自分と同じ人間として等しく認知することだと解釈できます。
話を戻します。
あらゆる主義主張に()は付属します。
()を限界まで細分化していくと(私にとっては)にたどり着きますし、限界まで拡大していくといつか()が取り払われ、普遍的な真理に辿り着くのです。
()を外すことが哲学者の目標
哲学者が目指す『普遍的な真理』とは何か。
それは()の必要がない結論です。
神は存在する
当然(私にとって)ではなく、(ある集団にとって)でもなく、(ほとんどの人にとって)でもなく。
(ありとあらゆる全ての集合にとって)とカッコで括れた瞬間に、その結論はやっと普遍的なものになります。
逆に考えると、ある主張があった際に、一つでも()で括れる例を見つけた瞬間に、その主張の普遍性は反証されてしまうのです。
(ひろゆき氏の「それってあなたの感想ですよね」はまさに()を利用した最強の攻撃なのである)
一般的に()で括られた集合の範囲が広ければ広いほど、その情報には価値があると見做されます。
だから例えば(日本人にとっての)正しいことみたいなものがあるのであれば、それはそれでとても崇高な素晴らしい情報なのです。
しかし、多くの哲学者はそれでは満足しません。
あくまでも()なしの真の普遍に挑戦するのです。
それは茨の道なのである
そうした普遍への挑戦は茨の道です。
どうやったって、どんな主張にも()の例(反証)を想定できてしまうし、そもそも()の中に自分が含まれているという自己言及のパラドクスもどうにかしないといけません。
これはもう無理ゲーと表現しても良いかもしれません。
もう何で見たか忘れてしまいましたが、過去にこんな意見を目にしたことがあります。
「普遍から逃げ出したのが相対主義である」
確かに直感的にはそう言えるかもしれません。
でも「普遍的な真理などない」という主張はそこに普遍を含みますから、相対主義だって()によって反論されてしまうのです。そういう意味では別に逃げではないと思う。
つまりどんな主張も突き詰めると最後は普遍の問題と対立してしまう。
だからこそ優れた哲学者たちはその普遍とずっと戦ってきたのです。
哲学は難儀な挑戦だ
①言語で表現できないものを言語で表現しようとするから哲学は難しい
②普遍的なものを求めているから哲学は難しい
以上が「哲学がなぜ難しいか?」への私なりの所感です。
だから、決してわざと難しくしているわけではありません。まぁ「どうやったって難しくなる」ことを理解して取り組んでいるわけですからわざとといえばわざとですけど。
そう考えると哲学者はドMです。
それがどんなに大変で、難しいことなのかを理解した上で人生を懸けているわけですから。
そして哲学者は「正しい」ということに恐怖と畏怖を抱いています。
私たちが日常的に利用する「正しい」という言葉は、非常に多くの()を含んでいるわけですが、哲学者はそれを理解しているからこそ「正しい」と安易に発言することができない。それがどんなに重い言葉かを知っているのです。(または(〇〇にとって)という前提条件をいちいち明記しないといけない)
だから、ある結論を導出するためにとてもレベルの高い厳格性を追求するのですし、簡単に「〇〇は〇〇である」と答えを提示することもできないのです。
そして、それを重々理解しているにも関わらず、それでも真理追求の欲望を抑えられずに身を削って思考し続ける彼らの姿に、私は常に大きな感銘を受け、生きる力をもらっています。
哲学書はそんな彼らが残した真理への欲望の一雫です。
だから私は哲学書が難しいことを有難いと思うし、そうでなければと感じます。
ということで、個人的かつ勝手な哲学に対する感想でした。
もし内容が「哲学を好きになる」一因になったらすごく嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
