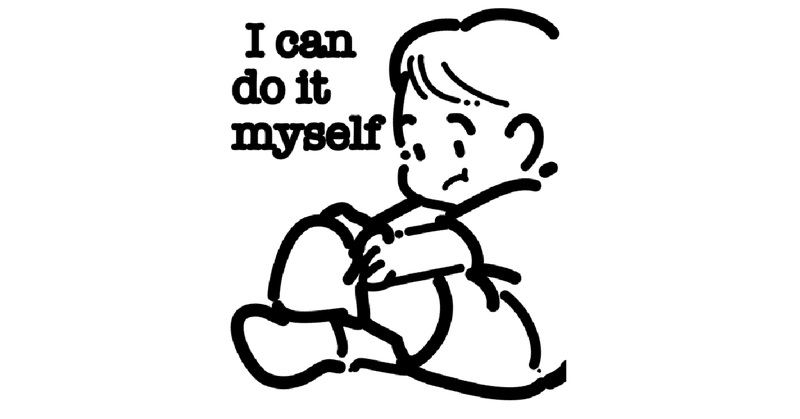
なにか、おかしくないですか?
この条例のニュースを聞いたとき、「うちの親は虐待してたのか 笑」と、思った。父が個人事業主で、母は専従者、子どもは5人、下宿生や居候もいる大家族で育った私は、小学1年生から津まで通っていたスイミングスクールが駅前に移転した3年生ときから、何の疑問も抵抗もなく、1人で電車に乗って通っていた。そのほかの習い事も当たり前のように、1人、ときに姉妹、兄妹で通った。長兄が11歳上だったので、私が低学年の頃から、両親は、子どもたちに留守番させて年に2,3回、2人で旅行に行っていた。同じ敷地内に兄の祖父母宅はあったけれど。
この条例を通すなら、スクールバスやベビーシッター、コミュニティの学童的な施設などインフラ(?)と地域の協力をもっと得られる環境づくりが先だと思う。そして、また子どもだけの時間や活動の減少は、5人兄妹の末っ子として生まれた私には、少子化対策と逆行しているのではないかと思える。
親御さんの負担を大きくしすぎている。
この夏、一時帰国していた幼馴染が、帰国中だけ地元の小学校に子どもを通わせていた。そのとき、自分は幼い頃そうしていたのに、アメリカに長く住んでいるために、子どもたちだけで学校に行かせるということにドキドキしていると言っていたけれど、アメリカとは、町の構造も違えば、アメリカはきちんとスクールバスやベビーシッターなど選択肢があるはずだ。
様々なことを欧米基準で考える人がいるけれど、欧米の例などを入れて説明することと、欧米の例を基準にすることは全く違うことだ。
私は、確かに今とは違う安全な日本に生まれ育った。だから、今は小学3年生を1人で電車で習い事に通わせることが危険だということは理解している。でも、納得はしていない。
今、毎日子どもたちと接しながら、子どもたちが子どもたちだけで過ごす時間の減少、ご家庭の負担の増加は、子どもたちの学力、コミュニケーション能力低下に影響を与えていると思うからだ。親御さんたちの負担を増やす前に、もう少し親や先生たち以外の大人や年齢の違う人たちと触れ合う場所ー子どもたちの居場所ーを増やすことも必要だと思っている。
そして、政治家の皆さんには、こんな条例を考える前に、これからを担う子どもたちが育つ社会の青写真を示してほしい。そして、そのためのインフラと条例を両方セットで提案、実行をしてほしいと思う。
いただいたサポートは、子どもたちの学ぶ環境づくりに使わせていただきます。よろしくお願いいたします<m(__)m>
