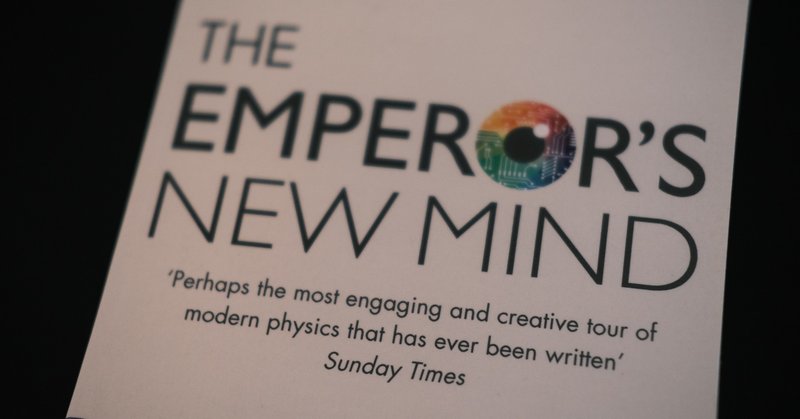
読書
本が知らない間にたまっていきます。
読むのは自然科学系の本か、文系のエッセイなどが多く、ビジネス本などは読みません。
最近読んだのは形態学 倉谷滋と、モード後の世界 栗野宏文の2冊です。どちらもジャンルは全く違いますが、とても面白かった。形態学の方は生物の進化を形態学的に捉えたものを歴史やその後の分子生物学的な発展を交えて解説したもので、特に全ての生物の進化が砂時計的に起こっていくという学説が実に興味深かった。内容は難しくて日本語でも4割ぐらいしか理解できなかったが、以前ロジャーペンローズ(こちらも超難解)の本で宇宙は膨張して収束して膨張するを繰り返す、という学説に近い気がして世の中の原理ってもしかしたらそういったものに近いのかもしれないと勝手に妄想した。クリストファーノーランの映画にもよく出てくる、エントロピイってやつです。
これは今の社会にも当てはまるのではないか、と思った。世界大戦が終わって民主主義が台頭した後、世の中のグローバリズム化が広まり、人の動きがものすごく動的になった後に今回のコロナショック。中国と米国を見ても急速に世界はまたナショナリズムへの動きを取り戻しつつあるのではないか。日本に関していえば、絶対に民主主義以前の世界には戻らないと思っていたけれど、意外と豪華主義や経済競争主義というものはいささか勢いを失って来ている印象がある。人々がもはやそんなことを求めていないのだ。デジタルな部分は進化しつつ、原理的な生活様式へともしかしたら戻っていくのかもしれない。竪穴式?高床式?
モード後の世界も、ファッションという観点から社会学を切り取ったような内容で、人間の消費行動が時代により全く違う動きを見せており、そこを冷静に見つめながらビジネスを展開していくプロの目線を感じる事ができた。日本語もとてもわかりやすく、内容も重いものでなかったのでとても読みやすかった。しかし、2冊を通して感じた事として学者の書く文章は何故こんなにわかりにくいのだろう、と思った。もちろん例外もたくさんあります。他者への共感とコミュニケーションデザインがこれからの時代のkey pointなのではと感じた。その点で栗野さんの本は文章からその人柄を感じた。
そんな事を感じながら秋の夜長にアルコールを消費し、私の連休は幕を閉じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
