
丘の上学園卓球部 球拾いの幸福な憂い 【丘の上の学校のものがたり ②】
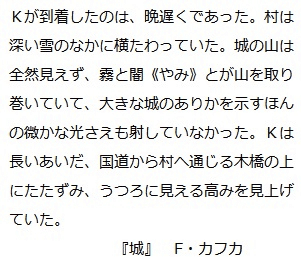
00
少年が卓球部に入部したのは、中学1年生の初夏で、退部したのは、高校1年の春だった。およそ3年という期間、卓球部に在籍していた。
中高一貫校である丘の上の学校での中学生時代をまるまる卓球部で過ごしたことになる。それだけ、ひとつの競技にかかわれば、それなりの技術の向上や達成感があるのが当たり前と思われるが、残念なことに、少年には、どちらもなかった。
卓球は、1対1のシングル、あるいは、2対2のダブルスでおこなわれる競技なので、練習し、技術の向上を図るには、それを助けてくれる練習相手が必要となる。
シングルならば、ひとり。ダブルスならば、チームを組んでくれるひとりと対戦相手になってくれる二人が必要というわけだ。ダブルスの場合は、チームは固定しているので、相手チームを探すことになる。
練習相手は、練習での目的に適うひとであり、例えば、自分が下回転の球に弱いとしたら、下回転の球をきちんと返してくれる技術を持っている人に依頼することになる。かくして、卓球台が4台あれば、卓球台に向かっている部員は、全員シングルならば、8人、そこにダブルスが入ればその分2人づつ増えてゆく。全台でダブルスの練習をすることがないのは、動き回る部員が隣の台の部員とぶつかるようなことが起きるからだ。従って、卓球台4台では、8~12人ぐらいが同時に練習することとなる。
毎日部員が全員練習に参加するわけでもないが、毎日の練習には、20人ほどが参加しているので、卓球台に向かって行う練習は、当然のことながら交代制で、練習に参加できない、ボールを打てない部員が何人か出てくる。
練習に参加していない部員は、卓球台に向かって練習している部員の後方に立って、こぼれ球を拾い、効率よく、渡す役となる。これが、即ち、「球拾い」だ。
自分の練習時間以外に、他の部員から、練習相手の依頼がないと、その時間はずっと球拾いになってしまう。
少年は、練習相手に選ばれることはなく、練習時間のほとんどは、球拾いだった。
球拾いの時間が長いことは、練習に誘ってもらえないぐらいの力量でしかないことを赤裸々に表しているのであり、相手のペースに合わすことのできない狷介な性格も疑われ、とてつもない屈辱感を味わうこととなる。
ふつうに考えれば、努力して卓球の技量をあげることがまず必要なことは眼に見えている。ただ、その球拾いの時間の多さを見れば、少年には、球拾いをしているそのときどきの悔しい気持ちは、ひとまずおくとしても、事実上、卓球への向上心はなかったというしかない。
しかも、他の部員の大多数から、あれじゃかわいそうだから、練習相手に使ってやるかという、一種の憐憫の情を起こさせなかったことでも、やはり少年の性格にも問題あり、人間関係も上手くいっていないという、技術と人間関係での負の両輪が稼働しているとしか見えないし、思えない。
それでも、少年は、卓球部に3年間在籍していた。この屈辱に耐えられる理由が何かあったのだろうか。
01
丘の上の学校の卓球場は、古い大きな講堂の地下の一室にあった。講堂を正面から左側に沿ってゆくと人ふたりが通れるか通れないほどの地下に向かう石の階段があり、そこに近づくと、ざわざわとした人声のなかにポンポンという卓球台やラケットに球があたる音が地下から響いてきた。
その学校では、文化系や運動系の同好会やクラブに入り、活動を始めるのは、中学1年生の初めての中間試験が終わってからになっていた。入学してから中間試験が終わるまでの2ヶ月の間に、少年は何度か卓球場を訪れていた。覗きに行ったというほうが適切だろう。
少年が小学校の高学年になって親しんでいたスポーツは柔道だった。従って、中学入学後のスポーツ部への入部の選択は漠然と柔道部と考えていた。入学してから、柔道部員から、入部勧誘の声を何度かかけられており、やはり外眼にも自分は柔道向きなのかとも思ったりもしていた。
しかし、同じ小学校出身の唯一の先輩は、卓球部員で、その先輩の家に入学の挨拶に行ったときに偶然お会いした、丘の上の学校の快活な先生は、卓球部の顧問だった。また、先輩の部屋からは、たまたま訪れていた卓球部員たちの楽しそうな声が聞こえていた。
そのときから、まったく未経験にもかかわらず、少年のなかに、卓球というスポーツが入り込んできて、置かれるようになった。
初めての中間試験の結果は、惨憺たるものだった。小学校でも進学塾でも経験したことのない成績結果に、さすがに少年はたじろいだ。その実、この学校の試験でこういうやり方で勉強すれば、こういう結果になるのかといったという穿った見方も少年はしていた。敗者としての悔しさの裏返しでもあり、少年らしい負けん気で試験で勝つための方法を考えているのであった。少年は、両親への手前もあり、表面上は謙虚にしていたが、相変わらず意気軒高で生意気な内面を維持していた。
中学1年のクラス担任にスポーツ部への入部希望の報告にゆくと、君の成績なら少し待った方が・・・という反応だったが、生徒の自主性を重んじる校風もあり、入部することの判断は少年に委ねられた。
この4月から友人のいない新しい環境に飛び込んでいた少年は、試験結果が悪いことで、ますます孤独感が強くなっていた。ただ、そのなかで運動部へ入るんだという固い意志だけはぐるぐると回り続けていた。そうなってみると、あらためて、今まで付き合いがほとんどないとはいえ、小学校の先輩がいるという卓球部の存在が少年のなかで、だんだんと大きくなっていった。
少年は、卓球部への入部を心の中で少しづつ緩やかに自分の心の様子をさぐりながら決めていき、両親や親しくなった同級生たちにもそっと話すようになっていた。
そして、6月も半ばの暑い日に、授業が終わると入部するために意を決して卓球場へ向かった。しかし、地下への石階段を下りてゆくのが、ためらわれ、地下の入り口あたりに佇んでいると、卓球ユニフォームを着た小柄で手足のひょろ長い痩身の部員が、バケツ片手に地上に出てきて、暗い地下から明るい場所へ出てきた小動物が警戒するように周りを見回した。少年を見つけるとじっと見つめていたが、すぐに興味なさげに眼を逸らし、近くにあった、水飲み場へむかい、バケツに水を入れ出していた。
その目つきの険しさと大きな口元、身体から発散している殺気みたいな熱気に、少年はたじろぎながらも、今がチャンスとばかりに、勇気をふるい、その部員に近づき「あの…卓球部へ入りたいんですけど・・・」と言ってみた。
水道の蛇口からバケツに注ぎ込まれる水を見ていた部員は、少年の方へゆっくりと顔をむけ、少年の様子を観察すると、蛇口を止め、「ついて来な。」とよく通る声で短く言い放って、バケツをさげてもと来た方へ歩き出した。
地下の卓球場は、練習の最中らしく、大勢の部員たちが動き回って、球の音と人の声が飛びまわり、騒然としていた。
「タカハシさん、卓球部に入りたいという新入生が来てます!」
奥の方から、黒縁の眼鏡をかけた中背の大人びた猫背のひとがゆっくりと現れた。
「この人が、キャプテンのタカハシさん」
「卓球部に入りたいっていうのは、君か?」少年をじっと観察しながらの声からは、ほぉー卓球部に入りたいかといった感心した様子が伝わってきた。
「はい、お願いします。」タカハシキャプテンは、眼が優しくなり笑顔でうなずいた。
キャプテンと小柄な部員の背後には、地下室の天井にかかった蛍光灯がいくつも並び、卓球台を照らしており、その人工的な光の中で、大勢の部員たちが声をかけあって、球を打ちあっていた。室内の光と音は、周囲の濃いベージュ色の壁のあたりでは薄くなり、4台ある卓球台は、頭上からのライトに照らされながらもとても淡い墨色の空間に包まれているようだった。
02
入部の手続きは特になく、卓球のスタイルとラケットの選択、ユニフォームの発注、見るからに個性的な部員たちへの紹介といった具合だった。卓球場の奥にあるロッカーの空いているボックスの使用を許可された。卓球のラケットやユニフォーム用だが、先輩たちを見ていると登校して着替えた後の服やら教科書やらノートやら本やらいろんなものをいれていた。やがて、少年も先輩を見習い、登校するとまずロッカーにいろんなものを入れ込んで上履きにかえてから、教室へ向かうようになった。
練習の初日は、壁打ちから始まった。卓球台の半分が壁に向けられ、ネットが壁に張り付いており、その壁に、球をぶつけては打ち返すという練習だった。少年が少しは卓球をやっていれば、初日から、卓球台へ向かわせてもらえたのかもしれないが、それまでは卓球そのものをやったという記憶もあいまいなただの素人なのだから、まずは、ラケットをもって、球を打つことになじむ練習となった。
そのころの、卓球ラケットは、大きく3種類あった。球に上向きの回転をかけるドライブマンの選手には、ペンホルダー。球に下向きの回転をかけるカットマンには、シェイクハンド。卓球台の前に距離を詰めて細かく打ち返す中国式前陣速攻型。少年は、自分の上背を生かすことを考え、卓球台に少し距離を取ってドライブをかけるロングマンを目指し、ペンホルダーのラケットを選んでいた。部内を見ると、ペンホルダーが圧倒的に多く、その半分くらいがシェイクハンド、前陣速攻型は、数えるほどしかいなかった。少年は、ペンホルダーのラケットを選んだ。卓球台から少し離れて、上回転のドライブをかけて攻めてゆくロング・ドライブマンを目指すのは、まだ、先の話だ。
卓球は、始めてみると卓球台での球のやり取りが会話しているようで、しかも、自分の言葉を相手とお互いにぶつけ合って新しい言葉をつくり出そうとしているみたいで、とても新鮮だった。
球筋の読み合い、球とともに上下左右に全身で躍動する身体、デリケートで戦略的な心理戦、ふいに訪れる神の恩寵・・・
少年は夢中になり、毎日の放課後は練習に参加し、時間があれば卓球台に向かっているようになっていた。そして、そこは、個性にあふれた先輩たちが大勢いる空間でもあった。
この学校では、高校3年生は、大学受験に専念するということで、授業自体が減り、登校もほとんどなくなり、部活は事実上の引退で、キャプテン、副キャプテン、マネージャーは、高校2年生が務めていた。中学生向けには、中学キャプテンも設けられ、各学年には、学年キャプテンがいた。
中学1年生からみれば高校2年生は、まったく大人であり、近寄りがたい雰囲気があった。この先輩に対する近寄りがたさは、自分たちの学年に近づくほど少なくなり、1学年上の中学2年生の先輩は、何でも聴ける良い兄貴分であり、卓球部のなかのいろんなしきたりも2年生から手取り足取り教わった。また、少年が入部したころの中2生には、面倒見の良い兄貴がたくさんおり、あれこれと教わることが多かった。
例えば、土曜日は半休で、弁当を持たずに登校していたので、午後の練習前には、昼食を摂らねばならなかった。さて、どうしようかと戸惑っている姿をいち早く見つけ、飯を食いに行こうかと誘ってくれたのは、肉付きが良く声が高い一つ上の先輩だった。よし、今日は蕎麦屋だと学校近くの蕎麦屋へ連れてってもらい、学校近くの蕎麦屋、中華屋、洋食屋、などについて、一軒ごとにそこの人気メニューやときどき夫婦げんかが始まる店、なぜか生徒があまりゆかない店のことなどを丁寧に教えてもらった。こういう情報は、この学校で生活してゆく上でとても重要な情報だった。昼休みに、先生だけでなく、生徒までもぞろぞろと校門を出て行った理由がやっとわかったのもこの時で、土曜日に限らず、昼は外食という生徒が少なからずいたわけだ。
03
そして、あっという間に夏休みになり、夏合宿が始まった。まだ、同級生の部員も少なく、中1で夏合宿に参加するのは、少年含めたった二人だった。もうひとりの新入部員は、少々太り気味の寡黙なシェイクマンで、どうも少年とは相性が良くないらしく、ほとんど口をきかない関係だった。
合宿所は、日光市で、地元の学校の体育館を借り、宿は、神橋近くの旅館で、1週間行われた。よほどのことがないかぎり部員は全員参加なので、40数名ほどの規模になった。
朝食前には、長距離のランニングがあり、旅館前に集合し、キャプテンを先頭に列を組んで、神橋を横にみて通り過ぎ、山の方へ向かう坂道を上り折り返してゆくコースは、少年にはきつく、いつもびりの方だった。毎朝、坂道を走りながら、今日はどこで折り返すのだろうとキャプテンの背中を見ていた。
昼間の練習はきつく、ふらふらになった。卓球の最大の天敵は、風で、卓球台の上を風が吹くと球が泳いでしまうことになるため、練習中は、扉や窓は、締め切りとなった。1時間ごとの休憩時間に、扉や窓を開けたときに、吹き抜ける風は気持ちよく、これ以上ないくらいに、汗でびっしょりの体をなごませた。部員たちの多くは、広い体育館の床に座って足を投げ出し、ラケットを団扇がわりにして、ひらひらとさせていた。
夕食後のミーティングが終了し、明日の練習予定が立ってから就寝までは自由時間。先輩たちは幾人かに分かれて、町へ散歩に出たりしていた。少年は、その先輩たちについて、夜の町に出かけるのが楽しかった。散歩するだけのこともあり、ゲーム屋に行ったり、喫茶店でジュースを飲んだりしていた。少年にとっては、夜の街を大人なしで徘徊することも、喫茶店に入るのも初めてのことで、新鮮でワクワクしていた、というよりは、今夜はどんな場所へ行けるんだろうかとドキドキしていた。
最終日の夜は、就寝時間の規定もない自由時間で、外に出かけた部員たちも帰ってくる夜中から、寝てしまう人は寝てしまうが、そんなひとはほとんどおらず、5~6人づつのグループに分かれて、トランプをしたり、雑談したり、猥談したり、とまるで文化祭のようになっていった。少年は、面白いので、ひとつひとつのグループを覗きに行って、できれば参加した。猥談グループは、それ専門の先輩がおり、後輩たちが拝聴するような趣があり、トランプはナポレオンというカード取りゲームが盛んだった。上級生のグループでは、とても真面目な議論が行われており、ひょいと顔を出したとたんに、なぜ、きみはなぜ卓球をやっているのか?卓球ってのはきみにとって何だ?とか聞かれてしまい、答えられず、そのまましばらく上級生たちの真面目な話に耳を傾けることとなった。すぐ、隣のグループでは、洋楽の好きな先輩がビートルズの新曲や音楽が聴けるテレビの話をしていた。
顧問の先生は、30歳になるかならないかで、学校の先輩であり、丘の上の伝統的な校風である自由な雰囲気をとても愛し、部員たちに自然に融けこんでおり、いろんなグループに出没しては、座をわかしているのだった。
卓球部のこの自由な合宿風景は、少年が辞める直前の春合宿まで、同じで、練習のきつさや時によっては、人間関係のややこしさがあっても楽しい経験だった。
年上の先輩たちと1週間起居を共にするというのは、両親と妹の4人暮らしの少年にとっては、今まで見たことも聞いたこともない人たちと日々接し、人間関係の機微を学びながら、そこからあふれてくる刺激的な新情報の濁流のなかで、何とか踏ん張って立っているという感じだった。
練習場にとぼとぼと歩いてゆくときに、先輩が聞いたこともないメロディで鼻唄を歌っていることが何度かあり、さすがにその歌は何ですか?と聞いてみた。ビートルズの新曲だよ、えっ、知らないのか。知りません、どこで聞けるんですか?土曜日の夕方にビートポップスというテレビ番組があって、そこでは、アメリカで流行っている曲を紹介してるんだ、そういうのも見とけよ。えっ、でも、土曜日の午後は練習がありますが・・・。う~ん、卓球だけでは、世の中狭くなるんだぞ、毎週(見る)ってわけでもないしな。
少年は、土曜日の練習中にふと姿を消す先輩の秘密を知り、また、練習をときどきサボってでも聴きに行くという洋楽に興味を持ち出すのだった。
夜の自由時間に毎晩出かけるのも小遣いが続かないし、と、合宿所に残っていると先輩たちが読んでいた雑誌やマンガ本も転がっており、そのなかには、マガジンやサンデーだけでなく、COMなんていう聞いたこもとないマンガ雑誌があり、めくってみて出会ったのは、手塚治虫の『火の鳥』で、読んでいるうちに旅館の部屋がぐるぐる回りだすような衝撃を受けた。すぐに、COMを持ってきた先輩を探し出して、手塚治虫っていうのは、マガジンやサンデーにも書いている漫画家ですか?とか聞き、こういうヘンなマンガはほかにもあるんですかとか聞き出すことになる。
いつの春合宿だったか、真夜中近くに、横で寝ていた1級上の先輩にこずかれて眼を開けると、静かにしろ!これから、カワダさんと5月の文化祭をどうするか(どう過ごすか)という話をするので、お前も参加しろ!周りは、昼間の練習の疲れで眠っているので、もぞもぞと腹ばいのまま足元の方に行くとカワダさんとほか何人かが頭を突き合わせて、そっと話をしていた。いいか、文化祭ってのは、な、女の子が来るんだ!女の子がたくさん学校に来るんだ!チャンスだぞ!カワダさん、服装はどうしましょう?だからな・・・。カワダさん、今年はT商業の卓球部を招待してます。あそこは強いですね。バカか、お前は!と頭を軽くはたかれた。そこから、カワダさんの女性への接し方についての話が続いたが、カワダさんが女性にもてるという話はまったく聞いたこともないよなとぼんやりしつつ、昼間の疲れが出て、眠ってしまった。朝起きると、少年だけが、天地逆になっているありさまだった。
その年の文化祭、卓球強豪校を緊張した面持ちで校門で迎える部員たちの横を赤地のネクタイにアイビールックで身を固めてポマードの匂いをぷんぷんさせたカワダさんが通り過ぎた。傍にいた、この4月からキャプテンになったばかりのヤマグチさんが、普段の柔和な顔から一瞬怖い顔になり、カワダ!と低い声でつぶやくのが聞こえたのだった。
04
夏休みの学校での部活は、さすがに毎日あるわけはなく、決まった期間に集中的におこなわれた。練習は、午前中に終わるので、せっかくだから午後は残って卓球でもやってゆくかと思っていたら、先輩に、午後はソフトボールをやるが人数が足りないので、参加しないかと誘われ、参加してみた。少年は、小学生時代に友だちとしょっちゅう野球をやっていたので、丘の上の学校の土の広いグランドの野球はすこぶる楽しかった。
それから、夏の間は、午前中は卓球、午後はほかのスポーツという日々が続いた。グランドが空いていれば、野球やサッカー、プールが空いていれば、水泳、といった具合だった。異色だったのは、缶蹴りというのがあった。地下に卓球場のある講堂と本校舎とのあいだの僅かな空間で建物の死角を利用して缶蹴りが実行された。
丘の上の学校には、夏休みの宿題がなかった。現代国語の先生が、夏休みの読書の勧めという、日本文学や外国文学の名作と言われている文庫本が30冊ぐらい並んでいるガリ版を配るだけだった。生徒は、他に宿題もないので、夏休みの間に、これらの本を一生懸命に読んだ。入学以来、びっくりし通しの少年は、開放感あふれる夏休みにさらにびっくりし、その開放感のまま午後のスポーツに精出すこととなった。
秋が来る頃には、入部者も増え、いつのまにか、同期は10人以上になっていた。少年のクラスからの入部者はおらず、初めて会う同級生ばかりだった。
卓球は面白かったが、それよりも先輩たちから猥談やら音楽やら映画やら、また、知的な好奇心をくすぐるような話を聞くのが面白かった。
中1の頃は、授業が終わると1級上の先輩の教室に行き、今日はどうしましょうとか聞くような毎日が、何だかとても面白かった。卓球部自体は、校内のスポーツ部のなかでも特に民主的な部と言われていたが、少年はだれに命令されるわけでもなく、男子校の上下関係に厳しい運動部の下っ端のようなことをやっていたのだった。
ある試験の最終日、試験終了後にいつものように先輩のところへ行くと、今日は、神田の書店街にゆくけど、どうする?と聞かれた。当然卓球場へ向かうと思っていたので、意外な感じだったが、神田の書店街ということばは少年のなかでしばらく眠っていた好奇心を奮い起こした。
もともと本好きの少年は、小学生の頃に、本屋ばかりの町があると聞いて父親に頼み込んで連れてってもらったことがあった。神保町の三省堂の小中学生向けのコーナーには、天井まで届きそうな書棚が並び、本がびっしりと陳列してあり、少年を圧倒した。また、行きたかったが、ひとりでは行けず、胸の奥深くしまい込んでいた。
先輩の行くという神田の書店街とは、あの神保町のことだと察し、喜んでついていった。
先輩は、母上に頼まれた本があり、それを探しに行くということだった。
銀座線神田を下りて、靖国通りを西に向かいしばらく歩くと、一軒の古書店があった。先輩はためらうことなく、扉を開けて入り、書棚を一見した後で、奥の帳場に行き、捜している本の有無を尋ねた。この後も、靖国通りを西に向かい、段々増えてくる古書店を1軒1軒訪ねて同じことを繰り返した。
少年は、先輩の先導で、神保町の書店街という密林を探検しているみたいで、密林のなかのところどころの特徴を知ることとなり、しかも、ぶらぶら歩きに倦んだら喫茶店に入り、買ったばかりの本をペラペラめくってみるという、密林での過ごし方までいつのまにか教わっていた。
卓球部を通して、少年は、未知の世界を知ったり、興味はあったが深くは入れなかった世界への入り方を教えてもらっていた。しかも、どの世界も少年には奥行きが深く、その得体のしれなさに慄きつつも好奇心にあらがうことは出来なかった。
05
秋になり、初めての試合が六本木の交差点のすぐ近くの中学校の体育館で組まれた。卓球部入部以来、卓球以外の刺激には手ごたえを感じていたが、卓球には、それほどの手ごたえを感じることもなく、過ごしていたので、試合への緊張感はあったが、勝てねばならないという荒ぶるものはまったくなかった。
試合は、公立も含む地域の複数校の同学年同士で争う男女別トーナメント形式だった。ところが、少年が、組まれていた相手が急にいなくなり、代わりに同級の女性と戦うことになった。
試合は、1ゲームで21ポイント獲った方が勝ちで、3ゲームを先に獲った勝ち上がる形式だった。
接戦と言えるような試合でもなく、球のコントロールが中途半端で集中力に欠けた悪い癖が出ているなと少年が思っているうちに、2対3で負けてしまった。少年自身がびっくりするよりも、試合場にいたひとたちが皆びっくりしていた。同じ卓球部員は、あれあれと呆れて苦笑い。気の毒だったのは、次の第2戦で女子にあたる男性選手で、優勝候補だった彼は、けっこう余裕をもった雰囲気で、試合場にいたが、第1戦で男子が負けたことでプレッシャーを感じたのか、表情が強張っていた。
第2戦を男子選手は勝ち抜けたが、3対2というスコアだった。
少年は、試合結果を反省するよりも、先輩や同期に対する恥ずかしさや卓球に対する情熱が希薄なことが内外に露わになったことに戸惑いを覚えていた。やはり、自分には卓球は向いていないのかという思いがあらためて静かにこみあげてきた。それもひとつの言い訳に過ぎないことに、少年は、まだ、気づいていなかった。
そうこうしているうちに、年末恒例のOBもやってくる卓球場でのすき焼き大忘年会も終わり、冬が過ぎ、いつの間にか、新しい春がやってきていた。
06
この春に、中学2年生になった少年に大事件が二つ起こった。
地下の卓球場は、練習の時以外は、他の生徒に解放されており、昼休みや放課後に卓球をやりにくる生徒の常連が少なくなかった。その中でも、特に上手で強い二人の同期が勧誘されて入部してきた。
この二人は、今までの同期の部員の誰よりも強かった。まったく敵わなかった。お手上げだった。
もうひとつは、新入生からの入部が相次いだなかに、呆れるほど卓球が上手なふたりがいた。卓球の上手な新入生が入ったというので、少年も楽しみしていたが、ふたりのラリーを見てたまげてしまった。少年よりも抜群にうまいのだった。
同期と新入生の卓球の上手な部員の出現で、いったいこの1年の練習はなんだったんだろうと、少年はじめ中1より卓球部で練習してきた同期は思いこまざるを得なかった。
同期のふたりのネット際や台の端に打ち込む筋の勝負強さには、少年にない卓球への確固たる意志を感じ、新入生ふたりの信じられないくらいに延々とつづくラリーには、卓球のボールの弾むような躍動感に一体となって、新しい会話と運動に身を任せているような軽快な楽しさがあった。
まったく、少年の出る幕はなくなっていた。卓球に神様がいるならば、この瞬間に少年は完全に見放されたと思った。努力やプライドなんかではどうしようもない能力の差なんだろう。神様と能力のせいにしながらも、少年は、さすがにおのれの非力にがっかりしていたが、一方で、この学校に来てから何度も味わってきた、素晴らしい才能に出会うことの嬉しさも感じていた。負け惜しみもあるが、これらの才能は称賛するしかないくらい素晴らしいのだ。
こうして、卓球部にいて、卓球に向上心のない、少年の球拾いの卓球人生は始まり、決定的になった。本人にやる気がないのだから、仕方ない。しかも、本人のやる気以前に、全くかなわない才能が目の前に現れたら、もうお手上げにして、自分なりの工夫に向かわないという少年の自分勝手な意固地が傍目にも剥き出しになっていた。
それからも、卓球部の練習に参加し、合宿も全参加、少年にとって卓球場にある自分用のロッカーがこの学校の生活の基本であることは変わらなかった。ただ、ボール拾いに費やす練習の時間がしだいに多くなり、だんだんと肩身の狭い日々が増えていった。こうなってくると不思議なもので卓球のボールですら、小さく見えはじめ、回転の角度や強度が見えなくなっていったのだった。対戦相手との卓球を介しての会話も貧相になってきていた。
卓球は、ほとんど上達しないまま、少年のボール拾いの日々は続き、特に合宿は、体育館の壁際で立って、こぼれ球を拾い、渡す作業の明け暮れで、さすがに気が伏せってくるようになった。ここまで立場が悪化すると、卓球の技能以前に人間性までをも問われているようで、部内では楽し気にふるまいながらも、気鬱な感情が心の底に溜まってきていた。
07
少年が中学3年生を終えようとしていた冬、2月10日のことだ。朝からの曇り空で肌寒く、少年は早く帰ろうと友人と連れ立って中庭を歩いていた。そこでは、もうその頃には珍しくはなくなった、学内での集会が開かれており、紀元節復活反対と大きく書かれた幕の前に30人ほどの生徒が校庭にしゃがみ込み、アジ演説を聴きながら、時折シュプレヒコールを上げていた。何となく、その手の集会にしては静かな雰囲気だと思い、主催者らしい人を見ると、卓球部の3年先輩のナガタさんがいた。ナガタさんは、高校3年生だったから、もう学校には来なくていいはずなんだが、頑張るなと思い、通り過ぎようとすると、そのナガタさんから呼び止められた。お~い、帰るんなら、これに少し参加してゆけよ。集会の参加数が少ないので、サクラになれよと言われているわけだった。
これが、丘の上の学校の歴史に残る紛争の始まりになるなんてことは、少しも思わず、ナガタさんに見つかったんだから、仕方ないなと集会の左端に座ってみた。
聞くともなく聞いていると、演説の話題は、紀元節反対の表明だけでなく、学園内における集会の自由という問題に移っていった。現在学園内での集会は、届けて許可をもらうことになっているが、これは表現の自由などから言ってもおかしいことで、自由に開催、あるいは届けるだけで充分ではないかといった議論になっていった。
集会自体がいつの間にか少しづつ参加人数も増えて、熱を帯びてくるようになってきて、校内で集会をする自由について、直接校長と話し合おうということになり、そのまま、校長室へと大勢で押し掛けた。校長は、生徒たちに囲まれ、憮然としながらも、彼らに向き合って対話をしようとしていた。その校長にスピーカーを向けて、大声でしゃべっているが、高音過ぎて、何をしゃべっているのかがさっぱりわからないひとがいた。しかし、その高音の特徴ある声は、卓球部の先輩のひとりであることは間違いなかった。
やがて、他の先生たちも校長室に入ってきて、満員電車よりも混んでいる状況で、話し合いが行われたらしく、建国記念日明けから、全校生徒と全教員、校長による、学園内の集会について、表現の自由についての、全校集会を行うことが約束された、ということを少年はもみくちゃになった校長室から出てきた後に聞いた。
この後も、全校集会開催に至るまでにはいろいろあったが、全校集会は、約束通りに行われ、学園内での集会の自由や教師と生徒との協力関係について詳細に議論され、決められた。1週間ほど続いたその集会は講堂で行われ、少年も生徒と教師の間で生徒同士で教員同士で行われる活発な議論を全てを理解できないまでもその熱気に押されるように聞いていた。
しかし、4月の新学期になると、事態は一変した。
今までの校長は辞任し、理事会から送られてきた、校長代行(教員資格をもっていないので、校長にはなれないので、校長代行と称した)が、前期末の全校集会の合意をあっさりと反故にし、校長代行による専制ともいえる体制を実行してきた。
08
自由を謳歌してきた少年たちにとって、校長代行の出現とその方針は驚天動地だった。日常生活での規則による締め付けは、半ば自由化していた制服着用の強制、学校史上初の生徒規則の制定、生徒規則が載っている生徒手帳の常備携帯とその検査、放課後の校舎で三人以上の届け出の無い会合の禁止・・・と続いていった。
学校内には今までに無い妙な緊張がただよい、そのなかを身長は190センチ、体重は100キロは超えているであろう巨体の校長代行が竹刀を片手に巡察し、目につく生徒がいると大声で怒鳴りあげるといった始末だった。
卓球部のキャプテンは、1級上のヤマダさんになり、新入部員を迎える準備が進んでいるところだった。学校内の名を馳せた活動家には、なぜか卓球部部員が多く、また、顧問の先生は教員のなかでもリベラルな立場で発言していることもあり、卓球部への校長代行からの何らかの圧力も心配されたが、表面上は何ごともなく4月は学内混乱のなか過ぎていった。
高校1年生になった少年は、数ヵ月前から漠然と思っていた退部ということを実行することにした。部内での高校1年生は、部そのもの、部員全体への有形無形の責任も出てくる立場だった。卓球は下手、熱意もなし、部内での人望もない、高校1年生の部員としては、明らかに大欠陥部員であり、周りに迷惑をかけるといったきれいごとよりも、当の本人がこれからどんどん苦しくなるのは予想するまでもなかった。
新キャプテンのヤマダさんに直接言いにゆくのは、少年は控えた。せっかくキャプテンになり、張り切っているところへ欠陥部員とはいえ、退部の話をしにゆくのはヤマダさんの直情清明な性格を思うとこれまで面倒を見てもらっていたヤマダさんに悪くてとてもできなかった。
そこで、まず、学年キャプテンのもとへ向かった。終業時間で教室の席で教科書をカバンに入れ帰り支度をしていた学年キャプテンは、少年の話を聞くと一瞬手を止め、また、動かしながらボソッといった、オレも辞めようと思ってるんだ。
えっ!!!
学年キャプテンは、思慮深い誠実な人柄で、部内の人望も篤く、だれもが次期キャプテン候補と自然と思い、次期キャプテンになることを信じていた。
少年が、まず思ったのは、学年キャプテンの退部は引き留めなければ!だった。辞める人間がそんなことを思うのはおかしいが、卓球部のことを考えればそうなるのが少年にとっては当然だったのだ。一気に話がややこしくなった、みたいだった。
とりあえず、ふたりで、退部について話し合おうということになり、渋谷に向かい、まだ、喫茶店に入ることに慣れていない少年二人は、駅前の246号線の車道にかかっていた四角い歩道橋をぐるぐる回りながら、数時間しゃべった。
少年は、学年キャプテンにあれこれ聞き、慰留の方向はないかと探ったが、彼の心のなかでさんざん倦んで出した決意は固く、本人にとっても苦い決心であり、少年が立ち入ることでないことを理解した。退部届けは、二人別々に、部に提出することとなった。
少年という季節は終わりかけていた。
少年には、自分が退部するよりも、学年キャプテンが退部することの方がショックで、そのあとの退部届けやキャプテンや部員たちとのやりとりはどっか他人事だった。
ただ、最終日に、先生とキャプテンや幾人かの先輩たちが、恵比寿の喫茶店でささやかな送別会を開いてくれたことを少年は大事に記憶しているばかりだった。
09
少年が退部できたのは、卓球部が少年にとって学校生活の基盤ではなくなっていたからだ。登校して地下の卓球場においてあったロッカーで上履きにはきかえ、時によっては、卓球のユニフォームに着替え、その上から学ランをはおってゆく日常がいつのまにか変わっていた。校長代行による授業時の上下制服着用の締め付けにより、着替えができなくなったことも小さな要因としてはあったかもしれない。いずれにしろ、いつのまにか卓球場によらない生活が普通になっていった。
卓球場が生活の場だったことで少年が思い出すのは、人類が初めて月に着陸した日のことだ。
地下の卓球場のいちばん奥に分厚い木製の引き戸が二枚あった。上部にはガラスが組み込んであったが、色がついており、向こう側が部屋があるのかどうなっているのかはうかがい知れなかった。
卓球場は、講堂の地下にあったので、不思議なものがいくつかあった。地上からおり中へ入ると右側にもっと奥へ続く通路があり、先の方は真っ暗で先輩のだれに聞いてもこの通路の先にいったひとはいなかった。講堂の真下に向かっているが、誰も気にしなくなっていた。
それと同じように、卓球場奥の引き戸のことも誰も気にしてはいなかった。
夏休みの午前の練習が終わった日のことだ。
練習ですっかり汗をかいて疲れた少年は、奥の引き戸に背中をもたれペタンと床に尻をつき足を延ばして休んでいた。まだ、元気な部員たちもおり、汗びっしょりのまま、卓球台で景気の良い音を響かせていた。
すると、突然、少年の背中が動き出し、分厚い引き戸がごそごそと開きはじめた。少年は、びっくりし、引き戸から少し離れ様子をうかがった。引き戸のなかから満面の笑みの用務員さんが現れた。なんとそこは用務員さん夫婦が生活する茶の間だった。
人類が月に着陸するのをテレビでやってるよ、と言われ、茶の間にあるテレビの画面を見ると確かに、その日の朝からテレビやラジオで騒いでいた人類初の月面着陸の中継画面だった。
用務員さんは、人類の月面着陸という歴史的な出来事の中継を卓球部員たちにも見せてあげようと開かずの引き戸を開けてくれたようだった。
開かずの引き戸から、用務員さんの茶の間が現れたのにはびっくりしたが、用務員さん夫婦のご好意に応えるべく、少年は、卓球場の床に座りこんだまま、世間話をしながら用務員さん家のテレビを一緒に見始めたのだった。
それは、妙な居心地だった。
卓球場の床にペタッと座って、左側を見ると、引き戸のなかの用務員さん家の茶の間でご夫婦でちゃぶ台を囲んでいるむこうではテレビが月面着陸を中継しており、右側の目の前では、この年の3月までキャプテンだったヤマグチさんがタッパのある体から汗をほとばしらせながら、豪快なドライブを声を出しながら卓球台に次々と叩き込んでいた。
やがて、人類初の月面着陸の中継は、最高のピークを迎え、月面に下り立った宇宙飛行士は、人類の月への第1歩を厳かに宣言した。そのとき、ロングで待ち受けていたヤマグチさんのからだが跳躍し、ラケットがボールをとらえると、ぐわぁーんと腕が振られ、腰が捻られ、鮮やかなスマッシュが、卓球台にバシッと決まったのだった。
こんな風景のなかにいて、少年は、卓球って面白いなという思いが唐突にわいてくるのを感じていた。
誰かが打った卓球のボールが、床の上をゆっくりと転がり、ペタンと座っている少年が投げ出している足に近づいてきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
