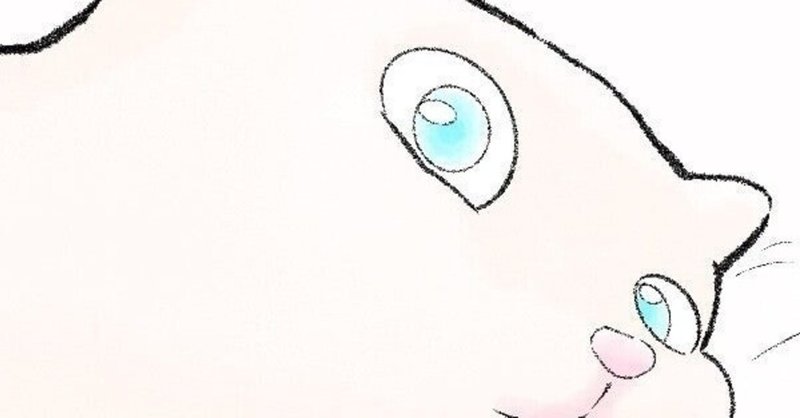
【読書日記】吾輩は猫から見た人間である(夏目漱石『吾輩は猫である』)
いつぞやも書いたが、自分が物を書きはじめたのは小学校四年生のときで、漱石の『吾輩は猫である』の真似をしたのが最初である。実は内容はほとんど理解できなかったのだが、猫の主観から世間を眺めるという視点が面白くて、そこだけ真似をしたのである。だけども、世間を知らない子どもがいかに世評をしようとしたって世評にならない。結局、マンガみたいな話にしかならなかった記憶がある。
とにかく、自分にとっては漱石はまず『猫』であった。あの漱石の顔はいつでも江戸っ子のひねくれた諧謔趣味と結びついていた。であるから、のちのもっと真面目で辛気臭い作品を読んでも、自分の漱石のイメージとつながらなかった。本当に同じ人が書いたのかと不思議であった。
このたび何十年かぶりに、この自分の物書きの原点を読みなおしてみた。子どものころ何度読んでもわからなかったのが、今では自分のことのようによくわかる。にやにや笑いながら読み進められた。おかしいことをおかしいと思うにはたいした修養はいらんものだと思っていたが、諧謔を理解するにはそれなりの知識が前提となるらしい。
それもそのはずで、『猫』にストーリーらしいストーリーはない。ただ英語教師の苦沙弥先生の家に寒月君、迷亭君、東風君、独仙君といった変人たちが集まって、とりとめのない話をしているだけである。その話が無駄に教養を身につけた人びとでなければわからない内容なのである。寒月君は物理学者の寺田寅彦がモデルらしいが、どうも迷亭君も独仙君も漱石自身の分身であるらしい。
変人といっても、みんな大学を出て学歴という文化資本を有したエリートである。知識人である。それが笑いの対象になるのは、そうした者の居場所が社会の方にまだ用意されてなくて「余計者」になるからである。
「余計者」という言葉は、元はツルゲーネフの小説に出てくる、情熱的な理想主義者であるが実践力に欠ける進歩的知識人を意味したらしい。当時のロシア社会では身の置き場のないツルゲーネフ自身の境遇が反映されている。ホフマンにやはり猫を主人公にした『牡猫ムルの人生観』という小説があって、『猫』は当時はこれと比較されたらしいが、むしろツルゲーネフの小説と比較した方がおもしろそうだ。
漱石は、余計者をツルゲーネフのように悲喜劇の英雄にしたてずに、猫に語らせることで諧謔とした。だが、この猫君がまた漱石の分身でもある。猫だからひとから侮られ軽くあしらわれている。でも、人知れず人間を観察し、人間について考え、妙に悟りを開いている。だがひとは猫語を解さないから、自分の知る真理を伝えることができない。ただひとりで得心してるだけで、まさに余計者なわけである。
漱石だって、自分や自分のような知識人をただ笑いものにしたかったわけではあるまい。だが、日本の余計者が、ロシアの余計者のように悲劇の英雄になれないのには、それなりの理由が考えられる。
まず第一に、近代化が遅れていた帝政ロシアと違って、さすがに明治の御代は文明開化の時代である。これを否定して、頭にちょんまげのっけて歩くわけにもいかない。彼らの精神が明治の啓蒙の賜物である。『猫』にも元旗本の家来だった迷亭君の伯父という人が出て来て、実際に頭にちょんまげを乗っけて歩いている。新しい時代にも動じずに古いものを守る頑固者で、苦沙弥君もちょっと羨ましく感じたりする。だけども、さすがにちょっと滑稽であって、今の時代の手本にならない。
だが、その明治のありがたい御代は、金田夫妻のような金満家が権勢をふるい、鈴木の藤さんのような利口者が出世する時代でもあった。文化にも教養にも関心を示さない俗物たちであって、金力と権力が人間の価値を決めると思ってる。金力も権力ももたない者をいじめることも当然だと思ってる。
そうやってみんなが世渡りのためにあくせくし、神経衰弱に陥っている。文化的な教養人は、苦沙弥君のように安月給で働かされてる。将来の金田君や鈴木の藤さんを多く育てるべくである。そうでなければ、寒月君のように研究室でガラス球を磨いていたり、迷亭君みたいに遺産を食いつぶしながらちゃらんぽらんに生きている。まだ太平の逸民であり高等遊民でさえない。ケーベル先生流の厭世観を身につけながらも、近代に背を向けられない以上、流されるしかない。
どうも文学者というのは近代の賜物であるが、同時に鬼子でもあって、その道義的な基盤が怪しい。近代化に貢献することを期待されながら、実は近代から距離をおいてる。実業家などの近代化の英雄をバカにしてる。だから世の中から重宝されない。頭がよければよいほど嫌われる。せっかくの頭脳を下らない遊びに費やしやがってと非難される。だが人語を話せない猫君のようにそれを聞き流せない。
この引け目が「太平の逸民」や「遊民」を主人公とする小説を書かせしめる。英雄ではなく諧謔の対象としてである。
『猫』が『ホトトギス』に連載されたのは1905(明治38)年の1月から1906(明治39)年の8月までであるが、それとほぼ平行して漱石は二年で7本の短篇や『坊つちやん』『草枕』『二百十日』『野分』を書いている。しかも東大と一高の英語講師をやりながらである。
もとより『猫』は『ホトトギス』の同人たちを相手に、余計者同士の身内ネタのような気軽な調子で書いたものらしい。それまでの漱石は日本の文壇には無縁の外国文学の文学者であった。ところが『猫』が評判になって、これが漱石の文壇デビューになってしまった。あちこちから原稿の依頼が来るようになって漱石は文句を言っているが、やはり嬉しかったらしくて、今まで抑え込んでいた創作意欲が一気に爆発したらしい。
自分が読んだ全集の解説によれば、『猫』の漱石が諧謔を好む現実主義者なら、短篇の方はロマン派詩人の顔を示している。本人曰く『猫』はスラスラ書けたが、こちらは相当言葉を選んで練った文章であるらしい。読むほうも『猫』はすらすらだが、短篇の方は時間がかかるものが多い。
内容も、アーサー王伝説に取材した西洋の中世を舞台にしたもの、恋愛が主題のものなど、ロマン主義の影響が強い。一目ぼれは過去の記憶が遺伝によって継承されたもの、というようなロマン主義的な似非科学を主題にしたものもある。小泉八雲などもどこかで書いていたから、当時流行した説らしい。後には漱石はそうしたものを一切書いてないから、ちょっと驚きである。
幻想的な内容であれば、別に日本を舞台としなくても書ける。日本の日常から小説になりそうな題材を探すという苦労はいらない。『草枕』の那美さんなども、いま読むと、男を誘惑するロマン主義的「魔性の女」の日本版という一面をもっている。そんな女を日本を舞台にして書くと淫売婦っぽくなるから、漱石は遺伝と不幸からちょっとおかしくなった山奥の良家の娘という、ちょっとありえないような設定にしなければならなかった。
だが、『二百十日』や『野分』あたりになってっくると、漱石は「非人情」の耽美主義から現実の社会の批評に移っていく。どうもイプセンなどの写実主義文学の影響らしい。文壇デビューを果たして日本の文学作品も目を向けるようになった漱石は、藤村の『破戒』(1906年3月)にも大きな衝撃を受けたようだ。
つまり、「余計者」は「人類の教育者」「社会改良家」に転身しはじめた。『猫』の登場人物のように世間に背を向けて雑談で無為に人生を費やすのでも、坊っちゃんのように反知性主義的な反抗で我を通すだけでもなくなってくる。物書きとしてやっていく自信をつけた漱石は、物書きの社会的使命というものを真剣に考え始めたらしい。
そういえば、『猫』も、最初は『ホトトギス』の同人の間で楽しむような諧謔文章が、終わりに近づくにつれて、文化を理解しない人間ばかりの社会でいかに生きてゆくべきかという真面目な主題がせり出してくる。だが余計者の無力を感じて気が塞いだ猫君は、最後には人間みたいに憂さを晴らすために酔っ払って、足を滑らせ甕に落ちて、自ら従容として死を選ぶ。いくら悟ったところで、ひとが自分の話を聴いてくれなければなんにもならない。そういう漱石自身の諦めが感じられる。そうやって余計者は葬られた。
そして、『二百十日』の圭さんは「革命」を口にし、『野分』の道也先生は文筆を武器に社会と闘う決意をしてる。彼らはもう諧謔の対象としては描かれてない。むしろ英雄に近い。ケーベル流の諦念ではなくイプセン流の社会的反抗やナロードニキ風の革命主義が前面に出て来ている。漱石でさえこうであったから、1910年の大逆事件が社会性に目覚め始めた文壇の出鼻をくじくことになったのは察するに余りある。
だが、興味深いのは、ケーベル流の人格主義もまた捨てられてないところである。トーマス・マンなどのドイツ文学と違って、漱石においては、文学者は市民と対立する芸術家であると同時に、道徳の教師でもある。社会が手本とすべき人間でもある。金もなく地位もない教師の武器は「人格」である。金も肩書もないが教養がある。いな、金も肩書もないからこそ、純粋に人格者である。世渡り下手なのは正直で嘘をつかないからである。誠実な人間であるからである。
これが国民の教育家としての資格を文学者に与える。金のことについては金持ちは一家言もっているだろう。だが人間に関しては、道徳に関しては文学者こそがプロである。だから道徳問題に関しては金持ちが文学者の言うことに耳を傾けるべきであって、その逆じゃない。こうしてケーベル先生の人格主義もまた社会改良にもち越されている。
これもドイツ以上に市民社会というものが未発達であった当時の日本の状況と関係してると思われる。トーマス・マンが回顧した19世紀の市民社会のようなものを日本は知らない。漱石においては、日本のブルジョアはみんな新興の俗物のように描かれてる。だから道徳的権威もまた芸術家の方に移っている。
だがその代償として、芸術学問もまた道徳化された。この後、初期の作品に見られたロマン主義的な耽美主義も世捨て人的諧謔も、漱石の作品では抑制されていく。漱石の諧謔を好む人には残念な事態であったが、問題はそれにとどまらなかったかもしれない。教養主義全体が笑いを忘れて、ちょっと辛気臭いものになっていくのも、このあたりの事情と関係していそうである。
ここから先は
¥ 100
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
