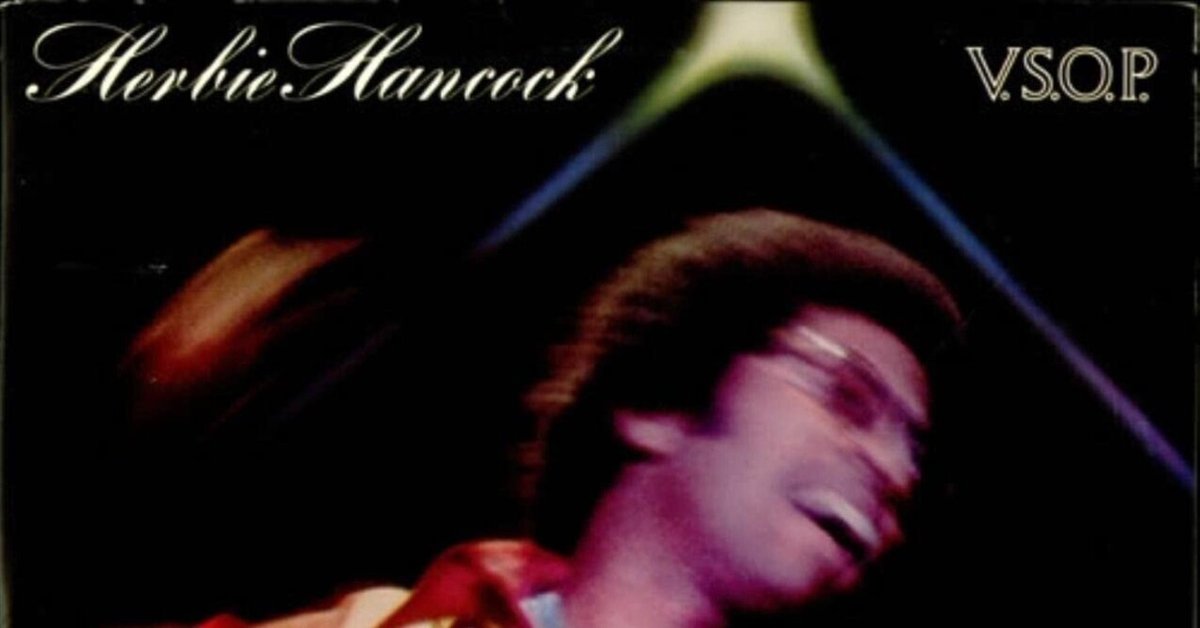
V.S.O.P./ハービー・ハンコック
ハービー・ハンコックの76年録音ライヴ・アルバム『V.S.O.P.』を取り上げましょう。
ライヴ録音:ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル、1976年6月29(火)
プロデューサー:デヴィッド・ルビンソン
レーベル:コロンビア
◉(1, 2, 3, 4) V.S.O.P.クインテット
(el.p)ハービー・ハンコック (tp, flg)フレディ・ハバード (ts, ss)ウェイン・ショーター (b)ロン・カーター (ds)トニー・ウイリアムス
◉(5, 6, 7) エムワンディシ・バンド
(el.p, Fender Rohdes, clavinet)ハービー・ハンコック (tp, flg)エディ・ヘンダーソン (alt-fl)ベニー・モウピン (tb)ジュリアン・プリースター (b)バスター・ウイリアムス (ds)ビリー・ハート
◉(8, 9) ザ・ヘッドハンターズ
(el.p, Fender Rohdes, clavinet, synth)ハービー・ハンコック (ts, ss, lyricon)ベニー・モウピン (g)ワー・ワー・ワトソン、レイ・パーカー・ジュニア (b)ポール・ジャクソン (ds)ジェイムス・レヴィ (perc)ケネス・ナッシュ
(1)ピアノ・イントロダクション (2)処女航海 (3)ネフェルティティ (4)プレイヤー紹介/アイ・オブ・ザ・ハリケーン (5)トイズ (6)イントロダクション (7)ユール・ノウ・ホエン・ユー・ゲット・ゼア (8)ハング・アップ・ユア・ハング・アップス (9)スパイダー

多くの名作を世に送り出したハンコック、本作は彼の諸作中とりわけモニュメンタルなライヴ・アルバムです。
ここではそれまでの総決算として、3つのセッションを企画しました。
一つ目は60年代ブルー・ノート・レーベルから『テイキン・オフ』『処女航海』『スピーク・ライク・ア・チャイルド』と言ったモダンジャズのエヴァーグリーンを発表、これらをベースにしたストレート・アヘッドなアコースティック・ジャズのコンセプトを再現したV.S.O.Pクインテット。
二つ目に70年代ワーナー・ブラザース・レーベルから『ファット・アルバート・ロトゥンダ』『クロッシングス』等の、マイルス・デイヴィス・バンドで体験したエレクトリック・サウンドを導入しつつジャズ・ファンクの路線を歩み始め、自身が率いたバンド、エムワンディシによるソウル、R&Bのテイストをベースにしたサウンド。
そして三つ目はコロムビア・レーベル移籍後73年に発表した名作『ヘッド・ハンターズ』、大ヒットを収め確固たる地位を築き上げ、ダンサブルなディスコ・ミュージックを、強力なグルーヴと高い音楽性で別次元にまで昇華させたバンド、ザ・ヘッドハンターズ。
数々の名演を生み出したニューポート・ジャズ・フェスティヴァル、ここでのオーディエンスの熱狂的なアプローズと、ライヴ・レコーディングならではの緊張感が相乗効果となり、ハンコックを中心としたメンバーは一丸となって演奏に臨み、素晴らしいパフォーマンスを繰り広げました。
おおらかに大きく音楽を捉え、共演者に基本好きに演奏させ、ある時は放し飼いの如きスタンスを保ちつつも、締めるところを確実に押さえる音楽性はリーダーとして理想と言え、包容力を感じさせる立ち振る舞いはミュージシャンはもちろん、周囲のスタッフ、ディレクターやプロデューサーからもさぞかし親しまれる存在だったでしょう。
一夜のコンサート中3つのバンドのリーダーを務め、それぞれ異なったコンセプトの音楽をハイクオリティさを保ちつつ、淀みなく次々と演奏出来る柔軟性とヴァイタリティ、タフさにはつくづく敬服させられます。

V.S.O.P.クインテットは、ハンコックの原点としてのフォーマットであるトランペット〜テナーサックスを擁する編成、彼の音楽性を開花させたマイルス・デイヴィス・クインテット、リーダーであるマイルスがフレディ・ハバードに、若しくは代表作『処女航海』でのジョージ・コールマンがウェイン・ショーターに代わった(リズムセクションはいずれもハンコック〜ロン・カーター〜トニー・ウィリアムス)メンバーによる演奏です。
付け加えるならばハンコックの64年作品『エンピリアン・アイルス』にショーターが加わった形とも言えますが、以降V.S.O.P.クインテットとして79年頃までレギュラー活動を続けます。
77年7月田園コロシアムで開催された第1回ライブ・アンダー・ザ・スカイにて、V.S.O.P.クインテットが出演し、日本のファンの前にその全貌を明らかにします。
バンドとして初来日の彼らのプレイの証人になるべく、私も会場に足を運びました。
超満員のオーディエンスの熱気が真夏の猛暑との相乗効果で、あり得ない温度と化しています。壮絶なテンションを有した彼らの演奏は、本作『V.S.O.P.』の時よりも緻密に、大胆さを増したように聴こえました。実際にかなりの数のギグをこなし、V.S.O.P.〜Very Special One-time Performance、名前に反し一度限りではないバンドとしての纏まりを身に付け始めていました。
ショーターの信じられないテナーの音色と孤高のプレイ、ハバードの絶妙なタイム感を駆使しつつ、いとも容易くトランペットを吹き切るテクニック、ハンコックの流麗にしてパーカッシヴ、かつ深い音楽性を内包したピアノプレイ、大柄なカーターの飄々とした中にもイマジネーションを感じさせるベース・プレイ、小柄なウィリアムスが黄色のツナギを着用し、同色グレッチのドラムセットを縦横無尽、かつ華麗に叩く姿、いずれもが大変印象的でした。
当時10代後半の私には演奏の中身や詳細は分からずとも、バンドが訴えかけるパッションと演奏の緻密さ、高度な音楽性に感銘を受けました。

次なるバンド、エムワンディシでの演奏経験については、ハンコックの自伝にもかなりのページ数を割き紹介していますが、それだけ彼にとって思い入れがあったバンドと言えます。
ハンコックには過渡期の演奏として位置し、ここで試行錯誤した経験を生かして、続くコロムビアでの成功を勝ち得たように理解しています。
3番目のバンド、ザ・ヘッドハンターズはブラック・コンテンポラリーの名手たち、グルーヴ・マスターを配し、キャッチーにしてダンサブル、ライヴでこれだけタイトなファンクを表現出来るのは、彼ら以外に有り得ません。

それでは演奏内容について触れていく事にしましょう。
1曲目ピアノ・イントロダクション、大歓声が静まり、徐にソロピアノ演奏からスタートします。
一聴ピアノ自体の音色が異なっています。エレクトリック・ピアノの音色とも聴こえますがフェンダー・ローズとは異なる、アコースティック寄りのサウンドを有します。
当夜の楽器はヤマハのエレクトリック・グランド・ピアノCP80、アコースティックとエレクトリック両方の性能を持ち、大音量の中でも確実にマイキング出来る特性を有するので、ザ・ヘッドハンターズのステージには打って付けの楽器です。
ハンコックがこのCP80を使っていた事でプレーヤーに影響を与え、日本人ピアニストも多く使用していました。運搬がまず不可能なグランドピアノと異なり、分解しての搬送が可能なのも魅力の一つで、フェンダー・ローズと並列させて演奏するプレイヤーもいました。
彼のサウンドには違いないのですが、グランドピアノに比べて陰影感が希薄というか、細かいニュアンスがあまり聴こえてきません。
個人的には大きなステージなので、グランドピアノも用意し、V.S.O.P.クインテットでは彼の素晴らしいピアノタッチも披露して貰いたかったですが。
例の印象的なイントロに続き、2曲目処女航海が始まります。オーディエンスは待ってましたとばかりに大きな声援で応えます。
おそらく他のメンバーはバックステージで待機していたのでしょう、彼らが現れた事による再度のアプローズも聴こえます。
通常冒頭のコードであるD9susでイントロを演奏しますが、ハンコックは緊張感を持たせるべく敢えて5小節目からのF9susのコードで開始し暫く継続、ベース、ドラムがスネークインし、D9susのコードを提示します。
トランペット、テナーサックスのユニゾンによるメロディが始まります。まずは独特の崇高さが提示されますが、同時にこれから繰り広げられるであろうジャズの真善美を暗示するサウンド感が提供され、身が引き締まる思いを抱かせます。
ハンコックはV.S.O.P.クインテットの船出に処女航海、全く相応しいナンバーをチョイスしました。
ソロ先発はショーター、60年代のマイルス・クインテットでの音色も素晴らしかったですが、また異なるコクのある漆黒、そして極太感を聴かせます。
当時の彼の使用楽器ですが、テナー本体はセルマー・マークⅥ、ゴールドプレート、マウスピースはオットーリンク・ハードラバー・スラント、オープニング10番、リードはリコ4番です。マイルス時代のマウスピースは同じくオットーリンクですがメタルを使用、ウェザー・リポート結成の頃よりハードラバーに替えた模様です。
歴代モダンジャズ・テナーサックス奏者の中で最も個性を有する一人、常にクリエイティヴで新しい世界を構築すべく、天から降りてくるサウンドを全身で享受するイタコ状態、斬新なプレイを聴かせます。
続くハバードのソロは端正な8分音符、リズムのスイートスポットに常にヒットさせるタイム感、デビュー時から確立された個性をここでも遺憾なく発揮し、パッショネートなフレージング、そしてグルーヴを提供、ソロがヒートアップするにつれリズムセクション、特にカーターが率先して倍のグルーヴであるサンバを仕掛けます。ウィリアムス、ハンコックはここぞとばかりにバッキングを繰り出し、有卦に入るように音楽を活性化させます。
ハバードは煽られつつも魅力的なフレージングを繰り出しバンドと一体化します。
これ以上はあり得ないと言うところでハンコックのグリッサンドと共に、元のリズムに戻ります。
ピアノソロはテナー、トランペットとソロが盛り上がり捲ったにも関わらず、委細構わずマイペースに展開します。ベースが再びサンバを提示しますが、追従するリズム隊はトランペットの時ほどにはハードなアプローチにはせず、常にクリエイティヴな彼らは瞬時にベストウェイをチョイスしています。
ピアノソロがディミヌエンドし、プレイがベースにフォーカスされると敢えてでしょう、再度サンバのグルーヴを聴かせます。カーターならではの興味深い表現方法です。
その後ウィリアムスのリムショットが一音、場面を刷新させるべくプレイされ、イントロのパターンに突入します。
ラストテーマはそれまでに起こった事象の数々を踏まえ、様々な色彩が施されたカラーリングが聴かれます。ショーターはソプラノを用いて違ったテイストを持ち込んでいます。

3曲目はショーターのナンバー、ネフェルティティ、古今東西数多く存在するジャズ・チューン中、難曲の筆頭に挙げられます。ここではマイルスのオリジナル演奏フォームに準拠し、テーマのメロディを多少のフェイクを交えてひたすらループします。
ですのでインプロヴィゼーションは聴かれず、リズムセクションが様々なカラーリングを施し、延々とテーマが演奏されますが、実に多様な表情を演出します。
ネフェルティティという荘厳にして気高いナンバーだからこそ、成り立つ技法と言えましょう。

4曲目はプレイヤー紹介/アイ・オブ・ザ・ハリケーン、ハンコックによるミュージシャンの紹介、そして各々の短いソロをフィーチャーした顔見世興行的プレヴューが聴かれますが、枕詞ザ・グレーテストを含めたハンコックの名調子が会場の雰囲気を盛り上げます。こちらは歴史的語り口と言って良いでしょう。
ウイリアムスはタム回しのソロからシンバル・レガートをプレイします。リズムのシャープさは言うまでもありませんが、音符の密度が尋常ではありません。
続いてカーターのウォーキング・ベースが始まります。お馴染みの彼のラインではありますが、ウィリアムスのシンバルとの合致度が素晴らしく、人間が発するリズムが合わさる事によって生じるグルーヴのロールモデルと言えましょう。ベースとドラムの理想のコンビネーションの一例でもあります。
ハバードのブリリアントなトランペットソロが始まります。管楽器奏者でありながらリズム隊と同等のビート感を提示し、ベース、ドラムとの抜群のグルーヴを聴かせます。
盟友ショーターの紹介にはハンコックも一層気持ちが入ります。既にプレイのテンションが高まっているショーターの咆哮に、ウィリアムスが噛み付くようにレスポンスします。
その後ハンコックがリズミックなヴァンプを演奏し、テーマが始まります。タイトルと曲想が合致した名曲、テーマのフォームとしてはマイナー・ブルースですが、アドリブはワン・コードで行われています。
先発のハバードはスペースをたっぷり取りつつ、アグレッシヴかつイマジネイティヴなプレイを展開します。
それにしてもハンコックのバッキングの物凄さ!付かず離れずを基本としつつ、天から舞い降りてくるイマジネーションを、何の躊躇もなく鍵盤にぶつけています。
ウィリアムスは極力ハンコックのプレイと被らない配慮を感じさせながら、しかし確実にハバードのソロへのレスポンスを怠りません。
これらが成り立つのは文字通り縁の下の力持ち、カーターのベースの驚異的なサポートがあっての事です。
さあ、次はショーターの出番です。漆黒の音色を湛えたテナーソロは表現内容が他のあらゆるプレーヤーと異なって聴こえます。一聴モノローグのようでいて、共演者に対するアピールが凄まじく、ハンコックのバッキングもフレディの時とは異なったテイストを表出させています。
自ずとウィリアムスのドラミングのアプローチも手法を異にしますが、淡々と凄まじいウォーキングを続けるカーターのプレイにも否応なしに耳が傾きます。
テナーソロが暫く続いたのち、ショーターがオフマイクになり、突如としてソプラノに持ち替えます。
ここでは場面転換を図るべく、ドラムがそれまでに無いカラーリングを聴かせ、ハンコックのバッキングも趣を異にします。
はっきりとは断言できませんが、テープ編集が行われているように感じます。ほとんど何の澱みもなく音楽は流れていますが微妙な違和感を覚えるのは、テナーからソプラノに持ち替える際に、実際にはもっとスパンがあったのをテープをカットして縮めたのではないかと。
状況としては一旦オフマイクになったにも関わらず再びテナーでのフレーズが一節あります。この点も不可解ではありますが、さらにその後僅か1, 2秒でソプラノにチェンジします。これはどう考えても物理的に不可能な次元、ソプラノをサックス・スタンドに立てておき、テナーを首からぶら下げたままの状態で持ち替えたとしても、この短い間では無理があります。
ショーターの真横にソプラノを携えた誰かが居て、すぐさま楽器を彼に渡せば瞬時の受け渡しが可能ではありますが、ひょっとしてハバードがその役割を担ったかも知れません?
謎多きジャズ史の中でもあまり語られる事が無い一件ですが、テナー、ソプラノを演奏する自分にとっては魚の骨が喉につかえたかの気になる案件です。当夜の詳細について細かく書かれた文献があれば是非とも読み、この持ち替え事件についてを知りたいところです。
持ち替わったソプラノのソロが開始されます。極太さと音の輪郭の明瞭さ、付帯音のあまりの豊かさから、ソプラノサックスという楽器の範疇を超えた存在です。ピアノとドラムが消え、ベースとのデュオになりソプラノの存在感がグッと増します。
ショーターの多様な成分が含まれるソプラノ音色のうち、可憐さを感じさせるトーンが主体となりソロは収束を迎えます。この音色は彼の75年作品『ネイティヴ・ダンサー』でも聴くことが出来ます。

ソプラノに被りながらピアノソロが始まります。ジャズの森羅万象が全て語られているかの様な猛烈なプレイ、ストーリー、物凄い音楽性です!
ドラム、ベースの二人は敢えて何もせずにハンコックのプレイを放置しています。この辺りは長年の共演歴による阿吽の呼吸、時たま繰り出されるフィルインが効果的にサウンドします。
一体どこまで行くのだろう、と感じさせたソロは次第にディミヌエンドし、ベースとドラム二人の世界になります。カーターのクールなウォーキング・ソロ、徐々にウィリアムスがフレーズを叩き始め、ドラムソロへ。フロント陣があまりにも壮絶な世界を構築してしまったからでしょう、ウィリアムスはコンパクトな演奏に纏め、いつものお決まりフレーズを提示してベース、ドラムを呼び込みます。その後ラストテーマがプレイされFineです。
5曲目トイズはスピーク・ライク・ア・チャイルド』収録のナンバー、こちらと7曲目はエムワンディシ・バンドによる演奏になります。

司会者の紹介があり、ビリー・ハートのブラシワークを伴いバスター・ウィリアムスのベースソロが始まります。カーターのプレイと似たスタイルですが、より粘っこさを感じさせます。
ハンコックがフェンダー・ローズでテーマの印象的な3連符を提示し、トイズが始まります。トランペット、アルトフルート、そしてベースとバストロンボーンのアンサンブルが魅力的ですが、全体的にバタバタした感じを受けます。
ハートのフィルインにいつに無くウィリアムスのテイストを感じるのは、本演奏前に本人の演奏を目の当たりにしてしまったからかも知れません。
ソロの先発はハンコック、ここでもアイデア満載のプレイを披露しますが、V.S.O.P.クインテットよりもバンドの一体感が希薄に聴こえるのが残念です。
エディ・ヘンダーソンのソロに続きます。いつもは自己の世界をしっかりと構築できるプレイヤーですが、こちらもハバードのプレイを目の当たりにし、その猛烈さと迫力に押され、気後れ気味でプレイに臨んでいたからでは、と推測しています。
その後ウィリアムスのベースソロに続き、ラストテーマへ。ヘンダーソンだけではなく、ハンコック以外のメンバー全員萎縮気味に演奏していると感じるのは私だけでは無いはずです。
6曲目に該当するイントロダクション、バンドをハンコックが紹介しますが、V.S.O.P.クインテット紹介の枕詞がザ・グレーテストだったので、ここではザ・ファイネストを用いるのが洒落ています。
トロンボーン、ジュリアン・プリースター、トランペット、フリューゲルホーン、エディ・ヘンダーソン、テナー、ソプラノサックス、アルト・フルート、バスクラリネット、ベニー・モウピン、ベース、バスター・ウィリアムス、ドラム、ビリー・ハートらを丁重に紹介しています。
7曲目ユール・ノウ・ホエン・ユー・ゲット・ゼアは、71年作品『エムワンディシ』収録のナンバーです。レイジーでありながらスピリチュアルなテイストを内包したサウンドは、このバンドのカラーを良く表しています。
エフェクターを施したトランペット・ソロ、リズムセクションのアクティヴさ、キーボードを駆使したサウンド・エフェクト、スリリングなアンサンブル、音楽的に高度な内容を表現していますが、メリハリがあって主張が明確な二つのバンドに挟まれての、難解さの表出は否めません。
しかしこちらもハンコックの有する多様な音楽性の一つには違いなく、コンサートに於いて彼の全貌を明らかにした点を高く評価したいと思います。
8曲目ハング・アップ・ユア・ハング・アップス、75年録音『マン・チャイルド』収録のナンバー、ここからはザ・ヘッドハンターズの演奏になります。

ギターのグルーヴィーなカッティングから始まります。ザ・ハービー・ハンコック・グループ、と熱のこもった叫ぶかの如き紹介がありますが、この声の主はポール・ジャクソンではないかと睨んでいます。これは私が彼と何度か共演した印象に依りますが、MCも達者なベーシストでした。
ハンコックがメンバーをひとりずつ呼び上げます。ザ・グレーテスト、ザ・ファイネストと用いてしまったからでしょう、流石にここで枕詞は使われていません。
以下ギター、ワー・ワー・ワトソン、ベース、ポール・ジャクソン、ギター、レイ・パーカー、ドラム、ジェームス・レヴィ、パーカッション、ケネス・ナッシュ、と紹介がありますが、この時点でバンドのグルーヴは既に頂点を極めたかのよう、ビート感が実に素晴らしく、座っている椅子から無意識に腰が浮き、リズムを取ってしまいます。当時ハンコックが憧れていたスライ・ストーンやジェームズ・ブラウン(JB)のバンドの如き、ダンサブルな様相を呈しています。
最後にサキソフォン、ベニー・モウピンと紹介があり、すかさずテーマが始まります。ハンコックらしい親しみ易さを有するキャッチーなメロディ・ライン、しかし同じ音が続くためにサックス奏者はタンギングに難儀しますが、モウピンも実際もつれ気味にソプラノをプレイしています。
ヴァンプ部分の躍動感、ブレーク部分を設け、ワトソンによる人間技とは思えないタイトなカッティングは場面をさらに活性化させます。
その後も二人のギタリストによるカッティング、ジャクソンのアクティヴなベースプレイ、レヴィのヘヴィかつどっしりとしたタイム感を持つドラム、ナッシュのカラフルなパーカッション、ハンコックのクラヴィネットらが織りなす、緻密にして荘厳、巨大な壁の如き音塊が続きます。
バンドが若干音量を落としてモウピンのテナーソロが始まります。本作2度の出演者はハンコック以外彼だけ、信頼ぶりが伺えます。
ショーターとは全く異なる音色ですがバランス感を伴った素晴らしいトーン、柔らかさとコクがブレンドし、とても魅力的です。比較的狭目のオープニング・マウスピース、リードも中庸のものを使用している節を感じます。
間を多く設けたソロのアプローチは、リズム隊の繰り出すリズミックなバッキングを映えさせます。時たまワウ音が聴かれるのでエフェクターを用いてプレイしているようです。
テナーソロが次第に熱を帯び、それに連れリズムセクション6人が多種多様な音を発しますが互いを聴き合ってのアンサンブル、全く過剰にはなりません。
とりわけジャクソンの自由闊達なアプローチによるベース・ワークが、ギターカッティングや打楽器系のバッキング・リズムの縦のアクセントに対する、横への流れを構築し、縦横で織りなす繊維の如き一体感を作り上げています。
その後ヴァンプが演奏され、ヒートアップしますがバンド自体の音量が大きいのか、テナー自体の音量の小ささによるものか、恐らく両方が作用しモウピンのプレイは埋もれがちに聴こえます。
ピークに達したところで全員がブレーク、ワトソンのカッティング・ソロになります。冒頭のカッティングよりもリズムがややラフなのは、演奏中に色々と技を繰り出したためでしょうか。
その後ベース、ドラムが戻り、クラヴィネット他が復帰しテーマを再演、異なったセクションを経てフローティングなパートでハンコックのソロが始まります。後ろで鳴るシンセサイザーが効果的です。ミステリアスささえも感じさせるこのパートは同じくハンコックのナンバー、カメレオンの中間部分を連想させますが、次曲での本人フィーチャーを踏まえたのでしょう、比較的短く纏められ、エンディングへと雪崩れ込みます。

声援が収まり、曲続きのように9曲目スパイダーが始まります。こちらもギターのカッティングから始まるダンサブルなナンバー、曲構成もかなり凝った作りになっています。
演奏中もギタープレイが重要なファクターとなっており、カッティングの他にワウを掛けたラインでの対旋律的なアプローチ、ベースとギターのユニゾンも効果的に用いられています。前曲以上にジャクソンのベースが活躍し、グルーヴ設定の要となっています。
ジェイムス・レヴィのドラムもバンドの重要なファクター、拍が長くビートを的確に刻むタイトなドラミングは、このバンドに相応しい存在です。
パーカッショニストも参加しているのでカラーリングは彼に任せ、レヴィは主にリズムを確実に提供する役割を担っています。
大きなストロークを感じるスティック捌きから背の高い、手足の長いドラマーと推測する事が出来ます。
全く同じメンバーで録音されたアルバム『シークレッツ』での収録曲がオリジナル演奏になります。

本演奏ではハンコックのソロを大きくフィーチャーしますが、ステディなリズムセクションに対し、ハンコックは幾分オントップにプレイしています。ミディアム・テンポのスイング・ビートではレイドバックし、イーヴン系のファンクでは少しだけ前にビートの位置を設定する、リズムのスイートスポットの使い分けはジャズ表現の大切な要素の一つです。
バッキングの集合体による複雑なリズム塊に、ハンコックの更にリズミックなソロが分け入り、これはもうポリリズムの坩堝、リズムの饗宴、この演奏を聴きながら踊る人達にとっては超濃密なリズムゆえ、寧ろ踊り易いかも知れません。
スライやJBのバンドもダンサブルですが、流石にここまでは白熱しませんでした。
盛り上がりに盛り上がったハンコックのソロ後、トリッキーなシカケがふんだんに施された、それでいてメロウでキャッチーなテーマがプレイされ、Fineを迎えます。
ザ・ヘッドハンターズによる2曲はプレイヤーが演奏を存分に楽しんでいる様が特に伝わって来ます。これこそハンコックの仕切りがなせる技でしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
