
Pop Pop / Rickie Lee Jones
今回はシンガーソングライターRickie Lee Jonesの1991年リリース作品「Pop Pop」を取り上げてみましょう。
Recorded: Toping Skyline Studio 1989 Produced by Rickie Lee Jones and David Was Label: Geffin
vo, ac-g)Rickie Lee Jones ac-g)Robben Ford ac-b)Charlie Haden, John Leftwich bongo, shakers)Walfredo Reyes, Jr. cl, ts)Bob Sheppard ts)Joe Henderson bandoneon)Dino Saluzzi vib)Charlie Shoemake violin)Steven Kindler ac-g)Michael O’Neil hurdy-gurdy)Michael Greiner backing vocals)April Gay, Arnold McCuller, David Was, Donny Gerrard, Terry Bradford
1)My One and Only Love 2)Spring Can Really Hang You Up the Most 3)Hi-Lili, Hi-Lo 4)Up from the Skies 5)The Second Time Around 6)Dat Dere 7)I’ll Be Seeing You 8)Bye Bye Blackbird 9)The Ballad of the Sad Young Men 10)I Won’t Grow Up 11)Love Junkyard 12)Comin’ Back to Me
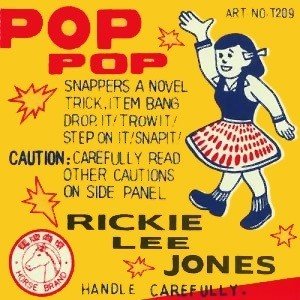
Rickie Leeは70年代後半から活躍する米国のロック、ポップスシンガーです。独自のセンス、音楽観を持った芸風には僕自身ずっと好感を持っています。この作品はスタンダード・ナンバーを中心に取り上げたジャジーなテイストを感じさせる、Rickie Leeにとって初めてアルバムになります。彼女に限らず昔からジャズ以外のフィールドのシンガーがジャズ・アルバム制作を行う事は少なくありませんが、多くの場合枠組みだけはジャズボーカルとしての範疇にあるけれど、中身が異なった風で何かが違う、歌唱力はあるけれど訴えかけるものやセンスに違和感や物足りなさを覚え、鯔のつまりジャズボーカルのハードルの高さを再認識させられる結果となりました。きっとロック、ポップス・シンガーはジャズへの憧れがあるものなのでしょう。この作品は参加してるジャズ・ミュージシャンの素晴らしさや選曲にバックアップされて、ロックシンガーとしては異例とも言えるジャズアルバムに仕上がっていると感じますが、Rickie Leeのコケティッシュでレイジーな歌唱スタイル、鼻が詰まったようなこもった成分が聴かれる声質(こんな声で歌うボーカリストは他には存在しません)、そしてほのかに感じさせる彼女の持つジャズシンガーの素養が合わさった結果、不思議なバランス感を持ったジャズ作品として成り立っています。89年リリースDr. Johnの作品「In a Sentimental Mood」収録のMakin’ Whoopee!にRickie Leeがゲスト参加し、Dr. Johnのアクの強い、やさぐれた歌声と彼女のカマトトチック(笑)なボーカルが絡み合い、互いにインスパイアし、そこにRalph Burnsのゴージャスなビッグバンド・アレンジがスパイスとして加味された素晴らしいテイクに仕上がっていますが、同年のグラミー賞最優秀ジャズ・ボーカル・パフォーマンス賞に輝きました。ここでの成功が本作制作へと繋がっているように思います。

遡ってRickie Lee83年の作品「Girl at Her Volcano」(邦題マイ・ファニー・ヴァレンタイン)でもLush Life, My Funny Valentine(いずれもライブ・レコーディング音源)と言ったスタンダードを取り上げていますが、本作で聴かれる歌唱スタイルの萌芽を十分に感じ取ることが出来ます。

本作参加メンバーで重要な役割を担っているのがRobben Ford、殆どの収録曲で全てアコースティック・ギターを演奏し、本来はフュージョンやスタジオ系のギタリストなのですが、スタンダード・ナンバーのバッキング、ソロでジャジーなテイストを存分に発揮しています。そして全曲ではありませんがCharlie Hadenのアコースティックベースのサポートが作品の品位を高め、Joe Hendersonのテナーサックスがジャジーな色合いをより濃厚なものにしています。ドラムレスという編成もアコースティック楽器の音色を際立たせる上で良い采配であったと思います。本作プロデューサーのDavid WasによればMiles Davisの起用も検討されたそうですが、ギャラの高額さから断念され(残念!でも一体幾ら吹っ掛けられたのでしょうか?)、Freddie Hubbardにも参加をオファーしたそうですが実現は叶いませんでした。
それでは本作収録曲について触れて行きましょう。ジャケットデザインも彼女らしい可愛らしさとコーニーな雰囲気がよく出ています。1曲目数多くのジャズミュージシャン、シンガーによる名演奏が目白押し、定番中の定番ジャズバラードMy One and Only Love、Rickie Leeはそんな数多の名演奏を全く関知しないかのようなマイペースさで歌い上げています。存在する名演を気に掛けていたら自分の歌唱は一切出来なくなりますし。Fordのアルペジオによるイントロ、曲中のバッキング、ソロで彼への評価を全く新たにしてしまうほどに美しいサウンドを聴かせます。Hadenの地を這うようなボトム感満載のベース、Dino Saluzziのバンドネオンでのカラーリングの巧みさ、異なるフィールドのミュージシャンが集い、静かな異種格闘技とも言えるインタープレイを楽しみましょう。
2曲目もバラード・ナンバーSpring Can Really Hang You Up the Most、個人的に大好きなナンバーで、本作購入のきっかけとなりました。Rickie Leeがこの曲をどう歌うのか、興味津々で作品に臨みましたが想像以上に一つ一つのセンテンスを丁寧に、情感たっぷりに、強弱を強調しつつ様々にイントネーションを効かせ、気持ちのこもった深い歌唱を聴かせています。1コーラス丸々歌いっきり、FordとHadenの素晴らしいサポートがあってこそですが素晴らしいテイクに仕上がりました。
3曲目はOn Green Dolphin StreetやInvitationの作曲者として名高いBronislaw Kaper52年作のナンバーHi-Lili, Hi-Lo、1曲目と同じメンバーによる演奏です。アコースティックギターのイントロから始まり、録音自体も実に臨場感溢れています。バンドネオンのDino Saluzziのサウンドが心地良いです。彼はアルゼンチン出身でAstor Piazzollaの影響を受けたプレイヤーですが、独自のスタイルを築きジャズマンとの交流も深く、かのECMレーベルから13枚もリーダー作をリリースしています。同じアルゼンチン出身のGato Barbieriの73年作品「Chapter One: Latin America」に参加し脚光を浴びました。

4曲目はロックミュージシャンのオリジナルからJimi Hendrix 67年のUp from the Skies、ベーシストがJohn Leftwichに替わり、Fordの他にMichael O’Neillのアコースティックギターも加わり、スインギーなグルーヴを聴かせます。Gil Evansの74年作品「The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix」でも取り上げられています。

5曲目はSammy Cahn, Jimmy Van Heusen黄金の作詞作曲コンビによるSecond Time Around、60年の映画「High Time」の挿入曲です。Ford, LeftwichにSteve Kindlerのバイオリンが加わった、意外と多くのジャズメンに取り上げられている隠れた名曲です。アコースティックギター・ソロのバッキングで聴かれるバイオリンの美しいカウンター・ライン、ソロ、KindlerはOregon州出身、The Mahavishunu Orchestra, Jan Hammer, Jeff Beck, Kitaro達との共演歴を持つバイオリンの名手です。彼らをバックに彼女はキュートに、感情移入が素晴らしい歌唱を聴かせています。

6曲目はBobby Timmons作の名曲Dat Dere、歌詞はシンガー・ソングライターのOscar Brown, Jr.によるものです。作曲者自身の60年初リーダー作「This Here Is Bobby Timmons」に収録、加えて当時参加していたArt Blakey and the Jazz Messengersの「The Big Beat」でも同年録音されています。


ここではFord, Leftwichに加えJoe Hendersonのテナーサックス、Walfredo Reyesのスネアドラムとボンゴ、プロデューサーWasのバックグラウンド・ボーカルが参加します。本作ハイライトの1曲、Rickie Leeの持ち味や声質と楽曲、メンバーとの巧みなコラボレーション、プロデュース力で名演が生まれました。冒頭部から曲中、エンディングまで赤ん坊の楽しげな声がオーバーダビングされていますが(これがまた実に効果的に使われています)、それもその筈タイトルのdatはthat、dereはthere、どちらも舌足らずな子供たちが使う赤ちゃん言葉、この曲の歌詞はママを質問攻めにして困らせている女の子が主人公なのです。そんな彼女も大人になり恋をして結婚し、子供が出来て母親になります。因果は巡り今度は自分の娘から質問攻めに合う立場になり、ゾウが好きな子の子供もゾウさんが好き、という内容です。ボーカリーズの初演Oscar Brown, Jr.の際の歌詞はdaddyと呼びかける男の子のヴァージョンでした。この曲の初演が収録されている「This Here Is Bobby Timmons」の1曲目、This Here → That There(Dat Dere)と対を成している訳ですね。余談ですが、かつて僕が参加していたドラマー日野元彦(トコ)さんのバンドSailing Stoneで、トコさんのオリジナルIt’s Thereという曲を事ある毎に演奏しましたが、本人曰く「この曲はTimmonsのThis Hereに肖って名前を付けたんだよ」との事でした。「The Big Beat」収録のヴァージョンではLee Morganがトランペットを演奏し、素晴らしい演奏を聴かせていましたがあいにくの故人、プロデューサーはJazz Messengers繋がりでFreddie Hubbardにこの曲を演奏させたかったためにオファーしたのかも知れません。何より本作の制作企画が持ち上がった時点で、真っ先にこの曲を取り上げようと目論んだような気がしてならないのですが、それほどにRickie Leeの魅力と個性、楽曲が見事に合致しています。
7曲目はSammy FainとIrving KahalコンビによるI’ll Be Seeing You、Ford, Leftwichのアルコ・ベース、Bob Sheppardのクラリネットというメンバーで室内楽的にコンパクトに纏められた演奏が聴かれます。
8曲目お馴染みのスタンダード・ナンバーBye Bye Blackbird、Miles Davisオハコの曲に彼自身が参加したらさぞかしの評判とクオリティの演奏になったかも知れませんが、ここではJoe Henが参加、むしろ適材適所な人選、演奏だと思います。ベースにLeftwich, Reyesはブラシに徹して伴奏、Fordは参加せずコードレスの演奏です。Joe Henが全編に渡り素晴らしいオブリガートを聴かせ、そのラインからコード進行も十分に感じられ、そしてブッ飛んだ間奏(歌番でこんなのアリですか?彼を起用するならアリですね!)を聴かせています。Rickie Leeこのテイクでは歌詞の内容を噛みしめつつ、歌うというよりも話しかける、更には叫んでいる風を感じます。
9曲目はThe Ballad of the Sad Young Men、2曲目Spring Can Really 〜と同じ作曲Tommy Wolfと作詞Fran Landesmanのコンビによるナンバーです。Ford, Haden, Saluzziが伴奏を務め、Rickie Leeが切々と若さ故の哀愁を歌います。Keith Jarrettも89年録音リーダー作品「Tribute」で演奏していますが、ここではAnita O’Dayにトリビュート、Gary Peacockのソロをフィーチャーし、Jack DeJohnetteと共に耽美的にリリカルに (むしろ凡庸な表現しか思いつかない程に素晴らしいのです!)演奏しています。

10曲目はまさしくRickie Leeにピッタリのナンバー、I Won’t Grow Up、お馴染みPeter Panからのセレクションです。歌詞の内容と彼女の持ち味が完璧にフィットしています。Ford, Hadenの他に男性ボーカルが2人バックグランド・コーラスで参加しており、Rickie Lee自身によるコーラス・アンサンブルのアレンジが施されていて、低音のボーカル・ハーモニーと彼女の声が対比となり、doo-wopのテイストも感じさせます。Fordのソロに被って口笛が聴こえますがRickie Leeによるものでしょう、歌唱同様にどこか危なげな音の発生、音程感から彼女らしさを感じますから。
11曲目Love Junkyardは本作中最も大きな編成での演奏、Ford, Leftwichの他Reyesのボンゴ、シェイカー、ビブラフォンにCharley Shoemake、O’Neillのアコースティックギター、Bob Sheppardのテナーサックス、Wasのボトル、ジャンク、そしてバックグランド・ボーカルというメンバーで、ボンゴとテナーのデュエットから始まります。演奏内容はこれまでの彼女の音楽活動で練り上げられたオリジナルなサウンドの延長線上が聴かれます。Sheppardのテナーにはオーバーダビングが施され、ハーモニーが鳴っていますが、Rickie Leeのアレンジによるものです。
12曲目Comin’ Back to Meは米国ロックバンドJefferson Airplaneの創設メンバーであるMarty Balin作のナンバーで、彼らの第2作目になる「Surrealistic Pillow」に収録されています。Leftwichのベース、Michael Greinerのhurdy gurdy(機械仕掛けのバイオリン)とglass harmonica(複式擦奏容器式体鳴楽器〜これは?)、Rickie Lee自身のアコースティック・ギターという編成で、フォーク・ミュージックのコンセプトで演奏されます。囁くような歌唱は本作中異彩を放っていますが、こちらも従来のRickie Leeのスタイルの延長線上にあります。後半で聴かれるシャウトでの気持ちの入り方に、彼女のロックシンガーとしての真骨頂を感じることが出来ました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
