
New Bottle Old Wine / Gil Evans
今回はアレンジャー、ピアニスト、作曲家Gil Evansの1958年作品、アルトサックス奏者Cannonball Adderleyをフィーチャーした名盤「New Bottle Old Wine」を取り上げたいと思います。
58年4月9日(tracks 1, 2, 5 & 6),5月2日(track 3), 21日 (track 4), 26日(tracks 7 & 8)NYC録音
Label : World Pacific Producer : George Avakian
p, arr, cond)Gil Evans as)Cannonball Adderley tp)Johnny Coles, Louis Mucci, Ernie Royal(tracks 1~3, 5 & 6), Clyde Reasinger(tracks 4, 7 & 8) tb)Joe Bennet, Frank Rehak, Tom Mitchell fr-horn)Julius Watkins tuba)Harvey Philips(tracks 1, 2, 5, & 6), Bill Barber(tracks 3, 4, 7 & 8) reeds)Jerry Sanfino(tracks 1, 2, 5 & 6), Phil Bodner(tracks 3, 4, 7 & 8) g)Chuck Wayne b)Paul Chambers ds)Art Blakey(tracks 1, 2, & 4~8), Philly Joe Jones(track 3)
1)St. Louis Blues 2)King Porter Stomp 3)Willow Tree 4)Struttin’ With Some Barbeque 5)Lester Leaps In 6)Round Midnight 7)Manteca! 8)Bird Feather
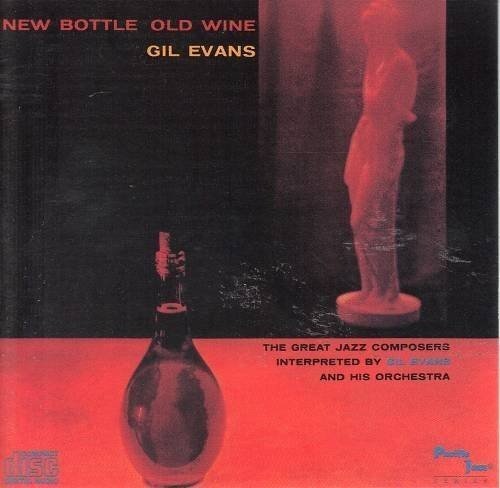
通常のビッグバンド編成とは異なるtubaやfrench hornを配したGil独特のアレンジ、ゴージャスで知的、細部に至るまで徹底的に配慮された気品溢れるサウンド、それらを活かすべく厳選して取り上げられたモダンジャズの名曲の数々、そして当時売り出し中のアルト奏者Julian “Cannonball” Adderleyをフィーチャリング・ソロイストに迎え、爽快感すら感じさせるほどに思う存分演奏させているエヴァーグリーンの名盤です。58年=モダンジャズ全盛期、演奏者、アレンジャー、編曲、選曲、プロデュースとパズルの全てのパーツが完璧に揃った、文句なしの1枚です。
本作のプロデューサー、ロシア出身のGeorge AvakianはColumbia Labelに於いてMiles Davisの55年録音「Round About Midnight」と58年録音「Milestones」のプロデュース、またMilesとGil Evansのコラボレーション作品57年録音「Miles Ahead」のプロデュースも手掛けました。ジャズ史に残る3枚の名盤の製作を行った訳ですが、続くやはりMilesとGilのコラボ作「Porgy And Bess」は以降のMilesの諸作をColumbia時代ずっと手掛ける事になる名プロデューサー、Teo Maceroに取って代わりました。Avakianは58年に在籍12年間に渡るあまりの多忙さからColumbiaを離職、その直後レコード会社としてはずっと小規模のWorld Pacificに招かれて移籍しました。しかし離れてはみたものの、Miles〜Gilのコラボレーションによる作品を再び製作したいと願っていたのかも知れません、レーベルが変わってしまえばそれは見果てぬ夢、レコード会社的にはフリーランス状態だったGilのアレンジメントは残しつつ誰か他のミュージシャンと組ませて作品を、ということで自らプロデュースした「Milestones」に参加していたCannonballに白羽の矢を立て、Avakianはこのアルバムを製作したのではないでしょうか。もしかしたら同じく参加していたJohn Coltraneにもオファーがあったかも知れません。
この作品はGilにとって2枚目のリーダー作、記念すべき第1作目は57年10月録音「Gil Evans & Ten」Prestige Label
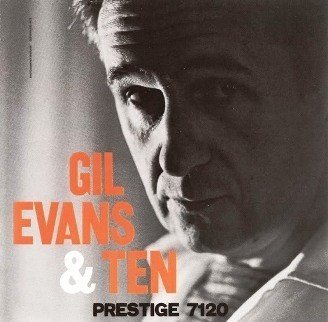
文字通り11人編成のアンサンブル、既にfrench hornが起用され他にもbassoonやSteve Lacyのソプラノサックスが参加し、8管編成ながらユニークな楽器構成による豊潤なGil Evansハーモニー、サウンドが聴かれます。「New Bottle ~ 」の方もCannonballを含めて10管編成ですが通常ビッグバンド編成〜管楽器13本に引けを取らない豊かで、むしろ個性的なサウンドが鳴っています。
フィーチャリングのCannonballも58年には「 Cannonball’s Sharpshooters」「Something’ Else – with Miles Davis」「Portrait Of Cannonball」「 Jump For Joy」「Things Are Getting Better – with Milt Jackson」と、何と5作もリーダー作を録音しており、まさしく破竹の勢いでした。CannonballはCharlie Parker系のアルト奏者とイメージされており、50年代から活動を続けているアルト奏者であればParkerの影響を免れることは難しい筈なのですが、彼の場合、むしろBenny Carterの音色やフレージング、センスに影響を受けていると思います。Parker没1955年、その直後にCannonballがデビューしたので、彼の後を継ぐアルト奏者としてイメージ的に同系列と捉えられたのでしょう。特にフレージングにはParkerのテイストを殆ど感じません。
ところでCannonballの音色の艶っぽさ、極太感は一体どこから来ているのでしょうか?良く抜けた明るい解放的な音色の中にも陰りやダークさを併せ持ち、音の立ち上がりの早い、楽器を自在に操る事の出来るテクニシャンにしてメロディを吹かせれば右に出るものはない歌心の持ち主。Coltraneと2管での演奏59年3月録音「Cannonball In Chicago」収録、ワンホーンでのバラードStars Fell On Alabama、ここでの演奏がCannonballの真骨頂です。
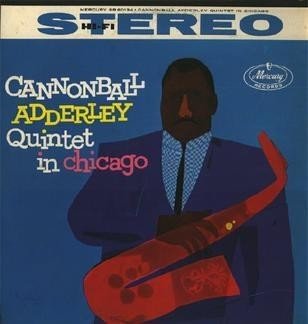
最低音部でのサブトーンを駆使しているので、テナーでの演奏と錯覚してしまうほどの低音の充実ぶり。多くのアルト奏者が中音域から高音域を中心にメロディ、アドリブを吹奏しているのに対し、Cannonballは低音域がメインのプレイヤーであることを確実に印象付ける素晴らしい演奏です。低音域重視のプレイヤーなので自ずと音色に極太感が伴い、サブトーンが充実しているので音の成分に艶っぽさが加味されるのです。この頃のCannonballのセッティング、マウスピースはMeyer Bros. New Yorkの5番、リードはLa Voz. Medium。楽器本体はKing Super 20 Silversonic。生音が相当大きそうに聞こえますが、Joe Hendersonと同じく生音は意外に小さくてガサガサ鳴っているタイプです。いわゆるマイク乗りの良い音、黒人プレイヤーに多いスタイルです。何十年か前に日本でCannonball、Charlie Mariano、渡辺貞夫さんの3アルトによるコンサートが開催されたそうです。前評判として「そりゃあCannonballの音が一番デカイに決まっているじゃないか、次がMarianoでサダオさんが一番小さいだろうね。」音量コンテストでもあるまいし、音の大きさでプレイヤーを評価するのはどうかと思いますが、レコードで聴いたCannonballの「鳴ってる」感、ジャケ写の巨漢ぶり、そのまんまが一人歩きしていたのでしょう。しかしいざ蓋を開けてみると、ダントツにサダオさんの音が大きく、次がMariano、演奏中に良く動くCannnonballはマイクからちょっとでも離れようものなら全く音が聴こえなかったそうです。Joe Henも演奏中良く動くプレイヤーだったので、全く同じタイプです。
Stars Fell On Alabamaのライブヴァージョンがこちらに収録されています。67 or 68年録音「Cannonball Adderley Radio Nights」。In Chicagoから10年を経てCannonball、音色がブライトになり、操る音域が若干上がったように聴こえます。Mercy, Mercy, Mercyの大ヒットでロック路線を歩み始め、バンドの音量が大きくなり、自身の音を良く聴くためにも自然と音域が上がって行ったのでしょう。
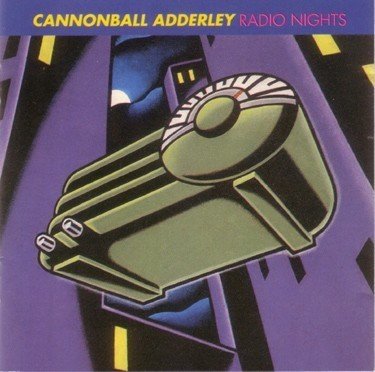
もう一つ面白いエピソードが、2009年にColumbiaからリリースされたMilesの59年録音「Kind Of Blue」50周年記念のボックスセット(大変豪華で充実した内容のセットです)に、未発表のスタジオ内でのミュージシャン同士のやり取りが収録されていますが、歴史的なレコーディング(演奏している最中はそんなことになるとはメンバー全員微塵も考えなかったでしょうが)で、何と言ってもMilesがリーダーのセッション、張り詰めた空気が漂い、緊張感が半端ないはずですが、Cannonballは何とSo Whatのテーマの何かに引っ掛けて「With A Song In My Heart」の冒頭のメロディを歌詞付き歌っているのです!根っからのハッピー・ガイ、サウンドや演奏に確実に表れています。
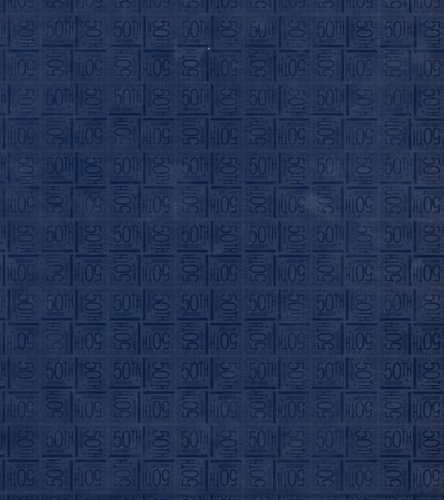
「New Bottle Old Wine」の意味するところは新しいボトル(アレンジ)に入った古いワイン(曲目)、Gilの素晴らしいアレンジ、Cannonballの実に的確な演奏により昔の曲が全く新しく再生されています。その収録曲について触れて行きたいと思います。1曲目St. Louis Blues、W.C.Handy作詞作曲による名曲、多くのミュージシャンにカヴァーされています。Cannonballのアカペラによるイントロから始まりますが一体何という音色でしょうか!まさしく正統派アルトサックスそのものの音色なのですが、一聴してすぐCannonballと分かる、音の成分が全て洗練され、雑味の入り具合、配合、バランスが絶妙に整い、あたかもオールド・ワインの如き味わいです!スローテンポになるとアンサンブルが加わり、Cannonballが早めのテンポで吹き始めて曲の本編が開始されます。ソロのフレージングの合間に、うまい具合にアンサンブルが入り、ソロと呼応しているかの如くです。エンディングのギターをフィーチャーしたフェードアウトもオシャレです。
2曲目King Porter StompはピアニストJelly Roll Mortonのナンバー、1905年作曲、23年に本人により初めてレコーディングされました。Cannonballの持ち味と合致した明るい雰囲気のナンバーです。ラグタイム風のテイストを随所に入れながらのアンサンブル、その後Cannonballのソロが進み、引き続いて1’54″から今度はCannonballがアンサンブルのリードに回るのですが、この時の音色が堪りません!昔風のヴィブラートを深くかけながらニュアンスたっぷりにリード=主旋律を吹くこの部分が大好きです!その後アンサンブルをバックに再びソロを取ります。3’17″と言う短い演奏時間の中にあらゆる音楽的現象が凝縮されているかのような凄い演奏です。Gilの76年の作品「There Comes The Time」に於いてもDavid Sanbornをフィーチャーして再演しています。
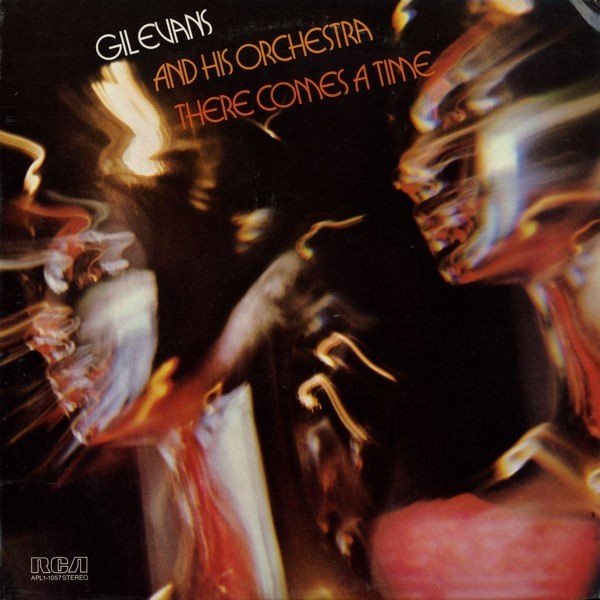
3曲目はFats WallerのWillow Tree、アンサンブルのダイナミクスが素晴らしいです!この日のCannonballは絶好調で、ミディアムスローのテンポでもスインギーな演奏を聴かせます。続くJohnny Colesの味わいのあるトランペットソロもイケてます。最後までとことんサウンドの強弱が徹底した演奏です。因みにこの曲のみドラマーがPhilly Joe Jonesに変わっています。ひょっとしたらPhillyのドラミングによるダイナミクス付け、Gilに買われて呼ばれたのかも知れませんね。
4曲目Louis Armstrong作になるStruttin’ With Some Barbecue、tubaに冒頭のメロディを吹かせるアイデアは流石です。Frank Rehakのトロンボーンソロの後、アンサンブルによるテーマ奏、その後のブレークから4小節のCannonballのピックアップソロが始まりますが、ブレーク前は曲のキーがFでしたがピックアップソロの最中に短3度キーが上がり、A♭に転調しているのです!Cannonball実に巧みにフレージングしています!これにはやられました!何とさりげにしてスリリングなのでしょう!On Green Dolphin Streetの引用フレーズの後、トロンボーン・セクションによるlow A♭のペダルトーンが50秒近く演奏されます。3人で順繰りにブレスをしながら音を継続させていましたが、演奏終了後トロンボーン奏者たちは「まったくGilは人遣いが荒いな〜」と話していたに違いありません(笑)
以上がレコードのSide A、5曲目はLester Youngの名曲Lester Leaps In、Art Blakeyは水を得た魚のように素晴らしいドラミングを聴かせています。ドラムのフィルインでは感極まってBlakey声を発しながら叩いています。この曲は他の収録曲に較べて比較的ストレートに演奏されていますが、ブラスのアンサンブルはかなり難易度が高そうに聴こえます。Chuck Wayneのギターソロ、再びRehakのソロも聴かれます。Gilのアレンジは細部にまで気配られていますが、エンディングの処理の仕方に特に音楽に対する情熱、愛情を感じます。
6曲目はThelonious Monkの代表曲バラード’Round Midnight、冒頭Gil自身がピアノでテーマを演奏する意外性、アンサンブルによるメロディのサポート、その後Cannonballのソロ、アンサンブルでは随所にTubaが活躍します。
7曲目は曲続きでDizzy GillespieのManteca、本作中白眉の名演、名アレンジです。フルートやギターのトレモロがサビのメロディを演奏して曲開始のムードを高めます。アンサンブルによるストロングなテーマ奏、対比するかのようにサビのメロディをCannonball実にスイートに吹いています。ここで聴かれるCannonballのソロは、そのクリエイティヴさからジャズのスピリットが降臨したかの如き、手のつけられない程の素晴らしさを提示しています。アンサンブルとのコール・アンド・レスポンス、テーマでは再びフルート奏によるサビのメロディ、その上でベースソロが聴かれます。エンディングには超絶技巧が要求されるアンサンブルが待っていました。当時は録音上の間違いを訂正するパンチイン、パンチアウトなどのレコーディング・テクニックは有りませんでしたから、一切間違いは許されません。とてつもないアンサンブル能力、技術、集中力が要求されました。そう言った意味で昔のミュージシャンの方がスキルが高かったかも知れません。
8曲目ラストを飾るのはブルース・ナンバー、 Charlie Parkerの名曲Bird Feathers、こちらも凝りに凝ったアレンジです!Blakeyによるブラシによるメロディ奏後、各楽器が次第に参加し、更にトロンボーンとベースのアンサンブルがサウンドに深みを加えます。Cannonballのソロの後半からアンサンブルが始まり、Rehakのトロンボーンソロでも随所にアンサンブル、Parkerのソロフレーズによるソリまで聴かれ、てっきりRehakのソロフレーズかと思いきやそのままトロンボーン・アンサンブルに突入、Colesのトランペットソロに続き、その後ドラムソロ、ここでもアンサンブルとのやり取りが有り、ベースのアルコソロ、もちろんここでもアンサンブルが鳴っています。最後にCannonballのソロがあってテーマの断片を組み合わせながら進行し、ラストテーマ、そして最後は冒頭に行われたドラムのブラシワークによるメロディに戻り、大団円となります。それにしてもこれだけ情報量の詰まったアレンジ、譜面にして一体どれだけの枚数の勧進帳になるのでしょう?!
久しぶりにこの作品をしっかり鑑賞しましたが、何と素晴らしいアルバムでしょう!何十年もジャズを聴いているとジャズに対する鑑賞力、とでも言うべき聴く事に対しての的確な判断力が身に付いて来るものです。①「昔よく聴いていたけれど、久しぶりに聴いてみると以前ほどの感動がなくなった」②「昔は内容がよく分からずピンと来なかったけれど、全く印象が変わり実に楽しめる」③「よく聴いていて随分と内容を楽しんだけれど、久しぶりに聴いてみて聴こえなかった部分をしっかり聴き取ることが出来るようになり、以前よりも増して更に楽しめるようになった」この作品は自分にとって③の最たるものになりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
