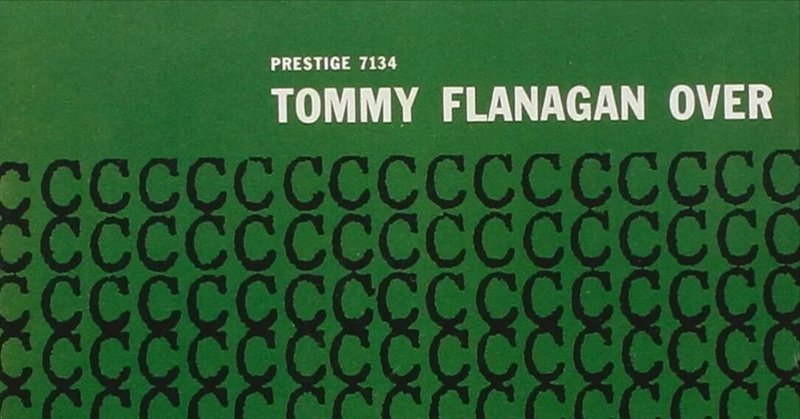
オーヴァーシーズ/トミー・フラナガン
トミー・フラナガンの57年リーダー作『オーヴァーシーズ』を取り上げましょう。
録音:1957年8月15日、メトロノーム・スタジオ、ストックホルム
エンジニア:ゴスタ・ウィホルム
プロデューサー:ボブ・ワインストック
レーベル:プレスティッジ
(p)トミー・フラナガン (b)ウィルバー・リトル (ds)エルヴィン・ジョーンズ
(1)リラクシン・アット・カマリロ (2)チェルシー・ブリッジ (3)エクリプソ (4)ビーツ・アップ (5)スコール・ブラザース (6)リトル・ロック (7)ヴェルダンディ (8)ダラーナ (9)ウィロー・ウィープ・フォー・ミー

本作はフラナガンの初リーダーにして代表作、ピアノトリオのエヴァーグリーンとして広くジャズファンに愛聴されています。
ピアニストのアルバム紹介があれば十中八九ノミネートされる定番中の定番、モダンジャズの黄金期1957年に録音されたゆえ演奏内容はもちろん、メンバーや収録曲の素晴らしさ、秀逸なアルバムデザインも要因の一つ、シチュエーションが揃った名盤です。
フラナガン自身は自分の音楽性を前面に打ち出し、リーダーとしてシーンで活躍するタイプのミュージシャンではなく、伴奏者然たるスタンスを常に保ちつつの演奏ぶりを示し、圧倒的に多くのサイドマンとしてのレコーディングを残しています。
いずれのプレイも素晴らしく、音楽を活性化させるカンフル剤としての役割を担っています。彼が参加するアルバムに駄作は無いとまで言い切れるでしょう。
その中でもソニー・ロリンズ『サキソフォン・コロッサス』、ジョン・コルトレーン『ジャイアント・ステップス』、2大テナー奏者のリーダー代表作への参加は、サイドマンとしての信頼度の最たるものと言えます。
64年から10年間以上に渡り、女性ヴォーカリストを代表するエラ・フィッツジェラルドの伴奏を務めたことも特筆されるべきで、15作近いアルバムで演奏しています。
リーダーの音楽性を最優先としつつ、自己のテイストをスパイス的に織り込み、共演者という立場ながら演奏を豊かに彩るスタイルは、職人芸という次元を通り越したアーティスティックな表現者です。
ハードバップを基本としつつ、中庸を行く演奏はメインストリームど真ん中と言えましょう。プレイは渋過ぎず尖り過ぎず、出しゃばらず、しかも適度なチャレンジ精神を抱きつつの打鍵、コードワーク、サポートを聴かせます。
タイム感の素晴らしさも特筆すべきですが、甘さや自己陶酔に流される事なく、常にドライに自分のプレイを見つめながら全体を俯瞰しつつの演奏、一度共演したプレイヤーの心を捉え、幾度も演奏を重ねる結果をもたらします。彼を雇ったリーダーはリピーターが殆どです。
50〜60年代のフラナガンは、純然たるリーダー作が本作を含めて僅か2作しかリリースされておらず、伴奏者としての活動が忙しかったのもあるでしょうが、本人にリーダー活動に興味がなかったゆえと思われます。
周囲からも名義作の録音を嘱望されていたことと思います。殊更本作の素晴らしさから、ファンはフラナガンを口説いてレコーディングを実現させたかった事でしょう。
75年録音の『ザ・トミー・フラナガン・トーキョー・リサイタル』から堰を切ったように、ピアノトリオやソロピアノを中心としたリーダー作を発表し始めます。

以降70年代に17作、80年代には13作、90年代晩年に6作のリーダー作をリリースします。リーダー活動が見違えて盛んになったとは言え、相変わらず伴奏者としては引く手数多、多くの作品に参加し続けます。
フラナガンは控えめな性格で、ピアノに向かう姿勢は別として、どちらかと言えばいつも遠慮がちだったそうです。
しかし奥方ダイアナが興味深い発言をしています。フラナガンの優しさと静かさは実は欺瞞的で、彼はとても強く、不屈の精神を持った人物だったそうです。
家族ならではの率直な印象でしょう。
75年以前は彼の控えめな側面が支配しリーダー作を遠ざけていたのかも知れません、その後俄然アクティヴに作品をリリースし始めたのは、不屈の精神の成せる技であったに違いないでしょう。
ロイ・ヘインズがリーダーでフラナガンが参加した62年作品『アウト・オブ・ジ・アフタヌーン』、ローランド・カークのプレイが異色ながら素晴らしい作品ですが、ヘインズのニックネームを冠し彼のドラムソロをフィーチャーしたナンバー、スナップ・クラックルで、フラナガンが「ロイ、ヘインズ!」とアナウンスした声が収録されています。控えめな彼にとっては緊張の一瞬であったかも知れません。
同じピアニストで12歳年上のハンク・ジョーンズ、フラナガンと同じくサイドマンとして数多くのプレイを残し、ジャズシーンの影の立役者として君臨しています。
二人は実に良く似た立ち位置で存在しました。
異なるのは、ジョーンズがリーダー作を初期からコンスタントに発表していた事です。それにしても膨大なサイドマンのレコーディング数からしてみれば、割合としては少ないかも知れません。
伴奏名人の彼ら二人を共演させたらどの様な演奏になるのか興味津々ですが、それが実現しました。78年1月録音『アワー・ディライツ』、同日の未発表テイクを収録した『モア・ディライツ』の2作を全編ピアノ・デュオで録音しています。


アルバム右側のチャンネルがジョーンズ、左側がフラナガン、穏やかなピアノタッチのジョーンズに比してフラナガンはより強い打鍵を感じます。
普段のフラナガンのタッチには滑舌の良さこそ感じますが、特に強さを感じる事はありませんから、ジョーンズのタッチの柔らかさが人一倍ゆえです。
取り上げられた楽曲はスタンダード・ナンバーの他、タッド・ダメロン、サー・チャールス・トンプソン、デューク・ジョーダン達ピアニストのオリジナルです。
演奏形態として、イントロを先にプレイする事こそありますが、テーマのメロディ、ソロの先発を全てジョーンズに任せ、フラナガンはバッキング、そして常にソロの二番手を担当、ここでもフラナガンは伴奏者然とした態度を貫き通します。
フラナガンが尊敬する先輩のジョーンズに共演を持ち掛け、レコーディングが実現したと推測出来ますが、レコーディング時に「トミー、俺ばかりがテーマを弾いたり、ソロを初めにプレイするのはどうなのかな?」「ハンク、貴方に最初に演奏して貰ってサウンドの道を作って貰いたいのです」の様な会話があったと想像しています。
両者のプレイには似たテイストも感じますが、明らかに異なるアプローチ、語り口を提示し合います。
ジョーンズの脱力感を伴いつつ、押し付けがましさのない気品のある優雅なプレイ、フラナガンもリラックスしつつ、バップの範疇にあってもそこから浮上しようとする、フレッシュなサウンドを模索する姿勢。
ここでは互いに触発し合い音楽が進行すると言うよりも、淡々と自己の世界を語りつつハードバップの美学を構築している作品と感じます。
これは優れた芸術家の邂逅を捉えた、隠れた名盤です。
93年に行われた二人のライヴ・レコーディングも残されています。

閑話休題、『オーヴァーシーズ』の録音はフラナガンが参加していたJ. J. ジョンソン・クインテットの欧州楽旅中スウェーデン、ストックホルムにて行われました。
共演者ベーシスト、ウィルバー・リトル、ドラマー、エルヴィン・ジョーンズ二人も同じバンドのメンバー、J. J. の57年1月、5月録音リーダー作『ダイアルJ. J. 5』リリースに際しての、欧州ツアーの一環です。
この作品にはフロントが入らず、一曲ピアノトリオをフィーチャーしたソー・ソリー・プリーズが収録されています。
J. J. は彼らトリオの演奏を気に入っていたのでしょう、フラナガンの尊敬するこのバド・パウエルのナンバーを存分にプレイさせています。
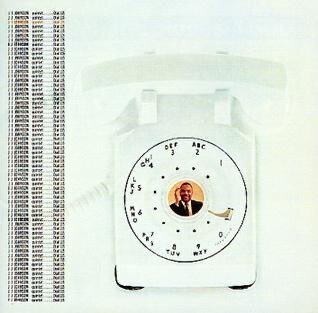
『オーヴァーシーズ』はこのテイクが発端となりレコーディングに繋がったと想像出来ます。
特筆すべきはエルヴィンがアップテンポ・ナンバーも含め、全曲スティックを使わずにブラシだけで演奏している点です。この事はエルヴィン本人の発案によるものか、リーダーであるフラナガンやプロデューサーのサジェスチョンか、はたまた単にスティックをスタジオに持参し忘れたためか、いずれにせよ彼はブラシワークの名人ですが、スティック使用による支配的な音量の大きさや、シンバルによる倍音成分のぶつかり合いが回避され、フラナガンのピアノ、リトルのベースがくっきりと浮かび上がり、ひと味もふた味も違うピアノトリオ作品へと昇華しました。
仮にエルヴィンがスティックを用いて演奏に臨んだとしても、十分に音楽的なプレイを展開したでしょうが、ここまでの名サポートを繰り広げられたかどうかは判断出来ません。
レコーディング・エンジニアに関して、この頃のプレスティッジ・レーベルは名手ルディ・ヴァン・ゲルダーを起用していますが、ストックホルムのメトロノーム・スタジオにてスウェーデン人ゴスタ・ウィホルムがレコーディングを担当しました。
ヴァン・ゲルダーのような個性的な録音では有りませんが、クリアーでバランスの取れた、各楽器の音像が明瞭な、ジャズのサウンドを良く分かっている技師による、音の取捨選択が確実に成された匠の技に仕上がりました。
それでは収録曲に触れて行きましょう。
1曲目リラクシン・アット・カマリロはチャーリー・パーカーのブルース・ナンバー、印象的なイントロから早速アップテンポが提示されます。
リトルのオン・トップなビートの位置、これは前述の『ダイアルJ. J. 5』でのプレイよりも明確で、使い分けているようにも感じます。
エルヴィンのスピード感が半端無いスネアを主体としたブラシ・プレイ、フラナガンのエッジーでブリリアントなピアノタッチが一つの音塊となって押し寄せて来ます。
時々聴こえる声の主はエルヴィン、ブラシ使用や音量の小さい時に顕著に現れますが、以降自分のバンドを率いるようになるとより気持ちが入ったため、声量が大きくなりました。
フラナガンの端正にしてリリカル、右手のフレージングは実にホーンライクにプレイされ、パーカーやパウエルを彷彿とさせますが、左手のカウンター・メロディの如く響くバッキングと相俟ってフラナガン・スタイルを構築しています。
セカンド・リフ後にベースがフィーチャーされ、その後ドラムもドラム・ブギー風メロディラインのリフを用いて同様にフィーチャー、ピアノソロも再び行われますが、3人を短い顔見世興行的にバランス良く配し、ラストテーマへ。
イントロがアウトロとして用いられFineです。
2曲目チェルシー・ブリッジはビリー・ストレイホーン作の名曲、コード進行、メロディ共に作者でしか成し得ない美の世界を提示します。
バラードにしてはやや早めのテンポ設定により、エルヴィンのブラシワークがより活性化されます。
ここではフラナガンの左手の使い方が、曲の持つムード高めています。流暢な右手のラインはこれ以上有り得ないほどに理想的な音の選択を感じさせ、演奏が盛り上がるにつれ、ベース、ドラムは確実に追従し、一体感を更にクリアーにします。
入魂3コーラスの演奏はピアノの独断場、エンディングは予め決めておいたと思われるコード進行を辿り、明るい解決感を与えます。
3曲目エクリプソはフラナガンのオリジナル、一風変わったベースラインからドラムがラテンのリズムを匂わせ、ピアノもイーヴン系のバッキングを聴かせます。
ハッピーなムードのテーマはそのままラテン、サビをスイングで演奏した後、ソロからスイングにスイッチします。
フラナガンはコード進行というある種の制約を逆手に取るが如く、自身のストーリーを巧みに語りますが、楽しげでこよなくハッピーです。
メロディの合間に挿入されるドラムのフィルインは、流石カラーリングの名人エルヴィン、と納得させられます。寧ろスティックを用いない事によるある種の制約が、ドラミングの表現を深淵にさせていると感じました。
その後ドラムと4小節交換が行われ、ラストテーマへ。エンディングはフェードアウトで余韻を残します。
4曲目ビーツ・アップはフラナガン作、リズム・チェンジのコード進行を用いたナンバーです。
トラディショナルな手法を用いた、ダイナミクスが心地良いテーマです。ベースとのやり取り、サビ後はドラムとトレードするはずが、勘違いしてベースが再度弾き始め、ドラムとぶつかり合い、「いっけねー!」とばかりに途中で止めるのがご愛嬌です。
ソロ中はリトルのビートの位置が実に適切で、フラナガンがほんの少しだけレイドバック出来るスタンスを提供します。
テーマのモチーフを用いてドラムと4小節交換、同じくベースとトレード、後に再びピアノソロ、ここでのフラナガン、初めのソロよりも一層歌っており、泉の如く湧き出るアイデアを確認できます。
ラストテーマでは改めて全編ベースとのトレードで纏められました。
5曲目スコール・ブラザースはブルーノートを用いた、ファンキーなテイストを湛えたブルース・ナンバー。
こちらもフラナガンのオリジナルですが、当日スタジオ入りし急拵えで作り出したように感じます。
このくらいのテンポになると、ベースとドラムのビートからバネのような粘りが表出し始めます。そこにフラナガンのタイトなリズムによるソロが加わり、極上のスイング感を醸し出します。
エルヴィンはラストテーマでお得意のシャッフル風リズムも繰り出し、賑わいを表現しています。
6曲目リトル・ロックはベースのウォーキングから始まる、こちらもブルース・ナンバー、本作中最も収録時間の長い演奏です。
エルヴィンはバスドラムでユニークなアクセントを付けつつ演奏に加わります。リトルも呼応するかのように3連符のラインをプレイし、フラナガンも断片のようなバッキングで対応しています。
ピアノソロはじわじわと盛り上がり、三者三様のプレイが違和感なく渾然一体となりますが、全く違う内容の話を続けている会話にも関わらず、互いがパズルのピースとなり、合わさりつつ、更に三つ巴の状況を呈します。
その後ベースソロへ、リトルの繰り出す三連符のフレーズに呼応するエルヴィン、その返答としてベース再びの三連符フレーズの際に、敢えて静観するエルヴィンの潔さ、バランス感。
更なるベースの三連符でエルヴィンは音無しの構えを保ちつつ、スタンド等の金属部分を軽く叩いてリズムを提示し、フレージングに返答しているが如しです。インタープレイとはこの事を指すと言う、ロールモデルになりました。
ドラムとの4小節交換では、既に後年のエルヴィンのプレイに聴かれるポリリズム的アプローチが発揮されています。
最後のコーラスはフラナガンがラストテーマに仕上げるべく1コーラス、12小節を弾き続けますが、今一つ二人には伝わっておらず、ソロが交錯する結果を招きましたが、ライヴ風演奏の醍醐味と感じました。
こちらも急拵えのブルース・ナンバーに違いありません。それにしても、いずれの曲でも異なった音楽展開が成されているのは、彼らのポテンシャルが半端無いことの証です。
7曲目ヴェルダンディはアップテンポのマイナー・チューン、印象的なテーマ・メロディ、エルヴィンのブラシ捌きの妙、リトルのウォーキングが冴え渡り、フラナガンのプレイもスピード感を伴いスリリングです。
テーマをモチーフに使い、ドラムとベースのソロを上手く挿入しています。
ラストテーマはこの手法を用いて極自然にFineします。
8曲目ダラーナは優雅さを湛えたフラナガン作の佳曲、気品漂うピアノプレイが心地良いです。
ベースの音の立ち上がりがビートの位置を確実にしている様が良く分かるテンポ、途中からエルヴィンは倍テンポに、リトルもそれに追従すべく動きます。程なくエルヴィンがリードし元のグルーヴに戻り、ラストテーマでは別なコード進行に移りFineとなります。
9曲目ウィロー・ウィープ・フォー・ミーはお馴染みのバラード、冒頭ピアノから相応しいテンポで始まり、ベースが果敢にビートを繰り出します。
テーマ後ソロに入り、すぐにエルヴィンが率先して倍テンポに変わります。
フラナガンの繰り出すアイデアは無尽蔵であるかのように次々と湧き出て、二人に刺激を与えますが、特にエルヴィンは強くインスパイアされ、結果ドラミングが一層場面を活性化させます。
ベースソロのバックでエルヴィンがアグレッシヴにアプローチしますが、決して過剰にはならず、ほど良き所でカーム・ダウンしラストテーマへ。
エンディングでもメリハリが十分に施され、この曲の代表的演奏が生まれました。
CD化に際し未発表別テイクが3曲追加されています。いずれもオリジナルテイクに遜色のないクオリティですが、特に異なったハプニングが収められている訳ではないので、ここでは触れずにおきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
