
At the Village Gate 1976 / Dexter Gordon Quintet featuring Woody Shaw

今回はDexter Gordonの1976年ライブ作品「At the Village Gate 1976」を取り上げたいと思います。
Live at the Village Gate, New York, October 25, 1976
Label: Domino Records
ts)Dexter Gordon tp)Woody Shaw p)Ronnie Mathews b)Stafford James ds)Louis Hayes
on Bonus Track “Bags’s Groove” ts)Dexter Gordon tp)Woody Shaw vib)Milt Jackson p)Kirk Lightsey b)David Eubanks ds)Eddie Gladden
“Playboy Jazz Festival”, Hollywood Bowl, Los Angeles, June 20, 1982
1)Fried Bananas 2)Gordon introduces the band 3)Strollin’ 4)You’ve Changed 5)Bags’ Groove
Dexter Gordonはジャズシーンが停滞していた米国を60年代初頭に離れ欧州に移住し、ParisやCopenhagenに居を構え悠々自適に演奏活動を送っていました。
同じ渡欧組であるKenny Clark, Bud Powell, Kenny Drew, Horace Parlan, Albert Heath, Bobby Hutchersonら、また本場のジャズプレイヤーからの薫陶を受けた優れた欧州ミュージシャンTete Montoliu, Niels-Henning Orsted Pedersen, Pierre Michelot, Alex Rielらとも演奏を重ね、足掛け15年の長きに渡り欧州で音楽活動を展開していましたが、しかしこの辺りが潮時と感じたのかもしれません、故郷の音楽シーンも随分と様変わりしたのもあり、76年10月頃に本国に戻りました。
とは言え65, 69, 70, 72年といずれもごく短期間ですが米国に戻り、Blue NoteやPrestigeにレコーディングを行っており、Dexterはこれらの一時帰国で合計10枚以上のアルバムを残しています。
渡欧はしたものの、one & onlyな魅力満載のDexterの演奏は米国ファンに求められており、ニーズによりアルバムをリリースし続けたと言う事です。
このバックグラウンドが存在したからこそ帰国してからも華々しくカムバック出来たのでしょう。 欧州でもSteepleChase Labelを中心にライブ、スタジオ録音を30作品以上をリリースしており、多作家ぶりを印象付けています。
想像するに本人の売り込みは全く無く(そもそも熱心に自己アピールするタイプのプレイではなく、ごく自然体での演奏ですから)、レコード会社の方から作品制作の依頼が舞い込んで来るのでしょう、彼ほどの個性と風格、気品、音楽性、人気、存在感、しかし何よりこれは時代の成せる技に違いありません。
一時帰国盤では65年5月録音「Gettin’ Around」69年4月録音「The Tower of Power!」70年8月録音「The Jumpin’ Blues」を挙げたいと思います。



76年12月、本作と同一メンバーでNYC, Village Vanguardでのライブ演奏を収めたアルバム「Homecoming」が文字通りの帰国第一声でしたが、本作は遡ること1ヶ月半、帰国直後の10月真にフレッシュなDexterを捉えた演奏で2011年に発掘、リリースされました。
正規の録音ではないので音質やバランスは決して良くありませんが、何しろバンド全員の一丸となった勢いが素晴らしく、個人的には本作の方に軍配を挙げたいと思います。

70年7月Swiss Montreux Jazz Festivalにて、Junior Manceとの演奏を収録した「Dexter Gordon with Junior Mance at Montreux」はワンホーン・カルテットによる絶好調のDexterを捉えた作品、ライブのオープニング・ナンバーが同じFried Bananasなので似たような印象を受けますが、本作ではトランペット界の鬼才Woody Shawを迎えたモダンジャズ黄金のコンビネーションによる2管編成、両者のユニゾン演奏だけでも相乗効果で何倍にもメロディが分厚く聴こえます。 Dexterのどちらかと言えば穏やかで朗々としたサウンドに強力なスパイスを加える効果を生んでいます。
しかもShawのアグレッシヴでスポンテニアスなプレイは決してtoo muchではなく、むしろDexterのプレイと素晴らしいコンビネーションを生み出し、対極を行く演奏を信条としていますが、互いに無い部分を補い合うかの如く絶妙なバランス感を伴い、オーディエンスを興奮の坩堝に誘い込みます。
DexterはFreddie HubbardやDonald Byrd、Benny Baileyら他のトランペット奏者とも共演を果たしていますが、Shawほどのプレイの相性の良さは感じられません。ふたりの人間関係が大変良好だった故のように思います。

DexterとShawのそもそもの出会いはSwiss出身のピアニスト/アレンジャーGeorge Gruntzの72年録音アルバム「The Alpine Power Plant」です。
Phil Woods, Rolf Ericson, Benny Bailey, Sahib Shihabらを擁しBaden, Switzerlandで録音されたビッグバンド・プロジェクト、ここでの共演で互いに惹かれ合うものを感じたふたりは「ぜひとも一緒にバンドをやろう!」と約束を交わしたのだと想像しています。

Shawが共演したサックスプレーヤー、テナー奏者ではJoe Henderson, Benny Maupin, Azar Lawrence, Billy Harper, Carter Jefferson、アルト奏者ではEric Dolphy, Jackie McLean, Gary Bartz, Rene McLean, Anthony Braxton, Kenny Garrettたちモーダルや前衛スタイルのプレーヤーで、Dexterのようなハードバップ・スタイルのサックス奏者との演奏は珍しい例です。
しかし本作に於ける、特にFried Bananasでの両者の一体感はジャズ史に残る素晴らしいコンビネーションだと思います。 スタイル的には全く異なる語法、方法論ですが、迎合することなく徹底的に自分を出した演奏を展開しても違和感がないのは、ひとえにお互いのプレイを尊重した結果に違いありません。
ドラマーLouis HayesとDexterは何度もセッションを重ね気心の知れた間柄、ベーシストStafford JamesとピアニストRonnie Mathewsは恐らく初共演になるので、Hayesの推薦があったのかも知れません。何しろ米国のジャズシーン、ミュージシャンの人脈にはDexter疎くなっていましたから。
Dexter Gordon

それでは演奏内容について触れて行きましょう。
1曲目Fried Bananas、スタンダードナンバーIt Could Happen to Youのコード進行を元に書かれたDexterのオリジナル、早い話替え歌ですね(笑)、メロディアスかつリズミックな名曲、自身は機会あるごとに取り上げて演奏していますが、前述の69年4月レコーディング「The Towe of Power」と同時録音「More Power!」が初演になります。
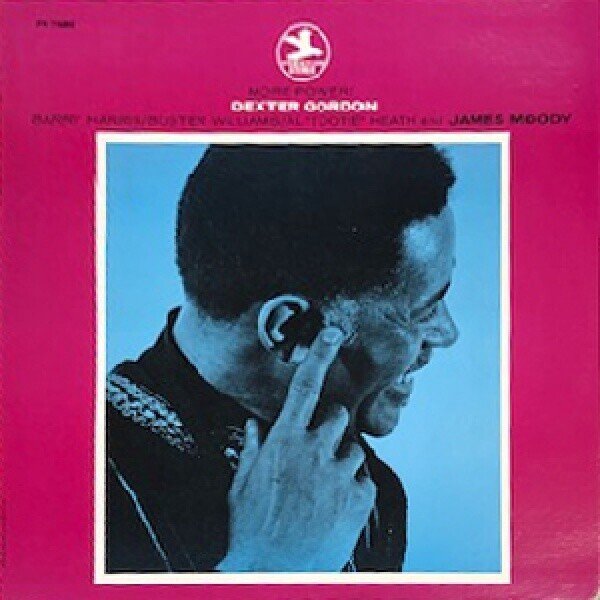
冒頭司会者のアナウンスが入りDexterの紹介が始まります。『Copenhagenから来た若者(この時49歳ですが)、one and only, Dexter Gordon!』その直後に聴かれるShawによるファンファーレ、さりげにこの音色の素晴らしいこと!リズムセクションも音を出して歓迎の意を表しています。
オフマイクで『Fried Bananas』とメンバーに演目を伝え、その後何故か仏語(CopenhagenはDenmark語が公用語ですが)での挨拶の後、マイクに向かい演奏曲目のアナウンスが始まります。2回続けて曲名を紹介していますが、Dexterはステージでタイトルやメンバーの名前を連呼する傾向があります。
通常よりも速いテンポでスタート、Shawがテーマをちゃんと吹けていないのはバンド発足が間も無いからでしょうか(汗)。
Dexterはテーマのメロディ奏から既に抜群のレイドバックを提示しており、この事に動揺したShawがテーマを間違えたのかも知れません。テーマの後半はShawもDexterのレイドバックに合わせ始めました。
ピックアップソロからDexterのアドリブが始まります。前述の通りIt Could Happen to Youのコード進行をベースにした曲ですが、いきなり半コーラス、16小節間ほとんどそのままに原曲のテーマを吹いています。引用フレーズの達人Dexterの面目躍如、というよりダジャレオヤジ現る!と言った方が相応しいかも知れません(汗)。
それにしても何という素晴らしい音色でしょう!誰よりも恵まれた豊かな体軀(身長196cm!)、分厚い唇によりマウスピースを容易く咥える事の出来るルーズなアンブシュアー、この事から生じる豊かな倍音を含んだ音色、脱力とレイドバック、長い8分音符ゆえのタップリ感、ユーモアのセンス、味わい深いニュアンス、そして決して枯渇する事のない砂漠のオアシスに湧き出る泉の如きフレージングとアイデア、ここでの演奏はこれら全てが文句の付けようのないバランスで表出されています。
リズムセクションのサポートも素晴らしく、on topのビートを繰り出すトリオに対しビハインドに位置するDexterとのバランスが絶妙、そして全編に於いてLouis Hayesのカラーリング、特にバスドラムのレスポンスが良い味を出し、Dexterとのスリリングなコンビネーションを聴かせています。
滞欧中のライブ盤の中には、地元のピアノトリオを相手に孤軍奮闘しているDexterの演奏を耳にする事があります。彼の演奏に対し何を行ったら良いのか、どんなレスポンスすれば適切なのかがほとんど分からない、マイナス・ワン状態、馬の耳に念仏の如きリズムセクションに対して、怯まず可能な限りのスイング・スピリットを注入するDexterがいます。
でもこんなことが続けば、素晴らしいリズム隊が大勢待つ母国に帰りたくもなるのも当然でしょうね。
Louis Hayes

テナーソロ後しばしスペースを置きShawの登場です。こちらもまた一聴彼と判断出来る素晴らしいトーン、ハスキーさと抜け切らないこもった成分、反するブライトネス、スピード感、これらがあり得ない次元でのバランス感を伴い発出されている、物凄い個性の塊です!
4分半にも及ぶロングソロではShaw独自のインプロヴィゼーションの方法論、ハーモニー感をとことん聴くことが出来ます。
ハーモニーに対してインサイドなアプローチではいわゆるリック的なフレーズも演奏されていますが、アウトする音使い、Shaw節フレージングでは全く独自な彼の世界に突入しており、Ornette Colemanのインプロヴィゼーションにも通じる、真の天才のみがなし得るオリジナリティを確認することが出来ます。
加えて、えも言われぬニュアンス、ビブラートから発せられる男の色気(堪りません!)、絶妙なタイム感、16分音符フレージングに於ける超絶ぶりとその確実なコントロール。これらの放出を誰も止める事のできないレベルで聴くことが出来るのです。
彼の吹くフレーズは毎回トランペットの機能の限界に挑むかのような難易度を極め、時としてミストーンが目立つ場合があります。フレーズの方が難しすぎてトランペットの機能が追いつかないとも言えるでしょう。
でもここでの演奏は全くパーフェクトと言って言い過ぎではなく、Dexterと共演できる事の喜びがShawにリラクゼーションを与え、肉体的、精神的コンディションが楽器の発音やコントロールに影響を与えがちなトランペット奏を、万全なものに仕立てたと判断しています。
Woody Shaw

引き続きRonnie Mathewsのピアノソロが始まります。Art Blakey and the Jazz Messengers他多くのバンドに参加し、職人タイプのピアニストとして活躍していました。ここでも堅実な素晴らしいプレイを聴かせています。
彼の第2作目75年アルバム「Trip to the Orient」はドラムLouis Hayes、ベースに我らがYoshio “Chin” Suzukiを迎えた日本制作盤、自身の音楽性を存分に発揮しています。

Stafford Jamesのベースソロ後、フロント陣とドラムとの8バースが聴かれますが、巧みなHayesのドラミングにインスパイアされたのか、ふたりとも大健闘、本編とはまた異なる素晴らしいプレイを繰り広げますが、惜しむらくはDexterが一度用いた引用フレーズIt Could Happen to Youのメロディを再奏した点です。引用フレーズを同曲で複数回用いるのは法律で禁じられていますから(嘘)。
Fried BanansのエンディングにはDexter入魂のアレンジが施され、この曲の価値をグッと高めました。
Stafford James

続いてDexter本人によるメンバー紹介があり、3曲目Horace Silver作の名曲Strollin’に繋がります。
こちらは彼の74年欧州録音の作品「The Apartment」に既収録されています。

The Apartmentでの演奏も好演ですが、コード進行の難しいStrollin’を実はセオリー通り無難にこなしている感を否めません。
本作でのプレイはチェンジを超越し、ウタを歌うが如くナチュラルに、まるで帰国出来た充実感を噛み締めるかのように味わい深く演奏しています。
ミディアムテンポでのDexterのリズム感はテナーサックス奏者全員の憧れ、実に素晴らしいタイム感をキープしつつ、前半ではオクターヴ下の音域を中心に演奏しており、音色の極太感からバリトンサックスと見紛うばかりのトーンです。
ソロが盛り上がるにつれ次第に音域が上がりますが、相変わらず8分音符を主体としたソロを展開、数カ所で引用フレーズも披露し、聴衆が彼のスイング魂に聴き惚れているのが伝わり、リズム隊も相応しいバッキングで徹底的に対応しています。 ソロ終わりの盛大なアプローズ後、やはり暫くの間があってShawのソロがスタートします。始めは16分音符を用いたラインが多かったのですが、次第にDexterの影響を受けたのか8分音符主体の朗々としたアプローチへと変化します。
ピアノソロに移行する手前にテープ編集の跡を確認しました。まだまだトランペットソロが続いていたようですが、前曲のプレイに比べると冗長さを感じさせるので、ソロをカットされたと想像しています。
続くMathewsのソロは倍テンポをプレイ中提示し、しっかりと二人が追従しています。その後おもむろに元のテンポを出し再びミディアム・スイングに戻りますが、幾分予定調和と聴こえてしまいます。ベースソロまでしっかりと回り、ラストテーマを迎えます。
Ronnie Mathews

4曲目はバラードでYou’ve Changed、61年5月Blue Note Labelで録音したアルバム「Doin’ Allright」ではFreddie Hubbardを迎え、トランペットがバックグラウンドを吹き、テナーが訥々とメロディを奏でるスタイルで同様に演奏しています。Dexterのバラード名手ぶりを堪能できるテイクです。

アナウンスの前にDexter自身がBud PowellのUn Poco Locoのイントロ・メロディを吹き、ピアノとドラムが追従しています。その後もう一度同じメロディを拍を少しずらして吹き始めます。わざとなのか、間違っただけなのか、これが妙に新鮮に聴こえました。彼らにとってPowellの曲はバイブルのようなナンバーなのでしょうね、このまま同曲を演奏してくれても良かったのに、とも思いましたがおもむろにYou’ve Changed、とDexterがタイトルを述べ、何とこの曲の歌詞を口ずさみ始めたではありませんか!低音の渋い声で!ここでその歌詞をご紹介しましょう。
『You’ve changed That sparkle in your eyes has gone Your smile is just a careless yawn You’re breaking in my heart You’ve changed You’ve changed』
Dexterはバラード演奏時にメロディはもちろん、歌詞も覚えてその意味を自分なりに解釈して演奏しています。『それはLester Youngから学んだ事なんだ』と言う本人の弁もあるように、彼が主演の86年映画「Round Midnight」、音楽担当のHerbie Hancockがアカデミー作曲賞を受賞、Dexter本人もアカデミー主演男優賞にノミネートされた作品です。街角でバラードを朗々とアカペラで吹いていると突然吹くのを止め『いかん、歌詞を忘れちまったぜ』というシーンには説得力があります。
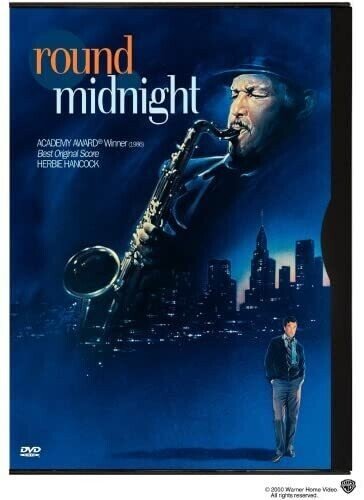
歌詞朗読はオーディエンスに大受けし、会場のムードが更に和んだところで演奏開始です。
いや〜それにしても何という凄い音色でしょう!Dexterのバラード奏は天下一品、朴訥さとニュアンス、感情移入が堪りません!
プレイはライブという事もありオープンなテイストを聴かせますが、「Doin’ Allright」時よりも渡欧生活で蓄積されたのでしょう、深みを感じさせます。
続くトランペットソロはしっかりと倍テンポで行われます。こちらも唄心をとことん感じさせるプレイ、明らかにDexterのスピリットに啓発された入魂ぶりを聴かせています。
ピアノソロを経てラストテーマへ、エンディングでのCadenzaのこれまた素晴らしいこと!Dexterの芸歴の中でもベストに挙げられるプレイです!サブトーン、実音の巧みな音色の使い分け、ジャジーなフレージングのオンパレード、最低音からフラジオを含めた高音域までバランス良く演奏し、センテンスの間に投げかけられる、感極まった熱狂的ファンの歓声が次第に大きくなり、ストーリー性をもった演奏はドラマチックに、ダイナミックに、申し分なく挙行されました。

ラストはBonus TrackのBags’ Groove、本編の約6年後に当たる82年6月、Los AngelesにあるHollywood Bowlにて行われたPlayboy Jazz Festivalでの演奏です。
Milt Jacksonをゲストに迎え彼の代表曲を選び、Shaw以外は全員メンバーが入れ替わったジャムセッション形式での演奏になります。
作品としての一貫性を持たせるべく、是非ともVillage Gateでのテイクで統一して欲しかったところです。何処かに存在するとは思うのですが。
ジャズ・フェスティバルでの広い会場の演奏はそれなりの盛り上がりは期待できますが、ライブハウス・ギグとは異なり、緻密さにかける傾向は否めず、どうしても演奏は大味なものになりがちです。こちらはどうでしょうか。
それまでよりも録音の音質はクリアーですが、案の定やや「お仕事」、「見せ物興行」的に演奏が進行していて、残念ながらsomething happensは起こっていません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
