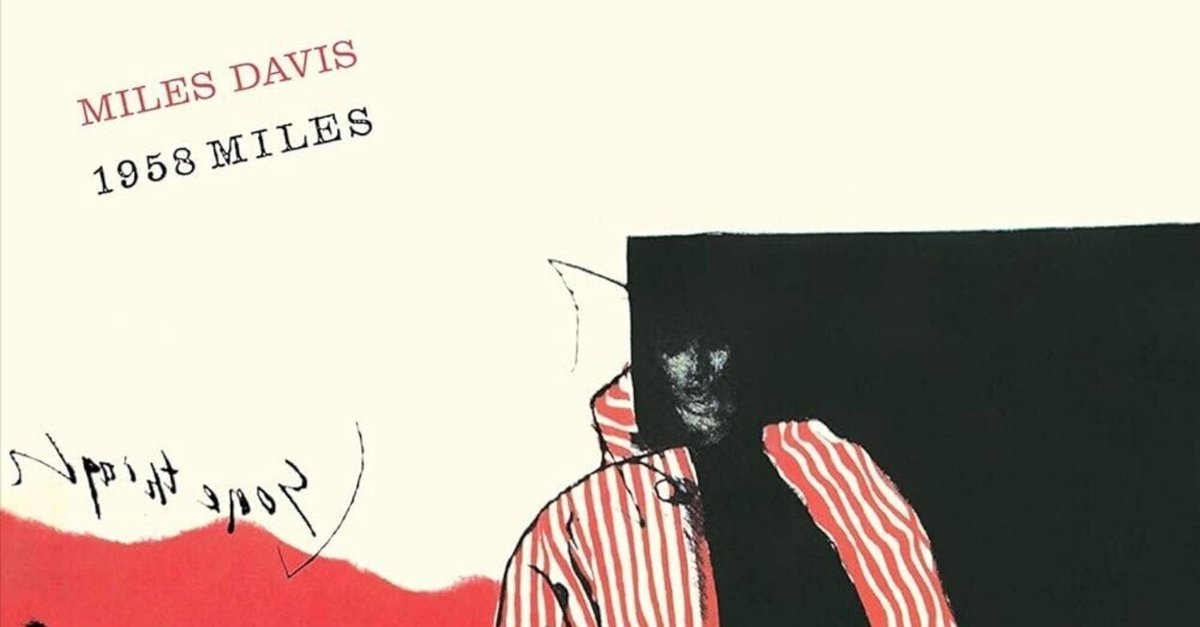
1958 マイルス/マイルス・デイヴィス
マイルス・デイヴィス1958年の演奏を収録したアルバム『1958 マイルス』を取り上げましょう。
本作には55年録音のナンバーも1曲収録されていますが、タイトルのコンセプトを鑑みここではオミットし、ボーナス・トラックとして後年追加されたフラン・ダンスの別テイクを取り上げる事にしたいと思います。
録音:1958年5月26日
スタジオ:コロムビア・30th Street スタジオ
プロデューサー:テオ・マセロ
ジャケット・デザイン:池田満寿夫
(tp)マイルス・デイヴィス (ts)ジョン・コルトレーン (as)キャノンボール・アダレー (p)ビル・エヴァンス (b)ポール・チェンバース (ds)ジミー・コブ
(1)オン・グリーン・ドルフィン・ストリート (2)フラン・ダンス (3)ステラ・バイ・スターライト (4)ラヴ・フォー・セール (5)フラン・ダンス(別テイク)

マイルス・デイヴィス・クインテットにもう一人のホーン奏者であるアルトサックスのキャノンボール・アダレーが加わり、セクステットとなったのが58年3, 4月録音の名作『マイルストーンズ』からです。
サウンドやアンサンブル、アレンジ、アイデアの織り込みはクインテット時代とは格段に進化を遂げ、深淵な演奏を聴かせます。ハードバップ期マイルス・ミュージックの頂点を捉えた熟し切ったサウンドの発露、尚且つモーダルなプレイの先駆けとなりました。
ピアニスト、レッド・ガーランドがマイルスとスタジオ内でのいざこざから録音途中で帰ってしまい、収録曲シッズ・アヘッドではテーマの際ピアノレス、各プレイヤーのソロ時にマイルスがピアノを演奏し、バッキングを行うというハプニングがありました。
トランペットの演奏後、コルトレーン、キャノンボールのソロ冒頭で、マイルスが打鍵し始めるまでの4~5小節程度の僅かな間ですが、スタジオ内でピアノ椅子にまで移動する距離を感じ、生々しさを覚えます。
そしてこのトラブルが原因の一つであったかも知れません(そもそもマイルスがガーランドに力量を越えた音楽的要求を行ったと推測しています)、新たにトライするサウンドへの的確さを求め、ピアニストがモードサウンドに長けたビル・エヴァンスに替わります。
とは言えガーランドのプレイをマイルスは認めており、本作で彼をフィーチャーすべく、マイルス諸作中異例の管楽器が入らないピアノトリオ編成でビリー・ボーイを演奏させています。加えてガーランドは返礼の如く、ストレート・ノー・チェイサーのソロ中に於いて、マイルスがチャーリー・パーカーと45年11月共演したブルース・ナンバー、ビリーズ・バウンスでのマイルスのソロを完全コピーし、さらにリハーモナイズして打鍵するという最大級の賛辞を行なっています。
フィリー・ジョー・ジョーンズのドラッグに基づく素行の悪さにより、ドラマーはジミー・コブに替わり本作『1958 マイルス』を収録します(とは言うものの、フィリーのドラミングを敬愛していたマイルスはその後も彼と仲が良く、機会がある度にフィリーを再起用していました)。
因みにベーシスト、ポール・チェンバースは留任でしたが、彼もアルコールやドラッグにまつわる悪癖を抱えていました。彼に匹敵するベーシストが見つからなかったのが解雇に至らない理由の一つでしょう。
肝心のマイルス本人もかなりのドラッグ禍にありましたが、そこはバンマスの特権、一切お咎め無しです。
的確なミュージシャンを擁するために行ったメンバーチェンジと共に、作品を制作し新たな境地に向かおうとするマイルス、音楽表現の発露が止まりません。

この後セクステットは多くのギグをこなしバンドとしての纏まりを強くしますが、そもそもコルトレーンとキャノンボール二人のサックス奏者の対比を行いたいと言うマイルスの目論見があり、それが見事に的中しサウンド、リズム的にも大胆に発展します。
そして丁度1年後の59年3, 4月同一メンバーで録音されたマイルスの傑作『カインド・オブ・ブルー』が新たなジャズスタイルの創造を遂げ、極めて高い音楽の成熟度を示し、セクステットは一つの完成形を迎えることになります。
マイルスがイメージするモーダルなニューサウンドにメンバーが呼応し、一丸となって創り上げた結果が『カインド・オブ・ブルー』での極めてクリエイティヴで斬新なサウンド、革新的プレイです。

芸術家は新たな境地を迎えるために多くの試行錯誤が必要です。『1958 マイルス』の演奏は『カインド・オブ・ブルー』の革新に至るまでの試金石として存在します。
僅か4曲の収録であったためアルバム1枚として発表するには曲数不足、55年録音のマイルスリーダー作『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』残りテイク、ジャッキー・マクリーン作曲リトル・メロネーを加えて日本盤はリリースされました。当時はレコーディング・データがはっきりしていなかったのか(耳を傾ければ58年の演奏でないのは一聴瞭然でしたが)、確かリトル・メロネーも58年録音のように扱われていたと記憶しています。
参加メンバー側の動向からも眺めてみましょう。コルトレーンは57年5月初リーダー作『コルトレーン』、同年9月ブルーノート・レーベル唯一のリーダー作にして傑作『ブルー・トレーン』を録音しますが、この頃セロニアス・モンクのカルテットに迎えられ、多くの共演の機会を持ちます。
モンクの独特にして孤高のプレイから、演奏中に奈落の底に叩き落とされたかの緊張感を体験し、同時に音楽的サジェスチョンを授けられ開眼し、急成長を遂げます。
58年2月コルトレーンの特徴的スタイルであるシーツ・オブ・サウンドが顕著に表れた『ソウルトレーン』、59年音楽的実験の側面とエンターテイメント性がバランス良くブレンドした『コルトレーン・ジャズ』等、充実した音楽活動を展開します。


キャノンボールの方は55年弟のナットと共にニューヨーク・ジャズシーンにデビューしますが、同じ頃に没したチャーリー・パーカーの再来という、スタイル的には全く異なっているにも関わらずの誤ったレッテルを貼られた事で、当初は活動がやや違った方向を向いていた感がありますが、何しろアルトサックス奏者としての存在感、艶やかにして極太の音色、グルーヴ感、只管ドライヴするプレイからシーンに名を轟かせます。
作品としてはマイルスとの共演による58年3月録音『サムシン・エルス』、同年10月『シングス・アー・ゲッティング・ベター』、59年2月マイルス・セクステット、リーダー抜きによるコルトレーンとの2管『キャノンボール・アダレー・クインテット・イン・シカゴ』、同年4月『キャノンボール・テイクス・チャージ』等、饒舌で明快な語り口、豊かなニュアンス、高度なテクニック、唄心、ワン&オンリーのトーン、ベニー・カーターやジョニー・ホッジスに影響を受けたオリジナリティに由来し、非パーカー・スタイルをキープし続けた豪快なプレイを繰り広げます。


エヴァンスは56年9月に初リーダー作『ア・ニュー・ジャズ・コンセプションズ』を発表、知的にして繊細且つ斬新なフレージング、透徹なハーモニー感を携えてシーンに登場します。
58, 59年のマイルスとの演奏でより内面を掘り下げ、音楽的な深さを得るのですが、寧ろ『カインド・オブ・ブルー』のモーダルなサウンドはエヴァンスの音楽観、コードワークが無ければ成り立たなかったとまで言える程に、作品全体に貢献しています。
黒人ばかりのバンド内に白人ミュージシャンがただ一人加わる事に対し、マイルス自身には全く拘りがありませんでしたが、エヴァンスのデリケートさやマイルスの取り巻きからのプレッシャーがあったのかも知れません、59年11月にマイルスバンドを離れます。
その後スコット・ラファロ、ポール・モチアンとトリオを結成し、同年12月録音『ポートレイト・イン・ジャズ』を皮切りに演奏活動を開始します。
彼はサイドマンとしても的確なプレイを行えるピアニストですが、自身がリーダーとなり最小限の表現フォーマットとしてのピアノトリオで、独自の演奏活動を行います。
退団に際しての置き土産とも言えましょう、『カインド・オブ・ブルー』の裏ジャケットにエヴァンスがライナーノートを執筆しています。
彼は日本文化に造詣が深かったのか、日本の水墨画の描き方についてを引き合いに出しながら、ジャズのインプロヴィゼーションとの類似性、そこからアーティストが即興芸術に対しどのように取り組むべきか、また集団即興の難しさにも関連させつつ、『カインド・オブ・ブルー』の演奏はそれらが非常に美しく対応され、解決されていると纏めています。
参加ミュージシャンがライナーノートを書く事自体が珍しいのですが、マイルスやプロデューサーのテオ・マセロが依頼したのか、それともエヴァンス自身の発案によるものか、含蓄のある素晴らしい文章なので気になるところであります。


マイルス・デイヴィス・セクステットには一つのバンド中にマイルスの他、コルトレーン、キャノンボール、エヴァンス、3人のリーダー資質を持ったミュージシャンが在団していた事になります。
勿論マイルスの陣頭指揮があってこそのユニットとしてのバンド活動ですが、オールスターのバンドはいくらリーダーが優れていても、そうは長続きするものではありません。この3人は自分のバンドで演奏したくてウズウズし、各人脱退を考えていたでしょう。実際にコルトレーンがバンドを辞めるのを周囲に公言していました。
マイルスの声掛けにより僅か2年間でしたが、今となっては夢のようなメンバーを集結させ、時代を変えるべくオーガナイズし『マイルストーンズ』『カインド・オブ・ブルー』を創り上げます。

本作『1958 マイルス』は両大作の間に位置します。全体を通して脱力を感じさせる演奏は寧ろ純粋にジャズを楽しむに当たり、格好のエンターテイメント素材を提供しているかのようで、肩肘張らないプレイの連続は見事に各ソロイストの本領を発揮していると言えます。
それでは収録曲に触れて行きましょう。
1曲目オン・グリーン・ドルフィン・ストリートはマイルスの重要なレパートリーの一曲です。エヴァンスのリリカルなピアノソロから始まり、テーマ冒頭部分4小節のコード進行をインテンポで提示し始め、途中からベースが加わります。
この時のチェンバースのビート感、シンコペーションの確実さがバンドのグルーヴを生み、かつ活性化させています。
マイルスと同時に加わるコブの何気ないブラシワークは、サポートする者にとって一つの理想、出しゃばらずタイトに、只管リズムを正確に刻む事によって、共演者の音をクリアーに浮かび上がらせます。
この頃のマイルスはドラマーに対しさほどレスポンスを求めず、伴奏者然としたプレイを求めていました。63年以降トニー・ウィリアムスが加入してからのクインテットでは俄然ドラマーの役割が重要になり、トニーのアグレッシヴなカラーリング、そしてソロイストvsトニーの構図が出来上がりました。
マイルスのトランペットによるテーマが始まります。ミュート音を駆使したプレイはデリケートさを保ちつつ、リリカルさを表現しながらも大胆な語り口を提示し、マイルスは聴く者を美の世界に誘います。
トランペットのソロフレージングの合間に挿入されるエヴァンスのフィルイン、バッキングはいつもの程良い距離感を保ちながら、マイルスのプレイ・コンセプトを浮揚させ、更に無駄な部分を削ぎ落とし、プレイエッセンスを的確に表現するのに貢献しています。
ヴァンプを挟みブレークからコルトレーンのソロにチェンジします。落ち着き払い力の抜けた発音によるフレージングには、僅か3年前の辿々しさは微塵も感じられません。
膨大な練習量、テナーサックスを習得するための研究、音楽を知るための学習、創造に対する飽くなき探究心、全てがバランスよく合わさり、突出した部分が存在しない事に、コルトレーンのミュージシャンとしての器の大きさを感じ、しかも見事なウタとなりながら自身のテイスト、クリエイティヴさを表現しています。
低音域からアタック音を伴い上昇するフレーズの連続とその驚異的な安定感、一転して高音域での歌い回し、コード進行を自身のストーリーを語るための媒体に置き換える巧みさ、8分音符のレイドバックに対する16分音符の正確さ、挙げればきりがないプレイ・トピックスの多さに同業者としてため息が出るばかりです。
キャノンボールのソロに移ります。ブレーク部分でのピックアップフレーズを如何に洗練されたものにするかで、以降のプレイのインパクトが変わります。
ここでのリズム的にも構成音的にも衝撃的なラインの連続が即興であるとすれば、類稀なインプロヴァイザー振りを示しています。
そしてピックアップから続くフレージングの長いことと言ったら!しかもコルトレーンが殆ど使わない低音域でのサブトーンを用いながら、2オクターヴの音域を跨いで終止するテイスト、結果二人のサックス奏者の奏法の対比を感じさせます。
パーカー的なアプローチを提示せず、かと言って非バップ的ではなく、知的さも十分に兼ね備えたスタイルは、新たな扉を開けようとするマイルスに相応しいフレージング能力を備えています。
迸る色香はアルトサックスならではの音域と音色にも由来しますが、何よりキャノンボールの懐具合の大きい、ユーモアを感じさせる人柄ゆえと睨んでいます。
続くエヴァンスのピックアップソロにも脱力感を感じます。優れたプレイヤーは間違いなくリラクゼーションを基本に音楽に臨んでいます。
シングルノートは殆ど用いず、ブロックコード、ハーモニーを全てのノートに付加させたラインの連続には、エヴァンスならではの知的センスと美的感覚が輝いています。
ラストテーマを迎えます。マイルスのテーマプレイは、曲中に行われた各ソロイストによるモダンジャズのエッセンスを凝縮させた演奏を踏まえ、説得力あるリリカルなブロウを聴かせます。
エンディングにはサックス奏者二人によるハーモニーが聴かれます。極小の音量ゆえ付帯音が豊かに響き、しかも2管が合わさる事で倍音発生に拍車が掛かります。その場での即興風にプレイされ、上手く演奏を纏めています。
2曲目フラン・ダンスはマイルスの当時のガールフレンド、後に正妻となるフランシスに捧げたミディアム・スローのナンバー、優雅さを感じさせる曲調は彼女のキャラクターからでしょう。
マイルスのアウフタクト・メロディから曲が始まります。アクティヴなチェンバースのベースラインが印象的、同時にビート感が強く伝わります。
ソロの先発はキャノンボール、艶やかな音色は音量を抑えて吹奏しているにも関わらず、所謂マイク乗りが良いためで、サックス奏者理想の倍音成分を有しています。タンギングの切れ味が鋭く、そのままでは強過ぎる表現になりがちですが、ソフトに吹いているために過剰には聴こえません。
コルトレーンのソロはキャノンボールの饒舌さと音域に対比したかの、中低音域を中心に間合いを十分に取ったフレージングに徹していましたが、ソロの後半では彼ならではの高音域での主張も感じます。
エヴァンスの短いソロの最中、チェンバースの精緻を極めたベースラインが光り、シンコペーションを用いて互いに刺激し合うプレイを聴く事が出来ます。
その後ラストテーマへ,ベースのバッキングはペダルトーンを生かした的確なサポートを聴かせながら、マイルスのメロディ奏を浮かび上がらせます。
3曲目ステラ・バイ・スターライトもマイルス十八番のナンバー、後年も頻繁に取り上げていました。ここではキャノンボールが抜け、サックスはコルトレーンだけが加わります。
ベースのアルコとピアノによる短いイントロから、ゆっくりしたテンポで演奏されます。テーマの最後に高音域を提示したマイルス、チェンジ・オブ・ペースを察知したリズムセクションはすかさずスイングテンポに変わり、コルトレーンが音域を同じくしてソロを開始させます。メロディフェイクを中心に張りのあるストロングな音色で1コーラスを演奏、エヴァンスに続きます。
こちらも1コーラスをリリカルに打鍵しますがスペーシーなソロゆえでしょう、チェンバースの活発なアプローチに、エヴァンス盟友ベーシスト、スコット・ラファロ的プレイを感じます。その後リズムセクションは元のグルーヴに戻りメリハリを付け、ラストテーマに繋がります。
エンディングで再び奏でられるチェンバースのアルコが印象的です。

4曲目ラヴ・フォー・セールはお馴染みコール・ポーター作曲のナンバー、約2ヶ月前に録音された前出アルバム『サムシン・エルス』にも収録されています。
両者の演奏を比較してみると興味深い発見があります。
まずテーマは両作ともマイルスがミュートトランペットで一人朗々と吹奏します。『サムシン・エルス』ではテーマ後直ぐにキャノンボールのソロに突入、アルトサックスの独壇場が繰り広げられ他のソロは無く、その後は潔くマイルスによるラストテーマへ、サビはピアノが打鍵し再びマイルスのテーマ奏で締め括られます。
ここで繰り出されるリズムセクションのビートがマイルス・セクステットよりもずっとハードバップ色が強いのは、アート・ブレイキーのドラミングとサム・ジョーンズのベースに起因します。ビートの揺らぎを敢えて聴かせるようなラフなグルーヴはブレーキーのドラミングがオントップに位置し、リズムの主導権を握っているからです。
打鍵担当のハンク・ジョーンズのピアノスタイルはハードバップの範疇に属さない、独自のスタンスに位置するので、オーソドックスさやコーニーさを感じさせません。この事はバッキングに顕著に表れています。仮にここでウイントン・ケリーやレッド・ガーランドが演奏していたのなら、ハードバップ真っ只中の演奏に終始したでしょうが。
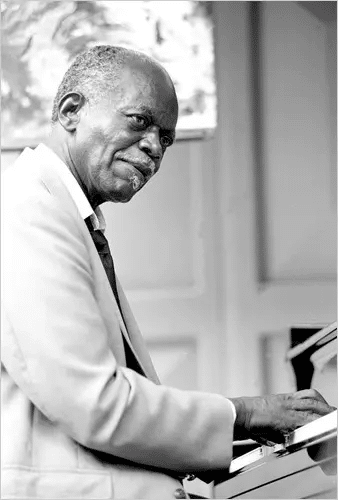
『1958 マイルス』の方は幾分テンポが速く、そしてバンドのグルーヴをチェンバースのオントップなベースが牽引し、タイトなコブのドラミングと絶妙なコンビネーションを聴かせます。

マイルスのフィンガースナップに始まり、エヴァンスによるシンコペーションが心地良い、深い打鍵音でのイントロがプレイされます。ベース、ドラムが加わるのと同時にマイルスがテーマを演奏し始めます。
ピアノトリオのグルーヴが違うだけで、マイルスのトランペットの響きが断然モダンに、都会的でスマート、シャープに聴こえるのが興味深いです。
切なくもムーディに、ニュアンスの豊富さ、音色の絶妙な使い分け、タイムを大きく取ったかと思えばシンコペーションの妙を用いて細分化されたリズムを表現し、メロディをプレイする際のあらゆる手法をマスターしているかの、抜群のテーマ奏を行います。
エヴァンスはビートの様々な位置に対し、縦横無尽にバッキング行うのでバンドのグルーヴが一層深みを帯びるのが分かります。
ソロは引き続きマイルスから、ブレーク後それまでブラシを用いていたコブがスティックでプレイし始めます。チェンバースは2ビートを主体にビートを繰り出し、サビではスイングに、その後は再び2ビートへ。2コーラス目からは全てスイングビートに移行します。
タイムの素晴らしいマイルスとリズム隊との一体感がダイレクトに伝わり、間を聴かせるべくのプレイは、トランペットならではのハイノートや多くの音列を吹かずとも、スインギーで説得力のあるプレイを行えるというショウケースとなりました。
続くキャノンボールのソロは水を得た魚の如きプレイを展開、ピックアップ部分から気持ちの籠った吹奏を行います。リズムに対する余裕を感じさせる8分音符、タンギングによる裏拍のスインギーなアクセント、ニュアンスの表出はサックス奏者最高峰の一人と感じさせます。
『サムシン〜』でのソロよりもずっと歌心、クリエイティヴさを聴かせるのは一重にベース、ドラムのグルーヴ感に起因しますが、エヴァンスの付かず離れずにも関わらず、ソロイストを鼓舞して止まないジャズスピリットを発揮するバッキング、そしてスタジオ内で横に並んでプレイするコルトレーンの存在感が、キャノンボールのミュージシャンシップを刺激しているのも一因です。
コルトレーンのソロに続きます。キャノンボールよりも8分音符のイーヴンさが際立ち、シングルタンギングを用いる事で音符の粒立ちもクリアーです。
ただコルトレーン、いつになく何か気になる事があるかの、プレイに躊躇を感じるのですが。ソロの2コーラス目からはやや58年5月時点の彼のペースを取り戻したように聴こえます。
まさかキャノンボールの絶好調ぶりに気後れしたわけでは無いでしょうが、いつもの泉の如く湧き出てくるフレージング、アイデアは控えめで、好意的に捉えれば間を活かしたプレイに終始しており、レスポンス担当のリズムセクションのアプローチも、やや大人し目に感じます。
エヴァンスのソロに移ります。透明感を湛えたタッチには他のピアニストでは行えない、ピアノの特別な鳴りを引き出せるテクニックを感じます。
加えてラインやコードワークの独特さ、フレッシュさ、タイムのスイートスポットに目掛けて確実に音符をヒットさせる瞬発力、知的にして力の抜けたプレイには押し付けがましさは皆無です。
ナチュラルにしてグルーヴィー、以降数多くのフォロワーを生み出したスタイリストの、開祖としての存在を認めることが出来ます。

その後は再びマイルスの独奏によるラストテーマへ、ラヴ・フォー・セールはヴォーカリストも多く取り上げていますが、ここでのヴァージョンは間違いなくインストルメンタルの決定版、ですが録音後ずっとお蔵入りしていて70年代にやっと日の目を見る事になります。
5曲目フラン・ダンス(別テイク)はオリジナルテイクと殆ど同じテンポで演奏されます。恐らくこの別テイクは後に録音したものでしょう、マイルスのメロディプレイはオリジナルの方にスポンテニアスさを感じます。
先発ソロ、キャノンボールはオリジナルテイクでのプレイを踏まえたかの、異なったアプローチに挑戦していますが、曲調からやや逸脱気味の感はあります。
続くコルトレーンのソロにはキャノンボールのトライアルに影響を受けたかの、チャレンジを感じます。音量も大きく、オリジナルよりもずっとアグレッシヴなプレイを展開し、個人的にはこちらの演奏に惹かれます。
エヴァンスはマイペースを保ちながらリズミックな展開を提示、マイルスのラストテーマへと続きます。エンディングに多少の不自然さを感じるのは、コブが最後に不必要なフィルを叩いた事によるものでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
