
Closeness / Charlie Haden
今回はベース奏者Charlie Hadenの1976年作品「Closeness」を取り上げてみましょう。
Recorded: January 26, 1976 at Kendun Recorders in Burbank, California (track 3) and on March 18 (track 1) and March 21 (track 2 & 4), 1976 at Generation Sound in New York City
Label: Horizon
Producer: Ed Michel
b)Charlie Haden p)Keith Jarrett(track 1) as)Ornette Coleman(track 2) harp)Alice Coltrane(track 3) perc)Paul Motian(track 4)
1)Ellen David 2)O. C. 3)For Turiya 4)For a Free Portugal
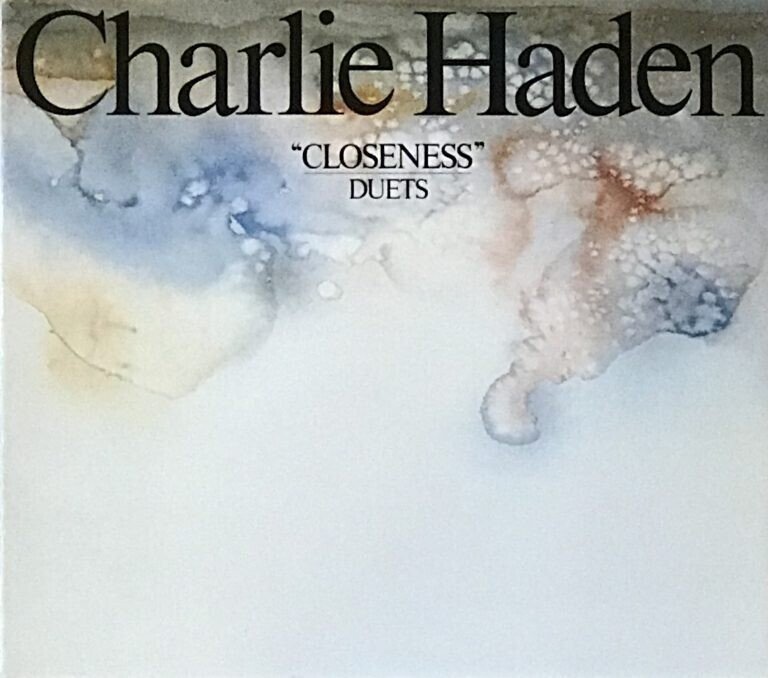
Charlie Hadenが4人のミュージシャンとDuo演奏を行なった作品です。
Duo形態で彼は色々なミュージシャンとのレコーディングを残しており本作もその一つ、直近では同76年Hampton Hawesと「As Long as There’s Music」、翌77年本作の続編とも言うべき「The Golden Number」ではDon Cherry, Archie Shepp, Hampton Hawes, Ornette Colemanたちと、そしてOrnette Colemanと全編サシで「Soapsuds, Soapsuds」、78年Christian Escudeと「Gitane」。
以降も多くのDuo作品を手掛けていますが、いずれも大変高い音楽性を湛えています。
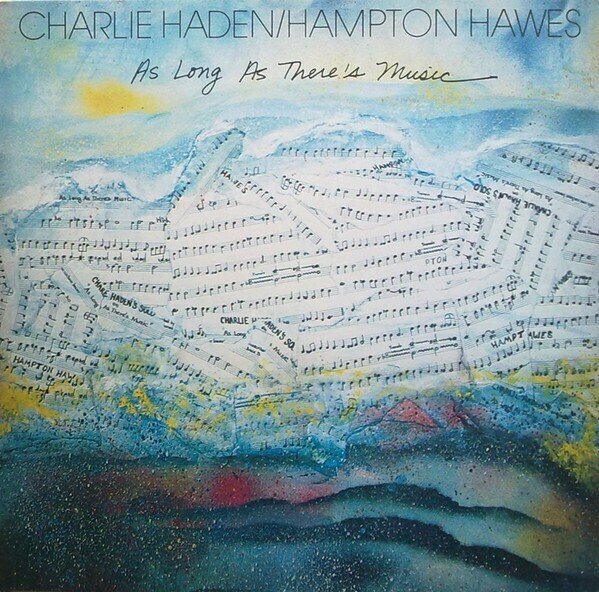



もう1枚紹介したい作品が81年録音Denny ZeitlinとのDuo「Time Remembers One Time One」(ECM)、San Francisco, Keystone Kornerでのライブレコーディングを収録したアルバムです。二人の音楽性が結実した演奏で、選曲にも工夫がなされています。ユニークなHadenオリジナルChairman Mao(毛沢東主席)、OrnetteのBird Food、Zeitlin作の表題曲、Ellen Davidの再演、アレンジされもはや別曲のCole Porter作Love for SaleやJohn ColtraneのオリジナルSatelliteとHow High the Moon(Satelliteの原曲です!)のメドレー、ボサノヴァの名曲Luiz Eca作The Dolphinなど、ライブ録音ではありますがアルバムリリースを考えて演奏をコンパクトに纏めており、両者のカラーがバランス良く凝縮しています。

Duo活動だけではなくHadenはCarla Bleyと67年に結成した13人編成のラージ・アンサンブル・バンド、Liberation Music Orchestra(LMO)も並行して活動を続けていました。
対極に位置する編成を組織していたわけです。 大は小を兼ねる、ならぬ小は大を兼ねる、サポートの達人であるHadenは大きな編成でも遺憾なく自身の音楽性を発揮しました。
70年作品「Liberation Music Orchestra」は参加メンバーGato Barbieri, Dewey Redman, Don Cherry, Roswell Ruddらの素晴らしくも個性的な演奏から、豊かなアンサンブルとインプロヴィゼーションを聴く事が出来、ユーモアに富みサウンドも充実したBleyのアレンジ、楽曲がとても魅力的です。
同時に反戦、反骨精神を躊躇することなく掲げ、スペイン内乱、キューバ革命のErnesto Guevara、戦争孤児やベトナム戦争をテーマに、組曲風にも仕上げています。
ジャケットのセンスも秀逸、メンバー全員が並ぶなかBleyとHadenがバンド名を記した旗を両脇で支えています。

2005年の同バンド作品「 Not in Our Name」のジャケットはLMOのデザインを踏襲しています。
こちらではBleyとHadenの立ち位置が入れ替わっているのにどこか可笑しみを感じ、そして背の高いメンバーが加わったために旗の高さも20cmは上がり、背景のブルーも合わさって成長と開放感を感じます(笑)。

LMOはHadenの逝去まで40年以上の長きに渡り継続され、作品を計6枚リリースしました。
11年のライブ録音2曲とHaden死後のトリビュートとしてBleyのオリジナルが3曲追加された(ベーシストは適任であるSteve Swallowが代役を務めました!)「Life/Time」がラスト作です。

Hadenのベースプレイはユニークな経歴に由来する独自なスタイルを聴かせます。
37年8月米国中部Iowa州で生まれ、家族全員がミュージシャンという環境、カントリーミュージックやフォークソングを演奏していたそうで、2歳の時にラジオのショーに家族で出演、ボーカリストとしてデビューしたそうです。15歳の時にポリオを発症するまで家族と共に歌い続けました。
08年にはHaden永年の夢であった彼の妻や4人の子供たち、親しい友人ミュージシャンRosanne Cash, Elvis Costello, Bruce Hornsby, Pat Methenyらとカントリー・ウエスタンを演奏したアルバム「Rambling Boy」を発表、楽しげに演奏している雰囲気が手に取るように伝わります。
ここではメンバーを統率するリーダーシップに加え、家長たる威厳と愛情を感じます。
またOrnetteのバンドやKeithと演奏している時と全く異なり、コードの1度と5度しか弾いていないのですが(汗)、絶妙なビート感と音の立ち上がり、いつもの深い音色、彼のルーツはこれに違いないと実感しました!

14歳でCharlie ParkerやStan Kentonのコンサートに触れ、ジャズに興味を持つようになり、後にポリオの症状を克服してからベースを独学で演奏し始め、ハーモニーやコードをBachの作品から学びました。
Los Angelesで本格的に音楽を学ぶべく、その費用を貯めるためにMissouri州にあるテレビ局のハウス・ベーシストとして演奏していた経歴は、彼の早熟ぶり物語ります。
20歳の時にLAに居を移し、Hampton Hawesを尋ねRed MitchellやPaul Bleyと親交を持ち、Art Pepperとも共演、かの名ベーシストScott LaFaroとはアパートの部屋をシェアしていたそうです。Ornetteの60年録音作品「Free Jazz」はLaFaroとのツーベースでの演奏を収録した、奇跡の名演奏です。

様々なミュージシャンと交流できたのは演奏能力はもちろん、彼のフレンドリーな性格からでしょうが、Ornette Colemanとは音楽の方法論やコンセプトに合致するものを見出し、運命的な出会いを感じていたようです。
59年にOrnetteの代表作「The Shape of Jazz to Come」のレコーディングに参加します。Hadenのプレイは幼い頃から経験したカントリーやフォーク・ミュージックに影響されたスタイルとTexasブルースの要素、そしてOrnetteのMicrotonalと言われる音楽的方法論とが合わさり、初期の段階からオリジナリティを獲得していました。
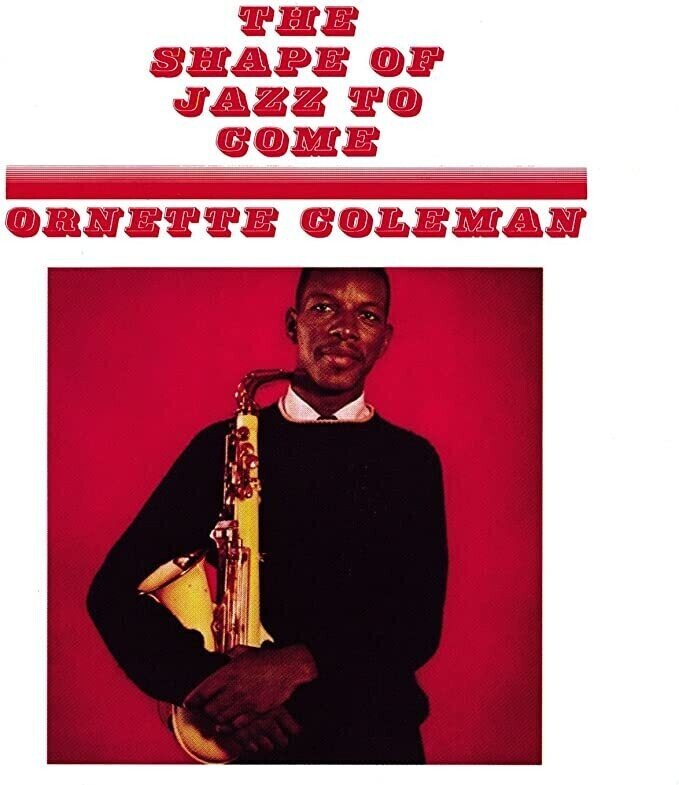
その後Ornetteのカルテットと共にNew Yorkに移り、ジャズクラブFive Spotでの6週間に渡る演奏の中で即興演奏時に新たな方法論を見出しました。
Haden曰く「我々の初めの頃の演奏は即興演奏時に曲のパターンの類を追い求めていたけれど、OrnetteがNew Yorkに移るなり曲のパターンを演奏しなくなった。曲のブリッジやインタールードの類もだ。言ってみれば耳だけを頼りに演奏すると言うことで、それからは徹底的に彼について行くように心がけ、彼がその瞬間、瞬間に感じた事で発生した新たなコードの構造、提示するコードチェンジを追うように、とにかく努めようとしたんだ」。
60年にドラッグ問題でOrnetteのバンドを離れ、自らの意思で薬物リハビリテーションプログラム施設Synanon(Joe Pass, Art Pepper, Chet Bakerたちも入所しました)で63年まで治療を受け、その後社会復帰を果たします。施設で出会った女性Ellen Davidと後に結婚しました。
64年に音楽活動を再開しJohn Handy, Denny Zeitlin, Archie Shepp, Attila Zollar, Thad Jones/Mel Lewisたちとプレイし、67年にOrnetteのグループに返り咲きます。バンドは70年代初頭までアクティヴに活動しており、HadenはOrnetteの複雑なアドリブ・ラインの転調に実に器用に対応することが出来るとベーシストと、評判が立つほどでした。
ベース奏者は基本的にコードのルート音を強拍(1, 3拍)に演奏し、コード感の基音を提示する役割を担います。
サックスを擁したカルテットであればその上にピアノのコード音が成り立ち、サックスが奏でるラインがコード感というデコレーションを纒い音楽が成立しますが、HadenのベースはOrnetteとの長年の共演で培われたアプローチから、演奏者が想定するサウンドやコード進行、構造に対して即座に反応し、瞬時に寄り添い、都度に的確な音をプレイします。
時にはコードのルート音を演奏せずにそのコードのサウンドとはかけ離れた音を弾きますが、ソロイストやバッキングのサウンドとの関係から、興味深いテンション感を伴って〜ジャズの醍醐味のひとつです〜音楽的に成立するのです。
他のベーシストと演奏を聴き比べてみてください。誰よりも深淵な音色、スピード感が半端ない音の立ち上がりとon topさはもちろん、決してリック(指癖)やパターンではない常にスポンテニアスでクリエイティヴな音使い。
ベースと言う楽器を鳴らす、操るテクニックに関しては常にマエストロぶりも発揮しますが、共演者に触発された際の瞬発力、独自のラインを構築するセンスで右に出るものは存在しません。
一般的なベーシストとは全く異なる演奏を聴かせているのです。 DuoはHadenにとって、彼の個性である「相方のアプローチを瞬発力を伴って引き立てる」を、最も的確に表現できるシチュエーションなのです。

それでは収録曲の演奏に触れて行きましょう。1曲目のDuo相手はKeith Jarrett。Keithとは彼のトリオで67年「Life Between the Exit Signs」からの共演歴になり、ドラマーにはPaul Motianを迎えたKeith Jarrett Trioとしての演奏のほか、Dewey Redmanを迎えたいわゆるAmerican Quartetとしても名作を数多くリリースしています。Quartet作品では「Treasure Island」を挙げたいと思います。

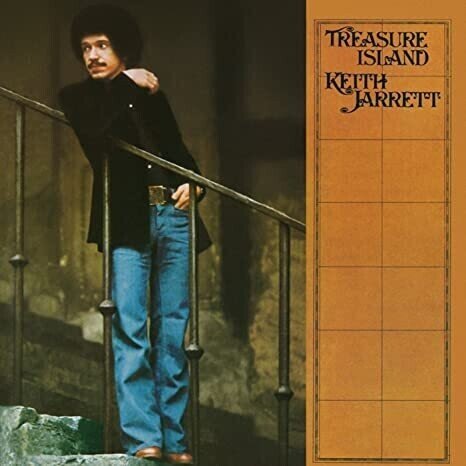
演奏曲はHadenの代表ナンバーEllen David、前述のSynanonで出会い、奥様となった女性に捧げたナンバー。
美しいメロディとドラマチックな構成を有すコード進行、Keithのピアノが実に叙情的に歌い上げます。
Haden自身も作曲したときにKeith以外にこの曲を弾きこなせるピアニストは存在しないと思ったそうです。
イントロはベースのトレモロから始まり、良く伸びる太くふくよかな音色で奏で、ムードを高めます。ベース自体の音色は多少ピックアップ音が混じりますが、生音の迫力を聴かせています。
聞くところによると彼の使用コントラバスは大変歴史的価値のあるヴィンテージ楽器、移動のことを考えると容易くツアーには持って行くことが難しいそうです。
弘法筆を選ばずではありますが、やはり良い楽器はそれなりの音がするのです。
Keithの力強く、しかしリリカルなピアノタッチから繰り出されるライン、コード、リズムはジャズピアニスト史上最高峰に位置するクオリティ、デュエットで対等に共演出来るのはHadenを置いて他には考えられません。
作曲者自身であるので、曲の解釈をどのようにするかは全権委任されて然るべきですが、それにしてもKeithの演奏するメロディやラインに対処していくアプローチは小気味良いまでに自由奔放です!
Keithを主体としてHadenがどのような音を繰り出しているのか、Keithのフレージングとの関連性、リズム的なアプローチを体感しつつ両者の絡み具合を認識する、また放置し出しゃばらずにKeithの成り行きを見守る部分の必然性(なぜ弾かないのか、どうして抑制しているのか)を考えてみる、などなど演奏の中により入り込み、音が耳に飛び込むのに身を任せるだけでなく、より一歩演奏に入り込んでプレイを聴くことをお勧めします。
TVのバラエティやお笑い番組は見ていて殆ど間違いなく楽しく笑わせて貰えます。そのように構成、プログラムされているから当然ですが、でも視聴後何も残りません。慣れとは恐ろしいもので「何をあんなに笑っていたのだろう?」とさえ考える事も無くなるのは、全てが受動であるからです。
Jazzにもそれらに近いテイストを持つものもありますが、少なくともHadenとKeithの音楽は真逆の位置にあります。自ら音楽に入っていかない限り彼らの真髄を体感する事は出来ません。
ベースソロが始まりHadenはメロディの断片を演奏します。Keithはまるで輪唱のように同じメロディをプレイ、Hadenはそれに対応するべく再びメロディの断片を弾き始めます。互いにメロディの応酬を行いますが、その間に聴かれるHadenのアドリブライン、繰り出すフレーズの崇高さ、Keithのフィルインの相応しさ、美しさには鳥肌が立つほどです!
Ellen David

2曲目は盟友Ornette ColemanとのDuo、曲のタイトルも彼のイニシャルからO. C.です!
HadenのナンバーですがまるでOrnetteが書くオリジナルの如きメロディライン、雰囲気、HadenがOrnetteの作風をイメージして作曲したのでしょうか。
印象的なテーマ後、アップテンポのスイングでカンバセーションが開始されます。 Ornetteの吹くラインは独創的、Ornette節も感じさせますが、何より常にクリエイティヴにフレッシュなラインを構築している事に驚かされます。決して指癖の類の手なりではなく、毎回違ったアプローチで対応しているのです。
何かのインタビューでOrnetteは「Charlie Parkerはコード進行に対する横の流れを重んじて演奏しているけれど、僕の演奏はコードに対するフレーズだ」と言うような趣旨の発言だったと記憶していますが、彼にとって自身の吹くアプローチがフレーズという捉え方は驚き以外ありません。僕自身のフレーズの概念が揺らぐほどです。
Parkerの演奏こそがまさしくフレーズによるアプローチと捉えていました。 Parkerスタイルの継承者Sonny Stittは全てがフレーズによるアドリブ、膨大なフレーズをストックし順列組み合わせの巧みさを活かして流暢な演奏を聴かせます。Parkerはフレーズの組み合わせも素晴らしいですが、スポンテニアスなアプローチも随所に聴かれるフレキシブルな方法論ではあります。
これらを踏まえるとOrnetteのフレーズとは、解釈の全く異なる次元に存在しています。ジャズ界の革命児と呼ばれる所以でしょう。
Hadenの猛烈なスピード感を伴った独創的ラインの上で、これまた異次元から発せられたかのような「フレーズ」をOrnetteが奏でます。常に一触即発、Ornetteが主体ではありますが互いを良く聴き合い、Ornetteの音楽性を100%信頼し尊敬するHadenならではの追従アプローチ、転調したキーに確実に合わせています。
翻ってみればOrnetteもHadenに対し全く同様です。
ひとしきりの会話後Hadenのソロ、アルトソロの余韻をしっかり残しながら、テーマの断片も交えつつ深い世界を語ります。 突然アルトが切り込み第二楽章がスタートします。暫しHadenはファスト・スイングを提示しますがOrnetteは朗々と吹き、先ほどとは異なったアプローチを模索しているようです。
その後もHadenは様々に仕掛けますがテンポ的にはもう少し遅いスイングをイメージしているようで、Ornetteは動かざること岩の如し。アルトのアッチェルランドやリタルダンド、ルパートに合わせる、フレーズに呼応したり、これらの様は長年の共演歴の成せる技以外の何者でもありません。
そしてほど良きところでテーマを吹き始めます。 ごく初期の「The Shape of Jazz to Come」の時とは全く異なる次元での深遠な世界、この演奏は本作の価値を全く高めました。
Ornette Coleman

3曲目はAlice Coltrane、彼女はピアノ奏者ですがここではハープを用いてのDuo、タイトルFor Turiyaとは彼女のサンスクリット語名Turiyasangitanandaに由来します。
Hadenが彼女のアルバムに参加したのは70年録音「Journey in Satchidananda」収録Isis and Osiris、New YorkにあったThe Village Gateでのライブ録音になります。

Aliceのハープ演奏に感銘を受けたHadenが彼女に捧げて曲を書きました。
とは言ったもののメロディを弾くのはHaden、Aliceは主にバッキング担当、テーマ後、Hadenの壮大なソロが聴かれます。Aliceは小さめの音量でバッキングを入れますが、そもそもハープの音色自体が効果音的なので、ジャズ演奏で用いられることはあまりなく、難しい楽器のチョイスです。Hadenひとしきり語ったところでルート音を決め、ハープソロへ。ラインを紡ぐように弾き、スペーシーな演奏を展開しますが、ハープのうねるような音階のラインは大海原を泳ぐイルカのようで、水中で回転したり時たま水上に顔を出したり、二人は気持ち良さそうに演奏を繰り広げます。

4曲目For a Free Portugalは盟友Paul MotianとのDuo、Motianはパーカッションで参加します。しかしこれは演奏というよりもメッセージ、しかも政治的なものとして収録されています。
曲の冒頭に聴かれるアナウンスメントは聴衆に対するHaden自身のスピーチ「この曲をモザンビーク、ギニア、アンゴラの黒人民族解放戦運動に捧げます」。Ornetteが録音していたテープから起こされたものですが、71年Portugal Cascadeで行われたインターナショナル・ジャズ・フェスティバルにHadenはOrnetteのカルテットで出演します。その時にLMOで演奏していた自身のオリジナルSong for Che(Guevara)を演奏し、Dewey Redman, Ed Blackwellたちと反戦のために抗議姿勢を示したのです。
演奏の途中にはオーバーダブされたアンゴラ解放人民運動のテーマ曲と、68年人民運動軍がPortugal軍と交戦した際の銃声も聞くことができます。
Portugalはかつてアフリカから奴隷要員を南北アメリカ大陸に輸出していた最大国であり、アフリカ大陸植民地化を率先して行いました。Hadenの挙げた3つの国はかつてのPortugalの植民地で、50年代以降激化するアフリカ大陸の黒人開放と共和国独立にPortugalは大変ナーバスになっていました。
当然の成り行きといえば違いないのですが、翌日HadenはLisbon空港でPortugal秘密警察に逮捕されます。しかし4時間後に米国大使館の猛烈な抗議で即釈放となりました。この出来事が動機となり、この演奏が生まれたのです。
本演奏は70年代初頭の時代のなせる技ですが、反戦運動家Hadenならではのテイク、曲自体はスパニッシュ調のムードを8分の6拍子で演奏しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
