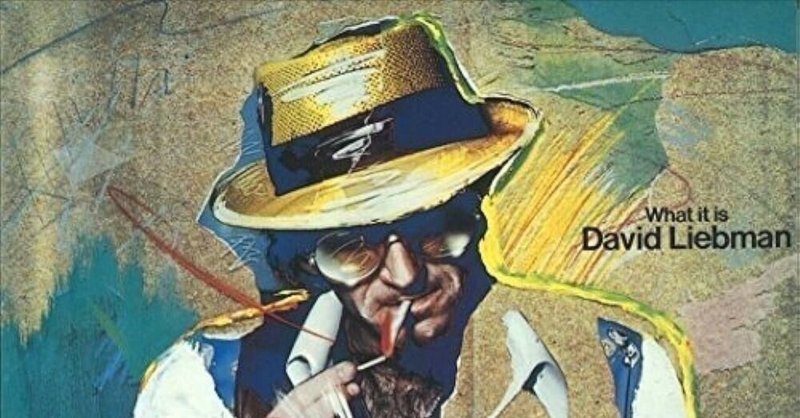
ホワット・イット・イズ/デイヴィッド・リーブマン
1979年録音デイヴィッド・リーブマンのリーダー作『ホワット・イット・イズ』を取り上げましょう。
録音:1979年12月11日〜16日
スタジオ:サウンド・アイデア・スタジオ、ニューヨーク
エンジニア:ジム・マッカーディ
プロデューサー:マイク・マイニエリ
レーベル:CBS/Sony
(ts, ss)デイヴィッド・リーブマン (g)ジョン・スコフィールド (key)ケニー・カークランド (b)マーカス・ミラー (ds)スティーヴ・ガッド (perc)ドン・アライアス (vib)マイク・マイニエリ
(1)パオリズ・ヴィジョン (2)ミス・ユー (3)ホワット・イット・イズ (4)ア・ダンス・フォー・ユア・ソウツ (5)チック・チャット (6)ユー・オンリー・シー・ユー

まさに80年代に差し掛からんとする79年12月、ニューヨーク・マンハッタン、サウンド・アイデア・スタジオにジャズ、フュージョン・シーンを代表するミュージシャンが結集しました。デイヴィッド・リーブマンの日本企画アルバム『ホワット・イット・イズ』レコーディングのために。
プロデューサーにはヴィブラフォン奏者のマイク・マイニエリを迎え、ギター、ジョン・スコフィールド、キーボード、ケニー・カークランド、ベース、マーカス・ミラー、ドラム、スティーヴ・ガッド、パーカッション、ドン・アライアス、眩いばかりに豪華なメンバーが集められました。
演奏形態、内容は彼らにはお手の物のフュージョン・ミュージックに違いないのですが、リーブマンのテイストが存分に発揮され、通常とは一味も二味も異なるサウンド、独特の屈折感を有しながら創造性に富み、オリジナリティの表出には一切の躊躇なく、真っ直ぐに前を見据えたヴィジョンを感じます。
サウンド的には重くダークでいながら、スパイスとして加えたポップさがプレイに深みを与えています。
リーブマンのカラーだけでは底無し沼にどっぷりと嵌まり込んだかの、粘着的なサウンドの纏わりつきが気になるところですが、それはそれで孤高のリーブマン・ミュージック、彼の音楽には襟を正してオーディオ・スピーカーの前に向き合う価値が十分にあり、頻繁ではないにせよクセになります。
本作ではプロデューサー、マイニエリの采配によりいつものリーブマン・ミュージックはそのままに、そして更に彼の音楽に容易に入り込み、サウンドをとことん堪能出来るような配慮が成されています。彼の諸作中最もリスナーに優しいアルバムと言えましょう。
リーブマンのソロに対するガッドを中心軸としたインタープレイの濃密ぶり、マーカス、アライアスの鉄壁状態にまで一体化したサポート、ジョンスコの危なさ満載にキレッキレのカッティングとホーン奏者の如くレイドバックしながらグルーヴするソロ、カークランドの煌びやかにして知的極まりないプレイ。
収録曲自体の素晴らしさと、顔が異なる全ての楽曲の多彩さ、充実ぶりには目を見張るものがあります。
当時マイニエリはアーティストのプロデュースやアルバムのアレンジ、オーケストレーション、コンダクトを頻繁に務めていました。プロデュース作品としては本作の他、渡辺香津美氏『トチカ』、カーリー・サイモンの3作『カム・アップ・ステアズ』『トーチ』『ハロー・ビッグマン』、ステファン・ビショップ『レッド・キャブ・トゥ・マンハッタン』、アレンジャー、プレイヤーとしてアート・ファーマーの『ヤマ』、オーケストレーションとコンダクター、プレイヤーとしてジョージ・ベンソンの『リヴィング・インサイド・ユア・ラヴ』などのジャズ・フュージョン、ポップスの名盤に関わります。
プレイヤーとしては常にヴィブラフォンのテクニシャンぶりを発揮し、参加バンド、ステップスやステップス・アヘッドの諸作に於ける作曲や編曲の才能にも非凡さを感じさせます。
前述のファーマー作品『ヤマ』収録、ウェザー・リポートのナンバーでジョー・ザヴィヌル作曲ヤング・アンド・ファイン、ここでの名アレンジにその事が如実に現れています。
他者の音楽性をトータルに俯瞰しながらサウンド細部の調整を確実に務め上げられる、バランス感に富んだ音楽家としての存在が光ります。




リーダーのリーブマンは本作『ホワット・イット・イズ』発表後、暫くしてテナーサックス演奏を封印し、ソプラノサックスを自身のヴォイスに絞る「宣言」を発します。
彼自身色々と考える事があったようですが、当時他の追従を許さない圧倒的な個性を発するテナープレイを封ずるとは俄には信じられませんでした。結局約6年間ソプラノ奏者に専念する音楽活動を行います。
しかし彼のテナーサウンドには根強い人気があり、プレイを必要とする音楽仲間は後を立たず、90年代に入ってからサイドマンとしてのレコーディング作品に対し、テナー奏を1, 2曲復活させる動きが見られ始めました。
そして96年1月、満を持して作品『リターン・オブ・ザ・テナー』を録音します。

本作のリリースでワン&オンリーの”エグエグ”リーブマン・テナー・サウンドが復活したわけですが、個人的にはアクの強さの中にもきめ細やかさ、音色の深みを感じさせる封印前のテナー・プレイの方に魅力を感じ、復活後の演奏や音色には大味を否めません。
『ホワット・イット・イズ』でのテナープレイは熟れ切った果実の如し、果物や肉、マグロなど腐る一歩手前が美味いと言われてます。ここでは熟成と言う言葉が相応しいでしょう。
個人的にリーブマンはソプラノに専念せずにテナーを吹き続けていれば、更に凄まじい境地に達していたのではないかと想像しています。こればかりは本人の音楽的な流れがあってこそですが。
彼のテナーの話ばかりになってしまいましたが、ソプラノの素晴らしさ、闊達ぶりは全く相変わらず、近年はプレイや音楽性を更に極めた感があり、まさに孤高のソプラニスタとしてジャズ界に君臨しています。
ジョン・コルトレーンやエリック・ドルフィー、スティーブ・レイシー、マイケル・ブレッカー、スティーヴ・グロスマンにまで教えたカリスマ・サックス・トレーナー、ジョー・アラード仕込みのソプラノサックスを自在に操る申し分の無いテクニック、音色ではコクとエッジ、枯れた味わいのブレンド感が、ある種理想のバランスを持ち、個人的に憧れのサウンドです。マルチフォニックス〜重音奏法や効果音的アプローチ、それこそ猫の発情期を思わせるエフェクトには驚き、圧倒されました。
一昨年ニューヨークのライヴハウスで行われたYouTube演奏を見るとこの事を実感しますが、同時にどうも彼の体調が優れないのでは、とも見受けられます。
マイケル・ブレッカー、グロスマン亡き後のユダヤ系コルトレーン派テナーサックス奏者最後の牙城としてのリーブマン、可能な限りパッショネイトなプレイを続けてもらいたいものです。

それでは収録曲について触れて行きましょう。
1曲目パオリズ・ヴィジョンはリーブマンのオリジナル、冒頭オーバーハイム系シンセサイザーが雰囲気作りを行い、ギターとベースのユニゾンによるハイパーなパターンがプレイされ、ガッドはシンプル且つタイトにリズムを刻み、リーブマンはソプラノを携えて明快にメロディ奏を行います。
コール&レスポンス状態でのテーマには崇高さすら感じますが、すぐさま対比するダークなパートが現れ、引き続き多層的に練られたアンサンブルへ、シンセサイザーのハーモニーが支配的に響き、ここでのサウンドにはノーブルさを感じます。
つくづくリーブマンのソプラノ・サウンドのアカデミックさを再認識するナンバーに仕上がっているのですが、続くソプラノソロの素晴らしさと、ガッドを軸としたリズム隊のレスポンスには完璧とも言えるインタープレイの妙味を感じます。
テーマ後ロングノートを出発点とし、ガッド〜マーカスの生み出すリズムのゆりかごにリーブマンは身を委ねつつ、ジョンスコのカッティングがゆりかごのサスペンションとなり、超安定感ゆえそのままいくらでもステイ出来そうな状態から次第に脱却を図ります。
ガッドのプレイは通常のドラマーではあり得ない手順によるフレージングの連続、露出する機会が多いために独特さは耳馴染みですが、レスポンスに関しても常人とは異なるアプローチを聴かせ、寄り添いつつ、ダイレクトに反応す場合もありますが付かず離れず、潔い放置などを行います。
一方リーブマンはガッドの手の内を熟知しているかの、呼び込みのフレージングを用いてガッドのプレイの誘導を図ります。巧妙な策略は功を奏し、リーブマン、ガッド、互いにインスパイアを繰り返し、二人のユダヤ系ミュージシャンの音楽的知的共同作業は深淵な世界を構築します。マーカス、ジョンスコ達の貢献度も見逃すことの出来ない事象であります。
エンディングは重厚なシンセサイザーのサウンド海にリーブマンが文字通り身を投じ、心地好く泳いでいるが如しです。
ここでのシンセサイザーはマイニエリが演奏しているのではないか、と感じています。ライナーにはマイニエリがヴィブラフォンを演奏している事になっていますが、アルバムでは一切聴く事が出来ません。

2曲目ミス・ユーはローリング・ストーンズのナンバー、78年に全米ヒットチャート1位を記録しました。
ストーンズのオリジナル演奏はずっとテンポが速く、ミック・ジャガーのアクの強いヴォーカルがシャウトしながら、時に囁くように、呟きながらも進行します。
本テイクは実にキャッチーにしてナイスなセレクションです。ヒット翌年に取り上げ、楽曲が耳目の新しいうちにリーブマンに思う存分咆哮させました。
ミス・ユーのダークな部分を強調すべくのスローテンポ設定、ガッドのヘヴィーにして超タイトなグルーヴを根底に、マーカスのスラップ・ベースを存分に暴れさせ、ジョンスコのロック魂を刺激させるため放し飼いの如く好き放題にカッティング、フィルインをプレイさせ、リーブマンはストイックさを感じさせるメロディプレイに始まり、次第に熱くハードなプレイに変化しつつも、ジョンスコにフィルイン、合いの手をとことん挿入させるために間を巧みにたっぷりと取ります。
これはリーブマンのかつてのバンマス、マイルス・デイヴィスのプレイ手法に他なりません。間の使い方、メンバーにレスポンスを促す達人がマイルスです。
そしてテーマ後いきなりリーブマンの凄まじい雄叫びからソロが開始されます。このインパクト、メリハリにこそマイニエリのプロデュース力が反映されていると感じました。「デイヴ、ソロの出だしはシャウトで行こうか。説得力が倍増するよ」のようなマイニエリのサジェストが、恐らくあったと思います。
ソプラノの猛烈なラインの連続に全く確実にレスポンス、合いの手を入れるジョンスコのセンスにはロックプレイヤー的テイストが見受けられますが、これは紛れも無くジャズスピリットを持つギタリストだからこそのアプローチです。巧みなフィルインを次々に繰り出す名手ぶりにつくづく脱帽してしまいます!
ジョンスコも若い時にストーンズを聴いたに違いないでしょう、ストーンズのギタリスト、キース・リチャーズのプレイが頭を過ったかも知れません。

3曲目タイトル・ナンバー、ホワット・イット・イズはリーブマン作曲、同名の彼の自伝が存在します。ジャズピアニストにして評論家のルイス・ポーターとの対話形式で書かれています。

テナーサックスの低音域を生かしたダーク且つファンキー、7thコードの#9thが暗明るさを感じさせるファンク・チューン。ジョンスコのディストーションを効かせたギターのユニゾンがメロディを一層重厚なものに仕立て、マーカスのベースワークがリズムのヘヴィーさに大きく貢献しています。
A-A-B-A構成のこの曲、2度目のAからはリーブマンがメロディを1オクターヴ上げて演奏し、サビであるBではグルーヴとムードが変わり、楽曲のメリハリを付けています。テーマ・メロディにおけるテナーとギターのニュアンスの合致度は完璧と言って良いでしょう。
ソロの先発はジョンスコ、一聴彼と分かる特徴的なギターの音色、ピッキングの正確さ、撥弦の滑舌の良さは他に類を見ません。実に豊富な表情付けを行いながら、自身のウタを歌おうとする姿勢が明確です。
フレージングもジョンスコ節満載ですが、同時にサムシング・ニューにもトライし、レイドバックしながらホーンライクなインプロヴィゼーションを行うスタンスはジャズそのものです。
ジョンスコがフレージングの最終部を纏め上げ、リーブマンのソロに変わります。タイトル曲ならではの気持ちの籠ったブロウによる入魂のプレイ、ソロの中ばに彼には意外な奏法であるグロウトーンも交え、更にリズミックなアプローチを繰り返す事により、静観していたガッドが刺激を受けアクティヴに動き始めます。ソロの終盤には叫びとも取れるフラジオ音での重音も聴かれ、インパクトを示しながらソロを終え、ラストテーマに向かいます。その後は次第にディクレッシェンドしながらも、メンバー全員怪しさを表現するのを怠りません。
4曲目ア・ダンス・フォー・ユア・ソウツはリーブマン出色のオリジナル、複雑な構成と変拍子のリズムが合わさり、魅力的なナンバーに仕上がっています。
テーマはじめは4/4拍子で演奏されますが、途中から5/4拍子が3小節、6/4拍子が1小節の変則的な4小節パターンに変わり、ソロはこの変拍子パターンで行われます。
ごく自然にプレイされるため一聴4/4拍子と何ら変わりなく感じられますが、実は難易度の高いリズム・フィギュア、ここでインプロヴィゼーションを闊達に繰り広げるには困難を極めますがリーブマン、カークランドは持ち前の音楽性と、リズム隊の素晴らしいサポートを得て縦横無尽に演奏を繰り広げます。
冒頭にマーカスのベースソロが聴かれます。当初ルパートによる演奏と感じましたが、よく聴けばガッドが音量小さくインテンポでサポートしています。
プレイはフレットレス・ベースを駆使したパイオニア、ジャコ・パストリアスを彷彿とさせます。加えて音色の深さや楽器を自在に楽器を操るテクニック、ガッドと繰り広げるグルーヴとレスポンスには、この時20歳とは信じられない豊かな音楽性を披露しています。

ジョンスコのカッティング、トレモロを含めたフィルイン、アライアスの巧みなパーカッション・プレイが隠し味となり、演奏をアクティヴなものに仕立てています。
先発ソロはリーブマン、芳醇なテナーサウンドを携えながら変拍子をものともせずに突き進むイマジネイティヴなラインの連続には、圧倒されます。
具体的には8分、16分音符の拍に対するリズムのスイートスポットにジャストミートする的確さに始まり、雄弁に語ったかと思えばモノローグのようにボソボソと呟き、フリークトーンを用いてアグレッシヴさを表現しながらもサブトーンを用いて音色を変化させ、間を取りつつジョンスコやカークランド、アライアスにレスポンスを委ねながらレイドバックしつつジャジーな雰囲気を表現し、アウトしたラインで場に緊張感を持たせる事も怠らず、短いソロスペース中に可能な限りの多彩な表現を行なっています。
続くカークランドのフェンダー・ローズのソロはハービー・ハンコックをルーツに感じさせるアプローチに徹し、饒舌にプレイを展開します。
些かオントップなタイムの取り方は弾き捲りの打鍵と合わさり、リーブマンのスペーシーさとの対比になり得、ガッドを中心にしたリズム隊とのアプローチの違いによる異なったレスポンスの応酬はこれまたスリリング、特にマーカスの更なる暴れぶりには凄まじさと同時にやんちゃさも感じました。
エレピのソロ後にヴァンプを用い、ラストテーマに入る必然を設けます。
エンディングに向けガッド、そしてアライアスが順次技を繰り出し、変拍子とは思えない魅力的なグルーヴを聴かせますが、残念な事に次第にフェードアウトを迎えます。その後ろで重音奏法〜マルチフォニックスを聴かせるリーブマンは、効果音的とは言え存在感を誇示します。
5曲目チック・チャットはその名の通りチック・コリアにリーブマンが捧げた変態ラテンナンバー(笑)。こちらにもリーブマンの非凡な作曲センスが表れています。
77年に弦楽四重奏団を含めたコリアのグループによるワールド・ツアー、リーブマンがサックス、フルート奏者として抜擢され日本を含めた各国でプレイし、コリアとリーブマン個性的な二人が、ミスマッチギリギリのレヴェルで相剋するが如く鎬を削ります。
例えばリーブマンのダークでエグい音色、聴き手の内面に挨拶なしに入り込むかの危ないニュアンス付けを伴った、コリア作の名曲スペインでのプレイは、異次元の産物でした。
コリアはツアー中にリーブマンの音楽性、人柄に惚れ込みブルース・フォー・リーバーストラウムと言うナンバーを作曲し彼に捧げます。
ツアーの途中まで二人は蜜月関係を築きますが、リーブマンの何かの行いか、発言がコリアの逆鱗に触れ、突如として中違いします。コリアはリーブマンに絶縁状を叩きつけるが如く手の中指を突き上げ、その後一切の関係を断ちますが、リーブマンはコリアとの共演経験を誇りに思い続け、本演奏に繋がります。
冒頭には物悲しくもリズミックでスピード感のあるベースパターンと、ギターの不協和音ギリギリのカッティング、両者により複雑にリズムが入り組み、そこにソプラノの猛烈に怪しげなメロディラインが入り、コリアが得意とするスパニッシュに類似するような、若しくは中近東的サウンドが不安感を醸し出します。
更にソプラノとリズム隊とのコール&レスポンスが繰り返され、その後コリア的なリズムのキメが入ります。
感じるのはさぞかしリーブマンとコリアの会話(チャット)は意味深で怪奇なものだったのでは、と言う事です(笑)。
ドラムとパーカッションによる4小節ヴァンプが入り、リズムはカリプソ、サウンドはメージャー系に一転します。とは言え随所に訝しい隠し味が盛られ、短いスパンで様々なパートが続け様に登場します。
いつの間にかソプラノソロにスポットライトが当てられます。ここでもリーブマンは間を多く設けて、リズムセクションとの音楽的レスポンスを持つと言う、会話の場を作ります。
マーカスはベースパターン遵守のため会話には参加出来ませんが、ジョンスコはカッティングに回りつつも会話に積極参加、そしてカークランドのハッとするフィルインの数々、ガッド、アライアスの良い意味で至極もっともなレスポンスには、濃密な会話を感じました。

6曲目ユー・オンリー・シー・ユーはゴスペル・ライクなリーブマンのオリジナル、アルバムのエピローグを飾るに相応しいナンバーです。
キース・ジャレットを彷彿とさせる、カークランドのピアノ奏によるイントロに始まり、リーブマンのソプラノが爽やかなメロディを豊かな音色、ニュアンスでプレイします。カークランドのバッキングはまさに痒い所に手が届く妙味を聴かせます。
美の世界にありながら一筋縄では行かないテーマ構成はさすがリーブマン、リリカルさと複雑さが入り混じり、コード進行に特徴を持たせ、美の世界にどっぷりと浸かりそうなオーディエンスに、踏み止まらせるかの刺激を与えながら、楽曲が進行します。
ソロはカークランドから、ピアノのタッチ、音色が何と言っても素晴らしく、ずっと聴いていたくなる魅力を放ちます。
リーブマンのソロはテーマのコード進行を巧みに利用し、音量をグッと抑えながらアグレッシヴさを内包するプレイに徹しています。
曲のエンディングは偽終止を何度も用い、終わったと見せかけて未だ終わらない、ネヴァー・エンディングを演じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
