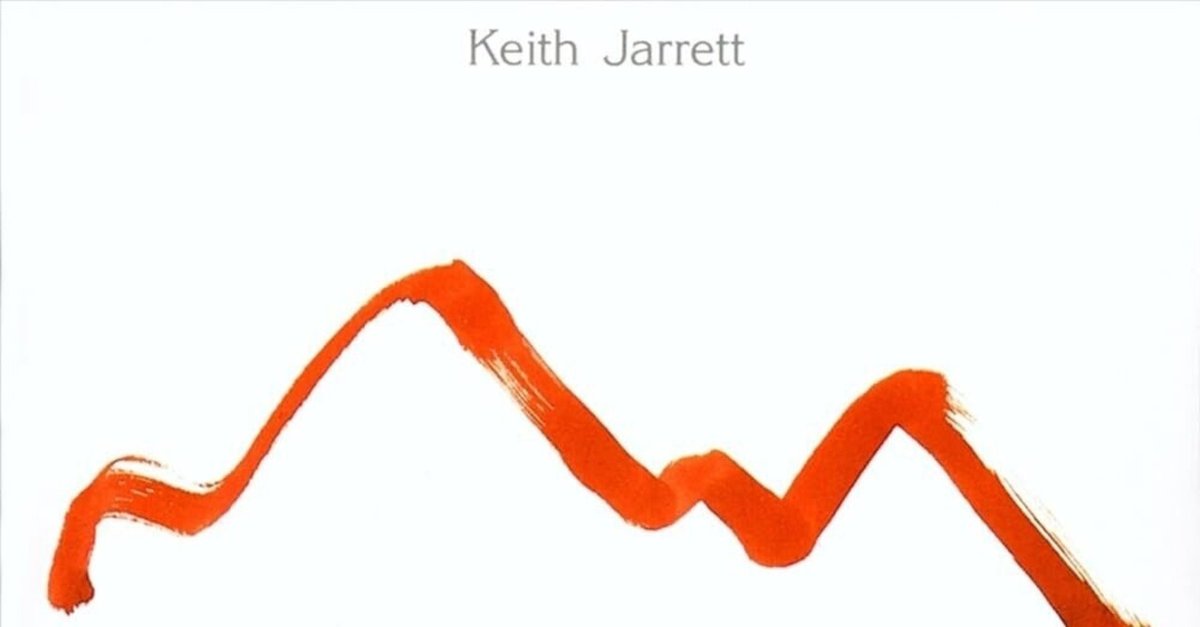
パーソナル・マウンテンズ/キース・ジャレット
ピアニスト、キース・ジャレットの1979年ライヴ録音リーダー作『パーソナル・マウンテンズ』を取り上げましょう。
録音:1979年4月2日、13日、17日
会場:新宿厚生年金会館、中野サンプラザ・ホール
エンジニア:ヤン・エリック・コングスハウク
プロデューサー:マンフレッド・アイヒャー
レーベル:ECM ECM1382
(p, perc)キース・ジャレット (ts, ss)ヤン・ガルバレク (b)パレ・ダニエルソン (ds)ヨン・クリステンセン
(1)パーソナル・マウンテンズ (2)プリズム (3)オアシス (4)イノセンス (5)レイト・ナイト・ウィリー

キース・ジャレット、彼の所謂ヨーロピアン・カルテットの日本でのツアー、東京新宿にあった厚生年金会館、中野サンプラザ・ホールでの演奏を収めたライヴ録音になります。
メンバーはキースの他テナー、ソプラノサックス、ヤン・ガルバレク、ベース、パレ・ダニエルソン、ドラムス、ヨン・クリステンセン。
ヨーロピアン・カルテットは同一メンバーで74年4月録音『ビロンギング』から79年5月ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴ録音『ヌード・アンツ』までの5年間活動を続けました。


71年から76年まで活動したキースのもう一つのバンド、テナーサックス、デューイー・レッドマン、ベース、チャーリー・ヘイデン、ドラムス、ポール・モチアンを擁する所謂アメリカン・カルテット、メンバーは米国で生まれ育ち、フリージャズ旋風吹き荒ぶ60年代の矢面に立ちながら、果敢に演奏し続けた強者ばかりで構成されます。
モーダルジャズ、フォーク、ゴスペル、カントリー&ウエスタン、ロック、リズム&ブルース、そしてフラワームーヴメント、多くのテイストを内包した演奏スタイルでキースの音楽を表現しました。
活動中に13作をリリースします。76年4月録音『ザ・サーヴァイヴァーズ・スイート』に彼らの演奏が集約されています。

/キース・ジャレット・アメリカン・カルテット
ヨーロピアン・カルテットはアメリカン・カルテットとほぼ入れ替わるように活動を開始しますが、キース以外メンバー全員欧州出身です。当然コンセプト、アプローチ、表現の方法論が異なります。
土地柄否応なしにクラッシックの素養がルーツに存在し、またジャズ演奏の経験値はアメリカン・カルテットのメンバーとは大きく異なります。
とは言え彼らが過ごした60年代は、欧州に米国からジャズ・ミュージシャンが仕事を求め、大挙して移住した時期に該当します。
移住組は欧州の人々に暖かく、好意的に迎え入れられ、デンマークやパリを中心に演奏活動を行い、彼らにジャズ・ミュージックを啓蒙する役割りを担いました。
ヨーロピアン・カルテットのメンバーが若い頃、本場米国のジャズ・スピリットに触れる機会は日常的で、彼らと共演する事も容易であったと思います。
そして次の様にも考えられます。キースはジャズ的な要素がアメリカン・カルテットのメンバーより希薄な彼らとの演奏に於いて、自身が持つクラシカルな要素を存分に発揮出来る様に起用したのだと。
米国ジャズシーンでの活動が無い彼らのプレイは、ある意味ピュアな要素を含みます。キースはアメリカン・カルテットで繰り広げたプレイとの対比を、ヨーロピアン・カルテットで楽しんでいたのでは、と想像しています。

閑話休題、79年4月2日から21日、行程20日間に及ぶジャパン・ツアーにはプロデューサー、マンフレッド・アイヒャーが随行します。そしてECMレーベルのサウンドを作り上げたと言って過言では無い名レコーディング・エンジニア、ヤン・エリック・コングスハウクを伴い、ライヴ・レコーディングを挙行します。
中野サンプラザで行われた彼らのコンサートを単独で収録した『スリーパー』も後年リリースされます。
本作、『スリーパー』そして『ヌード・アンツ』3作がヨーロピアン・カルテット演奏活動の総決算に位置します。

『パーソナル・マウンテンズ』『スリーパー』両ライヴ作品を聴いて感じるのが、各楽器の音色、レイアウト、エッジ感、セパレーションとブレンド感、トータルなバランス感等、総じて録音クオリティの素晴らしさです。
ECMのスタジオ・レコーディング作品と全く遜色なくECMサウンド、レーベルの音色が作られています。
スタジオ録音であれば音作りのノウハウをキープするのは比較的容易です。
特にECMレーベルのホームグラウンドであるノルウェー、オスロにあるタレント・スタジオに於いて、そこは数々のECM名盤が録音された言ってみれば聖地ですが、スタジオ自体の箱鳴り、使用するマイクロフォンの種類やレコーディング・ツールの数々、各楽器の録音ブースは用意されるのか、部屋の天井高や容積は如何程あるのか、壁面や床、天井の材料は?しかしエンジニアがコングスハウクであれば、レコーディング・サウンドのイメージ作りは全くイージーな筈です。
因みにそこにはECMレーベル・プロデューサー、マンフレッド・アイヒャーのコンセプト、イメージによる助言が事細かく、采配がきめ細やかに成されている筈です。
今回のヨーロピアン・カルテット・ジャパン・ツアー、一行はまずオスロからほぼ地球の裏側にある東京までの距離8,391km、飛行機で16時間以上かかる遥か彼方の地に向かい、赴いた先にある13ヶ所のコンサート・ホール、ツアー自体が、西は福岡県博多市から北は北海道札幌市までの移動距離およそ2,000km、恐らく全行程に於いてコンサートのレコーディングが成されたと想像出来ますが、各々のホールの様子やステージ自体がデッド(英語ではドライと表現します)なのか残響の多いライヴ状態なのか、どの様なレコーディング機材やコンソール卓が用意され、それらデヴァイスへの対応がエンジニア自身に備わる知識で対応出来るか否か。
ライヴ・レコーディングは通常では客席にレコーディング・コンソールを備えた複数席が用意され、ライヴを聴きながら録音作業を行いますが、客席の何処にコンソール卓が位置するのか。当然座る位置で聴こえ方が変わりますから。
総じてエンジニア・サイドの要望の実現度合いは如何程か、日本のプロモーター、主催者、ツアーに同行する音響制作会社、ホールのアンビエント担当者との的確なコミュニケーションに関して、円滑さは保たれているのか。
不確定要素は山ほどあったでしょう。録音当日にもトラブルは発生したかも知れません。しかしコングスハウクは確実にして余りあるプロフェッショナルな仕事をやり遂げました。
スタジオ以外ライヴ・レコーディング作品も手掛けるECMレーベル、欧州国内はもとより米国内、ニューヨークに足をのばす事があり、百戦錬磨のエンジニアにしてみれば実は録音に際する重要な幾つかのポイントを押さえれば、録音中を快適に過ごせるのかも知れません。と言うのは、出来上がった作品の音場に、実に楽しげな風情を感じる事が出来るからです。
歴史を揺るがすかも知れない演奏録音に居合わせる事が出来るレコーディング・エンジニアは、音楽シーンの生き証人に違いありません。
彼らは得難い名演奏現場に出くわす可能性があリ、それ故ミュージシャンと同様に魅力に満ちた、やり甲斐を備えた職種であり、演奏に寄り添う、プレイヤーと同じ立ち位置で音楽に参加するエンジニアが理想的です。
真逆の状況下ではどうでしょう、凡庸ないしは庸劣な演奏をレコーディングした場合です。
落胆ぶりはミュージシャンの場合、耐え難き状況を自身のモチヴェーションを向上させる、練習する、努力する、イメージを変える事で乗り切りますが、エンジニアの場合、大凡自己責任には該当しないので、行き場のないストレスに転じる場合があり、それこそ喫煙や飲酒行為等で発散せざるを得ません。
彼らの中に短命者が見受けられるのはこの事に起因するのかも知れませんし、当然ですがエンジニアには演奏に対する帰責事由は無く、中には録音された演奏の出来不出来を端から関知せず、馬耳東風を決め込む輩も存在する模様です。
前述の『ヌード・アンツ』、ここでのレコーディング・エンジニアはコングスハウクでは無く、トム・マッケニーが務めます。マッケニーもECMのレコーディングを度々経験したエンジニア、我々は知らず知らずのうちに彼による録音作品も耳にしています。
マッケニーによる録音も各楽器の音像、音色、レイアウト、バランス、いずれも申し分の無いクオリティで、巧みなレコーディング・テクニックを有しますが、コングスハウクとは異なるコンセプトでの録音です。
どちらが良い、優れているとは断言できませんが、マッケニーの方は幾分フュージョン、ロック、ポップス寄りのテイストで、多少マニアックな要素を感じさせます。
コングスハウクの録音手法が奥行き感とふくよかさに始まり、気品と音楽に対する愛情、そしてナチュラルさを全面に掲げているのが伝わる分、個人的には好みになります。

それでは演奏内容について触れていく事にしましょう。楽曲は全曲キースのオリジナルから成ります。
1曲目パーソナル・マウンテンズ、オープニングに相応しい荘厳なピアノのイントロから開始されます。
それにしても何と言うピアノの音色でしょうか。鍵盤を弾く上での全く理想のタッチを表現し、可能な限りピアノの倍音成分を鳴らし続けますが、打鍵に伴う不要な音の成分が一切排除された至高のトーン、極めて脱力感に富むために88の鍵盤を自然に操るピアノフォルテの権化、真のマエストロです。
程良きところでベース、ドラムスが加わり、ガルバレクのテナーによるテーマ奏が始まります。魅力的なメロディラインは神秘的なムードと崇高さを湛え、テーマのバックで打鍵されるキースの対旋律的ラインと絶妙にマッチします。
こちらのテナーの音色も極まっています。音のコアやエッジが明確でいて、付帯音が芳醇に響き、更に並行して鳴る幾つかのトーンが複雑にブレンドするために、実に個性的な音色が成立しています。ガルバレク自身の豊富なニュアンス付けがそれらを一層バックアップしています。
彼は14歳の時にジョン・コルトレーンの『ジャイアント・ステップス』収録の超高速にして圧倒的なナンバー、カウント・ダウンを耳にしテナーサックスを始めました。夢中になって朝から晩まで繰り返し聴いたそうです。
コルトレーンからのプレイ上の影響は限定的ですが、ガルバレクの内面ではコルトレーンと言うテナーサックス奏者の真のイノヴェーター振り、革新的音楽家としての存在に、常日頃から敬意を表しているでしょう、ガルバレクに経年によるプレイの上達、変化、サックスのトーン・クオリティの向上、個性の具現化を見出す事が可能な点から、推察されます。

キースのソロが先発です。圧倒的にして優雅、テクニカルにして情緒的、膨大な音塊が堰を切ったように押し寄せて来るのですが、全てのノートが入魂され、加えて無駄な音使いが皆無なので凄まじい説得力を伴います。
キースのプレイを盛り立てるべく、ベーシスト、ドラマーは只管リズムをキープしますが、彼らの入魂振りもキースと同レヴェルに位置し、トリオのコンビネーションは完璧です。
ピアノソロはテーマの断片を用いて終了させ、インタールード的にテーマ奏が行われ、その後極自然にガルバレクのソロに変わります。揺蕩う如きのソロラインには明確にオリジナリティを感じさせます。
ガルバレクのソロがある程度の佳境に達したところで、キースがバッキングを止めますが、恐らくパーカッション〜カウベルとスティックに持ち替えています。
テナーソロが感極まり、インパクトあるフリーク・トーンを放ち始め、そして次第に収束に向かいます。
その後はドラムスとパーカッションを中心としたセッションに変わりますが、ベースのフィルインによるキープ感が場を引き締めています。
ドラムソロです。キース、ガルバレクと個性派のプレイの後なので、比較的地味に聴こえてしまいますが、これで良いのです。このカルテットに3人目の鬼才は必要ありませんから。
その後徐に冒頭と同じピアノイントロが奏でられますが、一層煌びやかに、スリリングに響き、そのままラストテーマに移行します。
ここではピアノもユニゾンで参加し、魅惑のメロディを引き立たせます。
メロディの終わりと共にリズムが変わり、グッとリタルダンドします。ほぼバラードのテンポに落ち着き、ガルバレクは低音域でのサブトーンを用いて、ムードの変化を明確にします。
キースとガルバレクが中心となり、無から新たな世界を構築すべくの試行錯誤を繰り返します。まるで闇夜のしじまの中で静寂を破らないよう慎重に、しかし時折大胆さを持ちながら音を発しているかのようです。そしてベースがリードしながら次曲にメドレー形式で繋がります。
2曲目プリズムはベースがテーマを演奏します。マイナー調でエキゾチックな美しいメロディを有する佳曲、キース自身もスタンダーズ・トリオの83年1月録音作品『チェンジズ』で再演しています。

キースの盟友チャーリー・ヘイデンも自身のアルバム2002年5月録音、名盤『アメリカン・ドリームス』で取り上げています。テナーサックス、マイケル・ブレッカー、ピアノ、ブラッド・メルドー、ドラムス、ブライアン・ブレイド。
マイケルにテーマ・メロディ、ソロと存分にプレイさせ、ここでは全く異なる楽曲へと昇華させています。

ダニエルソンのピチカートには欧州の弦楽器奏者らしい闊達なプレイを確認できます。深いボディ鳴りによるウッディなトーン、正確なピッチコントロール、演奏表現の豊かさ。
つい先日(2024年5月18日)の彼の逝去が残念でなりません。
キースのソロに繋がります。恐らく音量を抑えてピアニッシモでのプレイですが、タッチの確実さ、そこに由来する音の輪郭の明確さを確認出来ます。
リズムに対する音符の位置、スイートスポットを押さえたタイム感にも確実さの他に美学を感じ、その後のガルバレクのテナーソロにも同様のテイストを見出せます。
ベース奏がアクティヴになり、ガルバレクもイメージを膨らませながらテイスティで魅力あるフレーズを繰り出します。
再びキースの登場、打鍵とユニゾンする声も印象的です。フレージング・ラインは驚異的な長さ、継続感を維持しますが、決してオーディエンスに押し付ける強引さは無く、ナチュラルに自己の世界を構築します。
リズム隊とのコラボレーションはまさしくECMサウンドならでは、イーヴンな音符を用い、透徹にしてクールなパッションと崇高な美の世界を表現します。
あたかも誘われるがままにガルバレク再登場、キースの精神を受け継ぎながらラストテーマをプレイし始めます。ベースのメロディ・プレイとの絡みもありながら、熱演の残り火を慈しむようにリタルダンドし、Fineを迎えます。
ピアノとベースの低音域での長い音符が止み、オーディエンスのアプローズに被りながらの最後の一言はキースによるものでしょう、シャイな彼らしいシンプルにして端的な謝辞になります。
3曲目オアシスは現代音楽風ピアノのアルペジオとベース、ガルバレクのフリーキーなソプラノから始まります。
彼のソプラノはテナーより更に個性的、ソプラノサックスの概念を覆す音色を有し、ニュアンス、そして神秘的ですらある表現の発露、美学を感じます。
用いる楽器自体はカーヴド・ソプラノ、曲管を有するソプラノ・サックスの使用が大きな要因ですが、様々なサックス・メーカーの楽器、マウスピースやリガチャー他各種パーツの試行錯誤を繰り返し、自分に合った最良の組み合わせ、コンビネーションを見つけるためのチャレンジを行います。
ひとえに良い音、快適な吹奏感を求めての探求です、この二点は演奏中にイマジネーション、アイデアを間違いなく提供します。自分も同じサックス奏者として共鳴する部分が多々あります。
そしてガルバレクの努力ゆえです、他のプレイヤーの追随を許さないクオリティをキープしつつ、彼は更なる進化を目指します。
ソプラノを中心としたテーマ奏が行われます。ピアノが随所にユニゾンを施し、うねりながら、ダイナミクスを設けながら、音符やサウンドを愛でるかのように情緒的にプレイします。
ベースやドラムのカラーリング、サポート感も万全に施されながら、バンドは蕩けるようにまで一体化し、ヨーロピアン・カルテットの真骨頂を表します。
キースのソロが始まります。ダニエルソンのベースと歩調を合わせるかのように演奏が進行します。
ピアノのフレージングに的確に、瞬時に反応するベースワークはオーネット・コールマンとのコラボレーションで名高いチャーリー・ヘイデンを彷彿とさせます。
そしてクリステンセンのパーカッシヴにしてデリケートなカラーリングが、演奏に深みを与えます。
ピアノソロが佳境に達し、ガルバレクのソロが始まります。キースのバッキングはスペースを保ちながら、ソプラノが発する天使の如きヴォイスをサポートします。
キースがメロディ・プレイを促すかのような打鍵を行い、ソプラノによるテーマが再び始まります。比較的テンポがキープされますが、うねる事を前提としたかのリズムの揺らぎも提示され、表現に彩を添えます。
急激な音楽の進行は決して行われず、全てが緩やかに進み、ドラムスとパーカッションによるヴァンプがプレイされます。
何でしょう、笛かカズー、若しくはマウスピースだけを使ったバズィングの様な音が継続して聴かれます。これはキースによるものと判断しています。次第に収束に向かい、ドラムがFade outします。
4曲目イノセンスはキースのリリカルなピアノイントロから始まります。
多種多様な音色を繰り出す事が可能なピアニスト、キース・ジャレットです。サウンド・メイキングに対するイメージが強烈ゆえでしょう、ゴスペル・ライクなコンセプトにベース、ドラムスが次第に加わります。
ダニエルソンのピチカートがサウンドの主役を匂わせた頃に、ガルバレクのキュートなソプラノが加わります。美しさとコケティッシュさ、どこまでも澄み切った北欧の空を感じさせるトーンとメロディ奏には大いに感銘を覚えます。
キースのヨーロピアン、アメリカン両カルテットの違いは多々ありますが、特にレッドマン、ガルバレクたちサックス奏者の個性、備わっている音楽性、音色が齎す表現の振れ幅に、全く別次元のテイストを感じます。
キースのソロが始まります。彼の作品『マイ・ソング』で聴かせたコンセプトを踏襲した表現には安堵感や豊かな情緒、子供の心を忘れない純粋さ、音楽的にも精神的にも常に一瞬にして初心に帰る事のできる柔軟性を感じさせ、音楽表現に於いてのナチュラルさが最も大切な事を再認識させます。
ガルバレクのソプラノが再登場し、短くソロをプレイした後ラストテーマに繋がります。ここではソプラノとピアノのメロディ・ユニゾンの美しさを堪能できますが、ガルバレク、キース両雄のトーン・クオリティがあってこその真善美と言えましょう。
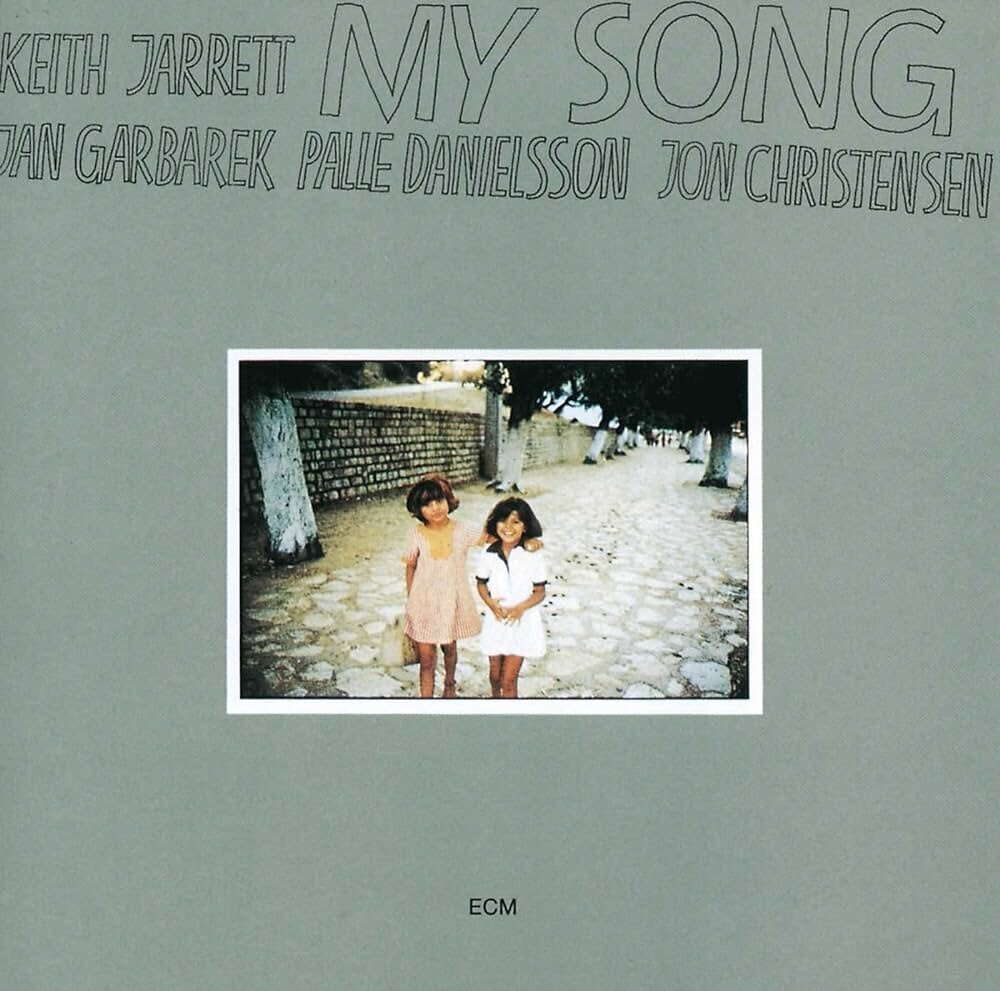
5曲目レイト・ナイト・ウィリーはCDのみでの追加テイク、ジャズロック調のリズムが開始され、ガルバレクはテナーを用いてテーマをプレイします。いつもよりもチューニングが低めに成されているのが若干気がかりではありますが。
キースのピアノソロが先発、こちらでもゴスペルのサウンドを活かすべくのアプローチにトライしています。総じてファンキーにしてフレンドリーなサウンド、アプローチは、アルバム冒頭に位置するにも相応しいテイストを内包するナンバー、こちらが1曲目に配されたならば、アルバムの印象は随分変わったと想像出来ます。
ジャパンツアー中演奏され、収録されたナンバーは膨大に存在する筈です。
いずれコンプリート・キース・ジャレット・ヨーロピアン・カルテット、ジャパン・ツアーがリリースされる日が来る事でしょう。CD20枚組程度のヴォリュームは間違いないと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
