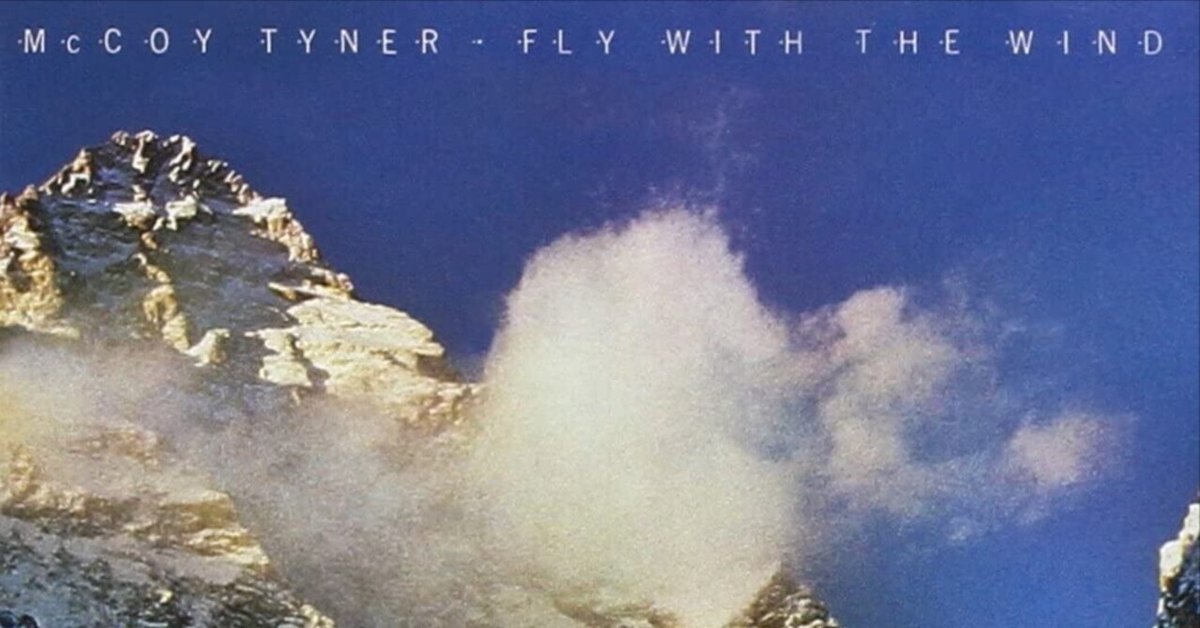
フライ・ウイズ・ザ・ウインド/マッコイ・タイナー
マッコイ・タイナー1976年録音の作品『フライ・ウイズ・ザ・ウインド』を取り上げてみましょう。
録音:1976年1月19, 20, 21日
スタジオ:ファンタジー・スタジオ、カリフォルニア、バークレー
エンジニア:ジム・スターン
プロデューサー:オリン・キープニュース
オーケストラ・コンダクター:ウィリアム・フィッシャー
(p)マッコイ・タイナー (b)ロン・カーター (ds)ビリー・コブハム (fl, alto-fl)ヒューバート・ロウズ (picc, fl)ポール・レンジ (oboe)レイモンド・ダステ (vl)スチュアート・キャニン、フランクリン・フォスター、ダニエル・コビアルカ、ピーター・シャッファー、エドムンド・ウェインガート、マイラ・バッキー(1, 3)、マーク・ヴォルカート (4, 5) (viola)セルワート・クラーク、ダニエル・イェイル (cello)サリー・ケル、カーミット・ムーア (harp)リンダ・ウッド (tambourine)ギレルミ・フランコ
(1)フライ・ウイズ・ザ・ウインド (2)サルヴァドーレ・ジ・サンバ (3)ビヨンド・ザ・サン (4)ユー・ステップト・アウト・オブ・ア・ドリーム (5)ロレム

多作家マッコイ・タイナーは70年代、年に2作のペースでコンスタントにリーダー・アルバムを録音、リリースしていました。プレーヤーとして生涯活動していましたが、この頃は特に充実を感じます。
前後には75年2月に『トライデント』、翌76年6月『フォーカル・ポイント』をレコーディング、本作のようにストリングス・オーケストラを擁した大編成から『トライデント』でのエルヴィン・ジョーンズ、ロン・カーターとのピアノトリオ、『フォーカル・ポイント』では複数の管楽器をフロントに迎えたコンボ作品と、カラフルに自己の音楽を表現していました
印象的なオリジナル曲を素材として取り上げており、またそのいずれもが佳曲なのです。
常に硬派で情熱的な演奏を繰り広げつつも、「口ずさめる」メロディアスなナンバーを作品に収録し続け、ジャズファンには「マッコイは次作でどんな曲を聴かせてくれるのだろう」と期待させ、しかも決して裏切る事なくキャッチーなナンバーを世に出し続けました。楽曲には二番煎じやアイデアの使い回しを行わずにいられたのも、迸る才能の成せる技です。
曲作りに対する情熱を痛感しますし、オリジナル曲の演奏で自己表現のレベルが高まる事の認識、それに対する拘りには強いものがありました。
バド・パウエルに始まり、セロニアス・モンク、タッド・ダメロン、エルモ・ホープ、ホレス・シルヴァー、ハービー・ハンコック、チック・コリアたち多くのジャズピアノ奏者は優れた作曲家でもあり、シーンに数々の名曲を残していて、曲作りはプレイと不可分の関係である事を示しました。
彼らのナンバーは今だに取り上げられ、頻繁に演奏されますが、マッコイのオリジナルはそれほど取り上げられる機会がありません。
その理由として考えられるのは、彼のオリジナルが自身の演奏スタイル、ピアノプレイを伴わなければ、楽曲として成り立ち難いからなのではないか、また曲自体がメロディアス過ぎて、作曲者以外インプロヴィゼーションの素材として扱うのが難しいからと、推測しています。

本作ではマッコイのオリジナル曲を演奏するに相応しいミュージシャンを集め、そして華麗なまでに響かせ、適材適所にバックアップするストリングス・オーケストラを配し、ゴージャスにプレイを展開しています。
マッコイは作曲のみならずオーケストラのアレンジも担当し、非凡な才能を発揮しています。
参加メンバーの中で特に際立つのがドラマー、ビリー・コブハムです。そして彼の超絶ドラミングが無ければ本作の成功は有り得ませんでした。
圧倒的なプレイを聴かせるコブハムは44年パナマ生まれ、3歳の時に家族で米国に移住、ニューヨーク・ブルックリンで生活を始めます。
アーミー・バンドを経て68年ホレス・シルヴァー・クインテットに参加、70年にランディ、マイケルのブレッカー兄弟やジョン・アバクロンビーらとドリームスを結成、2枚のアルバムを世に出します。
マイルス・デイヴィスの歴史的作品『ビッチェズ・ブリュー』、ジョン・マクラフリンと共に次作に該当する『ジャック・ジョンソン』にも参加します。
その後マクラフリンのマハヴィシュヌ・オーケストラに参加、73年作品『火の鳥』を発表します。
スタジオワークも多面的に及び、スタンリー・タレンタイン、フレディ・ハバード、ガボール・ザボ等のCTIレーベル諸作に、存在感あるプレイを残しています。
『クロスウインズ』『シャバズ』『ア・ファンキー・サイド・オブ・シングス』等自身のリーダー作品も70年代初頭から発表し、当時まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍ぶり、そして本作への参加と繋がります。
ここでのドラミングには彼のリーダー作、参加作プレイ一連の総決算とさえ感じます。
「ビリー、君の素晴らしいテクニックと音楽性が作品には必要なんだ。委細構わず大暴れしてくれるかな」のようなオファーがマッコイからあったと思います。明らかに彼のドラミングを想定した曲作り、サウンドですから。
コブハムをドラムの椅子に迎えるべくストリングス・セクションを配したのか、その逆なのかは分かりませんが、ストリングス・オーケストラが参加しなければコブハムのプレイがダイレクトに露出し、かなり支配的であったでしょう。
メンバーに迎えたものの、強力なドラミングはマッコイを凌駕せんばかり、それゆえでしょうか、本作以後マッコイはコブハムを作品に迎えることはありませんでした。

フロントにはサックス奏者を迎えることが多いマッコイですが、ここではフルート奏者ヒューバート・ロウズひとりにリード・ヴォイスを任せています。
ストリングスが醸し出すサウンド、コブハムのドラミング・テイスト、そしてここでのオリジナル曲のコンセプトを鑑み、敢えてフルート奏者をチョイスしたように想像出来ますが、結果大成功でした。サックスやトランペット奏者よりもフルートの軽やかな音色、プレイが合致しています。
またマッコイは彼をオーケストラ・アンサンブルの一員としても、参加させることを考えていたと思います。

ロン・カーターはマッコイと60年代から共演する盟友ベーシスト、前作『トライデント』でも素晴らしいコンビネーションを聴かせました。多くのベーシストを起用するマッコイですが、ここぞと言う時に登場するキーパーソンのように捉えています。

それでは収録曲に触れて行きましょう。
1曲目はマッコイ作の表題曲フライ・ウイズ・ザ・ウインド、イントロはカーミット・ムーアのチェロによる美しいアルコのメロディから始まります。徐々に他の楽器が加わり、ゴージャスなオーケストラ・サウンドが提示されます。
マッコイ73年録音『ソング・オブ・ザ・ニュー・ワールド』もブラス、ストリングス・セクションを配した大編成による作品、本作はこちらの進化系と言えますが、音楽の内容、緻密さ、表現力には格段の進歩を感じます。

その後おもむろにピアノトリオによるイントロ、テーマ奏、そしてフルート、オーケストラによるアンサンブル、実に分厚いサウンドが層となり押し寄せて来るが如しですが、これを纏めると言うか、逆に破壊と表現すべきか、コブハムのドラミングが大暴れします。
猛烈な連打のセンス、ドライヴ、スピード感はビッグバンドを率いていた当時のバディ・リッチを彷彿とさせますが、コブハムのプレイはよりヴァージョンアップとソフィスティケイトを伴います。
そしてこのスタイルは多くのドラマーに影響を与え、後にデニス・チェンバースへと受け継がれて行きます。
テーマの時点で既に半端ない音楽性を表出していますが、演奏の本番はまだまだこれからです。
ソロの先発はマッコイ、メロディを受け継ぎ、ストリングスのバックアップを伴い、炸裂するコブハムのドラムと共に、それまでに無かったマッコイ・ワールドを構築します。
随所にドラムのフィルインソロのためのブレークが用意され、コブハムは毎回異なったアイデアを提供し、音楽を活性化させています。
それにしてもハードさを通り越して爽快さすら感じさせる演奏、私が大学1生生の時に代々木にあるジャズ喫茶で初めて本作を聴いた時の衝撃を、今でも忘れる事が出来ません。
大型スピーカーから流れる大音量と、天井の高い店内の広さも相俟った豊かな音空間、そこにピアノの怒涛のアドリブ、ストリングスの豪華絢爛な響き、これでもかとばかりに暴れまくるドラムの猛烈なプレイは、よく分からないなりに、ジャズと言うカテゴリーを超えて凄過ぎるかとも思いましたが、現在の耳には丁度良い、ないしはもっと暴れてくれとさえ欲している自分がいます(笑)。
もう一つ感じたのは、演奏者がオーディエンスにサーヴィスし過ぎなのではないか、ここまで徹底的にプレイをアピールしなくても良いのではないか、演者は常に尊厳を持つべきであり、安売りは禁物だと。
サックス奏者として生活し続け、とことん自分を出す事の大切さを覚え、今は寧ろバランスの取れた演奏と感じています。
続いてテンションを落としロウズのフルート奏が始まります。バックでのストリングス、ドラムスを筆頭とするアンサンブルは継続し、渾然一体となった世界を表出します。
ラストテーマではコブハムのカラーリングに更に拍車がかかり、これはもう色付けどころかペインティングの世界、キャンバスに絵の具で彩色していたのでは間に合いません、様々な色のペンキを広大なキャンバスにぶちまけているかのドラミングです。
コブハム自身は手足の長いプレーヤーで、スティックを振り下ろすストロークがあるため、かなりの音量が出ます。
加えて口径の大きな、複数のタムやバスドラを有するロック仕様のセット使用、ジャズドラムの高めのチューニングとは異なるヘヴィーで野太い音色を聴かせます。
フェードアウトを伴い演奏がFineに向かいますが、まだまだ熱演は収まらなかった事でしょう。
2曲目サルヴァドーレ・ジ・サンバもマッコイのオリジナル、こちらも情熱的で躍動感溢れるナンバーです。
彼の74年録音『サマ・ラユーカ』、『アトランティス』両作でも切れ味の良いプレイを聴かせたパーカッション奏者ギレルミ・フランコ、彼のタンバリンが随所で活躍します。
ピアノのリズミカルなイントロからスタートしますが、ラテン・プレイヤーにとってマッコイは神格化された存在だそうです。
もちろん彼はジャズプレイヤーでありますが、ラテン・フレーヴァーを有するオリジナルの数々、ダイナミックなプレイ、パーカッシヴな打鍵、イーヴンでスクエアな8分音符を信条とするため、ラテン奏者には受け入れ易いジャズピアノ奏者の一人です。
スペイン系の彼らがマッコイの名前を発音する際に、コイの方に強くアクセントが付くため、マッコイが「ッコイ」と聞こえるという話も耳にしました。
テーマはフルートが担当、空間に音を詰め込むかのドラミング、同時に縦横無尽に鳴り響くストリングス、この狭間でサックスやトランペットがテーマを奏でたのでは、トゥ・マッチであったことでしょう。
そのままフルートソロに続きますが、コブハムのドラミングを支えるロン・カーターのベースが大健闘しています。サンバのグルーヴを見事にキープし続け、多少揺れ気味で拍の短いのロウズのタイムを補正しつつ、音楽を推進させます。
続くピアノソロは装甲車が猛烈なスピードで走り抜けるかの壮絶な音塊、和音の渦、ピアノ、ベース、ドラム3者のタイム感が合致し、音符の長さが拍からはみ出さんばかりの、たっぷりとしたグルーヴを提供します。
ソロの後半にはストリングスがバックリフとなり、ソロを後押しします。
演奏は崩壊に至る寸前に、次第に収束感を得ます。
コブハムの大きなフィルに続いて、ベースとドラムふたりのユニークなやり取りを交えたソロ・プレイが行われますが、ベースの録音は比較的マイクに近く、ドラムはさぞかし大きな音量なのでしょう、奥行きを持たせて録音されたブース内でのサウンドがします。
ストリングスが力強く参入し、ラストテーマへ、案の定コブハムは更なるパワープレイを導入し、エンディングに向けてアクティヴにドラミングします。
一度演奏が終わったかに見せかけ、マッコイがフランコを伴ってイントロのパターンをリフレインしますが、これはラテンでしばしば行われる手法のひとつ、今度こそFineとなります。
3曲目ビヨンド・ザ・サンはピアノとオーケストラをフィーチャーしたマッコイのナンバー。フルートやベース、ドラムはオーケストレーションに内在する形で演奏しています。
まずハープやオーボエ、ヴィオラをフィーチャーし、厳かにイントロが奏でられます。大変に凝った構成からなるアンサンブルは、編曲を施したマッコイの音楽性の充実ぶりを感じさせます。
ピアノの独奏に移り、揺らぎを伴った抒情性を聴かせつつ冒頭のパターンを踏襲し、豊かな響きのストリングス・アンサンブルへ。
1, 2曲目とは全く異なった色合いを聴かせる仕上がりになりました。
4曲目スタンダード・ナンバー、ユー・ステップト・アウト・オブ・ア・ドリーム 、ベースパターンから始まり、イーヴン系のリズムを提示します。
原曲のメロディを殆ど感じさせないアレンジですが、コード進行はある程度踏襲しつつ演奏され、他曲とは異なるタイプのアレンジ、アンサンブルを聴かせます。
コブハムも違ったグルーヴ、カラーリングを提示しますが、饒舌さは変わらずプレイされ、ピアノ、フルートのソロをバッキングします。
5曲目マッコイのナンバー、ロレム。ユニークなフルートとベースのユニゾンによるパターンから始まり、ピアノ、オーケストラが加わり、荘厳なサウンドを奏でます。
比較的短くシンプルなテーマの後、意表を突いてスイングのリズムに変わり、マッコイお得意のsus 4のサウンドを展開しつつソロを取ります。
カーターのスインギーなベースには推進力を感じますが、対してコブハムの4ビートにはやや門外漢を覚えます。例えるならケニー・ドリュー・トリオのアルバート・ヒース的なグルーヴ、ややビートが硬く聴こえるので、コブハムはどちらかと言えばイーヴンのプレイに本領を発揮するドラマーと判断出来ます。
本作の楽曲がこれ以外16ビートやサンバ、ラテンのリズムであったのも頷けるというものです。
イーヴン系のグルーヴとスイング・ビートを自在に行き来出来るドラマー、実はあまり存在しません。どちらかのリズムがどうしてもメインになる傾向があります。
スティーヴ・ガッドのスイング・ビートはかなり特殊なスタイルですが、イーヴン系との行き来に関しては、ずば抜けた自在さを感じます。
ベースのウォーキング・ソロに続き、冒頭のアンサンブルを再使用しラストテーマへと繋がります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
