
The Kicker / Bobby Hutcherson
今回はBobby Hutchersonの63年録音リーダー作「The Kicker」を取り上げてみましょう。
Recorded: December 29, 1963
Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ
Label: Blue Note
Producer: Alfred Lion
vibe)Bobby Hucherson ts)Joe Henderson g)Grant Green(#4-6) p)Duke Pearson b)Bob Cranshaw ds)Al Harewood
1)If Ever I Would Leave You 2)Mirrors 3)For Duke P. 4)The Kicker 5)Step Lightly 6)Bedouin

Bobby Hutchersonがリーダーですが全面にフィーチャーされたJoe Henderson, Duke Pearson、後半3曲に登場するGrant Greenたちの存在感も大きく、リーダーを特に決めないメンバー全員が対等なレギュラーコンボの様相を呈しています。
本作の約1ヶ月前に全く同じメンバーでBlue Note(BN)に録音されたGrant Greenのリーダー作「Idle Moments」と双子のような関係にあり、こちらも素晴らしい内容のアルバムです。
演奏もさることながら選曲が良いですね。Pearson作の表題曲やGreenのオリジナル、John Lewis不朽の名曲Django等、これら哀愁を帯びたナンバーをメンバーは楽曲に吸い寄せられように、何の迷いもなくスインギーにプレイ、とりわけ絶好調のJoe Henが思う存分ブロウします。
レコーディングから1年強を経た65年2月にリリースされましたが、こちら「The Kicker」の方は何と36年間もオクラ入りし、99年にやっと発売され日の目を見ます。 内容的に2作は60年代初頭のモダンジャズの雰囲気を存分に湛えた、ナチュラルでテイスティな演奏です。
寧ろ「The Kicker」の方がバラエティに富んでいる作品ですが、当時のBNはアルバムを多発していたので、リーダーは違えど同じメンバーによる同一傾向の作品では売れ行きを懸念したのかも知れませんし、他の理由があったのかも知れません。 2枚の大きな違いは「Idle Moments」の方がマイナーのダークな曲調、「The Kicker」がメジャーの明るめな曲調を中心とした点です。
Idle Moments / Grant Green

BNから再びお呼びがかかった彼らはスタジオ内で再会を喜んだ事でしょうが、個々でも多くの共演を行なっていました。
当時のBNでビブラフォンはHutcherson、テナーはJoe Hen、ギターもGreenたちが筆頭アーティストなので、顔を合わせる機会は多かったと思います。
Pearsonもプレーヤーとして活躍していましたが加えて作曲家、アレンジャーとしても諸作に携わっていて、巧みなピアノプレイ、都会的なセンスを有したオリジナル曲、コンボからビッグバンドまで緻密にして洒脱なテイストを聴かせる知的なアレンジを多く披露しました。
BNには優れたピアニストが数多く在籍し、その数には枚挙にいとまがなく、ある種ピアニストのレーベルと言っても過言ではありません。
創設者でありプロデューサーでもあるAlfred Lionが67年リタイアし、レーベルをLiberty Recordsに売却した際にPearsonは後釜を引き受け(実は63年からA&Rとしてアーティストのスカウトも担当していました)、BNのプロデューサーとしても数年間活躍し、レーベルの顔として広く知られました。
50年代から60年代中頃にかけてBNは時代を代表する名作、名盤を数多く発表していました。 BN自体がジャズを牽引していたと言っても過言ではありません。
しかし60年代後半から次第に音楽シーンが混沌を極める中でそのステイタスに翳りが生じ始めました。
その最中のプロデューサー就任はさぞかし大変だったと思います。71年BNのもう一人の創設者であるFrancis Wolffが逝去するまで、Peasonは在籍しました。
Duke Pearson

本作はBobby Hutchersonの初リーダー録音に該当するのですが、リリースがずっと後になるので、次作65年4月録音のアルバム「Dialogue」が事実上の処女作になります。
Dialogue / Bobby Hutcherson

ピアノに鬼才Andrew Hill、Alfred Lionのお気に入りですね、彼を迎え収録6曲中4曲Hillの超個性的なオリジナル、2曲Joe Chambersのこれまたユニークなナンバーを取り上げた、しかしリーダーHutchersonのオリジナルは含まれない作品です。 彼のプレイはHillを始めとしてFreddie Hubbard, Sam Rivers, Richard Davis, Joe ChambersたちBNの花形ミュージシャンの影に埋没気味です。
それはそうですね、本人はどちらかと言えば強く自分を押し出して演奏するタイプではなく、加えてビブラフォンという楽器の特性上、管楽器以上には音のエッジが立たず、ピアノほどの複雑な和音を演奏出来ず、その上これだけ音楽的に主張のある、アクの強いメンバーを集めたのであれば、どうしても脇役に収まらざるを得ないでしょう。
アルバム自体のクオリティは本当に高いのですが、一体誰が作品の主人公なのかと、ふと考えてしまいます。
リーダーアルバムは本人が音楽性を発揮し、存在感が主張されている事が前提だと思うのですが、豪華な入れ物を用意し中身もしっかりと収容したにも関わらず、容器に書いてある名目とは異なる収容物が納められていたかの如しです。
後にも挙げますがBNの重要作品に連続参加したHutcherson、ひょっとしたら前衛的な演奏スタイルが彼の本質と曲解され(前衛の傾向は確かにありますが、本質はオーソドックスなプレイヤーだと思います)、Lionの秘蔵っ子である前衛と主流派の狭間を行き来するHillを筆頭に据え、フロントやリズム隊にChambersほか柔軟性のあるミュージシャンたちを配して、Hutchersonの前衛方向の音楽性を開花させて、華々しいデビューアルバムをプロデュースする算段であったと推測できますが、実態は異なりました。
Andrew Hill

同じビブラフォン奏者で強力なスイング感とタイム感を有し、打鍵テクニックも圧倒的であったLionel Hamptonは、ビッグバンドを率いて自身をフィーチャーしても管楽器のアンサンブルに埋もれる事なくソロを聴かせていました。
リーダーに成るべくしてなったと言えるHampton、華があり、派手さゆえにその存在感は誰よりも抜きん出ていたように思います。
Lionel Hampton

Hutcherson自身が単独でフロントに立った作品である、66年2月録音の3作目に該当する「Happenings」で初めてその存在を誇示したと言って良いでしょう。
ビブラフォンとピアノトリオによるカルテット編成でHerbie Hancockの名演奏も光りますが、自身のオリジナルの秀逸ぶり、そしてHancockの名曲Maiden Voyage収録!
選曲の良さも魅力のアルバムで、ジャケットの色合い、デザイン、雰囲気と見事にリンクした名作です。
Happenings / Bobby Hutcherson

Lionel Hampton, Milt Jacksonらの流れを汲む左右1本づつのシングル・マレット・スタイル(Gary Burton, Mike Mainieriらは左右2本づつを駆使するダブル・マレット・スタイル)のHutchersonは、41年1月Los Angeles, California生まれ、12歳の時にMilt Jacksonが参加したMiles Davisのアルバム「Miles Davis All Stars, Volume 2」を聴き、啓示を受けビブラフォンを開始、後にかのDave Pikeに楽器の手解きを受けたそうです。
Hutchersonの姉が当時Eric Dolphyのガールフレンドだったので(!)彼に弟を紹介した事があるそうです。Dolphyの作品への参加にはこんな伏線があったのですね。
60年代に入りNew Yorkに活動の場を移し、タクシードライバーをしながら音楽活動を始め、幼馴染みのベーシストで先にNew Yorkに移住していたHerbie Lewisを通じシーンに進出しました。その後次第にミュージシャンに演奏を認められ、彼らのバンドに参加します。
63年4月録音、若干17歳Tony Williamsの名演奏も光る新生Jackie McLeanを表出した「One Step Beyond」、64年1月録音、Elvin Jonesのドラミングが冴え渡るAndrew Hillワールド全開にして代表作「Judgment!」、64年2月録音、リーダー本人の欧州客死後に発表されたモダンジャズ永遠の問題作Eric Dolphy「Out to Lunch!」、以上のBNを代表する傑作に矢継ぎ早に参加、これらで聴かれる演奏はビブラフォン従来のオーソドックスさを排除したかの如き革新性を持ち、一躍脚光を浴びました。幸先の良いスタートを遂げたのです。
One Step Beyond / Jackie McLean

Judgment! / Andrew Hill

Out to Lunch! / Eric Dolphy
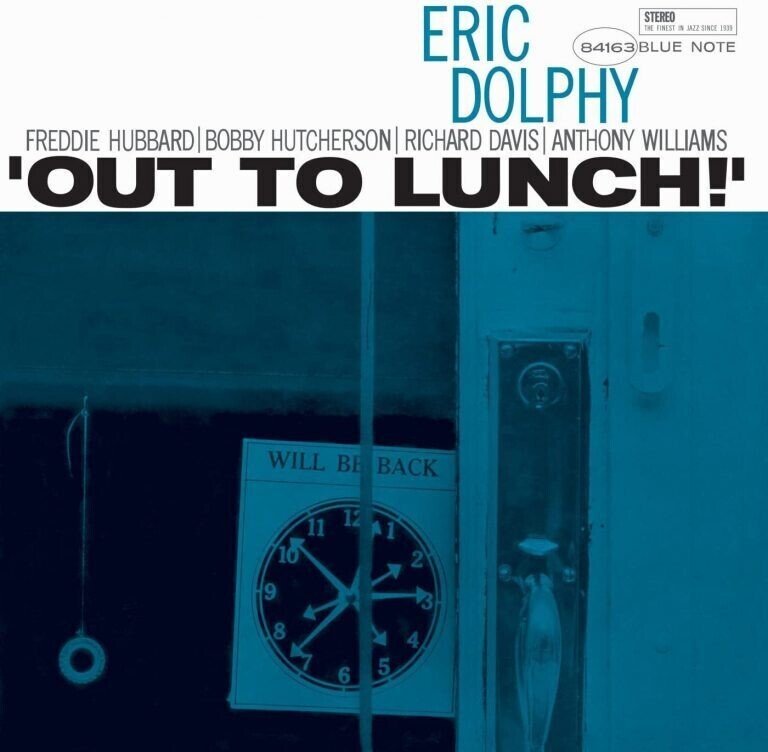
それでは演奏曲について触れて行くことにしましょう。
1曲目スタンダード・ナンバーIf Ever I Would Leave You、渋いナイスな選曲です。この曲は60年のミュージカルChamelotで初演され、62年にSonny Rollinsが自身のリーダー作「What’s New?」で取り上げました。
リリース直後のTV映像で素晴らしい演奏も残されています。 https://www.youtube.com/watch?v=-iPMqJuGQes
(クリックしてください、視聴出来ます)
What’s New? / Sonny Rollins

Kenny Dorhamも63年4月録音「Una Mas」で演奏していますが、こちらはCDの追加テイクとして87年に初めて日の目を見ました。
他の収録曲とは異なった雰囲気の演目、演奏ゆえにレコードリリース事にオミットされた模様です。本作同様Joe Henも参加しています。
Una Mas / Kenny Dorham

Don Grolnickの95年作品「Medianoche」でもMichael Breckerをフィーチャーして演奏されています。タイトルがIf Ever I Should Leave Youと微妙に異なっていますが、Would, Should両方で流布しているようです。
ここではラテンでプレイされており、Michaelはかなりon topに演奏していて、個人的には共演者のDave Valentinのフルート奏のように、もう少し後ろのタイミングでソロを取ってくれたのなら、より心地良かったと感じています。
Medianoche / Don Grolnick

ピアノのメロディアスでリラックスしたイントロ、要所をベースが合わせつつ、テーマが演奏されます。Joe Henのジャジーでいて個性的、正統派でありながら異端を内包した音色によるメロディ奏は実にスインギーです!当たり前ですが前出のRollinsのプレイとは全く異なります。スイングとラテンのリズムの違いも含め、ぜひ聴き比べてみてください。
テーマ後のピックアップソロからして既にアイデア満載、ひょうきんさとファンキーさ、リラクゼーションを掲げ、あたかもソロの本編はとことん聴かせちゃいますよ!と宣言しているかのようです。以降の演奏のコンセプトを明確に提示してくれました。
知的にコードのテンションを散りばめたアドリブラインは、フレーズとフレーズの間を実に的確に取りつつ、適度なユーモアや遊びを感じさせながら脱力感を保ちつつ、何と言っても曲想に相応しくナチュラルに展開されます。
Joe Henderson

続くHutchersonのプレイは思わずアドリブを採譜したくなるような魅力に満ちた、フレージングの構成音にオシャレな音が散りばめられたソロを聴かせています。彼以前のビブラフォン奏者とは明らかに一線を画す演奏と認識しています。同時に彼のインプロビゼーションからは真面目な人柄を垣間見る事ができます。
そのあとのPearsonのソロ、イントロでも聴かせたリラクゼーションを全面に感じさせ、メロディの断片をスムースに用いつつ、Joe Henよりも更に力の抜けた、言ってみれば大人の演奏を展開しています。
ソロイストの演奏を巧みにサポートするリズム隊、特にBob Cranshawの立ち上がり良くon topなベースが要になっています。
Bob Cranshaw

始めのテーマではピアノだけがバッキングしていましたが、ラストテーマではビブラフォンも加わり、両者のバッキングはバランスを保ちつつ、決してtoo muchにはなりません。サビのメロディをビブラフォンに任せたのも効果的です!
エンディングにはこれまたコピーしたくなる巧みなシカケが施され、演奏を楽しんだ余韻を一層印象付けてくれますが、サウンドやアイデアから、これはPearsonのアレンジによるものではないかと踏んでいます。
アルバムの1曲目にこれだけ魅力的な演奏を位置させた事で、本作のクオリティはグッと上がりました。この後どんな演奏が来ようが全てを吸収する緩衝材としてワークする事でしょう!
Bobby Hutcherson

2曲目はChambersのナンバーMirrors、98年自身のアルバム「Mirrors」でも取り上げています。こちらはかなり早いテンポでの演奏なので、別曲と見紛うばかりです。
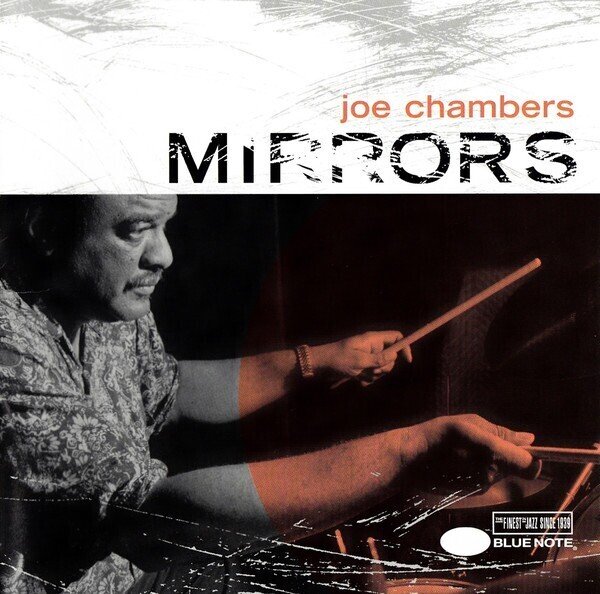
哀愁を感じさせるメロディをHutchersonが美しくプレイし、Joe Henがテーマ最後に付随するバンプ部分でハーモニーを吹く、ユニークなアンサンブル構成です。 ソロはそのままビブラフォンが引き続き淡々とプレイ、スローテンポをCranshawのベースがタイトにキープします。
Joe Henのソロは自身は演奏しなかったテーマのメロディを随所に用い、これまた強力なイメージを保ちつつムーディに、スペーシーに、演奏します。
Pearsonの目立たなくともスパイスとしての確実なバッキングも印象的です。
Joe Henderson

3曲目はHutchersonのオリジナル、Pearsonに捧げたマイナー調のハードバップ・テイストを感じさせる、しかしsomething newを巧みに織り込んだ佳曲For Duke P.、ソロの先発は作者から、快調にプレイします。Hutchersonの生真面目さを随所に感じますが、個人的にはもっと弾けてやんちゃな面を聴かせて欲しいと願う時があります。
続くJoe Henのソロには流石です!素晴らしい!と思わず頷いてしまう流麗さ、スイング魂、意外性を心底感じます。
Pearsonの演奏には様々な事象が頭の中で鳴り響いているのでしょう、奏でるラインには度重なる音やコードの取捨選択を認識することが出来、ハーモニーやライン組み立ての達人ぶりを聴かせています。
Duke Pearson

4曲目はJoe Hen作の名曲The Kicker、Horace Silverの「Song for My Father」でも取り上げられていました。自身のアルバムでもこの名前を冠したアルバムがありますが、Grant Greenの64年録音作品「Solid」にも収録されています。
ここでは作曲者の他、Elvin Jones, McCoy Tynerの超弩級を擁して演奏していますが、プレイやアンサンブルが総じてあまり噛み合っていない、何処か隙間風の吹くセッションに感じます。こちらもオクラ入りし15年後の79年にリリースされましたが、その理由を推し量る事は出来そうです。
Solid / Grant Green

本作の演奏についても、テナー、ギター、ピアノでイントロのメロディを演奏しますが難しいラインで、今ひとつ合奏に問題があるように聴こえます。
テーマでのPearsonのバッキングには小粋なセンスを感じましたが、これは脱力の成せる技の一つです。 この位の早いテンポになるとHarewoodのグルーヴに難を感じ始めます。
いくらCranshawがon topとは言え、ドラムはもう少しタイムが前に位置しないと演奏のスピード感を削いでしまいますし、ドラミングのセンスが些かcorny(新鮮味のない)に聴こえ、アンサンブルでシカケを合わせる際のカラーリングやフィルインにもっと工夫が欲しいところです。ましてやソロイストとインタープレイを丁々発止の次元には、かなり距離があります。
「Idle Moments」録音の時はリラックスして演奏を楽しんでいる風を感じましたが、ここでは多少ナーバスな印象を受けます。
先発のJoe Henはほぼ無反応で、リズムをキープするのが精一杯(?)のドラムを相手にクリエイティブに、構成力を持たせて自己の世界を表現していますが、彼の演奏はCallを表し、共演者、特にドラマーにはResponseを担当してもらわないと究極、Joe Henのインプロビゼーションは成り立たないのではないでしょうか。
ジャズの様式美のひとつがCall & Responseですから。
とは言えコンパクトに纏めて次のビブラフォンへ、律儀なHutchersonのアプローチにはHarewoodのドラミングにさほど違和感を感じず(他者の介入がなくとも、自分一人の世界だけで演奏するタイプゆえと言えるでしょう)、続いてこの曲から参加したGreenのギターソロにも同様に違和感を覚えませんが(フレーズを紡ぎ、順列組み合わせでソロを組み立てるタイプなので自己完結しています)、Pearsonのプレイにはこのドラミングはあまり相応しくないと感じました。クリエイティブさを発揮しているからでしょう。
タイムやグルーヴ感、音楽に対するコンセプト等、色々と作用していますが、特に斬新な感覚をふんだんに織り込んだこの曲、Harewoodのテイストでは対応し切れていません。
Grant Green

5曲目もJoe HenのオリジナルStep Lightly、Blue Mitchellの63年8月録音リーダー作「Step Lightly」、同じくMitchellの64年7月録音、若きChick Corea参加で名高い「The Thing to Do」(こちらはJoe Hen不参加)にも収録されています。Step Lightly / Blue Mitchell

The Thing to Do / Blue Mitchell
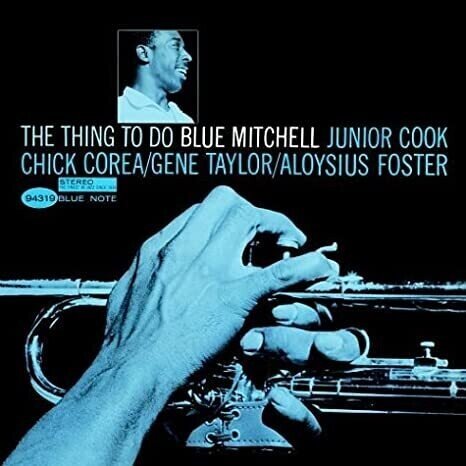
本作最長の14分以上の演奏時間を有します。変形のブルースで、リラックスしたジャジーなムードの中、レイジーさと変形のブルース・フォームが生み出す新鮮さをソロイストは楽しみつつ、伴奏者もそれを共有しています。
ピアノのイントロが一節あり、テーマ奏開始です。
この類の曲想はHarewoodの演奏に良く合致していますし、Cranshawのベースワークがあってこそ、安定したタイムを供給する事が出来ています。
先発はPearson、オーソドックスなスタイルでのアプローチの中にノーブルなテイストを感じさせます。続くHutchersonのソロにも同様なものを見出せ、Greenのプレイではブルーノートを効果的に用いたフレージングを存分に聴くことが出来ます。
淡々とした雰囲気が続いたところでJoe Henの登場、それまでのムードを継続させつつも新たな世界を設けようとする試みを次第に感じさせますが、あくまで自分はサイドマン、とことん盛り上がって主役を奪ってはマズイとばかりに、盛り上がりの五合目辺りで下山し始めました。
とは言えJoe Hen本作中の演奏では全てハイレベルな音楽性を光らせており、間違いなくアルバムの主人公ではありますが。
Bob Cranshaw

ラストを飾る6曲目はPearsonのオリジナルBedouin、自身の作品では64年11月録音「Wahoo」にてJoe Henを含めた3管編成で、編成を拡大し67年12月録音「Introducing Duke Pearson’s Big Band」にてフルバンドで素晴らしいアレンジを伴って演奏しています。
Wahoo / Duke Pearson
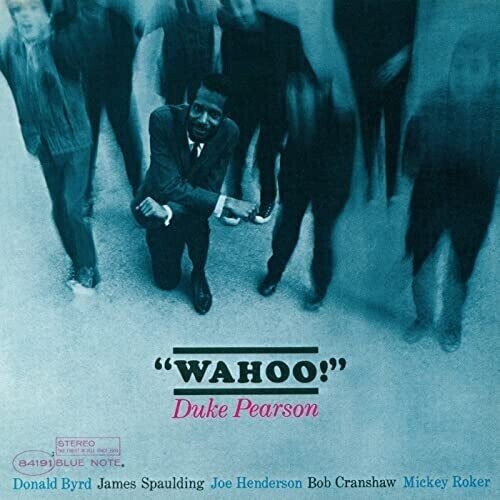
Introducing Duke Pearson’s Big Band

タイトルは砂漠の住人を意味し、普通アラブの遊牧民族に対して用いる名称で、メロディラインやサウンドも中近東を感じさせます。
テナー、ギター、ビブラフォンによるテーマはかなりユニークに響き、エスニックなリズムにHarewoodのドラミングは対応し切れるか懸念するところですが(汗)、スイングにチェンジし、ひとまず胸を撫で下します。
Joe Hen, Green, Hutcherson, Pearsonと順当にソロが続き、ソロ交代時に演奏されるアンサンブルが効果的です。
Joe Henのプレイの革新性、そしてピアノソロには流石コンポーザーとしての深い演奏解釈を聴き取ることが出来ました。
Al Harewood

兄弟アルバム「Idle Moments」での成功を踏まえて1ヶ月後に同一メンバーを揃え、「今度はまだリーダー作を出していないBobby名義でやってみるかい?」のようにオファーされ、「えっ?オレがリーダー?」のようなノリで録音されたのかも知れません。
と言うことで本作は柳の下の二匹目のドジョウを目指しましたが、メンバーの力量を超えてしまった選曲に全体のバランスを些か欠いた出来になり、お蔵入りしてしまったと見るのが妥当かもしれません。
