
Hamp and Getz / Lionel Hampton – Stan Getz
今回はヴィブラフォン奏者Lionel Hamptonとテナー奏者Stan Getzの1955年共演作「Hamp and Getz」を取り上げてみましょう。
Recorded: August 1, 1955 Radio Recorders, Hollywood, California Label: Norgran Records Producer: Norman Granz
vib)Lionel Hampton ts)Stan Getz p)Lou Levy b)Leroy Vinnegar ds)Shelly Manne
1)Cherokee 2)Ballad Medley: Tenderly / Autumn in New York / East of the Sun(West of the Moon) / I Can’t Get Started 3)Louise 4)Jumpin’ at the Woodside 5)Gladys

今までにも当BlogでStan Getzを何度か取り上げたことがあります。Getz自身の演奏は常に絶好調で、共演者の人選、彼らの演奏クオリティにより左右された出来不出来が無い訳ではありませんが、今回共演のヴィブラフォン奏者Lionel Hamptonの猛烈なスイング感、グルーヴがGetzとどのようなコンビネーション、化学反応を示すのかに興味が惹かれるところです。この作品のプロデューサーNorman GranzはJATP(Jazz at the Philharmonic)を 1940~50年代に率いて米国、欧州各地をジャズメンのオールスターで巡業し、最盛期には全世界を風靡しました。彼には興行的な才覚があり、ミュージシャン同士の組み合わせ、時には意外性、奇抜な人選を考えて作品を多数制作、自身のレーベルClef, Norgran, Down Home, Verve, Pabloからリリースしました。本作もその一枚に該当しますがGranzの狙いは今回大いに当たったと思います。
Hamptonは1920年代後半Californiaでドラマーとして活動していましたが、30年頃からヴィブラフォン奏者に転向しました。Gary BurtonやMike Mainieriのような片手に2本づつ、計4本のマレットを使いコード感もサウンドさせるコンテンポラリー系のヴィブラフォン奏者では勿論ありません。Red Norvo, Milt Jackson, Dave Pike, Bobby Hutchersonらのような片手に1本づつ、計2本のマレットで演奏するオーソドックスなスタイルの奏者です。正確なマレットさばきとグルーヴ感、驚異的なタイム感で噂となり、36年にLos Angelesを自身のオーケストラで訪れたBenny Goodmanが彼の演奏を聴き、その素晴らしさに自分のトリオへの参加を誘い、ほどなくピアニストTeddy Wilson, ドラマーGene Krupaから成る、人種の垣根を超えた初めてのジャズ・グループ、Benny Goodman Quatetが誕生しました。超絶技巧と高い音楽性から人気を博したバンドです。
その後40年にGoodmanのバンドから円満退社で独立し、Lionel Hampton Big Bandを結成しました。当時の若手精鋭たちをメンバーに迎え、コンスタントに活動を行い、53年に挙行した欧州への楽旅の際にはClifford Brown, Gigi Gryce, Monk Montgomery, George Wallington, Art Farmer, Quincy Jones, Annie Rossといったジャズ史に燦然と輝く素晴らしいメンバーを擁していました。同時にスモールコンボでも演奏活動は継続され、Oscar Peterson, Buddy DeFranco, Art Tatumたちとも共演、名作として名高いBenny Goodmanの伝記的映画「ベニーグッドマン物語」にも演奏者(もちろん本人役)として出演しています。

言ってみれば当時の米国ジャズ界のスーパーアイドル、ドンとして君臨していたHamptonはこの時47歳、お相手のStan Getzは若干28歳、Jack Teagarden, Nat King Cole, Stan Kenton, Jimmy Dorsey, Benny Goodmanのビッグバンドを経験し、その後Woody HermanのThe Second HerdでZoot Sims, Serge Chaloff, Herbie StewardたちとThe Four Brothersを結成し白熱の演奏を聴かせました。因みに彼らの敬愛するLester Youngのヴィブラート・スタイルでアンサンブルを統一したようです。本作の前年にはトランペットの巨匠Dizzy Gillespieとの共演作「Diz and Getz」、Getz自身のリーダー作としては52年「Stan Getz Plays」をリリース、キャリア的にはまだまだニューカマーの域を出ていない若手テナー奏者Getzでしたが、自己のスタイルを確立した演奏を聴かせています。ベテラン・ミュージシャンとの異色の組み合わせ、胸を借りた演奏はプロデューサーGranzのセンスある采配によるものです。

「Stan Getz Plays」

それでは演奏に触れて行きましょう。1曲目はお馴染みCherokee、アップテンポの定番の1曲です。リズムセクションには米国西海岸を代表するミュージシャン、ピアニストにLou Levy、ベーシストはLeroy Vinnegar、ドラマーにShelly Manneを迎えています。おそらく当時Hamptonが西海岸に在住、GetzがNew Yorkから単身赴任してのレコーディングになり、ご当地のリズムセクションを雇った形になったと思います。ドラムの8小節イントロから曲が始まりますがテーマはなく、いきなりのテナーソロ、ヴィブラフォンがウラ・メロディのような形でバッキングしています。Getzはいつもの彼の一聴で分かる個性的テナーの音色、スピード感ドライヴ感満載のスインギーなソロですが、60年代以降のGetzとはやや趣を異にしており、タイムがかなりon topに位置しているのです(バックを務めるベースの音符の位置はon topであるべきなのですが)。60年代以降晩年まで、完璧とも言えるタイム感を聴かせてテナータイタンとしての存在感を誇示していました。この事は続くHamptonのソロで明確に判明します。早いテンポであるにも関わらず音符の粒立ちの良い安定したマレット・テクニック、そして何よりタイムです!リズムのスイート・スポット目がけて、全くちょうど良いところに音符がはめ込まれています。リズムに対して「のる」のではなく拍の枠に「はめる」が如き演奏、絶対音感ならぬ絶対リズム感を感じさるプレイです!ミディアム・テンポではレイドバックを余儀なくされる、と言うかリズムの後ろにのることは比較的容易に行う事ができます。一方アップテンポや逆にバラードでは音符のリズムに対する位置を的確に維持する事が難しく、そして重要です。前述の作品「Stan Getz Plays」収録のバラードBody and Soul、Getz初期の名演奏として名高いテイクでイマジネーション溢れるフレージング、美しい音色、ニュアンスやアーティキュレーションが十二分に発揮されていますが、タイムがかなりのon topに加え8分音符音符の揺れもあり、後年の演奏とは隔たりを感じさせます。本作録音55年はGetzのタイム感にとっては過渡期であったのではないかと思います。57年10月録音「Stan Getz and the Oscar Peterson Trio」翌11月録音「The Steamer」では全く揺るぎのない、後年に通じるタイム感をしっかりと披露しているのです。ひょっとしたら本作でのHamptonとの共演で刺激を受け、タイムに対する概念を伝授されたのかも知れません。
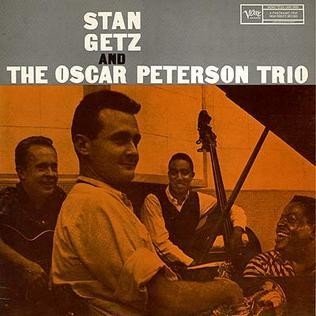
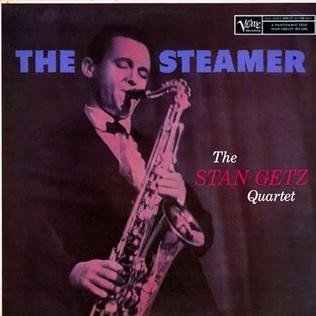
Hamptonに続くLevyのピアノソロ、フレージングは心地よいものを感じさせますが、Getzよりも更にon topのタイム感で演奏しています。その後GetzとHamptonの8小節交換が行われますが、丁々発止とはまさにこの事でしょう、手に汗握るトレードが聴かれます!Shelly Manneのアクセント付けもバッチリ、感極まったHamptonの声も演奏の一部に聴こえてしまいます!ラストテーマも結局提示されずFineですが、それにしてもHamptonのタイムの安定感を嫌という程思い知らされた演奏です(笑)
2曲目はバラード・メドレーTenderly / Autumn in New York / East of the Sun(West of the Moon) / I Can’t Get Started、GetzがTenderlyとAutumn in New Yorkを2曲続けて、HamptonがEast of the SunとI Can’t Get Startedをやはり2曲続けて演奏しています。1コーラスづつ曲の切れ目なしに4曲連続しての演奏、なかなか珍しいフォーマットでのメドレーです。テナーサックスの多彩な表現〜Getzのバラード・プレイの深さに改めて感銘を受けました。Hamptonもヴィブラフォンでのバラード表現を可能な限り表出しているように聴こえます。ここまでがレコードのSide Aになります。
3曲目は古いスタンダード・ナンバーLouise、Hamptonがテーマを演奏してそのままソロへ、なんとも味わい深さを感じさせるプレイです。自然体でメロディを奏でその延長での鼻歌感覚のアドリブが堪りません。ピアノソロ、テナーソロと続きますがこの手のナンバーでのGetzの小粋さも申し分ありません!ラストテーマを匂わせるプレイをGetzが行いますが、Hamptonが再登場、ラストテーマを演奏しGetzはサビを吹いています。
4曲目はCount BasieのナンバーからJumpin’ at the Woodside、1曲目Cherokeeに続く速さでの演奏です。テーマにおけるピアノ、ヴィブラフォンのバッキングがBasieビッグバンドのサウンドを醸し出しており、Manneのシンバルの使い分けも巧みです。ソロの先発はHampton、スピード感とグルーヴ感から高速走行中のアメ車を思わせます。4コーラス目にテナーによるバックリフが入り、そのまま続けてテナーソロに突入します。ここでのGetzのソロ、曲想の解釈が素晴らしいと思います。曲のイメージの中に深く入り込み、曲の構造を基に大胆に再構築しているかの如きアプローチ、タイムの捉え方さえも実にスムーズです。どこかホンカーを思わせるテイストも感じます。ピアノソロ後1コーラスHamptonのソロ、後ろでGetzがバックリフを何故か吹いています。その後HamptonとGetzの8〜4小節交換、ソロの同時進行にも発展しますが物凄いやり取りです!テナー奏者はとことん盛り上がるとホンカーに変貌するのは仕方のない事なのでしょうか(笑)、その後頃合い良きところでいきなり音量を下げてラストテーマへ、その急降下振りに驚かされますが、ヴィブラフォンのバッキングが実に相応しい!
5曲目ラストを飾るのはHamptonのオリジナルで彼の奥方の名前を冠したナンバーGladys、変形のブルースナンバーです。ヴィブラフォンとテナーのユニゾンでテーマが演奏された後、ヴィブラフォンのソロからスタートしますが、さすがコンポーザー然とした流麗なソロを聴かせます。8分音符が少しハネているように聴こえるのは奥方のイメージを反映させたのでしょうか?続くGetzはムーディに、歌うが如く朗々と、付帯音を豊富に含ませたハスキーなトーンでソロを取っています。短いLevyのソロもスインギーです。その後HamptonとGetzの1コーラス・トレードが和やかに、気持ち良さそうに、互いのアドリブの内容を反映させつつ、スリリングに展開され、ラストテーマを迎えて大団円です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
