
Captain Marvel / Stan Getz
今回はStan Getz1972年3月録音のリーダー作「Captain Marvel」を取り上げてみましょう。Billy Strayhorn作のバラード1曲を除き、全曲Chick Coreaのオリジナルを取り上げ、至高のメンバーと素晴らしい演奏を繰り広げています。
Recorded: March 3, 1972. A&R Studios, New York City Label: Columbia Producer: Stan Getz
ts)Stan Getz electric piano)Chick Corea b)Stanley Clarke ds)Tony Williams perc)Airto Moreira
1)La Fiesta 2)Five Hundred Miles High 3)Captain Marvel 4)Times Lie 5)Lush Life 6)Day Waves
ジャケット表面

ジャケット裏面

Getzの伝記「Stan Getz / A Life in Jazz: Donald L. Magginースタン・ゲッツ―音楽を生きる―村上春樹訳」によると、この作品録音の少し前、彼は生活が荒れて体調も優れない日々が続いていたようです。レジェンド・ジャズミュージシャンの伝記はその数だけ世の中に出回っていますが、Getzの場合も御多分に漏れず出版されており、日本ではジャズ通として名高い作家、村上春樹氏が翻訳を手掛け、微に入り細に入り的確な表現で読むことが出来ます。熱心なGetzファンの方ならこの本をご存知の事でしょう、ひょっとしたら座右の書にして彼の音楽的歩みを紐解きながら作品を鑑賞しているかも知れません。実は僕はその一人なのですが、前後作品との関連性と成り立ち、ミュージシャンやレコード会社とそのスタッフとの関わり、Getz自身の思い、家族との葛藤や愛情を辿りながら彼の作品を聴く事は、新たな発見や種明かしにも通じて、Getzの音楽を知る上での実に楽しい行為の一つです。それにしてもよくもこれだけ生々しく赤裸々に、全てを曝け出すように人生を吐露出来るのか、詳細に述べられている記述、Miles Davisの自伝の時もそうでしたが本人の驚異的な記憶力、また綿密な周囲へのリサーチ、事実関係の確認には頭が下がります。
神からの授かり物のようなあの美しいテナーサックスの音色、誰よりも表情豊かな演奏、完璧なタイム感とクリエイティヴなインプロヴィゼーション、聴く者を真善美の世界へと誘う創造性を全面に掲げたStan Getzですが、実は私生活は同一人物の行いとは想像できないほど真逆の世界なのです。ジキル博士とハイド氏、過度の飲酒行為に端を発する酒乱癖から(この頃はより症状が劣悪なドラッグ禍からは脱していましたが…)、家族に暴言を吐く、暴力を振るうGetzに対し、妻がこっそりと服用させていたアンタビュース(抗酒癖剤〜アルコール依存症で飲酒を控える必要がある人に対し、断酒を目的として処方される薬。少量の飲酒で動悸、吐き気、頭痛等の不快感を覚える)が功を奏し、71年末酒量は適度なレベルに落ち着き、69年末の危機的状況から肉体的にも芸術的にも回復を遂げていました。
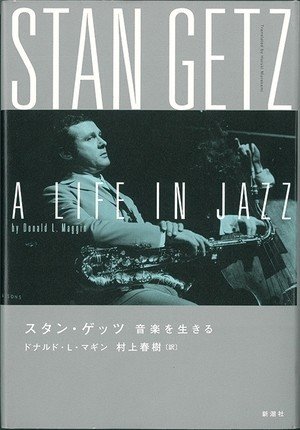
本作レコーディングの少し前、GetzはNew Yorkの高名なレストランRainbow Grillとの間で好条件の出演契約を結び、72年1月3日から演奏が開始されることになっていたので、当時滞在していたLondonを引き払い自宅のあるNew York Shadow Brookに戻るべく準備をしていました。その時Londonの街角でばったりとChick Coreaに出会ったのですが、彼とは67年3月録音の名盤「Sweet Rain」で見事なコラボレーションを遂げた間柄です。Coreaはこの頃一時的に、言わば仕事にあぶれた状態だったので、Getzの姿が救世主に見えたかも知れません、彼に対し自分が作曲中の幾つかの曲について熱く語り、また一緒に演奏したいと考えている二人のNew Yorkのミュージシャンについてもその素晴らしさ説きました。Coreaの熱心さはGetzの心を動かし、新曲を完成させるようにと困窮しているCoreaに金銭的援助を施し、12月後半にその仲間を連れてShadow Brookに来るように、そこでリハーサルをしようと決めたのでした。ストレスによる飲酒行為から離れた、クリーンな状態のGetzはまさしく彼のテナーサックスのサウンドと同様の、思慮深く知的で他人を思いやる心に満ちた紳士なのです。ちょうど欧州を離れる前にGetzは5年連続でSonny Rollinsを破って<ダウンビート>誌の人気投票で首位に輝いた事を知りました。時代の波はGetzに向かっていたのです。

CoreaがGetzの自宅に連れてきたのはStanley ClarkeとAirto Moreiraの二人で、Coreaを含めるとピアノトリオが出来上がり、そこにGetzを加えたカルテットで自分の曲を演奏するという目論見があったのでしょう。Clarkeは70年にHorace Silverのバンドで演奏しているところをCoreaに見染められ、MoreiraはMiles Davis Bandでの共演仲間でした。GetzはCoreaの新曲を大変気に入りました。「 Sweet Rain」収録とは異なり、今回用意されたナンバーは曲自体の構成もより明確に、メッセージ色が強くなり、またスパニッシュのムードをたたえた斬新なコンセプトから成ります。Clarkeのベースプレイにも感心しましたが、Moreiraのパーカッショニストとしての実力は認めたものの、ドラマーとしての伴奏能力には物足りなさを覚えたので、レコーディングに際して名ドラマーTony Williamsを起用し、Moreiraはバンドのパーカッシヴな領域を広げる役に配して対応することにしました。TonyはGetzの演奏に確実に寄り添う形で、しかも驚異的なセンスとパワーを兼ね備えたドラミングを披露し、MoreiraはTonyを補強しつつよりカラーリングする役割を担当、Clarkeのベースともコンビネーションの良さを聴かせ、結果この采配は大成功となりました。このメンバーでのRainbow Grillでの演奏は大変な評判を呼び、彼ら自身もCoreaのオリジナルという新鮮な素材を文字通りグリルし、じっくりと煮詰めて行くことが出来たので、レコーディングへの良いリハーサルとなりました。
それでは演奏に触れて行きたいと思います。1曲目はCoreaの書いた名曲中の名曲La Fiesta、本作録音のちょうど1ヶ月後の2月2〜3日、レコーディング・スタジオも全く同じNYC A&Rスタジオにて彼の代表作「Return to Forever」が録音されましたが、レコードのSide Bにおいて組曲形式でLa Fiestaを再録音しています。Coreaはやはり全曲エレクトリック・ピアノを弾き、サックス奏者にJoe Farrell、パーカッションを担当していたMoreiraがドラムの椅子に座り、そのMoreiraの奥方Flora Purimがボーカルを担当、Tonyのドラムは参加せず5人編成の演奏で、70年代を代表するアルバムが録音されたのです。以降作品タイトルReturn to Foreverをバンド名とし、メンバーチェンジを繰り返しながらギタリストを加えたり様々な編成にトライしつつ、次第にエレクトリック色が濃くなり、精力的な活動で計11作をリリースして。

Fender Rhodesによるイントロに導かれベース、ドラム、パーカッションが同時に加わりますがこの時点でリズミックなテンションが炸裂しています。Moreiraにパーカッションを演奏させたGetzの目利きにまず感心させられますが、様々な打楽器を駆使して繰り出すリズムの饗宴!Tonyにリズムの要、Getzの演奏への対応をほぼ一任し、Moreiraは細かい8分の6拍子を担当、リズムの祭り(Fiesta)を華やかに演じます!裏メロと思しきラインをCoreaが弾き、被るようにGetzによる主旋律が登場します。1ヶ月後の「Return to Forever」でのJoe Farrellによる演奏はソプラノサックスによるもの、こちらも実によく耳にしたメロディ奏なので違いがはっきりと伝わって来ますが、Getz特有のくぐもったハスキーな音色は奥行きを感じさせ、名曲は如何様にしても異なった魅力を発揮すると再認識しました。幾つかのメロディセクションから成るこの曲の、場面毎のリズムセクションのダイナミクス付け、グルーヴの変化に繊細さと大胆さを感じますし、Clarkeの変幻自在なベースラインの見事さには天賦の才を見せつけられました!スパニッシュ・モードから成るソロセクション、こちらはCoreaの歴代オリジナルに用いられていたパートの発展形と言えます。「Now He Sings, Now He Sobs」収録のSteps – What Was、「Sweet Rain」収録のWindows、両曲で部分的に聴かれていたスパニッシュ・モードを大胆に、全面に押し出し、結果その代表曲となり、そして同年10月に録音された「Lght as a Feather」収録、Coreaの代表曲にして傑作ナンバーSpainへと繋がって行きます。

前半序奏部Getzはムード作りに細かいライン、テクニックを用い場を温めて行きます。とは言え曲自体の持つテンションが高いのでリズム隊のポテンシャルは一触即発状態ですが!Coreaのバッキングは付かず離れずをキープしつつ、全くバッキングを行わない場面も設けながらGetzを泳がせているのですが、いつもとは異なる斬新なアプローチを聴かせる彼の演奏にどうバイト(噛み付く)するかを虎視淡々と狙っています!3’23″頃からソロの佳境に入ったのを察知しまさしく第二楽章に突入、3’29″からのCoreaのバッキング、3’46″からテナーの低音域でのメロディ奏、一転して4’03″からオクターヴ上げてのメロディに対し、Corea果敢にして大胆にバッキングを施し、Tonyも場面作りに賛同するが如くアプローチします!次なる異なったセクションに全くスムースに突入出来るのは、Rainbow Grillでのギグを重ねた結果に他ならないでしょう。Clarke, Tonyの「えっ?ここまでやっちゃうの?」と言う次元の伴奏にはリスナーとして姿勢を正し、背筋を伸ばして正座しながら音楽に対峙しなければなりません(笑)!続くCoreaのソロの凄まじい事と言ったら!Getzのフィーヴァーぶり(死語ですね)を受け継いだのですからこれは致し方ない事ですが(笑)、フリージャズの世界に突入せんばかりの勢いは、思わず70年頃に彼の率いていたバンドCircleでの演奏を思い出しました。
Anthony Braxton, Corea, Dave Holland, Barry AltschulによるCircleのパリでのライブ盤
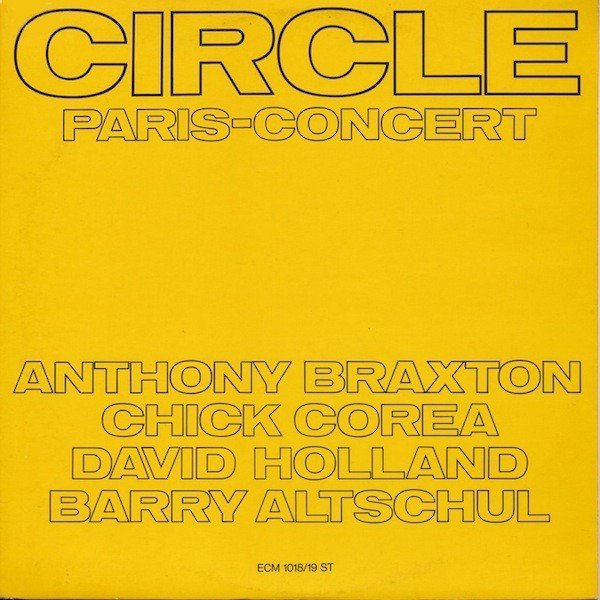
リズムセクションはCoreaと一丸となってグルーヴを共有し盛り上がっています。時間的制約のないRainbow Grillのライブではさらに物凄い事になっていたのでしょうが。ラストテーマでもリズム隊はメロディラインや曲の構成を更にデコレーションを施すべく、聴いていて笑いが出る程に巧みにアンサンブルして行きます!エンディングはゼンマイ仕掛けの猿の人形、両手で派手に叩くシンバルが次第にゆっくりに成るが如く、リタルダンドしてFineです。
本作録音の頃Getzは20年間在籍していたVerve Recordを離れ、より良い条件のColumbia Recordに移籍するべく交渉を行っていましたが、スムーズにはまとまらず、その結果アルバムの発売は3年近く遅れることになり、発売権も米国内市場ではColumbiaが、以外の海外市場ではVerveが発売権利を持つややこしい事態となりました。本作が録音順で「Return to Forever」よりも先にリリースされていれば、La FiestaはGetzヴァージョンの方がポピュラー、定番になっていたに違いありません。個人的には演奏内容はこちらの方に軍配が上がると信じているだけに、些か残念な話です。
2曲目のFive Hundred Miles High、エレクトリック・ピアノが弾くテーマ・メロディのルパートがイントロとなり、リズムを提示し曲が始まります。Even 8thのリズムで哀愁を感じさせるメロディ、Coreaにしては比較的シンプルなオリジナルですがよく練られた構成のナンバーです。Getzのメロディ奏は的を得ていて、ソロも実に巧みです!50年代〜60年代のスタイルとは全く異なる、変化を遂げているのを実感しました。ソロの3コーラス目から倍のグルーヴ、サンバにチェンジしますが4コーラス目3’04″から、Tonyの煽り方の凄まじい事!かつて僕が在籍していたドラマー日野元彦(トコ)さんのバンド、音楽としてはフュージョンを演奏していましたが、ここでのTonyの演奏をトコさんずいぶんと研究した節が窺われます。ソロイストに寄り添い、フォローしつつ、様子を伺い隙なく一瞬を捉えて違う次元に演奏をワープさせるが如きドラミング、二人は同じコンセプトをたたえたドラマーでした。随所に聴かれるMoreiraのパーカッションは様々な色合いを感じさせ、爽快感を覚えます。Coreaのソロでもサンバのリズムが聴かれますが、テナーソロ時とはまた異なった音が鳴り響いています。Clarkeのベースソロは超絶で饒舌はありますが、必然性と意外性を旗頭に自身の歌を聴かせています。ラストテーマに入る前のTonyのバスドラ、カッコイイですね!ラストテーマで所々に演奏中表出したサンバが出るあたりもニクイです!それにしてもTonyとClarkeの相性の良さを痛感しますが、Tonyのラスト作になった95年12月録音「Wildernesss」、彼自身の作曲になるストリングス・オーケストラの演奏もフィーチャーした意欲作ですが参加メンバーがオールスターズ、Michael Brecker, Pat Metheny, Herbie Hancock, そしてStanley Clarke!二人のコラボは長年に渡り継続していたようです。
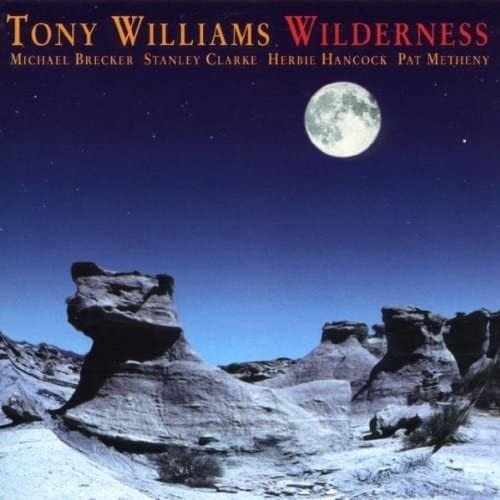
3曲目は表題曲Captain Marvel、リズミックなテーマとサンバのリズム、ラテンのmontunoのパターンが組み合わされたユニークなナンバー、こういった曲を収録するのであれば尚更の事、パーカッションが必要になって来ますね。リズム隊のコンビネーションが心地よく聴こえますが、曲のコード進行や構成のハードルがかなり高く設定されているようで、アドリブを発展させるのはなかなか難しいようです。比較的あっさりと演奏され、コンパクトにまとめられた感があります。03年にリリースされたCDにはこの曲の別テイクが収録されていますが幾分テンポが早めに設定され、Getz, Coreaも全く違ったアプローチを聴かせています。
4曲目Times Lieはワルツで始まり、3拍を4拍子に捉えたサンバにリズム・モジュレーションする構成のナンバー。パーカッションの味付けが巧みです。Coreaの演奏が軸となり、印象的かつ難易度が高そうなシンコペーションのメロディがアクセントで入り、再度演奏後にテナーソロ開始、場を活性化させるべくリズミックなアプローチにトライしており、ここでもCoreaのバッキングの付かず離れず感が印象的です。次第に収束に向かい、冒頭のワルツに戻るという、ストーリー仕立ての演奏です。最後はゆったりとしたラテンのリズムになり、なし崩し的にFineです。
5曲目はBilly Strayhornの名曲Lush Life、Getzはバラードの名手でもありますし、時期限定で取り上げる曲のチョイスが素敵です。バースはルパートで始まり、エレピとアルコが伴奏を努めます。テーマからインテンポでTonyがブラシを携え参加しますが既に倍テンポの様相を呈しており、いきなりスティックが登場して一瞬スイングのリズムになりますが、すぐさまリタルダンド、演奏終了です。ちなみにTonyのバラード演奏でブラシを一切使わず初めからスティックを用いて行われているのが、76年録音作品「I’m Old Fashioned : Sadao Watanabe with the Great Jazz Trio」に収録されている、同じくStrayhorn作Chelsea Bridge です。外連味のないストレートな演奏に仕上がっていますが、印象的なナンバーです。
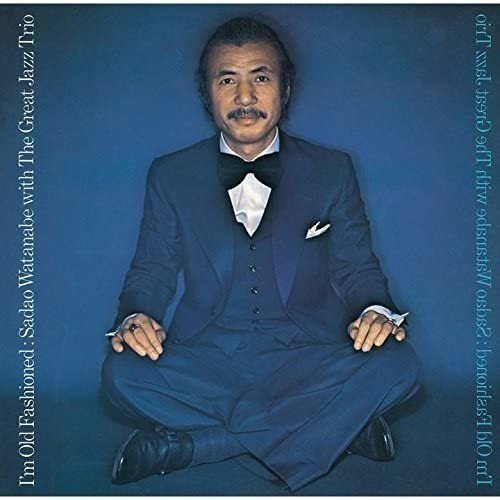
6曲目はラストを飾るDay Waves、こちらもEven 8thのリズム、テーマでダイナミクスが強調されています。Getzが吹くラインで倍テンポが決まりますが、構成がやや平坦なきらいがあり、他の曲でも倍テンポチェンジは行われているので、何が何でも倍テンにせずにじっと元のリズムでステイして、アプローチするのも良かったと思うのですが。ピアノ、ベースとソロが行われ、ラストテーマもGetzダイナミクスを思いっきり強調してFineです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
