
アニメ映画『ねらわれた学園』を読む
筆者は、本作(アニメ映画『ねらわれた学園』)とは、中村亮介監督が描いた「科学の再婚」の物語だと考えている(作中において、『夏の夜の夢』という「結婚」と結びついた恋愛喜劇が引用されているのも、そのことを暗示するためだと解釈している)。

村井さだゆき「この場合の「科学の再婚」っていうのは、精神的なことと科学的なことが乖離してしまったのが近代で、それをもう一度結婚させたいことを願っている輩っていうことだと思ったんです」
中村亮介「僕もまったく同じ理解でした。(…)精神っていうのを肉体と分離して考えてしまうというのは、ガリレオ、デカルトの時代には宗教っていうものから科学が自由になるために必要だったわけですけど、時代を経てきて二〇世紀になって、逆にそれが人を苦しめてる部分があるっていうようなことで僕は捉えてるんです」(『魍魎の匣』最終話「魍魎の匣、あるいは人の事」オーディオコメンタリー)
したがって、本作における「敵」をあえて挙げるとするなら、それはリョウイチの父親(京極博士)に代表されるような、ひとりの人間を能力者であるかないかで判断し、まるでその人の精神を肉体から分離させ、人間を計算可能な「対象」として扱ってしまうような考え方だと言えるのではないだろうか。

リョウイチ「風が甘い。空気に、匂いがあるんだ。ここが、地球」
共感覚的知覚は〔むしろ〕通例なのであって、われわれがそれと気づかないのは、科学的知識が〔具体的〕経験にとってかわっているからであり、また、われわれが見ること、聞くこと、一般に、感覚することをきれいに忘れてしまって、われわれの身体組織や物理学者が考えるような世界からわれわれの見たり聞いたり感覚しなければならぬものを演繹しているからである。(…)つまり、形は対象の固有の本性と或る関係をもち、視覚にだけでなくわれわれのすべての感官に語りかける。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
身体という「主体」(いわゆる「意識」)ともなれば、物質的な「対象」ともなる両義的であいまいなものに着目し、デカルト的二元論の超克を図ったとされるフランスの哲学者モーリス・メルロ=ポンティによれば、例えば音を聴くと色が見えるというように、ひとつの感覚から別の領域の感覚が引き起こされる「共感覚」的な知覚というのは、実は特別なことではなく、むしろそうした感覚こそが、本来の知覚の形式なのだという(「音は色の残像を変えてしまう」(『知覚の現象学』))。本作の冒頭、未来の月で生まれ育ったとされるリョウイチは、地球に降り立ち初めて体験する地球(鎌倉)に吹く自然の風を、まさに身体全体で感じながら、普通の人には考えられないような、「甘い」という感覚を受け取っている(このように感じている時点で、リョウイチが悪いキャラクターではない印象を受ける)。
中村監督は、「京極〔リョウイチ〕という、一分の隙もなく完璧に見える子が、ケンジのペースに自然に巻き込まれていって、しだいに人間性を見せていく物語をやりたくて」 (*1) と語っているのだが、ドビュッシーの「月の光」を弾いている姿や、学校の裏山から見える「絶景」に対して素直に驚いている姿から想像するに、おそらくこのリョウイチというキャラクターは、(時間はかかっていたかもしれないが)ケンジたちと出会っていなくとも、地球を好きになって、京極博士の考えとは相反するような「人間性」を獲得していったことが予想されるだろう(例えば、夢中になってピアノを弾くという行為は、いわばピアノとの「一体化」を表しており、それは京極博士のように、相手を「対象化」して支配しようとする行為とは真逆のことを意味していると言えるだろう。なお、このことは、後述するカホリにとってのサーフィンにも当てはまることである)。

彼〔=オルガン奏者〕は腰掛けに坐り、ペダルを操作し、音管を引き、楽器を自分の身体に合うようにし、楽器の方位や大きさを自分の身体に合体させ、あたかも家のなかに収まるように楽器のなかに収まる。(…)楽譜面で指示されているような楽曲の音楽的本質と、実際にオルガンのまわりで鳴りわたる音楽とのあいだには、きわめて直接的な関係が確立されていて、その結果、オルガン奏者の身体と楽器とは、もはやこの関係のあいだの通過点でしかなくなっている。そうなるともう、音楽はそれ自体で存在し、音楽によってこそその他の一切のものも存在する、ということになる。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
「ドビュッシーが描こうとしたのは、ただの月の光の情景ではありませんでした。作曲のきっかけは、フランスの詩人ヴェルレーヌの詩集「雅(みやび)なうたげ」に収められた「月の光」。この詩には、楽しいこと、悲しいこと、という相反するものがこん然一体となった、あいまいな世界が描かれています」 (*2)

中村亮介「シロは、ケンジの超能力を封印して具現化したものです。まあ、ケンジの分身ですね。だからカホリと会った時とか、ケンジの内的欲求に忠実で、犬のくせに分かりすぎてるといいますか(笑)」 (*3)
中村亮介「たとえば大人から見るとみな一様に幼く見えても、 中学生の頃にはすごく大人びて見えた同級生っていましたよね。それが女の子だと、彼女を見る自分の視線ってすごくエッチだったりして(笑)。 そんな中学生の時の自分の感性も、思い出せるかぎり思い出して。卒業文集も読み返して、身もだえたり(笑)。でもそれを恥ずかしがらずに、恰好つけずに見せるように心がけたつもりです」 (*4)
たとえば、女性はかすかな気配からも――また彼女自身は自分を見つめている当の相手を見ることがなくとも――自分の身体が欲望の対象となり、見つめられていると感じるものである。このばあい、「テレパシー」と言われるのは、それが他人による実際の知覚に先行するということによる(色情狂)(メルロ=ポンティ『見えるものと見えないもの』研究ノート)
学校に到着したナツキは、「さては、あいつ〔=ケンジ〕が何かやらしいことしたんでしょ?」とカホリに問い詰める。ケンジが直接カホリに対して「やらしいこと」をしたわけではないのだが、これはなかなか的を射た発言である。というのも、ケンジが連れていた犬のシロは、がっつりカホリに対して「やらしいこと」をしており、実はこのシロの正体とは、ケンジのチカラそのものであって、いわば(ケンジの欲望や本能の象徴である)シロが、ケンジの代わりにカホリの胸を触っていたとも言えるからだ。
もしかしたらナツキは、シロの正体についてうすうす感づいていたのかもしれない。そして、仮にそうだとしても、それは決して不思議なことではないだろう。なぜなら、現在のナツキには超能力はないのだが(「ナツキは過去に能力を持っていたけど、今はなくなった人。ケンジは能力を封印されていたけど、目覚める人。カホリは元々能力を持ってなくて、今もない人。そして、京極は能力を持った状態で未来から来て、それをなくす人」 (*1) )、そもそも人間とは、相手の表情や動作、目配せなどから、多くの情報を読み取ることができる生き物だからである。それこそ「テレパシー」のように、相手の心を読めてしまう場合もあるからである(もちろん単なる妄想でしかない場合もあるのだが)。例えばカホリが、「胸が大きいことを気にして、小さい下着をつけている」(『公式ガイドブック ねらわれた学園』)要因のひとつには、カホリが無意識的に男子たちの心を読んだということが考えられるだろう。

予鈴を聞きながら、彼は校門をくぐり、二年三組の教室に走りこんだ。セーフである。(眉村卓『ねらわれた学園』)
精神はもはやそれだけ離れてあるのではなく、自然発生によるかのように、数々の身ぶりの端に、数々の単語の端に芽生えてくる。(メルロ=ポンティ『シーニュ』)
教室に駆け込むケンジの姿は、原作からのオマージュだと思われる。ケンジという主人公は、良くも悪くもマイペースを貫けるキャラクターであって、いわば場の空気を「ずらす」ことができる存在だと言える。この場面では、ケンジが勢いよく走りこんで来たことで、リョウイチの自己紹介が中断することになる(この時リョウイチは、ケンジから強い「風」を受けることになり、人間らしい驚いた反応を示している)。さらに、席に着いたケンジを嬉しそうにからかうナツキの姿が描かれ、そんな2人を見つめるカホリのカットが挟まれる(身体を持つ私たち人間が、「見るもの」であると同時に「見られるもの」でもあるということが示されていると言える)。また、その直前では、リョウイチを見て顔を赤くしたカホリを見るナツキのカットがあり、ナツキがケンジを好きなことにカホリが、カホリがリョウイチを気になっていることにナツキが、それぞれ携帯電話や超能力などを使わなくとも、すでになんとなく気づいている様子が描かれているのである。まさに劇中においてカホリが言っていたように、「言葉がなくても伝わることもある」というわけだ。そして、「風」がカホリのノートのページをめくるように、リョウイチが転校してきたことで、物語が動き出すのである。


ナツキ「永遠のお隣さん。そう、それが私のポジション。今までも、今も、これからも。ずっと、ずっと」
中村亮介「ケンジに限らず僕も、いや誰でも、今生きているという現在は、いろいろなちょっとした偶然のうえに、たまたまあるもののはずだと僕は思っているんです」(『公式ガイドブック ねらわれた学園』)
われわれが生きてきたところは、われわれにとって永久に存在しつづけるものであって、老人は己れの幼年時代と接続しているのだ。産み出されてゆく各現在は、時間のなかにあたかも楔のようにうちこまれ、それぞれ永遠たることを主張している。(……)現在に到来することによってのみ、時間の一瞬は消しがたい個体性、〈決定的一回性〉を獲得するのであり、そのお蔭でこの一瞬はそののち時間を貫いて進むことが可能になるのだし、われわれにも永遠性の幻想が与えられることになるのだ。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
ケンジのことが好きなナツキには、超能力がなくとも、ケンジの考えていることが手に取るようにわかるようである。一方(カホリのことが好きな)ケンジには、そんなナツキの本当の気持ちが、まったく伝わっていない様子である。おそらくナツキはこれまでに何度も、ケンジのことが「好き」というサイン(仕草など)を、意識的にせよ無意識的にせよ、出し続けていたに違いない。少なくともカホリは、そのサインに気づいていた。しかし、まるで「好き」という言葉だけが決して伝わらない、あのナツキが見ていた夢のように、サインだけでは伝わらないことが、すなわち、実際に言葉にしなくては伝わらないことがある、ということをここでは示唆しているのだと思われる。
そしてナツキは、本当の自分の気持ちにまったく気づく気配のないケンジのことを、いったん諦めようとしてしまうのである。自分は「永遠のお隣さん」なのだと。「それ以上でも以下でもない」のだと。しかしこの考え方は、端的に間違っている。この時のナツキは、永遠の意味を誤解している。なぜなら、お隣さんでしかない「今」が「今まで(=過去)」として認識され、お隣さんであったことは確かに永遠かもしれないが、「これから(=未来)」もお隣さんであるかどうかは、誰にもわからないことであるからだ(未だ「現在」に到来していない時間には、永遠を主張する権利などないのだ)。

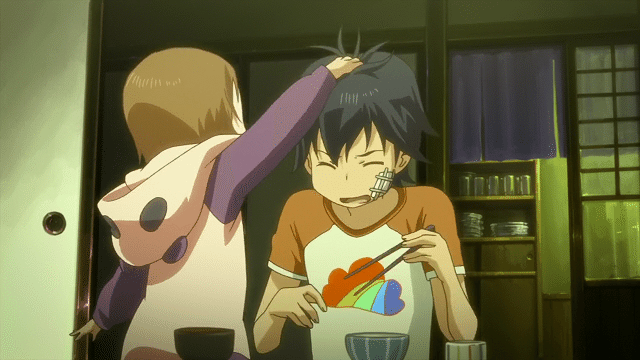
中村亮介「登場人物の心象や、見ている人の心象が絵に投影されるような画面作りをしたい。そういった絵作りを、今回は全編通してやってます。言葉にすると「青春」なんですけど、それは今の時代の空気的に、言葉ではすごくすごく表現しづらいことなんですよ。だから映像で表現する。でないと、すぐに上滑りしてしまうものだと思うんです」 (*5)
中村亮介「心の風景…というのかな。実際には世界のどこにもないけれど、僕らの心の中にだけある風景であり、心の中にだけある時間としての「青春」――。アニメという表現には、それが適していると思うんですよ」 (*6)
絵画は世界の模倣ではなく、それ自体が世界なのです。(メルロ=ポンティ『知覚の哲学』)
韻文または散文のテクストに空漠としたうなりのようなものを伴奏につけて舞台音楽だと称している場合があんまり多すぎるのです。そんなのは舞台音楽ではありません。テクストと緊密に一体化していてこそ舞台音楽ですよ。(ドビュッシー『音楽のために』)
ケンジは、「何かに見える雲」を撮りためていた。同じものを見ても、人によって連想するものや解釈は違ってくる(とはいえ、完全に違うというのも珍しいことであり、基本的に連想や解釈には、社会的文脈において「何らかの傾向が見られる」場合がほとんどであろうが)。本作の『公式ガイドブック』には、「どれひとつとして同じものはなく、それぞれが少しずつ形を変えていく――。そんな、人の気持ちにも似た雲は、映像作品では登場人物の心象風景として、よく使われる。(…)「ねらわれた学園」の空と雲を見て想いをはせてみてほしい。そこにはケンジとナツキ、カホリや京極達の解き放った想いが静かに、雄弁に描かれているはずだ」とある。雲を雲というひとつの「対象」として捉えるのではなく、ハンバーガーに見立てるケンジの考え方に、リョウイチは興味を惹かれ、笑って応えるのである(ケンジが着ていた服が示すように、雲にも様々な色があるというわけだ)。
そして、お腹が減っていたケンジが雲を見てハンバーガーを連想したように、恋するカホリは夕日を見て、「私、生まれて初めてかも。こんなきれいな夕日」とつぶやくのである(「生まれて初めて」という表現から、初恋であったことが推測される)。まさにここでは、中村監督が言うように、「その人たちの目線から建物がどう見えたのか、風景がどう見えたのか、その心情に寄りそう」 (*7) ような描写が、丁寧にされていると言えるだろう(カホリに「好きな人いないの?」と問われ、「いないよ」と無理をして明るく答えるナツキの言動にあわせて、だんだん日が沈んで画面全体が暗くなっていくのが印象的である)。
普遍性と世界とは、個別性と主観の深部に見いだされるものだ。このことは、世界を対=象〔対立像〕として考えているかぎり、永久に理解できないであろう。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
ヘレナ「恋すれば、誰も目では見ない、心で見るの」(シェイクスピア『夏の夜の夢』)

カホリ「ここでだけ、私は父さんを感じられる。父さんと会話できる気がするの」
中村亮介「死は生の対立概念であるけれども、生の一部でもある。生きるという行為には、実は大変な矛盾があるけれども、それはコミュニケーションも同じで。その究極の形がテレパシーであるとしても、それを僕は「人間的」とは決して思わない。僕は音楽をやっていたから「倍音」という言葉が好きで。音がそのとおりに聴こえなかったとしても、「倍音」は聴こえているんじゃないか。空気の振動が、熱が、相手に何かを伝えているんじゃないか。この作品の中でも、希望的に、僕はそう考えたいんです」(『公式ガイドブック ねらわれた学園』)
「生」とは、実感できるもの、「経験」領域に存在する。しかし、「死」の経験とは、まさに「死ぬこと」によってしか経験できない。故に、生者にとって、「死」そのものは「夢想」や「観念」としてしか描きようがない。ましてや、生きている者が「生きられる世界」のあるがままを描くのならば、当たり前のようだが、それは生者の「見る」世界なのだ。つまり、「死」の次元に属するものは、「対象」として実見することができないのである。(小嶋洋介「死と「鏡」としての現象――自然の存在学のために:セザンヌとメルロ=ポンティ」)
カホリがサーフィンをするのは、亡くなった漁師だった父を感じるためであり、そこには、母子家庭で育つカホリなりの「ささやかな母への抵抗」という意味合いもあるそうだ(『公式ガイドブック ねらわれた学園』)。一般に、死者とは、目で見ることのできない存在である。仮に見えたり感じられたりする人がいたとしても、それをすべての人に共有できる形に、すなわち「対象化」することはできない。同じ雲を見ても、どう感じるかは見る人によってそれぞれ違っていたように、海を漂う中で、カホリの亡くなった父と会話できる(気になれる)のは、カホリしかいないだろう。
本作における4人のメインキャラクターの中で唯一カホリだけが、現在においても過去においても、超能力とは無縁な存在として描かれるのは、カホリが小さい頃からそうした絶対的に「対象」とすることのできない存在を、身をもって知っていた(経験していた)からではないだろうか。中村監督はカホリのことを、「僕の理想の女の子」として設定したそうだが(『公式ガイドブック ねらわれた学園』)、それは外見的なことだけでなく、そうした「人間性」を持った内面をも含んでのことだったのだと思われる(良い意味で、普通の子にしたかったのではないだろうか)。


まだ能力者として覚醒したのが山際ゆりこだけだった頃、チカラを持つ山際(とリョウイチ)は、校内の外で描写されていた。しかし、彼らのチカラが徐々に校内に広がるにつれ、今度はチカラを持たないカホリ(と神野)が少数派として、校内の外で描写されることになる(このとき、校内でガラス越しに不敵な笑みを浮かべる山際の姿が印象的である)。
山際たちは、生徒会を牛耳り、自分たちにとって都合のいい「規則」を制定していく。原作にもあったようなこうした生徒会シーンは、恋愛面にフォーカスした本作においては不向きだと考える人も一部で見られるようだが、筆者は、そんなことはないと考える。というのも、冒頭でも述べたように、本作は、精神的なものと肉体的なものを分離させ、二者択一を迫るような考え方に対して否定的だと思われ、どちらか一方を称賛するような態度はとらず、あえて言うなら、分離する以前の「自然」そのものを称賛している作品だからである(このことは、マイペースなケンジの性格にもよく表れていると言えるだろう。また、本作において見られるいくつもの生き生きとしたアニメ的誇張表現からは、まるで「自然」そのものを称賛するような、アニミズム的な精神を感じることもできるだろう)。
そして「規則」とは一般に、「自然」と対立するものである。そのため、ケンジたちが生徒会(山際たち)と対立的な構図で描かれるのは、至って本作に適した展開だと考えられるのである。
中村亮介「僕の好きなアニメって、大塚(康生)さんが作監をしてた頃の宮崎作品とか、『トムとジェリー』とか。ワクワク、ドキドキするような躍動感のある作画、アニメーションであることの喜びを全身で謳歌しているような作品なんです」 (*8)
われわれは物理的なものに対して「心理的なもの」、心的なもの、生気あるもの、生命あるものを対置する。しかしこれらはすべてギリシア人にとっては、その後期においても、やはり physis〔自然〕 に属している。 physis に対立する現象としては、ギリシア人が thesis すなわち定立、措定と呼ぶもの、もしくは nomos すなわち人倫的なものという意味での法則、規則と呼ぶものがある。(ハイデッガー『形而上学入門』)

多くの意識が、大勢で演ずる独我論という滑稽劇をたがいに上演し合っているわけであるが、この状況をこそわれわれは了解しなければならない。われわれはこの状況を現に生きているのだから、それを解明する手だてもあるにちがいないのだ。(…)私の死の瞬間が私にとっては近づきえぬ未来であるのと同じように、私は他者の彼自身への現前を生きることは決してできないと確信している。けれでも、それぞれの他人は私にとって、否認しがたい共存のスタイルないし場という資格で存在しているのであり、私の生は、それが或る死の匂を伴っているように、或る社会的雰囲気を伴っているのである。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
自分の気持ちを理解しない周囲に絶望し、飛び降りようとしていた山際ゆりこは、リョウイチに助けられ、チカラを与えられていた。そのチカラを使って、人工的に能力者を増やしていく山際たち。その中には、生徒会長である曽我はるかの姿もあった。劇中において曽我は、「いつでも(…)自分の気持ちは自分の中にあるもの」という独我論的な考えを表明していた。このことは、自分以外のものをすべて「対象」として見なしてしまう考えにつながりうるものであり、おそらく曽我に能力者としての素質があったことと無関係ではないだろう(山際も、しゃぼん玉を例に出しながら、人が孤独で「つながっていない」ことを強調する)。そんな曽我とは対照的に、能力者として覚醒しなかった副会長の神野ゆうは、「自分以外の誰かがいるから起こる気持ちもある」と主張する。神野は、「本当の自分の気持ち」なるものを疑っているのだ。
神野の主張は、おそらく正しいだろう。というのも、確かに私たちは山際の言うように、孤独な「自分だけの世界」(精神)を持っているだろうが、私たちは身体を持つことで、「他者の存在するこの世界」を実感することができ、そして、この世界において他者から(強制的に)影響を受け取ることになり、その影響が、いわゆる「自分だけの世界」の方にも確実に及んでいると思われるからだ(そもそも思考する際に用いる言語が、社会(=他者)から与えられたものである)。すると、純粋な「本当の自分の気持ち」というものは、一体どこにあると言えるだろうか。まさに劇中で神野が言っていたように、自分の気持ちとは、「人と人のあいだの空気の中にある」とも考えられるのである。そして「空気」とは一般に、みんな=社会によって作られるものである。つまり私たちは、この社会の中で、ある意味強制的に共存させられているのであり、この社会から、絶対的な意味で孤立することは不可能であると言えるのである(山際は、私たち=しゃぼん玉が「つながっていない」と強調するのだが、実はそのことをカホリに対して言うのは笑止千万なことである。というのも、すでにカホリは、波の泡(=しゃぼん玉=私たち)が集まることで(=つながることで)、消えることなく海という社会を形成し、その中で、自分以外の人の想いなどを感じ取れることを知っているからである)。
社会を生き、社会から(強制的に)影響を受け取る私たちには、そもそも純粋な「本当の自分の気持ち」などわからなくて当然なのである。曽我や山際の言うように、確かに相手のことを完全に理解するのは不可能であろう。しかし、それと同じくらい、自分のことを完全に理解するのも不可能であると言えるのだ。劇中において斉藤先生は紙飛行機を飛ばしながら、「携帯にしろネットにしろ、ただ持ってるだけ、つながってるだけってのは、コミュニケーションとは呼ばない」と言っていた。紙飛行機とは、正確にどこへ届くのかわからないものであり、まさにその性質こそがコミュニケーションの本質であろう。山際は、自分たちの使うテレパシーのことを「完全な方法」と呼び、テレパシーによって「自分だけの世界」がつながった気になっているようだが、それは幻想でしかない。劇中におけるテレパシーの役割は、ほとんど携帯電話における通話機能の延長でしかなく、一時的に不安を和らげることはできても、相手の「本当の気持ち」を理解できるようなものではないのである(ちなみに、当たり前のことだが、これはテレパシーや携帯電話それ自体を否定しているわけではない。それらはあくまで、コミュニケーションをするための手段のひとつでしかない。本作における主張とは、どのような手段であれ、コミュニケーションにおいて大切なのは、伝えようとする想いであり、その想いとは、決して完全な形では伝わらないということであろう)。
要するに山際は、過去を省みることも本当の意味で他者と向かい合うこともせず――いわば、他者とのコミュニケーション(交通すること)を放棄しているのであり――、劇中のナツキの言葉を借りれば、「戦っていない」のである(なお、エンドロールを見る限り、リョウイチたちが未来に帰った後も、山際は普通に登校できている様子である。理由はどうあれ、おそらく生徒会の中心人物として活動した経験から、ある程度の自信をつけたということではないだろうか。他者を過度に恐れる必要がないことを、身をもって学んだ成果ではないだろうか)。
中村亮介「映画と、お客さんの間にも、コミュニケーションがあるんだと思うんですよ。 同じフィルムを見ても、映画とお客さんの間には、その数だけコミュニケーションが存在していて。お客さんひとりひとりが、どういう人間なのか、 どういう人生を歩んできたかで、同じ映画から感じること、受け取ることがまったく変わってしまうんですよね」 (*4)


中村亮介「自分にとっても、かぎりなく愛おしい作品になりました。何十年かして振り返ったときに、『ねらわれた学園』を作った日々は、青春だったなと(笑)。そんなふうに振り返れる作品に、なったと思います」 (*8)
言葉をつうじての他者の思想の獲得、他者への反省、他者に従って思惟する能力、というものがあるのであって、これがわれわれ自身の思想を豊かにしてゆくのである。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
ケンジは、超能力を封印されているにも拘わらず、カホリの危機を本能的に察して、見事助け出すことに成功する(この時ケンジは、倒れたカホリを起き上がらせようとして、冒頭においてシロがやっていたように、カホリの胸に手をやってしまう。しかし、この場面では、ケンジがカホリの胸に触れる直前、ケンジをコケさせて、彼の顔を崩して描くことで、私たち観客が、「この行為は無邪気な子供が無意識的にやったことだ」と感じられるような演出がなされており、あまりケンジが、「やらしいこと」をしたという印象を持たせない工夫がされている)。おそらく中村監督自身が、「直感を何より大事にしている」 (*9) ように、ケンジにも直感が働いたのであろう(原作においてケンジの祖母にあたる楠本和美は、初めから高見沢みちるの超能力を直観的に見抜いていた。ケンジの直観能力は、和美譲りと言えるかもしれない)。あるいは、冒頭でヘッドフォンをしているにも拘わらず、ケンジにはリョウイチの心の声が聞こえていたことから、未来からやって来たリョウイチ(や砂時計のチカラ)に触発されたことによって、ケンジの封印が解かれようとしているという徴候(予兆)とも読み取ることができるだろう。
ナツキは、山際に襲われた際、思わず「助けて、ケンちゃん!」と悲鳴を上げており、やはりケンジのことを諦め切れていない様子であった。そんなナツキは、ケンジが助けたカホリを3人で家まで見送った後、ケンジからカホリにふられた際の話を訊く。そして、自分の好きな人であるケンジが、勇気を出してカホリに気持ちを伝えていたことを確認したナツキは、真っ赤な夕日の中、顔を真っ赤にしながら、自分も勇気を出して、ケンジに想いを伝えるのである(これはナツキが、「永遠のお隣さん」というポジションを捨て、「今」を生きることを選択した瞬間と言えるだろう)。まるでケンジからナツキ(そしてカホリとリョウイチ)へと、実際に言葉に出して言うことの、ポジティブな連鎖が発生しているようである。全編通してきらびやかな本作は、まさに「青春」を体現しているような作品であると言え、このナツキが「ぶっちゃける」シーンは、その最も象徴的な場面であろう(本作について中村監督は、「パンクするまでやってみようと思った仕事」 (*10) とも述べている)。

リョウイチ「未来ではね、人類はもう、地球に住んでいないんだ(…)妖精だって、人に恋することもあると思うよ」
中村亮介「京極は未来から来て帰るみたいな話の筋立てですけど、彼らが生きてるのは今という一瞬一瞬の積み重ねなんだっていうのが、この作品のメッセージでもある」(『ねらわれた学園』オーディオコメンタリー)
実存はそもそもその根本的構造からして、それ自体で不確定的なものであって、というのも、それ自体では意味をもたなかったものが意味をもつようになり、性的意味しかもたなかったものがより一般的な意味作用をもつようになり、偶然的なものが理由あるものとなる――こうしたことを可能にする操作こそがすなわち実存だからであり、実存とは事実的状況のひき受けだからである。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
恋を生きている恋する者にとっても事情はおなじであって、ここでも恋は名前をもたず、はっきり劃定でき指名できるようなひとつの物ではない。それは書物や新聞で語られているあの恋ではないのであって、それというのも、それは恋する者が己れの世界との関係をつくりだす独特な仕方だからであり、ひとつの実存的な意味作用だからである。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
リョウイチはカホリに、自分の正体や目的について語る。「1人でも多くの能力者を覚醒させる」という目的に対して、単なる中学校を支配するという明らかに非効率と思われる京極博士のやり方は、原作譲りのツッコミポイントと言えるかもしれない。とはいえ、原作にしても本作にしても、タイムスリップや超能力といった要素は、あくまでメインテーマ(ファシズムやコミュニケーション)を掘り下げるための舞台装置でしかないため、ナツキが劇中において「携帯なんて関係ない、テレパシーも関係ない」と言っているように、過度に気にする必要はないだろう(実際に中村監督も、「SF設定になるべく注目してほしくない」 (*1) と述べている)。
劇中において斉藤先生は、「演劇のおもしろさは、限られた時間、その一瞬の自分達が形になることだ」と言っていた。最終的に(砂時計のチカラによる制約された滞在時間の中で)リョウイチが「演劇を好きになった」(=意味を持つようになった)最大の要因は、リョウイチが、カホリに恋をしたことであろう。劇中においてナツキが言うように、「好きになるのに、理屈なんてない」。つまり恋とは、理屈を超えたものである。おそらくリョウイチは、ケンジやカホリといったテレパシーの通じない人たちと交流し、「勘違い」などを経験する中で、「対象」として扱えないもの、計算(画定)することができないもののおもしろさを知ったのであろう(このことは、原作の終盤において、高見沢みちる(リョウイチの母)に「ついて行くわ」と言われた京極(京極博士)の表情に、「はじめて計算の結果ではない感情の色があらわれた」ことが思い出される)。
われわれは、同じ一つの世界のなかでの意識の交流を発見することを学ばねばならないのである。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)


ケンジ「海行かね?」
耕児、おまえたちの、やりたいようにやるんだ(…)おまえたちが正しいと考えることを、やるべきなんだ(眉村卓『ねらわれた学園』)
中村亮介「世の中がすごく変わるんだけどケンジだけは変わらないと、ケンジが逆に光って見えてきたりするようなキャラクターになるといいなぁと思ってたんですよね。だから京極が来るような出来事が起こらなければ、実はナツキとケンジの関係っていうのは、線路の平行線と同じで絶対交わらなかったのが、こんなことがあったから交わる点が生まれたみたいな、そんなふうに見えたらいいなぁと思いながらやってたんです」(『ねらわれた学園』オーディオコメンタリー)
中村亮介「いちおう段取りを追って説明しますと、子供の頃に糸電話で遊んでいたら、ケンジがベランダから落ちて、そのケガが元で死んでしまったと。死ぬっていうのはある意味メタファーでもあって、以心伝心で成立していた子供同士のコミュニケーションが、以後成立しなくなるという。別の言い方をすると、糸電話の糸が切れてしまうわけですね。で、ナツキが時間を跳んでケンジを救って、ナツキは運動神経がいいから脚を折るケガですんだという話は、夢の中のケンジが語った通りです」 (*1)
原作において耕児(ケンジの祖父)の父が、超能力を持つ高見沢みちる(リョウイチの母)に立ち向かおうとする耕児に向かって、「やりたいようにやるんだ」と言っていたように、本作では耕児が、ケンジのやりたいようにやらせるのである(「チカラをどう使うか決めるのはわしじゃない、君でもない」)。シロの首輪が外され、封印されていたチカラを取り戻したケンジは、ついにリョウイチとの最終決戦かと思われた場面で、「海に行く」ことを提案する。最後までリョウイチは、ケンジのペースに飲まれてしまうのである。また、このとき、ケンジはチカラだけでなく、実は過去に死んでいた自分を、ナツキが自身のチカラと引き替えに助けてくれていたことも思い出す(ナツキはチカラを失ったせいで、記憶が錯綜しているようだ)。本作の冒頭部において、遺影を思わせるフレームの中にいるケンジを、ナツキが蹴ることでフレームの外へと追い出すシーンが描かれていたのだが、もしかしたらそのシーンでは、そうした過去の出来事を暗示していたのかもしれないだろう(あるいは、ケンジが「枠を飛び越えるような人物」であることを暗示していたとも考えられる)。
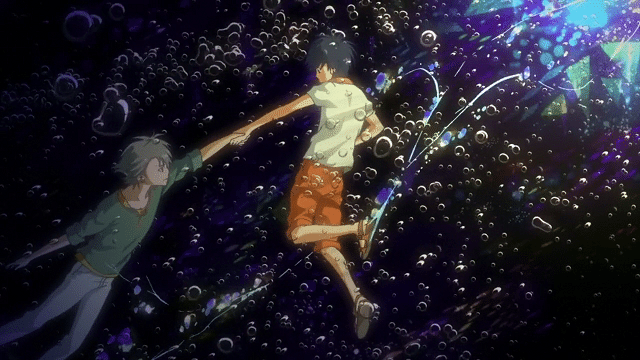

ケンジ「俺とお前は確かに心はつながってない。でも、手をつなぐことはできる。それじゃダメか? 手をつなげばあったかい。お前の熱が伝わってくる。それじゃダメなのか?」
中村亮介「一回だけでは確かに、テレパシーでもないかぎり、この映画の何もかもは伝わらないのかもしれません。そういう批判は受けるだろうと思います。でも、僕ら作り手の「熱」は、お客さんに伝わったはずだと。それを目指した映画なんだと、僕自身は思っています」 (*3)
私の身体は、世界に対して身を閉ざすことができるからこそまた同時に、世界へと私を開き、そこに私を情況づける当のものでもあるのだ。(…)思い出とか声とかが蘇ってくるのは、身体がまたあらためて他者なり過去なりへと己れを開くとき、身体が共存によって貫かれるとき、身体が(能動的な意味で)またあらためて己れ自身を超えて意味作用をおこなうときである。(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)
もし私が他人の手を握りながら、その人がそこにいることについての明証性をもつとすれば、それは、その人の手が私の手と入れ替わるからであり、私の身体が、逆説的にも私の身体にその座があるような「一種の反省」のなかで、他人の身体を併合するからである。私の二本の手が〔フッサールの言葉でいえば〕「ともに現前し」、「ともに存在し」ているのは、それらがただひとつの身体の手だからである。他人はこの共現前の延長によってあらわれ、他人と私は、いわばただひとつの間身体性の諸器官なのである。(メルロ=ポンティ『シーニュ』)
われわれは、あくまでも自然的人間のままで、われわれの内に身を置くとともに物の内に身を置き、われわれの内に身を置くとともに他者の内に身を置いているのであり、その地点では、われわれは、一種の交叉によって他者になり、また世界になるのである。(メルロ=ポンティ『見えるものと見えないもの』)
音楽には一つの「過去」があるのだ。その過去の灰をかき立てることが大切だろう。灰のなかにはまだ残り火が、ちろちろ燃えている。われわれの「現代」は、こんなに明るく輝いているが、その明るさには、いつでもあの残り火の光が、少しはまじっているだろう。(ドビュッシー『音楽のために』)
地球に滞在できるタイムリミットが近づいていたリョウイチは、「生と死を連想させる(…)夕方、それも日没寸前に」 (*11) 、自身が世界に存在できなくなることも覚悟の上で、砂時計に残されたチカラを解放する。しかし、リョウイチもすでにケンジと戦うつもりはなかったようである。おそらくリョウイチがチカラを解放したのは、自らの存在を消すことによって、母が元の時代へ帰れる可能性を生み出すためであったのだろう。チカラを取り戻したケンジはすべてを見抜いていたようであり、耕児や過去のナツキたちのチカラも借りながら、リョウイチを救い出し、「いないはずの人間なんていないんだ。いてほしいと想う誰かがいるから、まだこうしているんじゃないか?」と言う。ここでの、リョウイチに「いてほしいと想う誰か」とは、おそらくケンジ自身のことというよりは、リョウイチの母(高見沢みちる)のことを指していると思われ、ケンジは、リョウイチの母が本当に望んでいるのは、リョウイチに世界に存在して生きてもらうことではないのか、と言いたいのではないだろうか(このことは、海でカホリが死んだ父を感じていたことを想起させる。劇中においてケンジと「過去」のナツキが手をつないでいることが象徴するように、私たちは、「過去」とつながって生きていると言える。昼間に見えない月のように、目には見えなくとも、確かにそこに(ここに)「過去」は実在していると言えるだろう)。
また、この時ケンジとリョウイチは、手をつないでいる(原作においてクラスメートたちが一致団結して腕組みをすることで、高見沢みちるの超能力に押し勝ったことが思い出される)。メルロ=ポンティによれば、自己の右手と左手が同じひとつの身体であるように、接触する自己と他者の身体は、同じひとつの間身体性の器官なのだという。間身体性とは、自他未分の共同的な身体性のことであり、私たちは、この根源的領野を通じることで、実際にこの現実世界において、他者や世界と出会うのだとされる(完全に自己だけの身体でもなければ、完全に他者の身体でもないという意味では、神野が言っていた「空気」に近いものと言えるかもしれない)。つまりリョウイチは、ケンジと触れることで、間接的にリョウイチの母の気持ちとつながることができ、再び世界とつながることができたと言えるのである。そしてケンジは、リョウイチを世界に存続させるため、リョウイチを元いた時代へと連れて行く。これにより、現代の人たちからケンジとリョウイチが現代にいたという記憶が(少なくとも表面的には)消されることになる(もっとも、リョウイチは妖精・パックではない。彼が未来に帰り魔法が解けても、「好きだった気持ち」は残るだろう)。そのため、エンドロールに映る写真に2人の姿はないのである(なお、ケンジとリョウイチが消えた瞬間、切れていたはずの紙コップがつながった状態で出現するのは、まだケンジが現代とのつながりを保持していることの証であり、ケンジとナツキの2人が、両想いになったことの暗示だと思われる)。
中村監督は、「エンドロール後にケンジが帰ってくるところで、一緒についてきたのはお父さんじゃなくて京極本人なんです。デザインが違うのと、カホリとカットバックすることで、観た人にそう伝わっていればいいですね。時間移動を制限したから、京極はもうカホリの時代には生身で来られない。そのことで生まれた、切ない別れのドラマのつもりです」 (*3) と語っている。ここで最も興味深いのは、カホリであろう。というのも、カホリはこれまで一貫して、不可能性を受け入れた現実的なキャラクターとして描かれていたからだ。エンドロール後、ケンジとリョウイチ(使い魔)が現代へ戻って来たことで、カホリにも、彼らがこの時代にいたという記憶を思い出す可能性が生まれたことになる。では果たしてカホリは、もう身体と共に現代へは来れないリョウイチへの想いを、いつまで変えられずに抱いていられるだろうか。現実的に考え、どこかの段階でリョウイチとの別れを受け入れ、リョウイチとは別の新しい恋を始めるのだろうか。それとも、絶対的に不可能と思われるリョウイチとの恋の成就を、すなわち、文字通り「超越する」(能力者になる?)ことを目指すのだろうか。ケンジが「ただいま」と言った先の展開(出来事)は、計算不可能であり、誰にもわからない。だからこんなふうに、彼らの未来を想像してみるのも、おもしろいだろう。

*1 http://animestyle.jp/2012/12/07/3293/
*2 https://www.nhk.or.jp/lalala/archive140412.html
*3 http://animestyle.jp/2012/12/11/3322/
*4 https://www.neragaku.com/special03.html
*5 https://www.excite.co.jp/news/article/E1352824070412/?p=4
*6 https://www.neragaku.com/special05.html
*7 https://dengekionline.com/elem/000/000/116/116209/
*8 http://animestyle.jp/2012/12/18/3361/
*9 http://ryousuke1976.blog123.fc2.com/blog-entry-26.html
*10 https://akiba-souken.com/article/28501/?page=3
*11 http://ryousuke1976.blog123.fc2.com/blog-entry-25.html
大事なのは、みずからの命を「活動させる」ことなのであり、それこそがより深い生き方なのである。(メルロ=ポンティ『行動の構造』)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
