
20230717 桜ヶ丘、川平、中山(仙台市) #風景誤読
0.Intro:鳥滝川の謎について
2022年7月4日にみたらしと二人で桜ヶ丘を歩いたとき、「桜ヶ丘三丁目沈砂池」という謎の構造物(位置)を見つけた。


「桜ヶ丘三丁目2号沈砂池/桜ヶ丘三丁目3号沈砂池」と施設名表記があるが、
1号沈砂池は見当たらない。
沈砂池などという言葉は聞いたことがなかった。あとで軽く調べてみると「下水に混ざる砂を沈殿させておく施設」ということだったが、私の見る限り池の水は枯れていて、それはもう雑草の生い茂った石の壁にしか見えなかった。そして、そんな訳の分からないおおきな構造物が住宅地のなかに突如として現れる、その「見えてくる」瞬間が面白かった。さらに言えば、散歩者にとってはこんな小気味の良い違和感が、おそらく桜ヶ丘の生活者たちにとっては一切気に留めるようなことではなく、いつも簡単に通り過ぎているに違いないことが爽快でもあった。
地図やネットで簡単に調べてみるとこの沈砂池は、水の森公園にある三共堤(別名:丸田沢東堤、丸田沢東沢堤、三居沢堤)に繋がる水路の途中に設置されていることが分かった。

(Googleマップ)
水の森公園には丸田沢堤・三共堤というおおきな2つの農業用ため池があり、Wikipediaによればどちらも江戸時代に七北田川水系の高柳川・鳥滝川をそれぞれ堰き止めてつくられたという。
旺文社ハンディマップルで現在の水の森公園周辺を見てみると、丸田沢堤に流れ込む水路には確かに高柳川という名前がはっきりと記されているが、三共堤に繋がるもうひとつの水路にはどこにも名前が記されていない。また、仙台市のHPにおいても二級河川として高柳川が記載されているが、鳥滝川の記載はない。果たして、ほんとうに鳥滝川という川は存在するのか。Wikipediaの記述にはなにか根拠があるのだろうか。
(因みに、平成19年の国土交通省河川データにおいても、高柳川は存在するが鳥滝川は存在しないようだ。→参考ページ)

(『ハンディマップル:でっか字仙台詳細便利地図』2022年5月)

(『ハンディマップル:でっか字仙台詳細便利地図』2022年5月)
三共堤に接続している水路は鳥滝川では無いのだろうか。気になるので地図上でこの水路を追ってみる。

(Googleマップ)
三共堤を出発後、桜が丘三丁目を南に流れ、水の森三丁目の交差点に差し掛かるところで水路が途切れる。しかし、そのまま南西に地図を辿ってみると、

(Googleマップ)
桜が丘団地入口のバス停付近から川平一丁目の住宅地をふたたび水路が走っているのを見つけた。やはり河川名の表記はない。この水路もローソン川平一丁目店の手前あたりで途切れている。
この二つの水路に関係性はあるのか。しばらく地図上を彷徨っていると、川平水路の北西に「いかにもな」ものを見つけてしまった。

(Googleマップ)
中山鳥瀧神社(鳥瀧不動尊)。それまで地図上にまったく現れなかった「鳥瀧」の文字が現れた。相変わらず鳥滝川についての情報はネット上では皆無だが、鳥瀧神社についてはGoogleにレビューがあるし、参拝客によるブログなども見つかった。その名の通り、神社のなかに滝があるらしい。
文献を調べたところ、『荒巻地区平成風土記』(いきいき青葉区推進協議会、平成23年)と『川平地区平成風土記』(同上)において次のような記述を見つけた。
中山丘陵の東北面に深く切り込んだ谷間に古くから滝が流れ落ち、行者たちが滝水に打たれて修行していた。…この滝から渓流となって鳥滝川が流れ出し、小魚や沢ガニがたくさんいた。近隣の子供たちの遊び場であったが、マムシも多かったという。
開発以前の川平を流れる丸田沢川も鳥滝川も、決して穏やかではなかった。とりわけ鳥滝川は、鳥滝不動尊から流れ落ちる水で、滝道の言葉通り激しく流れた。
どうやら、鳥滝川という河川(名)が存在していたこと、中山鳥瀧不動尊において流れる滝水がその源流であることは確かなようだ。

(Googleマップ)
位置関係を整理すると、やはり途中にあった川平一丁目の水路が無関係とは思えない。鳥瀧不動尊から流れ出た水が地下に潜りつつ中山を下り、川平一丁目で開渠となって住宅地を流れたあと、再び暗渠となるが水の森三丁目交差点付近ですぐにまた顔を出し、そのまま桜ヶ丘を走って三共堤に流れ着いているのではないか、と推測した。つまり、ところどころ暗渠化してはいるが、この水路こそが鳥滝川なのではないか。
以上のことを、みたらしに説明した。彼は中山方面に住んでいるが、中山鳥瀧不動尊の存在は知らず、鳥滝川など聞いたことも無いようで、「中山にそんなものが…?」と面白がってくれた。
鳥滝川は、私が唐突に見つけたものではない。ちょうど一年前、二人で桜ヶ丘を歩いて発見した沈砂池に端を発している。「鳥瀧不動尊に在る滝を見てみたい」「川平一丁目の水路を実際に歩いて辿ってみたい」と希望を伝えると、二つ返事で「行こう」と言ってくれた。
1.のこされた「中山」:中山鳥瀧不動尊
イオン仙台中山店で待ち合わせ、まずは中山を八丁目、七丁目、六丁目…と下りながら鳥瀧不動尊を目指す。目指す、とは言え最終的な「目的地」を設定しているのではなく、ぜひとも行きたい「チェックポイント(経由地)」を設定しているに過ぎない。経由地という意識は「寄り道」へのハードルを下げてくれるので、この違いは大きい。

住宅団地に佇む、この近辺の常連しか来ないであろう「まちの理容室」。
「モードサロン」ということばの響きがなんとも古いが、鉛筆を模したサインポールがカッコいい
みたらしが中山に居る猫のはなしをする。夜散歩に出かけると猫に会う。あとをつけることもある。去勢された猫。塀のうえにいる猫。「この家とか、よく居るんだよ」と教えてくれる。二人して、なんとなく猫を探しながら歩いている。



住宅街なのでおなじような景色がつづくうえ、坂道ばかりで平たい場所が無い。みたらしが居なかったらあっという間に遭難しそうだ。

どうやら鳥瀧不動尊は中山商店街の通りに近いらしい。地図はなるべく見ないで、みたらしの勘に従って歩く。下り坂の末端、突き当たったところにテントとベンチがあり、なんだろう、あれが鳥瀧不動尊なんじゃないか、とわくわくしながら進んでいく。

仕方なく地図を開く。鳥瀧不動尊は目の前にあるはずだが、入口が見当たらない。うろうろしていたら中山不動公園という公園にたどり着いたので入ってみる。



公園を出てぐるっと回るとようやく鳥居が見えてきた。ここが中山鳥瀧神社らしい。


よく見ると白地の書き込みもあり、複層的すぎてもはや何を伝えようとしているのかが分からない。グリッチアートっぽい

木々に覆われて薄暗い境内に入れば、鳥の鳴き声と時折通過する車の音しか聞こえない。開発され、住宅が立ち並ぶなかに、なにも主張せず、ただ延々と「残っている」。その感覚は沿革を一読するとさらに強くなった。

約1200年前からここに鎮座し、藩祖政宗公に「鳥滝不動尊」と名をもらい、幾度も水害に遭いながらも残っているという。政宗の「金色の鳥」の伝説も面白いが、それよりも「天平の初期淳仁天皇の御代中山仙人が在住した」「又地方人は地名中山を冠し中山鳥滝不動尊と称するに至った」という記述はさらに興味深い。菊地勝之助著『仙台地名考』に中山という地名の由来は中山鳥滝不動堂であると書かれているが(昭和32年、えんじゅ書房版、114頁)、この沿革に従えば「中山鳥滝不動尊」と名がつく前から此処の地名は中山だったことになる。中山仙人とは何者?中山に居たから中山仙人?(ということは中山という名前はもっと古いのか?)疑問は尽きないが、少なくともこの辺りはずっと(政宗公が猪狩りをするような)山であり、宅地化されてひとが住むようになったのはごく最近のことであること、つまり、この鳥滝不動尊はむしろ自然そのものであった本来的な中山を象徴するような場所として残り続けていることが、ここを訪れることで体感的に理解された。
ところで、「社殿は明治初期の水害で流失した」「数次に及ぶ水害に遭った」という記述を読むと、豪雨や台風で鳥滝川が氾濫したりしたのだろうか、などと想像してしまう。文献にもあったが、当時の鳥滝川は水量が豊かでもっと激しかったのだろう。
参道の奥には三つの建物があり、一番ひだりの不動堂の脇に、滝つぼへと降りていく階段がある。ちいさく滝水が流れ落ちる音が響いている。水は透き通っていて、青い魚が何匹も泳いでいるのが見える。

いまのこの水量ではどんなに頑張っても氾濫などしないだろう
これで水源の姿は確かめることができた。神社を出て、鳥滝川と思われる水路を探していく。
2.のこされた「鳥滝川」を辿って


奥に県営桜ヶ丘住宅と給水塔が見える
川平一丁目に入り、NTTの社宅とローソンを横目に歩いていくと住宅街のど真ん中にいきなりちいさな橋が現れた(位置)。どうやらここから川平水路がはじまっているらしい。

無名。表示が全くない

東(桜ヶ丘・水の森方面)に向かって住宅の隙間を縫うように流れている

この水路が鳥瀧不動尊からはじまる鳥滝川ではないかと思われる
水路をみた瞬間、二人のテンションが異様に高まり、蛇行する水を心なしか早足で追い始める。もちろん、堰き止めてため池を作れるような川には到底見えないのだが、でもこれはちゃんと川だ。鳥瀧不動尊のちょろちょろとした滝を見たときの「これがほんとうに川に…?」という不安が払拭された。そして、いつの間にか、私よりみたらしの方が熱心に川を辿っている。


少しでも川が見えそうなポイントを見つけると、私よりも先にみたらしが歩み寄っている


水路はファミリーマートの裏側などを通って、パインリバーというアパート(位置)のあたりでまた暗渠になる。どこにも川や橋の表示がなく、立て看板もなく、完全に忘れられているような水路だが、ここにきてようやく「リバー」ということばが出てきた。やっぱり川なんだ。一応川という意識があるんだ…。


この川はこのあと桜ヶ丘三丁目方面に流れ、水の森公園内の三共堤にたどり着く。しかし、いったい川平や桜ヶ丘、中山に住むひとのどれくらいが、この川の名前や水源、到着地を知っているのだろうか。町内会で清掃をしたり、子どもたちが川遊びをしたりするのだろうか。見てきた限り、触れられるくらい川水に近づくことのできる場所がそもそも皆無だったが…。
それでも水が流れている。川面が光っていて、水音が鳴り響く。橋だってある。日常のすぐそばにある水路が、あるのにないような、隠されていないのに隠れているような、不思議な感じがするのだった。
3.Outro:滝道をとおって

「東映北隣」とあるので2005年(東映閉館)以前のものか

(散歩でペタグーグミ、食いがち→前回)

中山方面へと引き返している。さっきは水路を追いながら川平一丁目を歩いてきたが、今度はどこに続いているかわからない階段をのぼってまったく知らない住宅地へと入っていく。

住所表示の青いプレートに「滝道」と書いてある。この滝は鳥瀧不動尊のことを指しているのではないか。滝水の走る道ということか。あとで住居表示実施前の旧地名を調べたら、昭和52年以前は「荒巻字滝道山」と呼ばれていたらしい。

二人ともとてもお腹が空いていたので、よく水澤先輩と食べに行く「中華レストランとらの子」(中山商店街)で夕食をとる。みたらしは初めて来るということなので、バジル担々を熱烈に勧めておく。私はチャーハンを頼む。
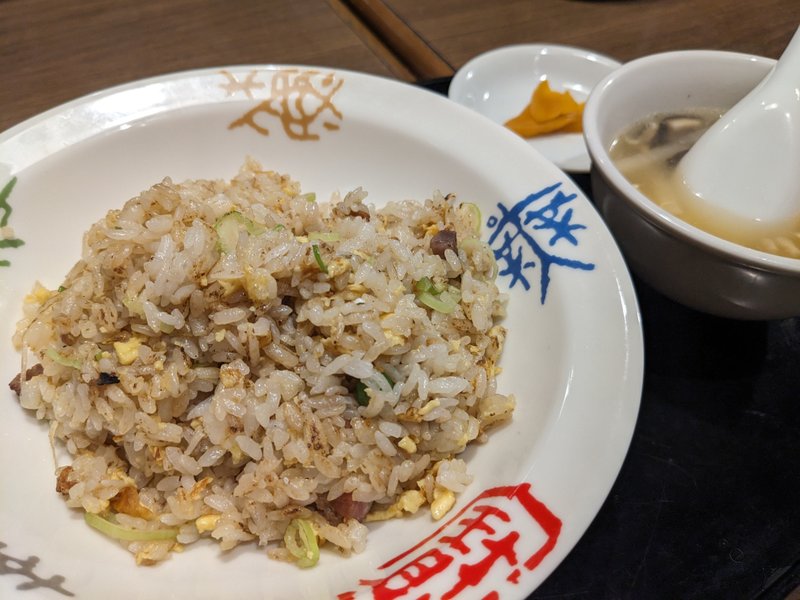

みたらしが「このあたりにハンバーガー屋があったはず」と言って中山七丁目に入っていく。もうかなり遅い時間だが、このあたりは街がとにかく新しく、街灯が多いので明るい。
*
鳥滝川について、実際に歩くことで分かったことも多かったが、まだまだ分からないことが多い。
そもそも、本当にこれが鳥滝川なのか。なぜ地図やネット等に名前が無いのか。いまはどのように扱われているのか。誰が管理しているのか。滝つぼの水に比べて川平一丁目水路の水量は多いが、ほかの地下水等と合流しているからか。このように一部暗渠になったのはいつなのか。古地図等に載っているのか。むかしの生活のなかではどのように捉えられていたのか。鳥滝川や三共堤の利水の現状はどうなっているのか。等々。
最終的には河川課や鳥瀧不動尊の管理者などに問い合わせてみてはなしを聞いてみる必要があるだろうが、そのまえに、建築系の仕事をしている水澤先輩や土木系の仕事をしているちだたくさんと一緒に歩いてみたい。風景誤読的には「調べる」ということは副次的なことで、まずは誰かと「歩く」、歩きなおしていくことがその核心である。
この日、中山で生活をしているみたらしと喋りながら歩くことで感じることのできた風景があった。次は別の関心や知識をもったひとと歩くことで違う風景を読み、感じたい。
[たかしな]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
