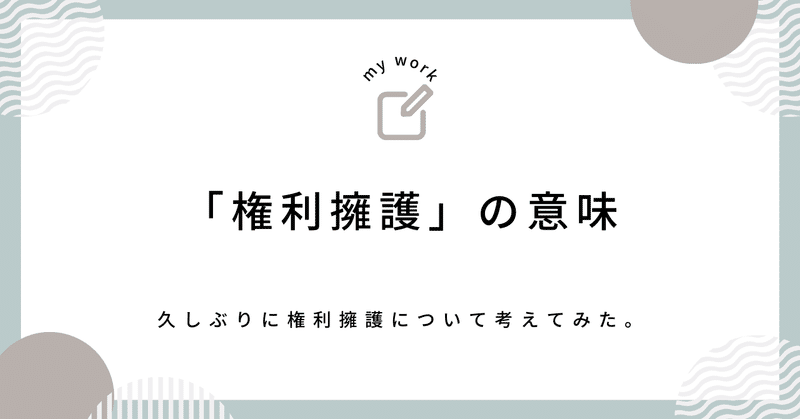
「権利擁護」の意味(前半)
機種変のおかげで高い本をがんばって買った話
現在の部署に異動してからというもの、権利擁護という単語に正面からぶつかることが少なくなっていたのですが、ちょっと野暮用でまた関わりそうな気配になってきました。実務から離れると、とたんに自信がなくなってきたもので、さんざん悩みながら買ってしまいました。
たっ、高い。高すぎる。大人のお年玉価格ではないか。。サラリーマンは、書籍を購入しても経費にできないんだぞ…
一度は購入を諦め、どこかの大規模図書館にでも入荷されないかなーと待つヘタレでしたが、目次を見ているとどうしても欲しい本だったので、ちょうどiPhoneを機種変したときに旧機種を下取りに出したところ、まとまったPayPayポイントが返ってきたのでそれでやってしまいました。あぶく銭、サイコー。
本書は、従来金銭・現物・サービスなどの「給付」を中心に提供されてきた社会保障制度において、2000年の社会福祉基礎構造改革による「措置から契約へ」の構造的転換の中で、高齢(介護保険)、障害、生活困窮の分野でぼちぼち現れてきた「相談支援」という概念について、法的に整理を試みようという、お値段にふさわしい難しい本です。
ただ、(一応)法律家として福祉・保健実践の場に身を置く私が、道中社会福祉士の資格を取りながらいろいろと相談支援を勉強してきた中で、法律学から記述をこころみたものはおそらく令和に入るか入らんかくらいのころからでてきたばかりです。なので、資格取得の際に読み漁った教科書と同じトピックを扱っているものの、法律学がソーシャルワークをどうとらえるのか、(一応)法律家としては興味のあるところです。
変容する「権利擁護」
本書は、「相談支援」という単語をテーマに、社会保障法や憲法、民法の学者がそれぞれ論考を寄せている中、特に権利擁護支援の意義について上山泰先生(民法/新潟大学)のお話が興味深いところでした。
さて、権利擁護という単語ほど、見る人によって意味の違う単語はないと思います。それでいて、福祉や相談支援にとって非常に重要なキーワードなので始末におえません。
大多数の福祉関係者は、「権利擁護≒成年後見制度」という見方をしますよね。私が受験した社会福祉士国家試験(2020年受験)も、「権利擁護といえば成年後見制度(一部虐待行為の経済的搾取)」というカリキュラムになっていました。
ところが、2022年3月25日に公表された第二期成年後見制度利用促進基本計画によると、このイメージがだいぶ方向転換しています。
…長いですね。難しいですね。参考程度にしておきましょう。
これによると、「権利擁護支援」(権利擁護、ではないんですよね)の語に、公的文書として初めてしっかりとした定義が書かれています。
権利擁護支援とは、地域共生社会の実現を目指す包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通基盤であり、意思決定支援等による権利行使の支援や、虐待対応や財産上の不当取引への対応における権利侵害からの回復支援を主要な手段として、支援を必要とする人が地域社会に参加し、ともに自立した生活を送るという目的を実現するための支援活動である。
なんだかよくわからんが、少なくとも成年後見制度の利用のみをさしているわけではなさそう、ということが伝わってきます。「徒然草」とか「枕草子」みたいに、言いたいことを全部1文で言おうとするからこんなことになるんですよ。
言わんとしていることは、
本人中心支援を基調とした地域共生社会の実現を目指す包括的支援体制の共通基盤である。
要支援者が地域社会に参加することや、ともに自立した生活を送ることを目的としている。
その目的実現のため、「権利行使支援」と「権利侵害からの回復支援」という2つの手段がある。
と、いうことがわかります。
医学的に判断能力が低下ないし喪失している人の場合、成年後見制度を利用すれば、権利行使支援も権利侵害からの回復支援も一体的に行えそうなので、成年後見制度がここに含まれることは間違いありません。しかし、この定義では、「判断能力の低下があること」という条件設定はされていないので、対象は「支援を必要とする人」すべて、ということになります。
すっげぇ広がってんの!!
「第二期基本計画」があるということは、第一期基本計画もあったわけです。で、自治体や福祉関係者はみな、第一期基本計画に沿って、必死のパッチで地域の後見ニーズを拾うべく、「中核機関」という、いわば成年後見制度利用のセンター機能を持つ機関を作ろう、作らせようとしてきたわけですよ。そして後見人の担い手もさっぱり足りないから、法人後見だ、市民後見だと担い手も育成してきたんですよ。これらはすべて、成年後見制度のため。
なのに、急に「ごめん、権利擁護って、もっともっと広かってん」とか言われて、成年後見業界はどうしたらいいのでしょう。本州から北海道へ開拓団が渡っていって、函館あたりを開墾し、ようやく米が作付けできそうな気配が出てきたところへ、「あ、ごめん、北海道全部開墾せなあかんねん」と言われたようなものです。
私、権利擁護行政(という言い方は聞いたことがありませんが)から離れているから悠長なことを言ってられますが、これ、第一期計画に基づいて権利擁護ネットワークを作り上げたところは、これからどうするのでしょう。と、若干心配になります。
でも、実務担当者は大変だと思いますが、私見では、これでようやく「権利擁護」本来の姿に近づいているようで、それについては良かったと思っています。
【全部書いたら非常に長かったので、前半はここまで】
後半に続く・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
