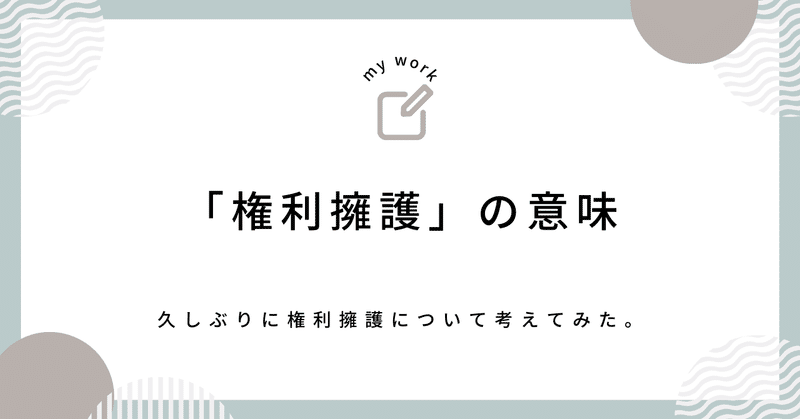
「権利擁護」の意味(後半)
権利擁護について久しぶりに考えてみた話の後半です。
前半は、こちら。
権利擁護の本来の意味
「権利擁護」ってそもそも英語のAdvocacy(アドボカシー)の訳です。そして、アドボカシーが何かというと、「本人の身上面に関する利益の主張を補助し、又は本人の身上面に関する利益を代弁すること」だと言われています。実は私は、「権利擁護」の単語よりも「アドボカシー」の単語の方に先に触れていた珍しい弁護士なのです(司法修習中にお世話になった先生の事務所名に「アドボカシー」とあり、「これ、なぁに」と聞いたのが最初だった)。最初にアドボカシーの説明を聞いた時、私は「あ、それって『人権保障』って言うと口幅ったいから『権利擁護』って言ってるんですね」と我流で解釈し、以来、私の中では、権利擁護はほぼ「人権保障」に脳内変換されています。これはこれで行きすぎた面もありますが、正直、「権利擁護=成年後見」という解釈よりは正鵠を射ていると思っています。
本稿によると、社会保障法の学説上、権利擁護の定義は広狭3つくらいに分けられるようです。これまでの第一期基本計画に基づく権利擁護行政は、「1」の【狭義】の権利擁護を念頭に置いていたんですね。本稿もそう言ってます。
判断能力が不十分な人々に対して憲法的要請から自己決定権を保障すること。【狭義】
判断能力の有無にかかわらず、立場性の違い(要支援者が支援者に対して非常に弱い立場にあること)から自己決定権を阻害されている場合に、自己決定の実現を法令上保障すること。【広義】
国民が有している諸権利について、事後的救済を含んで広くその実現に向けて努力すること。【最広義】
私のイメージは、3だと広すぎて逆に何を言っているのかよくわからないので、2が一番近い気がします。
大事なのは、「判断能力の有無にかかわらない」という点、そして「自己決定権を保障する」という二点です。
1つめの、「判断能力の有無にかかわらない」という点について。一般論として、自ら合理的な判断が可能な人は、権利侵害からの救済が必要と自ら判断し、救済に向けて動くことができます。このため、放っておいても自ら必要と思えば権利救済に向けて行動することができます。
ところが、この世の中、みんながみんなしっかり合理的な判断ができるわけではありません。認知症のような病気や、高次脳機能障害のような障害により、合理・不合理問わず判断そのものができなかったりすることもあります。それだけではなく、人は、医学的にまったく疾患性がなくとも、状況や環境的要因によっても一時的に合理的な判断が難しくなります。生活苦にあえぐシングルマザー、社会的養護のもとで育ったものの、成人と同時に社会へほうり出されてどうしたらいいかわからない人、リストラされた人、契約更新してもらえなかった契約社員、がんになった、予期せぬ妊娠をした、流産をした、ずっと介護していた親が亡くなったなどなど、前後不覚になるほどのショックな出来事の前に、人はどこまで合理的な判断ができるか。
そんなとき、信頼できる家族なり友人なりがそばにいてくれればいいですが、そういう人がいない場合、人の生活は何の病気も障害もないのに狂っていきます。ここを支援することが、アドボカシーであり、権利擁護支援ということだと思っています。
2つめの「自己決定権を保障する」ということについて。アドボカシーは、本人意思の代弁と訳されているところ、代弁するには本人意思の探求が先に来なければなりません。
現在、私は、精神疾患のある人や、自殺未遂をするほどに精神的に追い詰められてしまった人の支援をしていますが、特に後者については、「これと、これと、これをしたら大丈夫!」と状況整理をしても、ご本人の気持ちが追いつきません。本人の心の準備が整わないのに、やれ生活保護やろう、債務整理やろう、病院に行こうと調整しても絶対にうまくいきません。支援者としてはまことに歯がゆい思いをするのですが、ここはこれ以上生活状況が悪くならないよう現状維持に努めつつ、本人の気持ちが追いつくのを「待つ」しかありません。
このように、代弁すればいいってもんではなく、「本人が自分の意思を伝えることにできるようにする支援活動」こそが、権利擁護の本来の姿になろうと思います。ここですぐ「代弁」することが権利擁護と思われていたような気もしますが、ここはぐっとこらえて、本人が伝えられるようなエンパワメントに回らないといけないんですね。面倒くさいですけどね!
この点は、本稿の中で、佐藤彰一先生(国学院大/弁護士)の見解としても紹介されています。すなわち、本人自身による権利・利益の主張が、セルフアドボカシーという意味での「権利擁護」であり、このための環境整備や本人の意向の徹底的な追及等によってこれを他者が支援すること(セルフアドボカシー支援)が「権利擁護支援」にあたると。そういう整理ならなんとなくわかる気がします。第二期基本計画が、そういう趣旨で使い分けているのかどうかは、知らんけど。
権利擁護支援における法と福祉・保健の連携
この、本人が意思を伝えられるようになるように「待っている状態」、つまり権利擁護支援の主戦場は、だれかから攻撃されて権利侵害を受けている、とまでは言えないけれど、権利利益が実現されていて満たされている、とも言えない状態です。この場面こそ、法律だけでも、福祉・保健における支援だけでも満たされない、法と福祉・保険の連携が求められる場面だなぁと常々思っています。
たとえば、急に長年連れ添った配偶者が出ていって、その数週間後に離婚調停の申立書が届いた、とか。まぁこの人にもなにか配偶者が出ていく原因があったのでしょう。でも、今、この瞬間、この人にとって精神的には決して健康的な場面ではなく、人によっては自殺を企図するほど凹みます。この段階って、「違法ではないが、正当でもない」状態なので、法律を駆使してズバッと幸せになれるわけではない。
精神保健、自殺対策の対人援助は、ほぼほぼこの段階の人の支援になります。そうすると、弁護士は、ここで「待つ」支援が極めて苦手なので、つなぐのにまだ熟していないということになります。他方、福祉・保険の支援者にとっては、「いやいや、離婚を求められているなら法律事務所でしょ」と思います。あたりまえです。ところが、法律事務所でやることと言えば、
「あなたも離婚したいのか」
「相手が出ていくまでに何があったのか」
「子どもをどうするのか」
「相手に子どもを会わせたいのか、会わせたくないのか」
などなど、ストレスフルもいいところです。もし本気で出ていった配偶者とガチンコで争うのであれば、メンタルヘルス環境を相当調整しなければ耐えられません。そこを、法律家は「元気になったらどういうことができるのか」を支援者と共有すること、支援者は法律家から共有された見通しを参考に、メンタルヘルスの面からフォローしていただけるとありがたいのです。
このように、「権利擁護の対象となる行為は、事実行為と法律行為からなる一連のプロセス」なんですよねぇ。だから、法と、福祉・保健、どちらも必要になるんだろうと思います。
むっずかしいですねー。
・・・ていう似たような話をどっかでしたことあるぞ、と思って自著を読み返してみたら、「あとがき」で思いっきり同じ話をしていました。つまり、私のような俗物が考えるようなことは、すでに学術の世界で議論されているということで、調べもせずに大きな顔して権利擁護を語ったことを、今さらながら恥ずかしく思うのでした。もっと勉強してから書けばよかった。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
