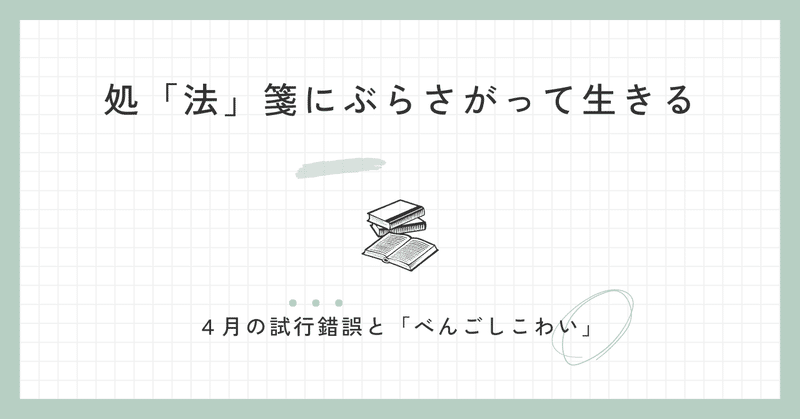
処「法」箋にぶらさがって生きる
生きています
退職して1か月たちました。
なんとか生きています。
体調は、悪いです。環境の変化に弱い疾患ですから。主治医も心配して、受診間隔を狭くしてくれるくらいです。通勤ははるかに楽になりましたし、朝もまるまる1時間遅くなったし、身体にかかる負荷は落ちているはずなのに、1か月ずーっと消化器の調子が悪いです。副腎がつかれているとこうなるので、GWに整えなければ。
「私」の有効活用
前回、退職のごあいさつでも書いた通り、在野に戻ると決めた理由のひとつが、「相談支援の処「法」箋」が好評だったことです。
なので、当面の間はこいつに思いっきりぶらさがって生きていかざるをえません。もう2年前の本ですが、今から全力でしがみつきます。ありがとう、過去の私。
私自身は、多数の案件を受けきる体力がありません。私一人が直接受任して役に立てるのは、せいぜい、瞬間最大風速的に20~30名程度が関の山です。しかも、誰の目から見ても「これは弁護士へ依頼しなきゃ」と相当煮詰まった案件にしか接触できません。
これじゃ、市役所へ入る前と一緒。そして大変効率が悪い。
それよりも、支援者支援の方法を取って、支援者の何気ない相談に助言し、明確に法律事項になる前に対処する方が、私一人で役に立てる人数が全然違うし、切羽詰まる前に解決するので本人にとってもいいだろう。
そう、私がやりたいのは、「支援者支援×ときどき本人支援」です。
これをやろうとすると、市役所で勤めるのが一番都合がいいのですが、当然のことながら任用された市でしかできません。
なんとか在野でもこれと同じことができないかということで、現在絶賛試行錯誤中です。
処「法」箋研修
その最たるものが、「相談支援の処「法」箋」を使った研修、略して「処「法」箋研修」です。
最初に、昨年2月に県外の社会福祉協議会からご依頼をいただいてやったものを皮切りに、何回か福祉系の団体から呼ばれました。
先日、5月1日には、弁護士とソーシャルワーカーの協働を考える会にお声かけいただき、オンラインイベントで2時間半もしゃべってしまいました…
2時間半のうち、「出回っても大丈夫そうな冒頭1時間」はアーカイブで見られるようです。出回ったらヤバいやつは、非公開でこっそりやりました。ええ。
このイベント、申込者120名越えの恐ろしいイベントでした。
期待する内容について一言書いていただいている方もいたのですが、
にも包括(精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築)
重層的支援体制整備事業
リーガルソーシャルワーク
児童福祉との連携
事例検討会的なこと
法と福祉の連携
などなど、全部応えようとすると大変なことになるぜ、という期待の大きさを感じる反響でした。あと、申込者の属性が非常に多様で、福祉職の中でも精神保健系、病院勤務系、障害福祉系、高齢者系、いろいろおられましたし、弁護士も何名かおられてドキドキでした。この、参加者の多様性が実現されるにつけ、書いてよかったとじわるのでした。
この本、本来は福祉職の方しか向かずに作っており、法律家がガン読みすることはそんなに想定していません。なので、福祉関係者や行政職員向けの研修をするのはやりやすいのです。ところが、出版から2年が経過し、今年度は弁護士からの研修のご依頼が来るようになりました。
「次は、司法×福祉×行政連携について、弁護士に向けて説明する本を書かないと」という感想をいただくこともあり、いずれは弁護士向けの発信も考えないといけないと思っていたところです。
ただ、「怒られそうで怖い」というのが正直なところ。
なんでこんなに怖いのか自分でも言語化しきれていません。畏怖なのか、恐怖なのか、それもよくわかりません。でもこの「怖さ」こそが、現在自治体なり福祉職なりが弁護士に対して抱いている気持ちそのものなのかもしれません。なんか、今、現に書きながらそんな気がしてきた。だって、処「法」箋研修してると、「弁護士怖かったエピソード」がいっぱい感想で来るねんて。「こいつなら言っても大丈夫」って思われたんでしょうね。
そんなことを考えていると、首長が政権交代して大変そうな古巣以上に自分が大変で、GWに寝込んでしまうのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
