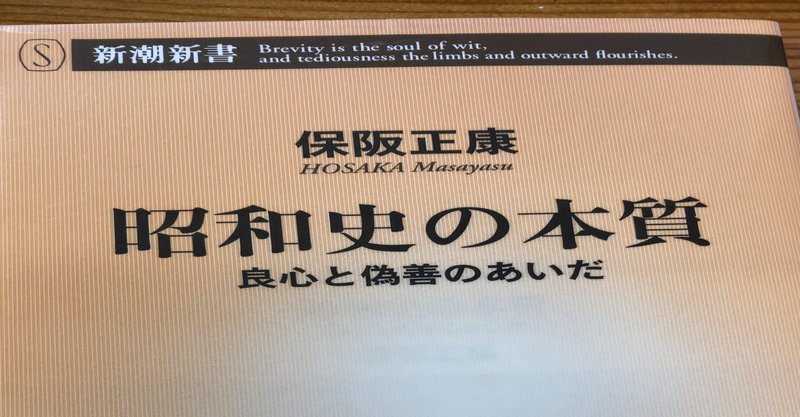
保阪正康『昭和史の本質』を読んだ
保阪正康『昭和史の本質』を読みました。令和になって、昭和は遠くになりにけり、という感じではありますなあ。
私は平成という時代を語るには、幾つかのキーワードがあると考えているが、そのひとつに「政治」という語を重ねている。平成六年の法改正により、日本社会は小選挙区(比例代表並立)制となった。これによって日本では戦後が始まって以来初めて、小選挙区による勝者が当選者となった(比例制を導入しているので単純な小選挙区ではないが)。その結果、政治家の質が著しく劣化した。過去も見ないし、過去に学ぼうとしないから、未来への展望も開けない。ひたすら己のための選挙で、あたかも有権者の姿など想定していないように見受けられる(国会での与党質問の陳腐さがそれを裏づけている)。(p.22)
サブタイトルが「良心と偽善のあいだ」となっています。良心について書かれている部分もメモ。
人生を冷めた目で見ていた芥川(龍之介)は、寸鉄人を刺すような一文で読者にはっと驚く刺激的な空間を広げてみせた。「一国民の九割強は一生良心を持たぬものである」は「侏儒の言葉」の「修身」というタイトルの一節である。この一節には特別に解釈や注釈はつけられていない。しかし、芥川は次のように考えていたのではないかと思われる。<良心という語は実に便利に用いられるが、その実、その内容はわかっていない。愚かな行為や恥ずべき行為をくり返して破廉恥漢の汚名を浴びてこそ、やっと良心とは何かがわかってくる。良心は確かに道徳をつくる因になるだろうが、しかし道徳そのものが良心の良の字をつくることなどありえない。良心という趣味をもつ病的な人物もいるが、それは大体が「聡明なる貴族か富豪か」なのである>
よりわかりやすく言うなら、良心などというのは特権階級の遊び道具、これ自体何の特色もない。道徳とは時間と労力の節約から生まれ、道徳の与える損害とは……と芥川は言い、「良心の麻痺」と決めつけている。良心というのはきわめて雑駁で、善人の用いるもっとも安心な持ち物といったところに落ち着くのであろう。どの国にあっても国民の九割強は、一生良心を持たない。そしてただひたすら、この言葉を安全弁のように用いていると皮肉っているのである。(p.35-36)
最近、僕はTBSラジオ「Session-22」の番組で国会答弁などを聴く機会が増えています。テレビのニュースだと抜粋されているので、いろいろと細かいやりとりが出ません。切り取られずに文脈がよりわかりやすい形で(それでもフル尺ではないので切り取られてはいるわけですけど…)、政治家の答弁や官僚の答弁を聴いていると「この人たち、本気で思っているのだろうか…それとも言わされているのだろうか…」と思うこともあるのです。
近代日本はいくつかの点で極めて後進国というべき点がある。デモクラシーを名乗ることなどはおこがましいといっても良い。例をあげる。昭和二十年八月の太平洋戦争の敗戦時に公文書を焼却したことがその一例である。
この文書焼却を細部にわたって調べていくと、昭和史の中での権力者の背中から本音が漏れていることがわかる。歴史や時代に背を向けて密かに書類に火をつけている姿が想像されるが、しかしその背中には「あかんべえ」と舌を出している己の姿が彫られている。つまり国民は知っているのである。無責任の極みの人格やら、名声に傷が付くという思い込み、そして欺くことへの恐怖心、それらに怯えて震えているのである。
(略)
史料焼却の理由は、つまりは「公なく私のみ」だからである。この手の官僚のあり方は今に至るも伝統として受け継がれている。森友・加計問題での官僚たちの国会答弁は前を見て話すのではなく、背中を見せて話してほしい。国民を愚弄している姿がよくわかるというものだ。(p.120-121)
戦果を伝える「大本営発表」は、嘘と誇大の代名詞だが、戦時下では国民は信じさせられた。戦時中に旧制中学の生徒だったAさん(戦後は大学教授)は、熱心な皇国少年だった。
彼は毎日この発表を聞いて、日本軍はアメリカ海軍の艦艇をどれほど沈めたかを計算しては、ノートに書き込んでいた。実はアメリカ海軍には空母が何隻、駆逐艦が何隻と、太平洋艦隊の戦力がかつて報道された時に知っていた。ところが大本営発表の数字を足していくと、太平洋艦隊の戦力をはるかに上回ってしまう。
「大本営発表は嘘を言っているのではないか。だって大本営発表を聞くと、アメリカ海軍は全滅しているのに、なぜ日本が勝っていないの」と彼は大人たちに質したそうである。誰もが、そんなこと心配しなくていいと言い、口に指を当てて、そういうことは口にしてはいけないと震え声で制したそうである。
日本が負け戦に入っていることは、昭和十九年のある時期からは誰もが知っていたのだ。知らないと思っているのは、大本営報道部の将校、あるいは軍事指導者たちだけだったのではないか。まったくのところ、裸の王様が軍服をまとわず、まさに裸で戦争指導を行なっていたのだ。お笑いである。(p.192-193)
いまはいまで、うーん、と思うことも多い世界ではあるのですが、きっと「今だから」というものだけではなく、すでに一度同じところを通っているのかもしれないな、と思わされました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
