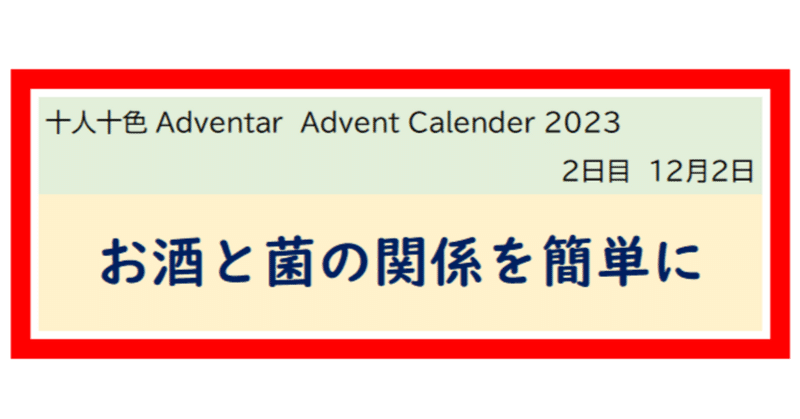
お酒と菌の関係を簡単に
お酒と菌の関係と書きました。大いに関係しているのですが、あまり関係しているイメージが薄い人が多いのではないでしょうか。私もあまり意識したことはありませんでした。今回はそのあたりについてお話します。
まず、お酒とは何か。おいしいものです。はい、そうです。乾杯!!! ビール、ワイン、日本酒、ほかにも色々ありますね。お酒とは...…真面目に考えれば、「エタノールを含む飲料」でしょうか。いかにも無味乾燥な言い方ですけども。
次に菌とは何か。なんとなく汚いイメージですか? それは「ばい菌」のせいな気もしますね。僕は生物屋さんではないので、細かな言及は避けますが、菌類には主に「きのこ・かび・酵母」という3つの分類が含まれます。どれも身近ではないでしょうか。
酵母で馴染みのない方でも「イースト菌」は聞いたことがあるのでは。別名、パン酵母、出芽酵母と言ったりもしますね。学名はサッカロマイセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevisiae)です(仕様上、斜体にできない...…かといって下線も引けず...…)
今回の主役はこのサッカロマイセス・セレビシエです。名前だけでも覚えてみましょう。カッコいいので。
サッカロマイセス・セレビシエ
見出し機能を使って無駄にデカく表示しました。
さて、サッカロマイセス・セレビシエはイースト菌なんだからパンを作るときに使うんでしょ。お酒と何の関係が? という疑問は至極当然です。素晴らしい。
ではもう一歩、踏み込んで。パンを作るときに使われるのはなぜか。それは発酵を担うからです。イースト菌を入れると膨らむ、というのは発酵によってグルコースから二酸化炭素が生じるからです。そして、そのときに一緒に生じるのがエタノールです。お酒と菌が関係していると言ったのはそのためです。
グルコースがサッカロマイセス・セレビシエによる発酵過程を経るとエタノールを生んでお酒になる、そういうことです。これがお酒の原理です。この文章は語弊1と語弊2を含むので次に詳しく説明します。
もうちょっと詳しく(語弊1解説)
さて、もうちょっと詳しく書きます。お酒は大きく分けると醸造酒と蒸留酒に分けられます。醸造というのはさっきの発酵過程を経てエタノールが出てくる過程みたいなこと。そして、蒸留というのは蒸発させた成分を集めることで、ここではエタノールを集めることを指しています。中学校の実験でみりんの蒸留とかしませんでしたか?
つまり、発酵過程を経てできるのはい醸造酒ということです。だからさっきの原理「グルコースがサッカロマイセス・セレビシエによる発酵過程を経るとエタノールを生んでお酒になる」は厳密には「醸造酒になる」ですね。
醸造酒はビール、ワイン、日本酒など。蒸留酒はウィスキー、ウォッカ、ジンなど。蒸留した分アルコール度数(エタノールの濃度)が高くなっていることが分かるかと思います。
さらにもっと詳しく(語弊2解説)
端的に言うと、サッカロマイセス・セレビシエ以外を使ったお酒もあります。「も」とか言うと失礼かもしれませんね。
まず、分かりやすい例で言えば、ペールエールやスタウトなどのエールビール。これに使われている酵母はサッカロマイセス・パストリアヌス(Saccharomyces pastorianus)。代表的な下面発酵酵母です。下面発酵というのは発酵後に酵母が集まって沈むタイプの発酵。上面発酵はその逆で発酵中に泡と一緒に浮いて来ます。日本でよく飲まれている4大メーカーなどのビールはこちらの上面発酵を経たものでラガービールと呼ばれます。その中に含まれるのはピルスナーやミュンヘンで、特に日本で飲まれているのはピルスナー。
サッカロマイセス・セレビシエ以外の酵母が使われているお酒で言えば他に、スペインのシェリーというワインがあります。これは、出来上がったワインにブランデーを加えて度数調整を行ったあと、貯蔵段階で敢えて満タンにせず7分目程度に留めます。そうすると、サッカロマイセス・バヤヌス(Saccharomyces bayanus)という酵母が液面に膜を作る。これが特有の香りを生み出すと言われています。この酵母は現在ではサッカロマイセス・セレビシエの一つに分類されていますが。
さらにマイナーなところでは、キビから作るタンザニアのビール(ボンビー酒)や糖蜜から作るジャワ島のチウというお酒。これらはサッカロマイセス・セレビシエとは増殖方法が異なる分裂酵母の一つシゾサッカロマイセス・ポンべ(Schizosaccharomyces pombe)が発酵を担っています。
また、フィリピンのヤシ酒には、サッカロマイセス・チェバリエリ(Saccharomyces chevalieri)やサッカロマイセス・バイリ(Saccharomyces bailii)という二種類の酵母が作られています(これらも現在ではサッカロマイセス・セレビシエの仲間として分類されています)。
さて、語弊2の解説まで読んでくださった方はいるのでしょうか。はてさて。こうやって見ていくと、発酵に用いる菌類の種類という観点でもお酒には色んな種類があることが分かると思います。これに加えて、原料の違い(つまるところ、グルコースの出どころの違い)や製法の違い、つくる場所の気候の違い、など様々なことが絡んでお酒の種類の豊富さ、多様性が生まれていると言えます。
何も考えずにうまいうまいと言ってお酒を飲むのも楽しいですが、たまにはグラスの中の、はたまたジョッキの中の、はたまたお猪口の中のお酒の来歴に思いを馳せてみるのもいいかもしれませんね。
参考文献を以下に示します。
吉澤淑, 『酒の文化誌』, 丸善株式会社, p.p.1-32, 1991年.
菊池韶彦, 『酵母のライフサイクル ―ノーベル賞にかがやいた酵母の話―』, サイエンス社, p.p.22-24, 2006年.
小崎道雄・椿啓介(両名は編著者), 『カビと酵母』, 八坂書房, p.p.11-42, 2007.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
