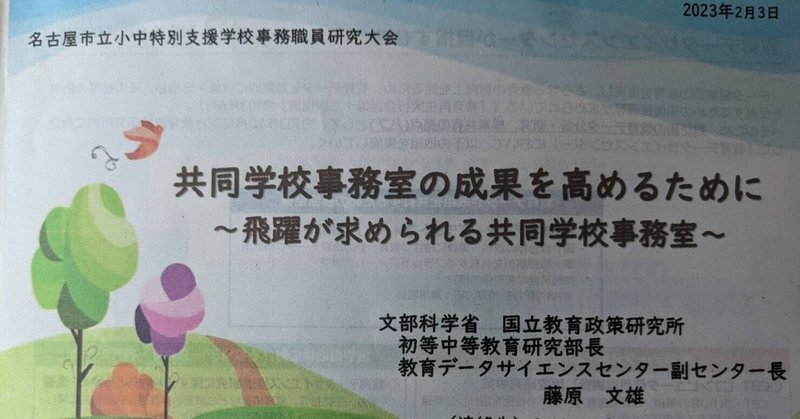
【感想】藤原文雄先生の講演が面白かった。
いつもありがとうございます。
毎回お土産で買ってるくせに名古屋ふらんすが何のお菓子かよくわかってない学校事務職員のタクトです。
#なんかあのやわらかくておいしいやつ
今回は、今日、名古屋市立小中特別支援学校事務職員研究大会に参加してきて、その中の藤原文雄先生の講演が個人的にとても面白かったので、それを受けての学びや感想?を記録として書こうと思います。
思いつくままに書いていこうと思うので長くなったりまとまりなかったりになりそうですが、ご容赦ください。
GIGAスクール構想の話
最初の挨拶?雑談?からもう面白かったです。
GIGAスクール構想で5,000億円かけてて、日本の学校のICTは世界最高水準。
ICTをみんなが使っている大きいメリットに「学習ログが取れる」がある。子どもの数だけデータが積み上げられるので、それが教育の質の向上につながると。
僕も本当にその通りだと思いました。ICTが学習のツールとしてどうか、タブレットか紙か、という観点だけでみると、「今回は紙の方が良い」という場合も当然あります。しかも、今の現場における環境(その他のICT機器の整備状況や使用制限、教員の活用力)を考えると、少なくとも今“は”、「ICTを活用していく労力の方が大きい」「無理にタブレットを使わなくても。」となっちゃうことが多いかもしれない。
でも、ICTを学習のツールとして使っていく、ICT化を推進していくことによって、教育の質の向上にどれだけ恩恵があるか、そういった未来のことまで考えてみんなで活用していけたら最高だなと思います。
事務を“つかさどる”の話
藤原先生は、「つかさどる とは、ずばり仕組みづくりだー!」みたいなことを言っていて(いや、もっとちゃんと説明がありました。)これが自分にはめちゃくちゃ刺さりました。
仕組みをつくって、進捗状況を管理していく。これがつかさどること。
そして、仕組みを考えて提案していくことこそが、学校運営参画だと。
僕は、学校運営参画というものをやりたくて、自分の感覚的なところで「これは学校運営参画だ!」と本気で思えることに取り組んできました。でも、周りの学校事務職員が誰一人そんなことやってないなんて状況もしょっちゅう。そして、事務もつかさどらなきゃいけない(笑)
そーなってくると、自分がやろうとすることに迷うことはないけど、指針みたいなものはあった方が全力でアクセル踏み込めるよなぁとはいつも思っていて、今回、「つかさどるとは、仕組みづくりとその管理。その提案をしていくのが学校運営参画。」とシンプルに定義してもらったのがめちゃくちゃすっきりしました。
3つやらなきゃいけない話
学校教育法第37条に規定されている学校事務職員の職務規定。昔は「①事務に従事する」。今は、法改正によって「②事務をつかさどる」に。そして、今求められているのが「③校務運営参画」。
よく「とにかく運営参画を!」という人がいるけど、それは違うと。
今の事務職員は、「運営参画」「つかさどる」「従事」という3層の仕事をしないといけない。「従事する」がなくなることはないし、それがなくなったら学校に要らない存在になってしまう、という話でした。
僕は、気持ち的には①②をガン無視して(実際にはやってます。)、③の運営参画に向かってる人間なので、僕が一括された気持ちになりました(笑)
定例業務が苦手で「従事する」があんまりできない人間としてはキツかったですが、従事する・・・いわゆる「処理する」仕事が変わってきているのは事実だと思うので、従事の仕事を思考からただ切り捨てるんじゃなく、何が不要になり、何が残るのか、従事するならどこに注力するのか、を自分なりに考えていきたいと思います。
教員との関係の話
「チームの一員でいるには、強みが必要」
「教員の領域にはリスペクトを持つ。」
「“知識”が足りないと、話し合いにならない。」
これ、ココの話、首がもげるくらい頷きました。
学校の課題に対して、学校にいる唯一の行政職の視点で・・・いや、そんな肩書きはどうでもよくて、シンプルに「お金(予算)を扱える」学校事務職員だから“こそ”できることがあると僕は思っていて、チームに学校事務職員を入れた方が強くなるのになーと周りの学校を見ていつも思っています。(自分の学校ではみんな入れてくれてます。優しい。)
で、いざ仲間になって一つの問題に一緒に向き合うときに、相手側のこと(事務職員だったら教育のこと)をある程度知っていないと話し合いが進みません。
これは僕が身をもって実感してきたことなので本当にその通りだと言えるのですが、その相手側を理解するのに必要なのが、教育への、そして教員への「リスペクト」。
これがあるから、僕がどれだけ口を出しても先生たちは聞いてくれるし、話し合いになる。
そして、これは副次的な効果なんですが、ちゃんと自分の学校の教育活動を知ると、見える景色が全然違うので、学校運営参画できるポイントなんて簡単に見つけられるようになります。自分の学校の課題が良く見えるようになるので。
これからやるべきことの話
「学校事務職員はどうあるべきか」「学校事務の仕事とは」みたいな話を昔はよくしていたけど、もうそれしなくていいよねという話が面白かったです。
昔は「学校事務職員」というものを誰も語ってくれなかったから、それについて自分たちで考えたり、グランドデザインみたいなものを考えたりしたけど、それはもういいと。
国の方でもはっきりと学校事務職員の方向性や求めるものを出してくれてんだから、そこの話し合いは今はいらないんじゃないか。それよりも、やること目指すとこが決まってるんだから、実践して、それを可視化して、他の学校事務職員に共有して、ということをやるべきだという話でした。
僕はあーだこーだ話すより具体的に実践していくのが好きなので、グラデザなどが不要かどうかは抜きにして、個人的にこっちの方がやりがいがあって意味がある(あと、楽しそー)と思いました。
どんどん実践して、可視化して、「おーい、この方法めっちゃいいぞー!」とか「やー、これやってみたら、めっちゃミスったわー!」って、みんなでトライ&エラーを共有して改善していけたら、めちゃくちゃ楽しいだろうな。
職務行動のデータを見て思った。
最後に、これは藤原先生が話した内容ではないことなんですが、講演資料にあったデータを見て、やっぱそーなのかなーと思ったことを。
ある県の学校事務職員314名から取った職務行動についてのアンケート結果があって、各項目(日常的な仕事の行動)ごとに、「かなりそう思う」「そう思う」のパーセンテージを示したものでした。
「正確な処理をしている」とか「計画的に仕事をしてる。」といった“実務遂行行動”の項目はどれも80~90%以上と高いのに、“学校経営参画行動”の項目はどれも50%以下。「学校経営方針に対する意見を提案している」に至っては20%にも満たないという結果でした。
僕がずっと感じている、「事務処理が完璧でないと学校運営参画なんかしちゃいけない。」という空気感を表してる気がしてしまいました。
“実務遂行行動”の中の「かなりそう思う」の人たちだけに絞ると最低の項目で25%前後なのを見ても、「完璧にできてる!」と言えてる(のはきっとベテランの偉い方が多いはず)のうち、一部の人が運営参画に取り掛かってみているという印象です。(すごく偏った見方かもしれませんが。。。)
この「処理が完璧でないと動けないバイアス」みたいのはすごくある気がしています。
もちろん、絶対に落としちゃいけない部分はあるし、ミスが無いように努めるのは当然です。でも、そんなに毎日ミスなく完璧に事務処理できる人間なんてどれだけいるんでしょうか。そして、そーゆー人たちしかそれ以外の部分で学校のために仕事することってやっちゃダメなんでしょうか。もっというと、全部が全部、運営参画したからミスが起こる、しないからミスしないなんてそんな世界じゃないのになあと思ってます。でも、今は、何か学校のために動いたときに、「学校のためになってよかった」より、「これで何かミスしたら叩かれる」が勝っちゃってる現状がある。
「事務職員」という名称の仕事なので、「ミスをしたら・・・」みたいなことをすぐに言われますが(ていうか自分たちで勝手に言い出す)、本来どの仕事にも人間がやる以上ミスはつきもので、日常の中でミスが起こってしまっても重大なミスは犯さないようにミスとうまく付き合ってやっていくものだと思います。
「公務員」「事務職員」というので結構ひっぱられがちですが、僕らの仕事は一般的な事務員の仕事とはまた違うもの。「“学校”事務職員」として、メリットとデメリット、学校運営全体で見た時の「学校(子ども・先生・保護者・地域)のためになるか」の視点をもって大切だと思うことを全力でやっていきたいと思います。
めっさ長くなりました。
現場からは以上です。
☆
最後まで読んでいただきありがとうございました。
未来を創るのは今の子どもたち。
明るく楽しい“未来”のために、明るく楽しい“学校”を創る。
学校の未来を拓く人になる、学校事務職員、タクト。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
