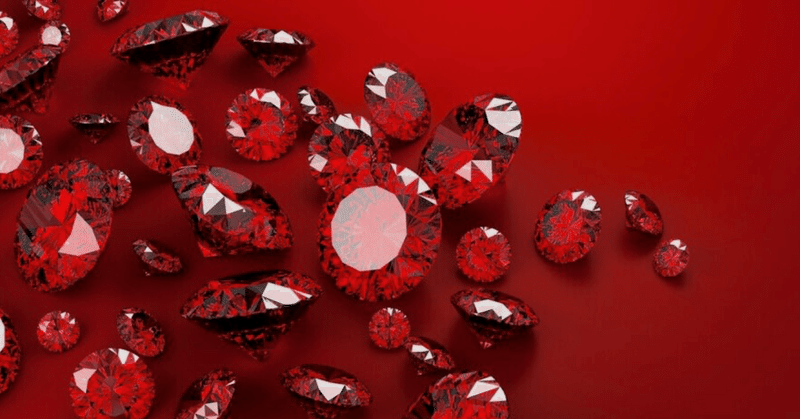
「加奈( カナ)」 赤い目 第1話
「うそつき」
あの子は そう言って
笑ったんだ
僕には なぜだか
それが とても
怖かったんだ
「赤い目」
「ねえ、さとしくん。どうしてウサギの目は赤いの?」
と、あの子は聞いたんだ
「ウサギの目が赤いのは、にんじんを食べてるからさ」
と、 僕はそう答えたんだ
子供の頃は僕は本当にそう思っていたんだ、、、
* * *
あの子の名前は「加奈」(かな)
真っ白い肌に 黒く長い髪
そして漆黒の瞳をしていた
僕の名前は「智」(さとし)
加奈は僕の家の隣に住んでいて、幼稚園も、小学校も、中学校も、そして高校もずっと一緒だった。
幼稚園、小学校の頃は仲のいい幼なじみで、中学生の頃はいつも僕の隣にくっついていた。そして高校生になる頃には、僕と加奈は幼なじみを越えた存在になっていた。
加奈は、自慢のその長い黒髪をいつも二つに分けて頭の上の方でくくり、赤いリボンでとめていた。その「うさぎちゃんヘア」は他の女の子達が羨むほど似合っていたんだ。
身長は165cm。それほど高くないけれどモデルの様にスレンダーで成績もトップクラス。英語だけでなくフランス語、スペイン語、中国語と語学も堪能。だけどスポーツ万能ではなかった。どちらかといえば運動オンチ。でも走るのだけは速かった。いや、速いというか走る姿がしなやかで華麗だった。
そんな学園のヒロイン的存在の加奈がいつも隣にくっついているんだから、当然僕は男子生徒からはいつも顰蹙を買っていて男友達は少なかった。別に必要でもなかったけれど。
女の子達といえば、はっきり言って非の打ち所がなさすぎて「加奈とは一緒に居たくない」というか時折に何ともいえない独特の存在感を放つ時がある様で「加奈って何だか怖い、、、」と思われている様だった。
そう、僕も時々そう思う、、、「加奈は何だかとても怖い」と 、、、
加奈は「にんじん」が好きなんだ。それも異常なくらいに毎日食べている。料理にはもちろん、そのままでも食べるんだ。
「おいしいよ」
にんじんを食べている加奈は、すごく幸せそうだ。だけど毎日毎日たくさん食べるなんていくらなんでも異常だ。けれど、誰もそんな加奈を止められなかったんだ。
僕の家はごく普通の2階建ての家で、加奈の家は隣だったんだけど、凄く大きな敷地に大きくてお洒落な洋館建てだった。そこに加奈は執事と給仕をする老夫婦と3人で住んでいたんだ。加奈の父親は「真島建設」という、世界的にも有名な大企業の会長で、両親共に外国に住んでいて日本にはあまり帰って来ないらしい。
加奈は両親の事は言いたがらない。というか、両親の事をほとんど何も知らないのではないか、、、そんな感じだった。
僕らが小学中学高校とずっと同じクラスメイトだったのは、その「真島財閥」の「権力」のおかげだった。この街のありとあらゆる所に影響力を持つ力。
だから加奈は生まれつきのお嬢様で、ずっとやりたい事を何でも思い通りにしていて加奈のする事に口出しする大人は誰もいなかった。
そして加奈は「赤い目」になりたい為に毎日毎日「にんじん」を食べていたんだ。
「ねえ、さとしくん。どうしてウサギの目は赤いの?」と、子供の頃聞いた時に僕が答えたあの言葉を加奈は成長しその知識を得るようになった今もずっと信じているんだ。
「ごめん、あれは間違っていたんだ。にんじんを食べても加奈の目は赤くならないんだよ。」と言えばよかったんだけど。
僕は怖かったんだ、、、それが僕の「うそ」だって分かった時の加奈の顔を見るのが、、、どうしてだかすごく怖かったんだ。
そんな僕らが、、、いつも一緒だった僕らは離れる事になった。
高校3年の秋、僕は引っ越す事になった。僕の父親は東北の出身で、仕事の転勤で僕も一緒に父親の故郷に帰る事になったんだ。
「いやだよ」と加奈は泣いた 。「はなれたくないよ」と加奈は泣いた。
「離れたくないのは僕もおなじだよ」と僕は言った 。「高校を卒業したら、またこの街に戻ってくるから」と僕は言った。
「それまで待ってるから」と加奈は泣いた 。「ずっと待ってるから」と加奈は泣いた。
それから、加奈は毎日手紙を書いて送ってくれたんだ。毎日毎日途切れる事無く。電話をくれればいいのにと言っても「電話はイヤなの。会いたくなるから」 と、ずっと手紙をくれたんだ。
僕はといえば返事は何日かに1回、1週間に1回、そして日が経つにつれ返事を書く事も少なくなっていった。
加奈の事が嫌だったからじゃないんだ。加奈と離れている事で自分の心の均等を保てている事に、ほんの少しの安堵感があったんだ。
思えば僕はいつも
加奈の思いに応えようと、そればかりを考えていた
加奈の喜ぶ顔を見たいと、そればかりを考えていた
加奈を泣かせはしないと、そればかりを考えていた
思えば僕はいつも
加奈は返事を書かない僕を責めるでもなく毎日毎日手紙を書いてくれた。その胸にあふれる思いを毎日毎日書いてくれたんだ。
それは、ときには囁くように、ときには叫ぶように、 自分の思いの全てを書いてくれていた。
そして「僕は加奈から離れている事で心の均等を保っている」それがどういう事なのか僕は気付いていなかったんだ、、、いつもいつも一緒だったから「離れ離れに暮らしている加奈から発する思いがやわらいでいる」その本当の意味に僕は気付いていなかったんだ、、、
そうして寒い冬の日、、、毎日毎日届いていた加奈からの手紙が途切れた。
あたり前の事は人の感覚を鈍らせてしまうものなのかもしれない。気付きもしない小さな「ささくれ」が、その「ささくれ」が全身に広がるのに3日もかからなかった、、、たまらなくなった僕は加奈に電話をかけた、、、加奈は家には居なかった。そして執事がその事を教えてくれたんだ。
そうして僕は加奈のいる大きな街へ向かった。
たどり着いた大きな白いコンクリートの建物の前で、そこ居る加奈の元へと向かえずに僕はただ立ち尽くしていた。
何の変哲も無い日常に鈍らされていた僕の感覚は自分でも思いもしない方向に研ぎすまされていて、加奈の元へと向かう僕の足を止めていたんだ。
重い足を引きずるように上る階段は果てしなく続いていて永遠に其処へとたどり着かなければいいのに、、、その願いも叶わず気がつけば大きなドアが僕の目の前にあった。
どうしてそんな錯覚が僕の脳裏に広がったのかその時は分からなかったのだけれど、他人の手みたいに言う事をきかない僕の手がかけたドアノブを引けば、、、
その向こう側に真っ白な雪原が広がっていて足を一歩踏み出せば懐かしいあの雪の感覚が足から全身にひろがって僕を優しく包み込んでゆき、そして目の前には白い雪の化身が、、、
その白い部屋の白いベッドの上に白いパジャマを着て頭に白い包帯を巻いている加奈が座っていて窓の向こうを静かに見ていた。
どう声をかけていいのか、、、なんて言ったらいいのか、、、ただただ静かな時間が流れていった。その白い世界だけ時がゆっくりと流れているかのように。僕の歩みがゆっくりなのか、ほんとうに時間の流れがゆっくりなのか、側に来るまで僕に気づかないで加奈は窓の向こうを静かに見ていた。
僕が名前を呼ぼうとしたその時、加奈はゆっくりと振り返って、そして僕の顔を見て。
「うそつき」 そう言って笑ったんだ
その瞬間、僕は思い出した。
あの日の事を、、、あの日の僕を、、、あの日の加奈を、、、
次のエピソードへ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
