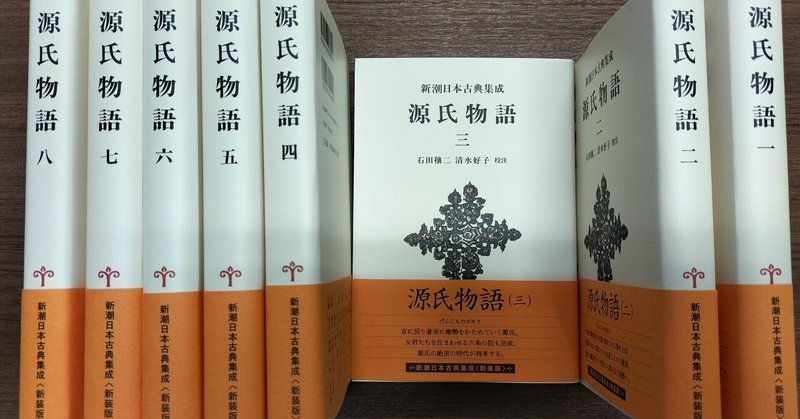
毎週一帖源氏物語 第二十二週 玉鬘
「玉鬘十帖」や「玉鬘系」という言い方があるらしい。この玉鬘巻から真木柱巻までは一つのまとまりを成すと考えられている。物語がここから新しい局面に入ると言ってもよい。
ちょうどよい機会なので、これまで読んできた部分を振り返ってみた。といっても、もう一度原文に目を通す余裕はないので、自分が書いた記事を読み直してみただけである。自分が何を読み取り、何を見逃していたか、とてもよく分かる。
玉鬘巻のあらすじ
源氏は夕顔のことを忘れていない。右近は、故君が存命なら明石の御方くらいの扱いは受けていたのではないかと思っている。
行方知れずの若君は、(西の京にいた)乳母の夫が大宰少弐に任じられたため、筑紫に下っていた。少弐没後も一家は当地にとどまり、上京の機会を窺う。姫君は美しく成長し、土地の豪族が言い寄る。中でも肥後の太夫(たいふ)の監(げん)は熱心で、少弐の長男の豊後の介は姫を伴って「夜(よる)逃げ出でて船に乗りける」(293頁)。
京に上った一行はひとまず九条に落ち着くが、つてがないので困窮する。神仏の御加護を願い、まずは八幡の宮へ、ついで初瀬に、詣でる。その手前の椿市に宿を取ったとき、折に触れて参詣していた右近と遭遇する。乳母も右近も再会を喜ぶが、乳母がまずは姫の父大臣に知らせてほしいと頼むのに対して、右近は源氏に取り次ごうとするなど、思惑が交錯する。
右近は源氏に「はかなく消えたまひにし夕顔の御ゆかりをなむ、見たまへつけたりし」(312頁)と報告する。これを受けて、源氏は姫を引き取ることに決める。姫は源氏から歌を贈られて戸惑うが、人々もまずは源氏のもとに身を寄せてこそ、父大臣が消息を伝え聞くこともあるだろうと説得する。源氏は姫を丑寅の町の西の対に住まわせ、東の御方に後見を頼む。御方にも中将の君にも、源氏は自分の実の子であるように触れ込む。豊後の介は家司に取り立てられる。
年の暮れに、源氏は新春のための晴れ着を女君たちに贈る。上は源氏に「着たまはむ人の御容貌(かたち)に思ひよそへつつたてまつれたまへかし」(326頁)と助言する。源氏が何を選ぶか、上はただならぬ関心を寄せる。それぞれにお礼の返事があるなか、東の院にいる末摘花からは古風な文と歌が届く。源氏は苦笑しつつ、歌を論じる。
「玉鬘」の名の由来
玉鬘は明らかに重要人物だ。その人が本格的に物語に導き入れられ、後世の読者は玉鬘と呼んでいる。この巻の名称でもある。その由来はと見れば、源氏が詠んだこの歌だ。
恋ひわたる身はそれなれど玉かづら
いかなる筋を尋ね来(き)つらむ
頭注の現代語訳は「亡き夕顔を恋しく思い続ける自分は昔のままだが、この娘はどのような目に見えぬ縁に引かれて自分の許に頼って来たのだろう」となっている。比べてみれば分かるように、「玉かづら」が「この娘」に対応している。だからこの姫を玉鬘と呼ぶわけだ。
それは理解できるのだが、何か引っかかるものがある。なぜ、夕顔の遺児を鬘になぞらえなければならないのだろう。
私が気づいた範囲では、「玉鬘(玉かづら)」という語句の初出は蓬生巻だった。その記事でも触れたが、末摘花が自分に長年仕えてくれた侍従に報いるために、自分の髪で作った鬘を与え、歌に「玉かづら」と詠み込んだのだった。このときは、物と言葉が正確に対応している。しかし、源氏の歌にはそれがない。「玉かづら」という語は、縁語の「筋」(現代語訳では「縁」)を呼び込むためだけに存在しているように見える。そこが強引に感じられるのだ。しかも、この歌は源氏が玉鬘に向けて詠みかけた歌ではない。紫の上を前にして発したものだ。言うなれば、源氏が一方的に(相手の意向などお構いなしに)「玉鬘」と名づけたようなものだ。本人にしてみれば、玉鬘と呼ばれる筋合いはないと感じるのではないだろうか。
源氏三十五歳の出来事
少女巻は足かけ三年にわたる出来事を語っており、その最後の年の八月に六条の院が完成している。源氏が移り住んだのは彼岸の頃だからやはり八月で、長月(九月)には紫の上と中宮のあいだで春秋の優劣をめぐる歌の応酬があった。明石の上が渡ってきたのは神無月(十月)である。
玉鬘巻は、この姫の幼少期の回顧は別として、主な出来事は少女巻の最後の一年と平行している。太夫の監から遁れるように上京したのが四月、玉鬘一行と右近の邂逅から源氏の決断までが九月に生じている(「かくいふは、九月のことなりけり」(318頁))。つまり、源氏が玉鬘の居所を知らされたのは、六条の院に移って間もない頃だったわけだが、その時間関係が分かりにくかった。玉鬘巻の冒頭に右近の内心が述べられていて、夕顔が生きていれば「この御殿(との)うつりの数のうちにはまじらひたまひなましと思ふ」(281-282頁)とある。六条の院に移り住む女君のなかに夕顔も入っているはずだという感慨は、この年の九月以降でなければ発せられない。そのせいで、玉鬘が上京するのは翌年の四月だと早合点してしまった。
玉鬘の養育
玉鬘は二十歳になるまで筑紫や肥前で過ごす。見た目の麗しさは親譲りで説明がつくとしても、教養の高さはどのようにして身につけられたのだろうか。西の京の乳母が力を尽くしたようではあるが、それだけでは不十分だろう。源氏が明石の姫君の養育を気にかけて、上京を急がせ、ついには紫の上に引き取らせたことを思うと、玉鬘は「ほったらかし」にされていたのも同然に思える。これで都の貴人たちを惹きつけられるのだろうか。
実の娘という触れ込み
源氏は玉鬘を実の娘と偽って、花散里に養育を依頼する。夕霧(中将の君)にも、そのように信じ込ませる。当然、二人とも真に受ける。だから、事情を知っている女房たちははらはらするのだ。他の誰よりも、その設定に付き合わされる玉鬘自身が大変だ。
嗤われる太夫の監
玉鬘に言い寄る太夫の監が、作者によって笑いものにされている。当人は教養があるつもりで、それも含めてからかいの対象となっている。歌を詠もうとしても時間がかかるし、二度目は浮かばなくて諦めている(「また詠まむと思へれども、堪へずやありけむ、去(い)ぬめり」(292頁))。自分の歌に対する返歌が失礼だと感じたまではよいが、うまく丸め込まれている。田舎者を徹底的に虚仮にしていて、太夫の監にちょっと同情する。
言葉の問題に触れておくと、この太夫の監の初出時に「勢いいかめしき武士(つはもの)」(287頁)とあったのが目を引いた。いかつい地方豪族は、武家のイメージで語られている。
源氏のたわむれ
以前から源氏は軽口を叩く人だと思っていたが、この巻ではとくに目立つ。右近を相手にたわむれてみたり(「例の、むつかしう、たはぶれごとなどのたまふ」(311頁)、「ただはかなき御たはぶれごとをのたまひ、をかしく人の心を見たまふあまりに、かかる古人(ふるひと)をさへぞたはぶれたまふ」(312頁))、紫の上に際どい冗談を飛ばしたりする(323頁)。上機嫌なのだ。
気の利いた言葉を口に出すのも、すぐれた歌を詠むのも、頭の回転が速くなければできないことだ。そのように考えると、たわむれ好きであることもまた、源氏の資質なのだろう。
似合う衣装で容貌が想像できる
源氏が女君たちのために新春の晴れ着を用意するとき、紫の上は容貌に似合うように見立ててさしあげるように述べる。それとなく女君たちの顔立ちを探ろうとしているのだなと、源氏は推測する(「つれなくて人の御容貌(かたち)おしはらかむの御心なめりな」(326頁))。
これより先、さまざまな衣装について、色合いを中心にかなり詳細に描写される。私には知識がないので絵が浮かばないが、当時の読者は具体的に思い描くことができただろう。そして、晴れ着に似合いそうな顔まで想像できたのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
