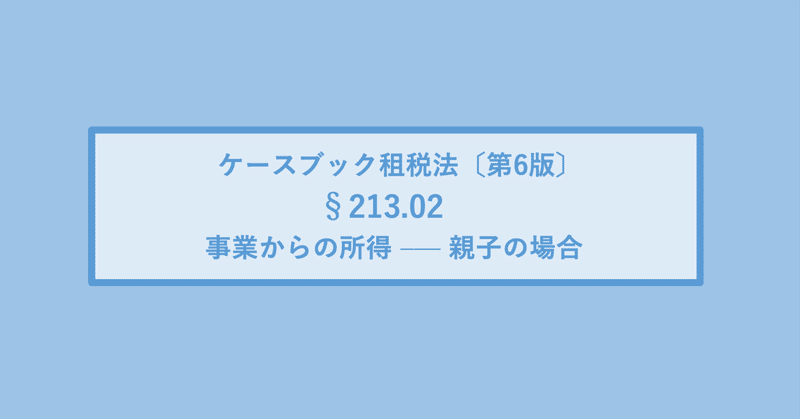
§213.02 事業からの所得 ––– 親子の場合
1.事案の検討
本件判決は、先行する最高裁判決を引用して、事業による収入は事業の経営主体に帰属すると述べている。
① 本件判決によると、「事業の経営主体」とはどのような者か。
本件判決は、事実認定の末尾で、「したがって、医院の経営に支配的影響力を有しているのはXであると認定するのが相当である」としている。このことから、「事業の経営主体」とは、事業に対する支配的影響力を有する者であると考える。
「事業から得られる収益は、その事業の事業主に帰属すると考えられます。そして、法律的帰属説の立場からは、事業から得られる収益が帰属する「事業主」とは、法律的な意味で、その事業を実質的に経営している人(経営主体)だとされます。」(佐藤〔第3版〕315頁)
② 本件のXが①に挙げた者に該当すると判断するに当たり、本件判決はどのような事実を指摘しているか。なお、【事実】欄で言及されている「開業届」については、所得税法229条参照。
本件判決は、次のような事実を指摘している。
1. 次の事情からXとSが全く別個の世帯とは認められず、このことはSの開業届が提出された昭和57年3月11日以降も同様であったこと
a. X夫婦とS夫婦は同一の建物に1階と2階で住み分けているが、2階には独立の出入口はないこと
b. Xは昭和57年3、4月ころ借入れをして、このような住み分けのできる家に改築したこと
c. 昭和56年10月から12月までの間、XからSに月25万円の給与が支払われている旨の届出が税務署に行われたが、実際は、医院の収入から借入金を返済したのちSとXで按分しており、按分割合は明確に定められていなかったこと
2. Xが昭和35年から現在までXとSの住所地で医院を経営していること
3. Sが開業にあたり必要とした医療器具等の費用は、X名義で借り入れられ、医療器具等の売買契約の当事者はXであり、借入れの返済はX名義の銀行口座からなされ、その借入れにあたり、X所有の土地建物に根抵当権が設定されていること
4. 本件各処分以前、医院の経理上SとXの収支が区分されていなかったこと
2.「経営主体」の判断要素
事業所得の帰属者たる経営主体を判断するに当たり、名古屋地判平成17年11月24日(判タ1204号114頁)は、以下のように判示している。
「事業所得の帰属者は、自己の計算と危険の下で継続的に営利活動を行う事業者であると考えられるところ、ある者がこのような事業者に当たるか否かについては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有するかを社会通念に従って判断すべきである。」
本件判決の判示で、「X夫婦と」(146頁下から2行目)から「相当であり」(147頁23行目まで)に挙げられた事実は、それぞれ、上記判示のどの要素について判断したものと考えられるか。
「法律行為の名義に着目」した要素としては、前問3の事実関係をあげることができる。「事業への出資の状況」の要素としては、「出資」を事業用資金の調達と捉えると、前問1. b.と3の事実関係をあげることができる。「収支の管理状況」の要素としては、前問4.をあげることができる。「従業員に対する指揮監督状況」の要素については、明示的に判示されていないが、前問1. a. c.と前問2.からSがXに従属していると状況を判示していると捉えることができる。
3.複数の事業/共同事業
本件で、①事業が2つあった(XとSがそれぞれ別個の事業を営んでいた)、または、②事業は1つだがXとSが共同してこの事業を営んでいた、と考える余地はないか。本件判決はどのような理由で、本件の事業がこの①②にあたらないと判断しているか。
設問①について
XとSが別個の事業を営んでいたと認められるためには、XとSが、それぞれ、自己の計算と危険で事業に従事している実態が必要となる。
本件判決の認定事実を概観すると、次のようになる。すなわち、Xが住所地において医院を経営していたところ、居住形態に触れながら、XとSがまったく別個の世帯とは認められないと指摘する。そのうえで、Sの事業に係る借入れ、担保設定、売買契約の名義が、すべてSではなくXであることを指摘する。さらに、XとSの収支が経理上、区分されていないことも指摘されている。
これらのことから、Sの事業がXの事業の一部に過ぎないことが窺われるため、本件判決は、①にあたらないと判断したのではないかと思われる。
設問②について
XとSが共同して事業を営んでいたと認められるためには、ひとつの事業について、XとSとの間の対等な関係(対等に支配的影響力を行使し得る関係であろうか)が必要となるように思われる。
本件判決の認定事実を概観すると、次のようになる。すなわち、設問①で確認したように、そもそも、Sは自己の計算と危険で、医院の経営に従事しておらず、Xの計算と危険で、Sの医療行為を含む医院は、経営されている。このため、XとSとの間に対等な関係は想定できない。このことは、収益分配の方法からも観察される。すなわち、明示されていないが、収入はすべていったんXの手許に入り、借入金の支払に充てられた後で、SとXとの間で按分されるが、肝心な按分割合が定められていない。手取金を支配しているXの意向で、25万円の給与の枠を超えて、資金がSの家計に融通されていたのではないかと思われる。このように、対等な関係であれば、必ず、合意される按分割合の合意がなく、かつ、事業からの収入もXの意向で使われていたと推測されることから、本件判決は、②にあたらないと判断したのではないかと思われる。
※ 佐藤〔第3版〕322-324頁「▶︎複数の事業や共同事業に関わる場合」を参照。
4.夫婦で農業に従事する場合の帰属判定
⑴ 夫は農地の所有者であるが、近隣の市に勤めているため、通常の耕作作業等はすべて妻が行い、夫は田植え、稲刈り等の重要な作業にのみ従事している。農作業に関わる決定はすべて夫名義で所属する農業協同組合の指導の通りに行っており、細部は妻が定めて、夫は時折相談にのる程度である。このような事案における所得の帰属はどのように考えるのが合理的か。
農業という事業に係る所得の帰属の問題なので、事業の経営主体、すなわち、農業の経営に支配的影響力を有している者に、所得が帰属していると考える。そこで、夫婦のいずれが、支配的影響力を有しているのかが問題となる。
農地は夫の所有である。また、農作業に関わる決定はすべて夫名義で所得する農業協同組合の指導の通りに行っている。そして、夫は、田植え、稲刈り等の重要な作業に従事している。これに対し、妻の関与は、農作業に関わる決定については細部を決定し、それすらも、夫に時折相談している。また、妻は、通常の耕作作業等に従事しているにとどまる。これらの事実関係を踏まえると、夫が農業に支配的影響力を有しており、妻は、夫の農業に従属亭に関与していると認められる。
したがって、経営主体は、夫であると考え、夫に農業に係る所得が帰属すると考えるのが合理的であると考える。
⑵ 現行課税実務は、このような場合の所得の帰属の判定基準を所得税基本通達12-3において明らかにしている。本通達の内容を調査し、通達の考え方だとこの場合の所得の帰属がどのように判定されるかを検討せよ。
通達は、「生計を一にしている夫婦間における農業の事業主がだれであるかの判定をする場合には、両者の農業の経営についての協力度合、耕地の所有権の所在、農業の経営についての知識経験の程度、家庭生活の状況等を総合勘案して、その農業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該農業の事業主に該当するものと推定する。」とする。
設問の事例では、耕地の所有権は夫に帰属していることが明らかにされている。しかし、それ以外の要素、すなわち、農業の経営についての協力度合、農業の経営についての知識経験の程度、家庭生活の状況等は、明らかにされていない。このため、上述の指針からは、夫婦のいずれが、支配的影響力を有するか判断できない。
このような場合は、通達は、「生計を主宰している者」が事業主であると推定する。つまり、設問の事例では、夫が事業主であると推定されることになると思われる。ただ、通達は、但書で「生計を主宰している者」が会社、官公庁等に勤務するなど他に主たる職業を有し、他方が家庭にあって農耕に従事している場合は、⑴から⑷に該当するときは、事業主は、家庭にあって農耕に従事している者と推定する。
ここで、⑴は、妻が耕地の大部分につき所有権を有している場合であるが、設問の事例では、夫が農地を所有しているため、⑴には該当しない。次に、⑵は、農業が極めて小規模で、家庭にあって農耕に従事している者の内職の域を出ないと認められる場合であるが、設問の事例からは明らかではないが、これに該当する可能性はあるのではなかろうか。そして、⑶は、夫が近隣の市の職業に専念していること、農業に関する知識経験がないこと、あるいは、勤務地が遠隔であることにより、夫が、ほとんどまたは全く農耕に従事していないときであるが、設問の事例では、夫は、重要な農作業には従事しており、これに該当しないのではないかと思われる。さいごに、⑷は、妻が、特有財産である耕地を有していることであるが、設問の事例からは、そのような事実関係は認められない。
したがって、通達の⑵に該当するのであれば、事業主は、夫ではなく、妻と認められることになると考える。そうではないのであれば、事業主は、やはり夫ということになると考える。
※ 佐藤〔第3版〕318頁参照
5.所得の帰属に関する考え方
本件判決と所得税基本通達12-1〜12-5を手がかりに判断すると、夫婦や親子などの親密な関係にある複数の個人が協力して事業を行い、所得を得ている場合に関して、課税実務と裁判例は、事業から得られる所得の帰属についてどのような考え方をとっているといえるか。
事業から得られる所得の帰属については、「(ア)事業から得られる所得は、その所得の事業主(経営主体)に帰属する」「(イ)事業主(経営主体)の判断基準は、①自分の名義で取引を行なっている者Aは、通常、事業主である ②Aのほかに、経営方針の決定に支配的影響力を有する者Bがいる場合には、Bが事業主である」とまとめることができる(佐藤〔第3版〕318頁)。
また、家族経営の事業の場合は、前問のとおり、「(ア) 事業の経営方針の決定につき支配的影響力を持つ者を事業主と推定する」「(イ) だれが事業の経営方針決定に支配的影響力を持つか分からないときは、『生計を主宰している者』が事業主だと推定する」「(ウ) (イ)については、整形の主宰者以外の者が事業主であると推定される個別事情がありうる」(佐藤〔第3版〕318頁)とまとめることができる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
