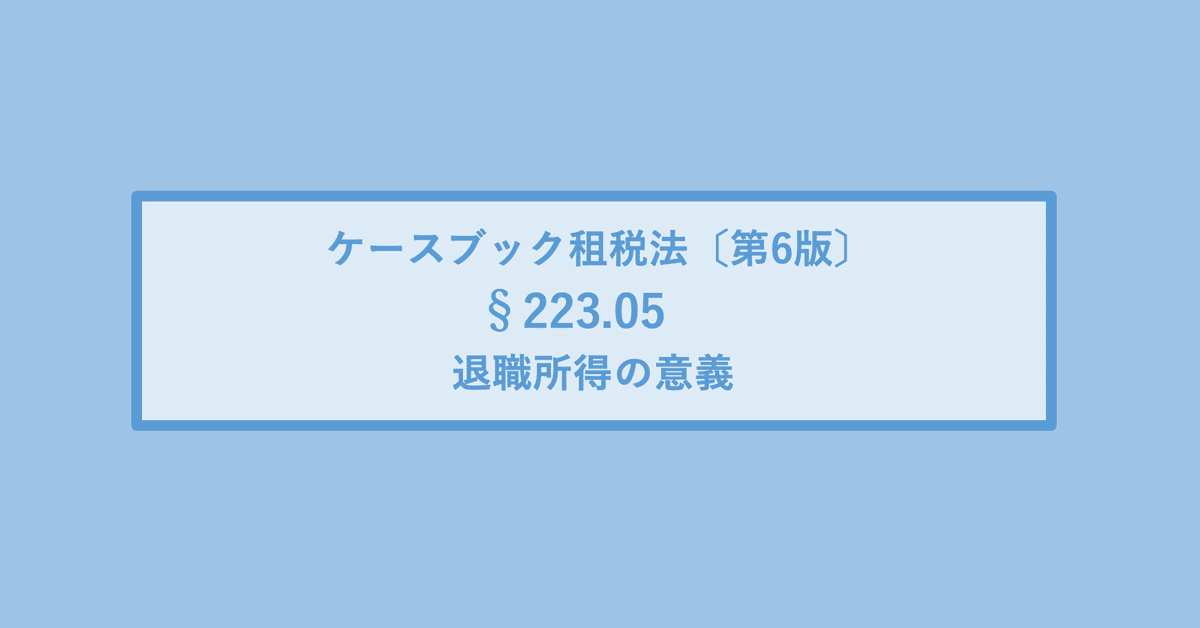
§223.05 退職所得の意義
1.退職所得の課税上の特徴
⑴ 所得税法30条1項は、退職所得をどのように定めているか。
退職所得は、①「退職により一時に受ける給与」および②「これらの性質を有する給与」、と定めている。
⑵①退職所得額の計算方法の特色を3点挙げよ。
まず、課税標準に算定にあたって、退職所得控除が適用され(①)、かつ控除後2分の1のみが課税される(②)。また、他の所得と分けて分離課税され、源泉徴収されるので、原則として申告不要である(③)。(佐藤〔第3版〕190-192頁参照)
②①で挙げた3点にはどのような理由があるかを説明せよ。
退職所得控除については、終身雇用制の下、退職金で老後を過ごす必要があるとの前提から、金額の割に担税力が低いことを考慮し、特別の控除が設けられたと説明される(①)。また、退職所得控除後の金額の2分の1のみが課税されるのは、長期間の勤労の対価としての所得という性格に鑑みて平準化措置として設けられたものと説明される(②)。さいごに、分離課税とされる点については、担税力が低いことを考慮し、他の所得と合算して高い累進税率の適用を避けるための措置と説明される(③)。(佐藤〔第3版〕190-191頁)
2.事案の検討
⑴ 本件判決が挙げる「退職所得」の特色をまとめよ。
①長期間の就労に対する対価の一部分の累積という性質と、②多くの場合いわゆる老後の生活の糧としての機能を有する。
⑵ 本件判決が挙げる「退職所得」の要件を、①「退職により一時に受ける給与」と②「これらの性質を有する給与」とに分けて整理せよ。
本件判決は、①については、「⑴退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること、⑵従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、⑶一時金として支払われること」という要件を掲げた。
また、本件判決は、②については、「それが、形式的には右の各要件のすべてを備えていなくても、実質的にみてこれらの要件の要求するところに適合し、課税上、右『退職により一時に受ける給与』と同一に取り扱うことを相当とするものであること」という要件を掲げた。
3.勤務関係の継続と「これらの性質を有する給与」
10年退職事件における最高裁判決の次に掲げる【判旨】を読み、①継続的な勤務の途中で支給される退職金名義の金員が、所得税法30条1項にいう「これらの性質を有する給与」に該当するためにはどのような事情が必要であり、②その事情に当たる具体例としてはどのようなものがあるか、を検討せよ。
設問①
「特別の事実関係」が必要であると判示した。
設問②
たとえば、①退職金支給制度の実質的改変により精算の必要があって支給されるものであるとか、あるいは、②勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみられないなどが、「特別の事実関係」の例として判示された。なお、「『特別の事実関係』の例としてあげられている①の点については制度変更に合理的な理由を求めている点、また、②についてはかなり具体的な考慮要素と判断基準が指摘されている点に注意してほしい。」とされている(佐藤〔第3版〕198頁)。
4.退職所得の範囲の拡大
⑴ この通達では、ある支払いが「退職所得」に当たるか否かをどのような基準で判断しようとしているか。
通達30-2で記載されている6項目は、次のように要約できる。
①新たに退職給与規程を制定等したとき、制定等の前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
②使用人から役員になった者に対し、その使用人であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
③役員の分掌変更により、職務内容等が激変した者に対して支払われる、分掌変更前における勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
④定年後、再雇用された使用人に対して、定年前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
⑤定年延長したとき、延長前の定年に達した使用人に対して、延長前の定年までの勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、相当の理由があると認められるもの
⑥法人が解散した場合、引き続き役員等として精算事務に従事する者に対して、解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与。
通達30-2の2で記載されている点は、次のように要約できる。すなわち、使用人から執行役員となった者が、受け取る使用人としての勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与は、執行役員退任後の使用人としての再雇用が保障されておらず、かつ、執行役員が役員に準じた責任を負担しているときは、退職手当等に該当するとされる。
⑵ この通達に挙げられた給与は、それぞれ、本件最高裁判決が指摘する「退職により一時に受ける給与」または「これらの性質を有する給与」の要件を満たしているか。
通達30-2の①のケースは、退職手当等を受け取った後で、雇用関係は終了するケースである。ただ、「退職により一時に受ける給与」の「⑵従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること」という要件を満たすと言えるのか疑義があるケースではなかろうか。なぜなら、退職金規程制定前の勤続期間に対応する労務の対価の後払の性質を有すると解されるのか、異論がありそうだからである。しかし、「これらの性質を有する給与」にあたるための「特別の事実関係」のうち、制度変更に合理的な理由が認められる場合にあたると解されたのではなかろうか。
これに対して、その他のケースは、退職手当等を受け取った後も、何らかの契約関係を継続するケースであり、「⑴退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること」という要件を満たすのか疑義のあるケースである。そこで、「これらの性質を有する給与」か否かを検討することとなるが、「特別の事実関係」のうち、勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみられない場合にあたり得ると解されたのではなかろうか。
5.退職所得制度の問題点
⑴ 以下の①②の事例において、A、Bが受け取る「退職金」は退職所得に該当するか。退職所得に該当すると、どのような課税を受けるか。
① Aは22歳で大学を卒業後、直ちにX社に入社し、23年間勤務した後、高給を提示してくれたY社に転職するためX社から「退職金」を受け取った。
この点、「退職により一時に受ける給与」(所得税法30条1項)にあたるためには、「⑴退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること、⑵従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、⑶一時金として支払われること」の要件を満たさなければならない。
Aは、退職という事実により金銭を受け取った(要件⑴)、そして、この金銭は23年間の勤務の対価の一部の後払の性質を有すると考えられる(要件⑵)、さいごに、この金銭は一時金として支払われている(要件⑶)、したがって、「退職により一時に受ける給与」に該当すると考える。
そして、退職所得として、退職所得控除後、2分の1に対し、源泉分離課税される。
② Bはアメリカに本社があるP社の100%子会社である日本法人Q社の幹部職員に就任した。P社グループにおける慣行に従えば、Bは3年ないし5年後には別の国の会社の役員等に就任することが見込まれていた。BはQ社在籍中は年間1,000万円程度の給与しか受け取らず、3年後に別の国の会社の役員に就任するためにQ社を退職したときに3億円の「退職金」を受け取った。
この点、「退職により一時に受ける給与」(所得税法30条1項)にあたるためには、「⑴退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること、⑵従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、⑶一時金として支払われること」の要件を満たさなければならない。
Bは、3年から5年の間で、P社グループの別法人で勤務するという慣行の下、P社の日本法人Q社に採用された。Q社では、3年間の勤務の後、別の国のP社グループの会社の役員に就任している。これらのことを踏まえると、Bは、Q社を退職した後も、P社グループの別会社に勤務しているため、実質的には、要件⑴を満たさないと考える。そして、転籍と退職金の支払いが、P社グループの制度であったとしても、これは、各社に在籍中の給与を低く抑え、退職金で支給することにより、税負担を軽減する仕組みと認められる。このため、この制度には合理性はなく、3億円の退職金は、給与所得として課税すべきと考える。
⑵ ⑴のAやBが受け取った「退職金」は、5年退職事件の最高裁判決が想定していた「退職所得」と同じか、異なるか。そこから現在の退職所得課税制度の問題点について、どのように考えるか。
Aの受け取った「退職金」は、5年退職事件の想定していた「退職所得」と同じと思われるが、Bの受け取った「退職金」は、異なると思われる。現在の退職所得課税制度の問題は、①長期間の就労に対する対価の一部分の累積という性質と、②多くの場合いわゆる老後の生活の糧としての機能を有さない、金銭の支払も、「退職金」に該当するとして、軽減された税負担を享受しようとする試みが行われ得ることにあると考える。
⑶ (略)
① 「特定役員退職手当等」、「短期退職手当等」とは、それぞれどのような手当等を指すか。所得税法30条4項、5項参照。
「特定役員退職手当等」とは、支払者の役員としての勤続年数が5年以下である者がその勤続年数に対応するものとして支払いを受けるものである。(金子〔第23版〕258頁参照)「短期退職手当等」とは、役員等以外の者で、勤続年数が5年以下である者がその勤続年数に対応するものとして支払いを受けるものである。
② 「特定役員退職手当等」、「短期退職手当等」に該当すると、それぞれどのような効果が生じるか。
特定役員退職手当等と短期退職手当等については、2分の1課税が廃止され、退職所得控除額を控除後の残額に対して税率が適用される。(なお、短期退職手当等は、300万円を超える部分の金額について2分の1課税を適用しないこととされている。)
③ これらの改正は、それぞれ、⑵で検討した退職所得課税制度の問題点に適切に対応したものといえるか。
5年を超えるかたちで、Bに係る仕組みと同様の仕組みが依然として成立し得るが、5年間という期間の長さを考えると、⑵で検討した退職所得課税制度の問題点に対して、一定の牽制となるのではないかと思われる。
6.企業年金課税等との関係
(略)
7.関連裁判例
(略)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
