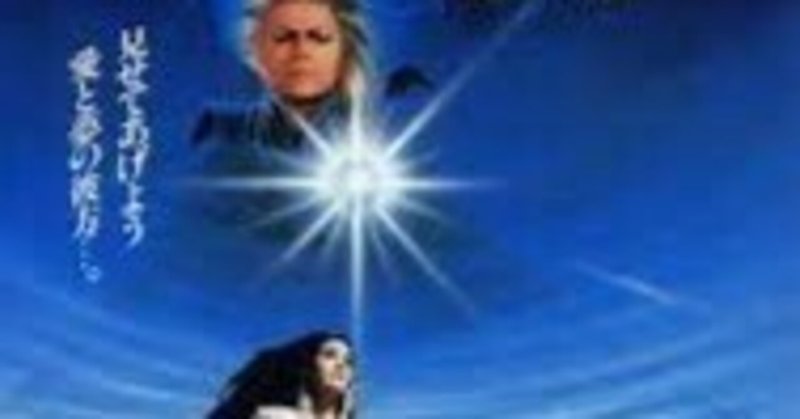
竹美映画評71 虚構が必要だった 『ラビリンス 魔王の迷宮』("Labyrinth"、1986年、アメリカ)
『ラビリンス 魔王の迷宮』を再び訪れた。本作は私にとって気になって来た映画。1988年だったか、ゴールデン洋画劇場で放送されたときの喜多嶋舞の吹き替えが印象に残っており(発音が良すぎて「トビーを返して!」が「ツォブィーを返しゅて!」になっているの!名前も「サラ」じゃなく「セアラ」だったし!喜多嶋舞への配慮が素敵!)、またジェニファー・コネリーという美少女女優(のちにはオスカーまで受賞)が冒険に出て健気に頑張る映画でもある。
おはなし
少女サラ(ジェニファー・コネリー)はおとぎ話の本『ラビリンス』を暗唱しようとするような陰キャのヲタク美少女。継母とうまくいっておらず、お出かけをする両親に弟トビーの子守を命じられて不満たらたら。「ゴブリンの王よ!お願いします、この子を連れ去って!」その言葉の通り、魔王ジャレス(デビッド・ボウイ)はトビーを連れ去ってしまう。「お願い、ツォブィーを返しゅて!」「時計が真夜中を指すまでに迷宮を抜けて城までこられれば返してやろう。来られるかなふふふふ…」。ゴブリンやその他ヘンテコな生き物が暮らしている魔界で旅の仲間を得たサラは、迷宮を抜け、無事に弟を奪還できるのだろうか。
ジェニファー・コネリーありがとう!(何か最近こういうことばっかり書いてるね私)
久しぶりに観て、長年一体何に惹かれていたのか分かった気がした。ジェニファー・コネリーだわ。ジェニファー・コネリーの存在感の勝利。ほとんど内面描写が無いのに観てる方が勝手に彼女の心情を想像してしまう。彼女にはそういう力があるの!やっぱり『フェノミナ』で鍛えて来ただけのことはあるッ(これも最近見直したけどやっぱり好き…ジェニファー…)!そして、お姫様みたいな衣装(エイリアンの卵位のサイズに見える髪の毛のボリュームが80年代!)でも着こなす。あのシーン、いいなぁ…。ジェニファーは最初っから現実感が無い。記憶をなくして普通の世界で暮らすお姫様と言われてもおかしくない。
ロック界のスーパー妖しいスターであるデビッド・ボウイは、股間もっこりのタイツに妙な(っていうか彼がやると妙じゃないのよ)メイクと髪型で、ちょっと間抜けなゴブリンの手下どもに囲まれて、気が向いたら皆でロックを歌ったりして結構楽しそうにしている。ティルダ・スウィントンにも似た彼のこの世のものとは思われない存在感のおかげで魔王役に違和感なく収まっている。
空想の世界が必要だったんだわ
私が惹かれたのは、サラの健気さと勇気だと思う。自分と正反対。実際の自分は…気が小さくて勇気や健気さも無く、勉強も嫌いなのに「自分はいい子、人から好かれたい」と願っていた(と思う)。本当は今考えても、どっちかと言えば妄想の中にいた方が幸せだったんじゃないかと思うような子供だった。冒険なんてあり得なかった。怠け者だったしね。でもどっかで、人から注目されたい、目立ちたいという気持ちもあった。歪んでるぅ!それを100%以上満たしてくれた…というか、大量の妄想の材料を与えてくれて、現実と乖離する程に妄想を膨らます結果をもたらしたのが、80年代、つまり私が小学生時代に観た様々なアメリカの娯楽映画だったの!!冒険に憧れながらどんどんうちに籠っちゃっていたんじゃないか!!
実は小学生の頃一時的に人の注目を集めるという快感を知った時期があってね、学校が嫌じゃなかった時期が私にもあるんだな。まあ、私の特徴である、調子に乗りやすさが十二分に発揮されていた時期だった。それ故に、それが全部「虚構」=私の頭の中の空想だったと思い知った小学校6年生辺りはつらかった。人から嫌われたり「お前何も役に立ってないじゃないか」「気が小さいね、もっと気を大きく持った方がいいよ」等と面と向かって数回言われるのって辛いけど、現実の自分…スポーツもできない男子、人前ではっきりとものを言わない、テレビも見てないし周囲の話題についていけないから別に面白くもない、結局調子に乗って担任教師その他の気を引きたかっただけで、担任教師が私に分かって欲しかったことは結局あの頃分からなかった。そういう自分に相応しい身の丈にあった世界が現れただけなんだから、仕方ない。むしろよかったじゃん。私に上記のようなことを言うような男子って、自分の身の丈も知らないまんま大きくなるんだろうよ(怨念すごいよねアンタ)。
『ラビリンス』は、私をどっか別の世界に導き、そこでなら自分に無い勇気や健気さが自然と発揮されるはずで、それでいて安全に帰してくれるという安心感をくれていた。虚構だよ虚構!サラがやったように、自分で「こんなの偽物よ!」と破壊しなきゃ!!!でも私はもうすでに虚構の与える麻薬にすっかりハマっていたのだった。この後もっと気が付きにくく、未だに直らない「マルクス主義」という虚構の麻薬から覚めるリハビリを要した…。
ファンタジーは、あなたを永遠に変えてしまうかもしれない、とル=グウィンは言った。
安全にあなたを元の世界に戻してくれる映画なんてファンタジーじゃないわよッ、と叱られそうだが、私にはあの安全さが必要だった。上記の通り、割と最近になってル=グウィンのファンタジー論を読んで感銘は受けたけど、実際のところ、そういうことを書けるル=グウィン、かっこいいなぁくらいのことしか思えなかったのが正直なところだ(それすらわずか2年位まえのことだが)。
アメリカ映画の与えてくれる夢が大好きだった。映画を観ていい気持ちになって、でも現実に帰って来ると…何となくぴりぴりした家の空気を横目に、どうしてアメリカの映画みたいに、普通の家みたいに仲良くないんだろう…。そんなことを考えていた。その頃は、他の家も大差ないんだって知らなかった。いい子ぶりっこしながら小心な自分を虚構で覆い隠しながら生きていたあの頃。『ラビリンス』はそういう子供時代の虚構の自分を思い出させてくれる。それが楽しくて好きだったんだよ。そのために虚構が必要だった。迷宮を抜けて、仲間と出会って助け合い、魔王を負かす。弟を取り返す。そんなのは幻想で、自分とは異質な人間のやること。身の丈に合った世界と空想の間で揺れ動いている自分がいるだけなの。まあ、いいんじゃないか。生きているから最高だ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
