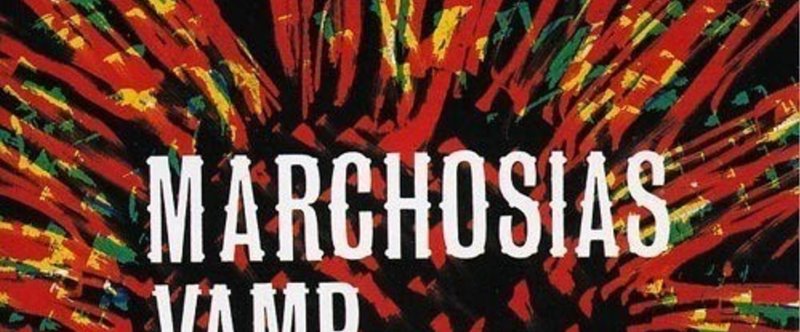
11枚目 MARCHOSIAS VAMP「PLEASURE SENSATIONS!」(1987年)
僕はイカ天ど真ん中の世代であるのに、ほとんど見たことがありません。ですが、当時マルコシアス・ヴァンプが出場したと聞いた時は驚きました。当時のマルコシは、インディーズの世界では既に実力が認められた、それなりに有名なバンドだったから。実は、この出場は3rdアルバム「乙姫鏡」のプロモーションのためだったらしいのですが、そこは実力派バンド。4代目グランドイカ天キングにまで上り詰め、メジャーデビューを勝ち取ったのでした。
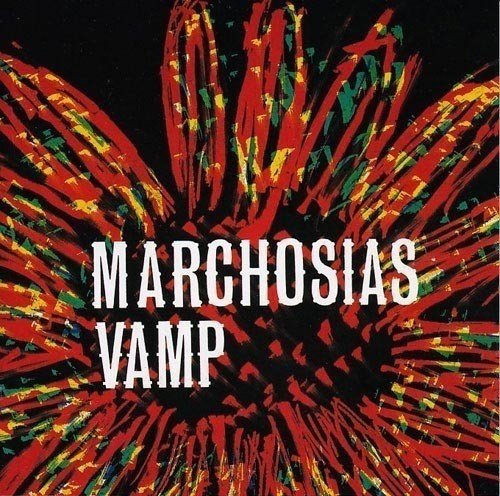
マルコシは、マーク・ボランに多大な影響を受けたヴォーカルとギターの秋間経夫の感性を中心に置くことで成り立っていたバンドでした。グラム・ロックだといわれるのはそこに理由があるのでしょう。確かに、歌詞の面ではマーク・ボランを日本語に置き換えたような難解さが目に付きますが、音楽自体はかなりヘヴィなもので、グラム・ロックが音楽面だけを捉えた言葉ではないにしろ、一概にグラム・ロックとして語ることはできないものでした。そうなったのには2つの理由が挙げられると思います。
1つは、ほかのメンバーもかなりの強者、個性派のテクニシャン揃いだったこと。ほかのメンバーのフェイバリットと演奏スタイルをざっくり書いておくと、ギターの鈴木穣はジョニー・ウィンター。ギターと格闘するかのように派手にピックを弦に叩き付け、えぐいチョーキングとビブラートを連発します。ベースの佐藤研二はジャック・ブルース。写真用の白い手袋をして(これがないと弾けないそう)、ブリブリに歪んだ音で低音を支える気などまるでない派手なフレーズを弾きまくるスタイルは、リードベースとでもいいたくなります。ドラムの石田光宏はブラック・サバス(だったっけ?)。つまり、ビル・ワードということだと思いますが、初期のミディアム・スローのヘヴィなドラミングに共通点を見いだすのは難しくありません。こんな強力な個性が集まれば、コンセプトなんてものは無用でしょう。マルコシは秋間経夫が用意した素材を、如何に料理するかという場だったのだろうと思います。
もう1つは、秋間が書く楽曲が<リフ・ミュージック>ではなかったということです。60〜70年代の英国ロックに影響を受けたバンドの多くは、シンプルなコード進行やリフを中心に組み立てた楽曲を書くことが多いのですが、秋間が書く曲は常にメロディを中心に成り立っており、言い換えれば、アコギでの弾き語りが似合うフォーク的な楽曲だと言えます。この傾向は2ndアルバムの「Destiny Calling」以降、特に顕著になります。そういった楽曲にロック的なバッキングを付けようとした時、短音のフレーズやメロディの展開に合わせたリズム・パターンの変更などが効果的になるのです(そうでない場合、ロックっぽくしようとすると、コードストロークやルートを意識したアレンジになりやすい)。これはマルコシのメンバーの持ち味そのものではないですか。秋間がそういったところまで考えて曲を作っていたわけではないと思いますが、これが他ではマネできない大きな個性に繋がったのだと思います。そして、こういった一見バラバラに見える演奏をしていてもバンドとしてまとまっていたのは、各メンバーのリズム感の良さと、ほかのメンバーの演奏をきちんと聞き分ける耳の良さがあったからだと思います。つまり、ミュージシャンシップが非常に高いということです。
1stアルバムの「Pleasure-Sensations!」は、インディーズのElephant Moonからリリースされました(後にBalconyよりCD化)。LPのA面にあたる4曲が、新宿ロフトでのライヴ録音。B面にあたる4曲がスタジオ録音。彼らの個性はこの時点ですでに確立されているのですが、以降の作品に比べるとキャッチーな要素は少なめで、ひときわヘヴィな作品といえます。しかし、ライヴでは定番の曲ばかりで、彼らの代名詞ともいえる「バラが好き」や、ライヴでは最後に演奏される(秋間のステンドグラス・ギターが点灯される)「Endless Charm」、ヘヴィながらもポップな顔を見せる「Attention Please」「My Baby Gonna Be My Dog」など、どの曲も非常に完成度が高く、2本のギターとベースの歪みがとぐろを巻くようにうねりまくるグルーヴ感は、病みつきになるというより、巻き込まれて逃れられないといった感じでしょうか。マルコシは以降も傑作を連発してきますが、どんどんソフィスティケートされていきます。このドロドロのヘヴィさはこのアルバムでしか聴けないものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
