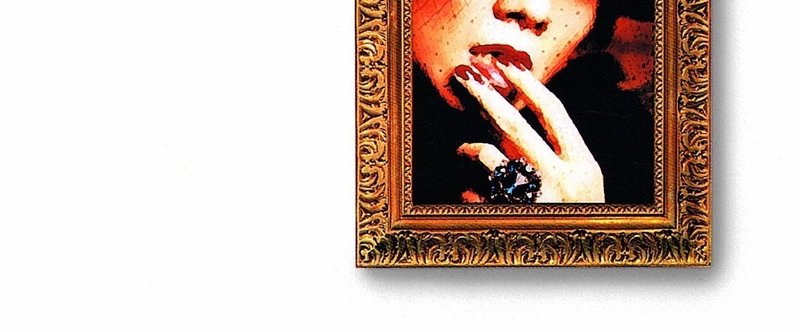
12枚目 THE YELLOW MONKEY「EXPERIENCE MOVIE / 未公開のエクスペリエンス・ムービー」(1993年)
僕が初めてイエロー・モンキーを見た時、僕は彼らの存在を知りませんでした。ライヴハウスの客席からは黄色い声。
「アニー!」・・・え、キラー・メイの?
「ヒーセ!」・・・え、16レッグスの?
「ロビン!」・・・誰だかわからないw 後でこのロビンというロンドンブーツを履いたヘタクソな<ギタリスト>がアーグポリスにいた人だと知りました。
その時のヴォーカルは元SHOCKの松尾賢一という人で、喋りがやたら上手くて面白かったのを覚えています。
そういえば、途中でヴォーカル・マイクが壊れて<これはマーク・ボランの呪いだ>みたいなことを言っていたので、1989年、ボランの命日に近い9月頃のことでしょう。
なんですか、この化石みたいな話はw

もういっこ化石級の話をしておくと、僕が再び彼らを見たのは91年でした。確か、浅草の常盤座か何かで行われたイベントで、その時、既にヴォーカルには吉井和哉、ギターには菊地英昭が座っていました。音楽性もこれまでの所謂"バッド・ボーイズ・ロック"と呼ばれていたケバケバしいものからよりポップかつグラマラスなものへと変貌し、<ベイ・シティ・ローラーズか!>と突っ込みを入れたくなるようなチェックの衣装を着ていたのを覚えています。このときの1曲目が「Suck Of Life」。これを見たときの衝撃たるや。この日のMCではもう直ぐCDが出ると話していて、それがインディーズ作品の「Bunched Birth」でした。しかし、そこには「Suck Of Life」は入っておらず、メジャーデビュー1枚目の「THE NIGHT SNAILS AND PLASTIC BOOGIE / 夜行性のかたつむり達とプラスチックのブギー」にも入っていませんでした。ちなみに、この「かたつむり」は楽曲は良かったものの、音質、ミックスともに妙に薄っぺらく、僕は2重にガッカリしたのでした。
だからこそ、僕はこのメジャー2枚目となる「EXPERIENCE MOVIE / 未公開のエクスペリエンス・ムービー」に思い入れがあるのかもしれません。ファンの間でもそれほど語られることがなく、メンバー本人たちからもそれほど思い入れが感じられないような印象があるんですが。いやいや、完成度では、イエモンの作品の中でも1、2を争う名盤であると断言しましょう。
突然話は飛びますが、僕は<J-ROCK>だとか<ロキノン系>と言われるバンドの元祖は彼らだと思っています。最初、イエモンは全く売れませんでした。彼らがメジャーデビューしたタイミングは最悪で、1992年はイカ天を頂点としたバンドブームは下降線を辿り始め、B-ing躍進の象徴であるZARDや小室ブームのきっかけとなったtrfはまだデビュー前。渋谷系もまだ出現していません(これらは93〜94年に一気に躍進します)。そんなエアポケットのようなタイミングで、既にブームが去った古臭いロックンロールバンドがデビューしても、売れるわけがありません。メジャー4枚目となるアルバム「smile」であえて売れ線を狙うことによって少しずつ一般的な人気を獲得していきますが、吉井がそういった売れ線曲を作る時に使ったのが<歌謡曲>のエッセンスでした。
90年代の半ばには<昭和歌謡>なる謎のブームが巻き起こりますが(個人的には<昭和歌謡>は90年代以降に歌謡曲を模して作った音楽で、本来は昭和の時代の歌謡曲を指す言葉ではないと解釈しています)、それに先駆けて歌謡曲への愛情を示していたのが吉井和哉でした。実は、これはシーンの中で大きな転換点だったのではないかと、後になって気がつきました。彼らのコロムビア時代のプロデューサーである宗清裕之が80年代後半に手がけていたバンド、Red WarriorsのシンガーであるDiamond☆Yukaiは、当時歌謡曲を痛烈にディスっていましたが(そして、乙女塾系アイドルCoCoの三浦理恵子と結婚するというw)、それは80年代のロックバンドの共通認識でした。まだまだ元気だった歌謡曲(ニューミュージック含む)のような<売るための音楽>に対して、ロックを如何に差別化して、商業主義と決別するかということは大切な命題だったのです。もちろん、メジャーデビューした時点で商業主義に乗っているのですが、当時のロックはまだまだ反抗のための音楽として存在していたということですね。それが、バンドブームという超商業主義に呑まれ、90年代半ばに差し掛かろうという頃には、ロックの反抗心はすっかり薄れ、商業主義だなんだというこということも言われなくなりました。そんな中で、商業音楽の代表とも言える歌謡曲への再評価が始まるわけです。それは主に<渋谷系>(とそこから派生するDJ文化)のムーヴメントを通して行われていきましたが、その裏でロックバンドへの影響は、THE YELLOW MONKEYというバンドを通して着実に浸透していったのではないかと思います。そして、ロックバンドの醍醐味であるプレイヤー同士でせめぎ合うような演奏や、演奏の熱量なんかよりも、イエモンのヒット曲で聴けた歌謡曲に影響を受けたポップなメロディや、こみ上げるような美メロをもった<J-ROCK>が生まれるわけです。イエモンを筆頭に、そういったバンドたちをいち早くプッシュし始めた雑誌が「ROCKING ON JAPAN」であったことも、それに追い打ちをかけたのでしょう。
95年に出た4枚のシングル「LOVE COMMUNICATION」「嘆くなり我が夜のFantasy」「追憶のマーメイド」「太陽が燃えている」は、どれも歌謡曲テイストが濃厚に出ています。その頂点はその2年後の「Burn」だと思いますが、その原点はというと、93年のこのアルバム「未公開のエクスペリエンス・ムーヴィー」に収録されたシングル曲「アバンギャルドで行こうよ」でしょう。そのキモはストリングスの使い方で、特にイントロ部分のフレーズとしてのストリングスはトニー・ヴィスコンティ的な、もっと言えば、ボウイの「Ziggy Stardust」で聞けるようなキャッチーさを感じさせるアレンジがされています。イエモンはメジャーの1枚目からストリングスを入れてきましたが(しかも1曲目でした)、ロックバンドの場合はオーケストラ的な弦の使い方はしても、オケとしての4ストリングスみたいな使い方はほとんどしないのです。おそらく、吉井は歌謡曲的なストリングスをイメージしたのだと思いますが、このあたり、プロデューサー宗清氏とどんなやりときがあったのか気になるところです。続くシングル「悲しきAsian Boy」も「熱帯夜」も歌謡曲の影響が濃厚ですが、歌詞の面でまだ退廃的、倒錯的なイメージが残っているため、それ以降の作品と印象が異なります。実は、彼らの世代にとっては、ロックと商業主義はまだ相容れないものだったのかもしれません。だから、かなりベタに歌謡曲っぽさを取り入れることによって、売れ線を狙うための隠れ蓑(というか言い訳)にしたのではないでしょうか。つまり、自分たちが子供の頃に聴いたルーツの1つとしての歌謡曲とロックの融合であると(ただし、吉井はデビュー時から歌謡曲のエッセンスを取り入れようとしていた節もあります)。この時期はまさに彼らにとっての転換点で、歌謡曲からの影響が強くなるほどに、初期に顕著だった「ジギー」期のデイヴィッド・ボウイからの影響が薄くなっていきます。
すいぶん遠回りしましたが、アルバムの話をしましょう。このメジャー2枚目となるアルバムは、歌詞の面では、同性愛、性転換などの倒錯的なイメージを強く打ち出していて、楽曲もそれに応じてダークでシアトリカルなイメージのものが多い印象です。アルバムを通して場末の劇場や、サーカスのピエロのような裏社会で生きる人間の悲しみや苦しみのような、狂気に近い感情が溢れています。1曲目はイントロにかぶせた女性のナレーションでスタートします。これは、デイヴィッド・ボウイの「スケアリー・モンスターズ」のオープニングからアイデアを拝借したのでしょう。「Donna」「4000粒の恋の唄」「フリージアの少年」「シルクスカーフに帽子のマダム」など、暗くスローな曲には狂気と背中合わせに祈りのような救いを求める感情が込められ、アップテンポの「Vermilion Hands」や「審美眼ブギ」のようなグラマラスなブギーは、感情が少し暴走しています。アマチュア時代からの代表曲「Suck Of Life」は、やはりデイヴィッド・ボウイの「Rebel Rebel」をマイナー調に転化したような曲ですが、名曲であることに代わりはありません。
このアルバムはどの曲も本当にクオリティが高いのですが、中でも感銘を受けたのが「フリージアの少年」です。ピエロか旅芸人か分かりませんが、少年の深い悲しみと彼が歌う歌にこめられた夢のような希望のコントラストが、楽曲の構成や演奏に見事に反映されているからです。イントロからAメロでのマイナーコードのところでは、現実を見つめた深い悲しみを歌い、ウラを強調したヘヴィなリズム(若干コンパスポイントっぽいか)がそれを強調します。サビからギターソロにかけてのメジャーコードの明るい響きのところが、少年の歌の部分に相当します。ここでドラムとベースが生み出すリズムは4ビートなのにまるで3拍子のワルツを踊っているかのようにドリーミーに響き、ギターソロは優雅なダンスを思わせるほどに華麗なフレーズを歌います。それらはヴォーカルが歌う世界と見事に一致しているのです。ヴォーカルの気持ちの入り方も、他の曲より深く聞こえます。フリージアの花言葉は「無邪気」「純潔」「あこがれ」など。もしかしたら主人公の少年は、少年時代の吉井和哉そのものなのではないでしょうか。このアルバムはほかにも見事な演奏がたくさん聴けますが、トータルで見た完成度ではこの曲がいちばんだと思います。
そして、このアルバムの最後に収録された「シルクスカーフに帽子のマダム」の主人公、マリー(ジャケットで吉井が扮しているのがこのマリー)は、次作「Jaguar Hard Pain 1944~1994」の主人公、ジャガーの恋人であるという設定となっており、この2作は連作であると見ていいかもしれません。こういったコンセプト・アルバムを作ること自体がアートな感性の発露であると考えるならば、イエモンが真にロックだった時代はこのあたりまでとみていいのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
