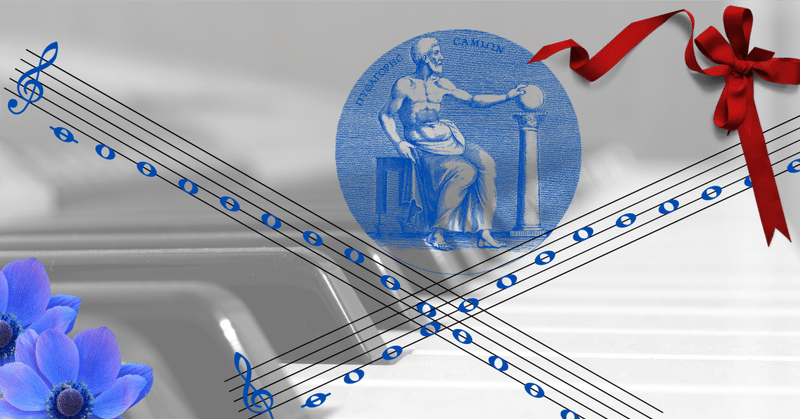
ソクラテス以前の哲学
哲学の始まりとしてのミレトスの自然哲学派
伝統としきたりを重んじるギリシャ本土の各都市よりも、それらに縛られない植民地の方が自由な発想ができたのであろう。
ギリシャ本土の対岸ミレトス都市は、そのような自由な雰囲気の植民地であったと思われる。 紀元前6世紀初め頃、ミレトスに生まれたタレスは万物の元のものは何であろうかと思い悩む。「万物の根源は水である」というのが結論である。彼は生命の維持に最も必要なものは何かと考え、この結論に達した。彼は水にまつわる様々な現象も観察した。
タレスの次の哲学者、アナクシマンドロスは、万物の根源は何かということよりも、万物がいかに対立物によって構成されているかと言うことに思い悩んだ。例えば「昼の明るさ」と「夜の暗さ」、「夏の暑さ」と「冬の寒さ」などがそうである。彼はこのような現実世界の対立物を超えた根源的な「無限なもの(アペイロン)」が存在するであろうと想定した。
この学派の中からあのピタゴラスが生まれてくる。彼はあのピタゴラスの定理として有名な数学者であったのではない。彼は若い頃サモスで哲学を修め、政治改革にのり出す。その試みは成功を収めたかのように思われるが、彼の支持したポリュクラテスが次第に独裁者になるに及んで、彼の政治改革は失敗する。
ピタゴラス教団が西欧思想に大きな影響
以後、 30年間、彼は各地を渡り歩く。南イタリアのクロトンに居を定め、そこで密議の学校として「ピタゴラス教団」を組織する。この教団では、男女平等を保ち、肉食を断ち、沈黙のうちに自己の魂を見つけることが求められた。それは人間の「神的本性」を回復するためであると言う。そのため、「知(ソフィア)」を求め、それによって本来の純粋な存在に立ち帰ることだという。ピタゴラスの教えは、その後の西欧思想に大きな影響を及ぼす。たとえば近代のコペルニクスの「宇宙論」、ケプラーの「宇宙論」も、古代ピタゴラスの思想の影響を受けていると伝えられている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
