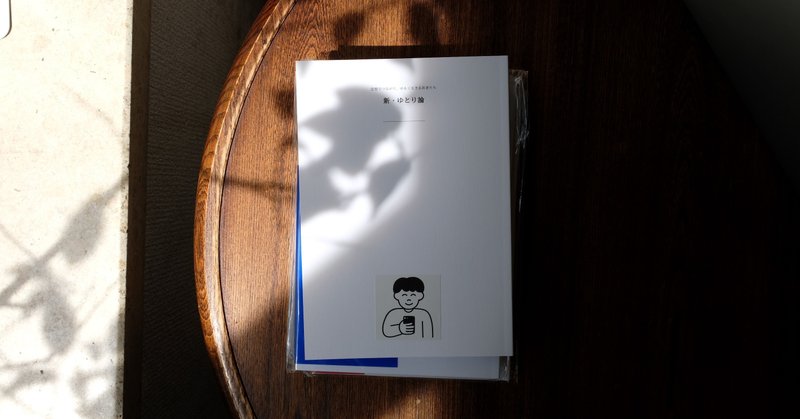
「ゆとり本」発売から1年が経ったので全文公開します
平成最後の4月23日。「新・ゆとり論〜思想でつながり、ゆるく生きる若者たち〜(通称、ゆとり本)」の発売イベントを開催しました。あれからちょうど1年。「ゆとり本」はすでに完売してしまったのですが、今こそなんらかの生きるヒントになるんじゃないかと思って、全文を公開することにしました。なお、原稿やリンク内容は当時のままを踏襲しており、もしかすると現在は事実が異なるものや、非公開になっているリンク先などがあるかもしれません。そのあたりは昨年時点のものだということでご理解をお願いいたします。
はじめに
僕は平成3年に生まれ、「ゆとり世代」ど真ん中の時代を生きてきました。私立の中高一貫校を卒業し、大学では医学部を卒業しておきながら、なぜだか夢中になったファッションを突き詰めようと業界紙で記者になり、今はフリーランスの編集者として仕事をしています。はたから見ると「ゆとり世代」のイメージにもれず、自由に生きているなと思われるかもしれません。
そんな僕が本書を書こうと思い立ったきっかけは、同世代の起業家への取材を通して、共通する悩み・違和感を抱えている人たちが一定層いることに気付いたからでした。それは「インタビューをされても、自分の思いが伝わらないことがある」ということ。彼らがどんな思いで起業したのかとか、その会社がどんな人を救うのかとか、同じ思想を持つからこそ自然と汲み取れた、彼らの根底にある「思想」が、一般的には理解されがたいのかもしれないなと感じたわけです。そして、そのギャップの背景には「ゆとり」という言葉の壁があるのではないかと。
「ゆとり」といえば「根性がない」「礼儀がない」などと、ネガティブな論調で語られることも多い一方で、「ゆとり」だからこそ新しい生き方を実践していたり、固定観念を覆すようなビジネスを始める人が増えているような気もします。本書では「ゆとり」を「思想」と捉えることで、世代論では語りきれていない価値観や思想が見つかり、もしかすると、これからの新たな時代を生きる全世代の人に対して、何らかのヒントになるかもしれないと思ったのです。
きっと「ゆとり」に正解はないだろうし、「ゆとり」を言語化すること自体ナンセンスだと思われる方もいるかもしれません。それでも、今を生きる人々の中にある思想を言語化し、ジャンルやカテゴリーを超えてつなぎ合わせていくことは、とても貴重な作業だと思います。そして、それは新しい時代を迎えようとする今、平成が終わるまでにやっておかなければいけないなと直感したのです。
本書は「若手起業家を特集したビジネス書」でも「若者の手引き」でもありません。「ゆとり」という思想が、あなたのキャリアやビジネス、人生において、なにかを考えるきっかけになれば幸いです。
すみたたかひろ
第一章 「ゆとり」を生んだ平成
平成とゆとり教育
「ゆとり」という思想を考える前提として、ゆとり世代について平成という時代とともに少し振り返ってみようと思います。なお、本書には「ゆとり世代」と「ゆとり」という表現が今後数多出てきます。前者は一般的な世代論としての若者を差し、後者は「ゆとり世代」を通して見えてきた、あらゆる世代の人々が持つ概念・価値観というニュアンスで使うことにしました。
「ゆとり世代」というのは非常に曖昧な概念です。ざっくり定義するならば「学生時代にゆとり教育を経験した世代」でしょうか。このゆとり教育というのがまた厄介で、かなり長期間にわたる試行錯誤の結果、徐々に形を変え、気が付けば2011年の新学習指導要領の施行とともに消えてしまった教育方針だというのです。
1970年代から「教科内容の精選」が盛んに行われ、1977年の学習指導要領の改定によって「ゆとりの時間」が誕生。その後、幾度もの改正を重ねながら、2002年の完全学校週5日制の実施や「総合的な学習の時間」の創設(平成14年度の文部科学省の指導要領)にいたるまで、段階的に施行されてきた一連の教育制度のことを指すそうです。1987年〜2003年生まれの人々が、小中学校のどこかでゆとり教育に触れている計算になります。
ゆとり世代といえば、勉強ができない、決断力がない、マイペースなどと批判的なキーワードがいくつも語られますが、ゆとり世代をひとまとめに説明することは難しく、学習時間の短縮や教科書の簡略化をゆとり世代と結びつけて批判するのは、短絡的すぎるように感じます。
ただ唯一、成長期に東日本大震災を経験しているということは、ひとつの共通した大きな契機となっているように思います。もちろん社会全体が大きく変わるきっかけになっているわけですが、自分の人生を左右する多感な学生時代に震災を経験し、その後の人生・思考が大きく変わったという人がこの世代には圧倒的に多い。不景気だとか就活がうまくいかないだとか、そうした連続的な社会情勢よりも、一瞬にして起こった固定概念の破壊こそが、唯一世代を通じて何かしらの影響を与えた事象なのかもしれません。
ゆとり世代と似たような表現に「ミレニアル世代」があります。一般的には団塊ジュニア世代の子どもの世代、平成初期に生まれた世代を指すそうです。この「ミレニアル世代」という言葉は企業マーケティングにおけるターゲット像として頻繁に出てくるのですが、ミレニアル世代を一括りに「これからの消費行動の指針となる若者世代」としてしまっていることにも大きな疑問を感じます。僕は2018年の末にテクノロジーの進化を見るために中国・北京へ取材に行ったのですが、そこにある大手IT企業の平均年齢は、なんと28歳。僕と同じ世代が今や中国社会の中心にいて、彼らが未来を作っていたのです。これは僕自身かなりのカルチャーショックで、ミレニアル世代という区分自体が中国では「社会を構成する中心世代」となっていたのです。ミレニアル世代を若者と定義して捉えていてはもう遅いのではないかと実感したのでした。
いずれにせよ、すでに世の中にはゆとり世代・教育に対する考察や議論が数多くなされていますので、ゆとり世代・ミレニアル世代に関する話はこれ以上しないことにします。ただ、冒頭で一つだけ言っておきたかったのは、長く断続的な制度をもとに「ゆとり」を世代論で定義することはあまり賢明ではなさそうだということ。そして、実際にゆとり教育を経験した僕たちの世代は、幼少期に受動的にこういった制度を経験しているわけで、価値観として影響を与えているであろう「ゆとり教育」自体に対する記憶はそれほどはっきりしていないのです。
インターネットに囲まれた日常生活
連続的な社会背景として僕たちの価値観に影響を与えているものがあるとすれば、それは間違いなくインターネットの隆盛でしょう。1990年代に日本でインターネットが誕生し、1996年にはYahoo! JAPANがサービスを開始。2000年にはGoogleやAmazonがサービスを開始しました(デジアルアーツ「日本におけるインターネットの歴史」)。2000年以降はテキストコンテンツから写真、動画とどんどん進化をたどって、前略プロフにはじまり、mixiやAmebaブログ、Facebook、TwitterといったSNSが次々と登場しました。震災をきっかけにLINEが生まれたのが2011年。ここでも震災は大きな起点となり、その後のコミュニケーションのあり方を大きく変えたのでした。
インターネットやSNSの台頭によって、誰もが個人単位で直接つながり、コミュニケーションをとれるようになりました。SNSではアカウントをいくらでも作れるため、実名だったり匿名だったり、趣味に応じてアカウントをわけたりと、いろんな自分を演じることが可能になりました。最近では自分自身をベースにオンライン上で別人格・仮想現実を作ることができるZEPETOのようなアバターサービスも話題になりましたが、こうしたインターネット上で自分とは別のキャラを形成する「別アカウント」という考え方は、ゆるいつながりで複数の顔を持つという点で、現代のキャリアなどあらゆる側面に広がっている思想でもあります。
このインターネット上の仕組みが2010年以降、あらゆるビジネス構造をも変容させつつあります。具体的には、消費者と生産者がダイレクトにつながることが可能になり、いわゆる「代理店業」のような中間をつなぐ既存産業が厳しい時代になってきました。お店に行かなければ買えなかった商品はインターネットですぐに見つかるし、工場から直接商品を消費者に届けることだってできる。2013年にスタートしたフリマアプリ「メルカリ」の利用者は今や月間1000万人以上ですし、自分で作った商品を販売できるECサービスのBASEを利用するショップ数も70万を突破しています。今や誰もが生産者であり消費者であるのです。主客逆転ではなく主客混合。これも大切な現代ならではの思想でしょう。
小さなメディアが生まれた
こうしたインターネット構造の影響を受けるという点では、メディアも例外ではありません。誰もがSNSを通じてリアルタイムに情報を発信・享受できる、しかも自分の趣味にあった情報だけが勝手に提案されるような便利な時代において、これまで莫大な発行部数を抱えていた有名雑誌が廃刊になり、大手出版社が倒産するという事態が起きています。「速報を見るならTwitter」ともいわれる時代のメディアの存在意義とは何なのでしょうか。
個人的には、それは「キュレーション力」に尽きると考えています。消費者はもはや情報を見抜く力を自然と持っているので、それでもほしいと思える情報を提供してくれるメディアなのかどうかが問われるというわけです。よく考えると昔の雑誌となんら変わらない視点なのですが、個人ですらキュレーションができる時代に、プロによる「キュレーション力」こそ試されているのではないかと思うのです。
だからこそ、よりニッチだったり、これまで光が当たらなかったような場所を見つけ出して、そこにある小さな声を拾うメディアが増えてきました。先入観に縛られない「ニュートラル」な視点を提案するメディア「NEUT Magazine」や小さな声を届けるウェブマガジン「BAMP」、障害や難病、LGBT、貧困、格差の中の子どもなど「社会的マイノリティー」の人々が持つ可能性が広がる瞬間を捉える「soar」などなど、それぞれが決してマスに響くわけではないけれど、届けるべき読者が見えていて、彼らに届けたい情報を地道に発信する、職人気質のメディアと言えるでしょう。肩書きも年齢も関係なく趣味嗜好でつながるSNSのあり方とも同じで、本書のテーマでもある「世代ではなく思想でつながる」という考え方を体現しているのが、こうした小さな声を拾うメディアだと思います。最近では、2014年にスタートしたブログのような投稿プラットフォームnoteが日本経済新聞社と共同コミュニティ「Nサロン」を立ち上げるなど、大手と新興メディアが手を組む事例も出てきました。メディア業界も変わり始めたのです。
音楽や映画、アートなどのカルチャー情報を発信するCINRA, Inc.から生まれた自分らしく生きる女性を祝福するライフ&カルチャーコミュニティ「She is」も、テーマを絞ることでファンを集めることに成功しているメディアの一つです。「She is」を立ち上げたのは編集長の野村由芽さんとブランドリーダー兼プロデューサーの竹中万季さん。女性のキャリアやライフスタイルについて悩んでいた自分たちの思いを形にしたメディアです。
竹中さんはこうしたインターネットという時代背景について「同じ年齢の人のなかでも、インターネットに触れたタイミングやその深度が近しい人とは価値観をわかち合えることが多い気がしている」と話します。竹中さんは幼少期からインターネットに夢中になる一方、当時はまだまだマイノリティーな存在だったため、「オタクだと思われたくなくて好きなことを隠していた」そう。「『She is』のアンバサダー的な存在でもあるGirlfriendsの方々に会うと、同世代で昔からインターネットにのめり込んでいた人が多くて驚きました」と。
たしかにインディー音楽やインターネットのような当時のサブカルチャーはまだまだマイノリティー的な存在でした。それに対して今はSNSによって同じ趣味を持つ人を見つけやすい時代。もはやマイノリティーであることが個性とも呼べる時代です。だからこそ「以前よりも、個性を打ち出すことができなければ目立たない、という意味での生きづらさもあるでしょうが、SNSがあることで、どこかにいる同じ趣味を持つ人との出会いが増えるという意味では、恵まれた時代なんじゃないでしょうか」と竹中さんは語ります。インターネット黎明期を経験してきたゆとり世代にとって、インターネットという存在は共通の価値観を見出す重要な場所だったわけで、そうした場所に早くから触れてきた人たちが今の起業家やクリエイターに多いというのは納得ができます。
代々木上原に銭湯付きコワーキングスペース「BathHaus」を作ったIT業界出身のプロデューサー兼デザイナーのroseさんも、とある取材(CAREER HACK「あの頃のインターネットを求めて。ぼくらが「リアル」に見出す、ニュートラルなつながり」)で「学校ではバカにされるからとインターネットオタクであることを隠していましたが、ポーランド留学時にサハラ砂漠のど真ん中で知らない人とFacebookを交換したのが衝撃的で。封印していた気持ちが解放されました」と話していました。かつて教室の中では肩身の狭い思いをしたかもしれない、インターネット黎明期にその魅力に気付いた先人たちが、インターネットを使って趣味嗜好でつながる今の社会を作りあげているのです。

「She is」公式サイト(https://sheishere.jp/)から
平成最後の何がエモいのか
2018年夏に「平成最後の夏」というバズワードが生まれました。ゆとり世代、特に平成生まれにとってはじめての改元で、しかも今回は天皇の崩御ではなく前もってそれがわかっているというかなり異例のケース。そんな時代背景もあって「平成最後の夏」という言葉が生まれたわけですが、これに関連して「エモい」という単語に触れないわけにはいきません。
マイナビティーンズが昨年11月に発表した「2018年10代女子が選ぶトレンドランキング(コトバ篇)」において堂々の一位に輝いた「エモい」という言葉。10代に限らず、昨年はとにかく多くの若者が「エモい」という言葉を連発した一年だった気がします。「エモい」という言葉の意味はすごく曖昧ですが、一般的には「感情が高まって強く訴えかける心の動き」というような解釈が多いようです。
こうした社会情勢に対して「2018流行語『エモい』は感性も語彙力も低下させる」という記事(Business Insider Japan 2018年11月28日)が話題になりました。「思考のチャンスを『ヤバい』で失い、感情表現のチャンスを「エモい」で失う。何が残るというのだろう」と。僕はこの問いかけに少し違和感を感じました。
僕が考える「エモい」とは「人が共感できる感情やストーリーがある状態」です。例えば、引退したばかりの安室奈美恵の曲を聴いて誰もが「エモい」と思うのは、みんなが昔聞いたことのある大衆的な曲だから。一方で、朝日を見て「エモい」と感じるのは、朝日になんらかの思い出・ストーリーがあるからで、朝日を「エモい」と思うかどうかはその人の経験によるのです。
だから、そもそも「エモい」の使い方がみんな正しいという前提で(正しい使い方なんてあるのかわからず、定義する時点でダサいのですが)、若者が「エモい」を多用するということは、それだけ語りたい・共感してほしいストーリーがあるということじゃないでしょうか。そして、他人がどこに「エモさ」を感じるのか、それによって共感ポイントを探るのです。「エモい」を使う背景にいろんな思い出があって、それを共感してもらうためのある種の共通言語として「エモい」という単語を形骸的に使っている。「エモい」という言葉自体に具体的な意味はないし、そのニュアンスは状況によって変化するのだろうなと考えました。
出張撮影サービス「ラブグラフ」を創業した代表の駒下純兵さんも同時期にこんなツイートをしていて、ひどく納得したことを覚えています。
インスタ映えは写真として綺麗さにフォーカスするのに対して、
エモい写真は背景のストーリーにフォーカスする。
目に見えるものに価値を見出すものがインスタ映え。
目に見えないものに価値を見出すものがエモい写真。
ただ、同記事内に書かれていた「ビジネスの潮流は逆、感性の時代が来る」ということには全くの同意で、感情やストーリーを通して人がつながる「感性」の時代だからこそ、言葉だけではないコミュニケーション方法に着目すべきだと思ったのです。Instagramによって確立されたビジュアル・コミュニケーションもその一つですが、今は言葉すら介さなくても写真一枚で感情を動かせる時代だと考えれば、むしろ未来は明るいんじゃないでしょうか。
さて、第一章の最後に「平成最後」と「エモい」に関連して、イベントを二つ紹介したいと思います。一つが大阪にあるミレニアル世代に人気のホテルHOTEL SHE, OSAKAで8月末に開催された「平成ラストサマー」という宿泊体験付きの音楽フェス。もう一つが稲沼竣さん・峯尾雄介さんによる「平成が終わルンです」という写真展です。これらは「感性」の時代に「エモい」事象に共感する人々が集まり、ビジネスになるのだと感じた事例でもありました。
HOTEL SHE, OSAKAは1996年生まれのホテルプロデューサー龍崎翔子さんが生み出したホテルで、人やモノ・情報の媒介としてホテルが存在する「ソーシャルホテル」という概念を提唱しています。イベントもまさに人と人を媒介する重要なファクターとして同ホテルでも数多く開催されているわけですが、「平成ラストサマー」に関して龍崎さんは「(趣味が細分化される中で)『平成が終わる』というイベントが、もしかしたら全世代的な最後の熱狂になるんじゃないか。若者期の終わりのような気がして、なんだかエモいんです」(WWDジャパン「『平成最後の夏』はなぜ若者を惹きつけるのか、ホテルプロデューサー龍崎翔子&roseに聞く」)と語っています。クラウドファンドで販売した宿泊券付きのチケットはすぐに完売し、趣味嗜好が細分化されたこの時代に同じ価値観を持つ仲間を見つけるための場所としてホテルが機能することを証明するイベントになりました。

「平成ラストサマー」の様子(PHOTO BY モリシタヨウスケ)
後者の「平成が終わルンです」は、稲沼竣さん・峯尾雄介さんが製作するTシャツ「平成ゆとりTシャツ」に関連したイベントで、Tシャツ購入者に対して100人限定で「写ルンです」を配布し、平成最後の夏の日(8月31日)の日常を撮影してもらうというもの。撮影に用いた「写ルンです」を回収し、一般の人々が切り取った飾らない写真を展示する写真展を10月に富士フイルム ワンダー フォト ショップで開催しました。結果、会期中には1000人を超える人々が訪れたようで、しかも来場者のほとんどが知り合いではなく、偶然Instagramでイベントを知った人だったといいます。
イベントを主催した稲沼さんは「脳内アーティスト」を名乗るドレッドヘアの謎多き人物。コミュニケーションをテーマにした「喋るTシャツ」というTシャツブランドをやっており、「平成ゆとりTシャツ」もその中の企画でした。具体的には共通の話題になりそうなロゴを入れたTシャツを作っているのですが、「平成ゆとりTシャツ」では生まれ年を自動生成できるサイト「平成アイコン」と、それを胸元にプリントしたシンプルなTシャツを販売したところ、1万5000枚を超える画像が作成され、Tシャツは再販を含めて1200枚以上が売れたといいます。それだけで売り上げは100万円以上。平成最後の日・4月30日にも抽選で「写ルンです」を配布するそうですが、今回はなんと1000人。平成が終わった7月19~31日に「hotel koé tokyo」など三会場で写真展をするそうです。
このように、イベントやプロダクトといった言葉ではない共通言語を生み出すことで、共感を集められるというのは非常に現代らしい手法なのだと感じたのでした。この「エモい」は一例でしかありませんが、インターネットやテクノロジーによって一度機能化・効率化を目指した世の中において、ある意味対極にある「感情」を行動指針とするような流れが確立されはじめており、平成はまさにその移行期間であったのかもしれません。

生まれ年を自動生成できる「平成アイコン」
第二章 「ゆとり」が暮らす今
多様性よりグラデーション
インターネットによって価値観や共感をベースに個々がつながる時代。一言でいえば、平成とはそんな時代だったのではないでしょうか。第二章ではこうした時代に生きるゆとり世代の今を探るべく、キーワードやテーマに合わせて彼らの日常を深掘りしていこうと思います。
まず、ここ数年、プロダクトもサービスもより個人のニーズに合わせて細分化され、個にフィーチャーされることとなりました。まさに「リコメンド」「キュレーション」という、インターネットによる効率化の恩恵を受けているわけですが、そんな現代において重要なテーマの一つが「多様性(ダイバーシティ)」でしょう。ダイバーシティといわれると渋谷区から始まり、今や全国の都市に広がりつつあるパートナーシップ証明書やLGBTQ+の話題を思い浮かべがちですが、もっと広く、一人ひとり育ってきた背景が違うからこそ、同じ人間はいない、いろんな意見があって当然だというふうに論点に広げて考えると理解しやすいのかもしれません。最近では「多様性」とともに「グラデーション」という言葉が使われるのをよく目にします。僕はこの言葉がすごく好きです。
本書の編集担当でもある若尾さんは以前note(これからの時代に必要だと思う、「グラデーション」の思想)にこんなことを書いていました。
少数派って何?ほとんどのことは、白黒つけられるものじゃないのだ。私たちが簡単に世の中を認識するために、便宜的に「言葉」によって分類されているだけ。
自分自身を含めた誰しもが、様々な軸の「グラデーション」の中にプロットされている曖昧な存在でしかない。そう気づくことこそが、「自分も他者も生きやすくなる世界」、ひいてはダイバーシティなるもののスタート地点だと思うのです。
最も重要なことは自分自身もグラデーションの一部であると気付くこと。この考え方は、LGBTQ+やフェミニズム、多様性をテーマにしたメディア「Palette」を運営する編集長の合田文さんからも教わりました。「人をジェンダーや見た目などの記号で判断しないことは、今やビジネスマナーでもあります。ギャルだから礼儀を知らないとか、男性だから絶対女性が好きとか、女だから結婚したいのだろう、とか。そうではなくて、人として人を見て、関わっていくということを大切にできたらいいなと思っています。よく『どうやってマイノリティーを受け入れていくべきか』と聞かれますが、その時点で自分は受け入れる側、そしてマイノリティーが受け入れられる側、と壁を作ってしまっているかもな、と。自分だってグラデーションのどこかにいるだけだ、ということに気付くことが大切だと思っています」と合田さん。
性的マイノリティーを指すLGBTQ+ではなく、異性愛の人なども含め誰もが持つ属性であるSOGI(Sexual Orientation and Gender Identity:性的指向と性自認)という言葉もあって、これはマイノリティーのみに配慮するのではなく、性のあり方の問題はすべての人の平等や人権に関するものだという考え方に基づいています。「たとえば誰かがゲイだという情報は、埼玉県出身だということと同じくらいの、至極当然な情報として受け取られる世界が来たらいいですよね。出身地が違うのも、性のあり方が違うのも当たり前じゃん」と。とりわけゆとり世代にはそういった考え方を持つ人も多いのですが、これはインターネットの普及による発信のしやすさや、自分と考え方や個性の近いコミュニティの見つけやすさが大きな理由となってくるのではないかと考えられます。
恋愛、結婚、家族の自由化
そんなグラデーションという観点から、システム化されたあらゆる社会制度への疑問が生まれたのものこの時代です。ここでは恋愛や結婚などライフステージに関するテーマについて考えてみたいと思います。
10年前には「出会い系サイト」と言われて、いかがわしいものだというレッテルを貼られていたオンライン上での出会いは今や「マッチング」と呼ばれ、一般化しました。特にエウレカによる「Pairs」やイグニスによる「with」など、IT企業によるサービスが数多く生まれ、立教大学経営学部とネオマーケティングによる2018年の独自調査(立教大学経営学部の春学期科目「eビジネス&マーケティング」を受講した学生とマーケティング支援のネオマーケティングによる調査(2018年7月12~17日、全国の20~39歳の未婚の男女が対象))によれば、マッチングアプリの利用状況はなんと21.5%。5人に1人がマッチングアプリを使っている計算になります。恋愛に限らずとも、ビジネスマッチングサービス「yenta」などのサービスが続々登場しており、「マッチング」は現代における重要なビジネスの要になっています。インターネットにおけるレコメンデーション機能もユーザーと情報のマッチングですし、「メルカリ」のようなCtoCサービスも需要と供給をマッチングする仕組みだと思えば、納得がいくはずです。
こうした動きを恋愛の「自由化」と名付けるのであれば、それは結婚においても同じことが起こっています。2018年の11月22日、Twitterで「#結婚式に自由を」というハッシュタグが話題となりました。火付け役は自由なウエディング提案を行うCRAZY WEDDINGで、既存の結婚式に対する議論が相次ぎました。事実、僕のまわりでも結婚式をフェスのような自由参加型にしたり、結婚式資金をクラウドファンディングで集めたり。これまで考えられなかったようなアイデアも次々と生まれています。
CRAZY WEDDING創業者の山川咲さんは時代背景について「自分自身が25歳で結婚式を挙げたこともあって、今までの結婚式を求める層もたくさんいる一方で、既存の商業的な仕組みに違和感を感じる人が少なからずいることに気がつきました。新郎新婦が主人公となる非日常的な結婚式よりも、形式通りじゃなくてもいいから、フラットな関係で本心から人生を祝えるような『温度感』のある結婚式を求める人が増えたんです」と語ります。ある種のブラックボックス状態だった結婚式ビジネスの裏側や過去の口コミをインターネット上でいくらでも知ることができる時代に、あえてお金をかけてイベントをやるのなら、自分たちとゲストが本当に満足できる形にしたいと思うのは至極妥当な考えだと思うのです。
その延長というべきか、ほんの少しずつ「家族」のあり方が変わってきていることもたしかです。これまで「結婚」といえば「永遠の愛を誓うもの」で、「家族」は「一生添い遂げるもの」だったのかもしれませんが、例えば、離婚をポジティブな選択肢として捉えたり、血のつながりではなく思想を持って家族を定義したり。「WIRED CAFE」などで知られるコミュニティ企画会社カフェカンパニーで働く永井あやかさんは、自身のnote(わたしの新しい家族記念日。)で「両親の結婚記念日。わたしが25歳を迎える年。わたしは妹と一緒に、両親に「離婚」という選択を提案しました」と公表しました。家族のあり方を模索する中で「子育てを終えた両親にも、ひとりの人として、もっともっとこれからの人生を生きる上での大切な関係があるのではないか」と考えたそうです。内閣官房シェアリングエコノミー伝道師の石山アンジュさんも、渋谷キャストのアパート「Cift」での約60人のクリエイターと共同生活を通じて、「拡張家族」(詳細は石山さんのnote「新しい家族のかたち『拡張家族』。 働き方の次は、家族観を見直していこう。」を参考)という、血のつながりを超えた新しい家族の形を提唱しています。複数人でルームシェアをする若者も増えていますが、これもひとつの家族の形なのかもしれません。
最後に「自由化」という観点から「性」についても考えたいと思います。これまでいかがわしいもの、触れづらいものとして、オープンな場でタブー視されてきた「性」ですが、自らの体についてきちんと考え、発信することは決して悪いことではないという思想から、ゆとり世代を中心に「健全な性のオープン化」が進んでいます。前述の「NEUT Magazine」では2019年1月の特集を「セックス’19」とし、次のようなテーマを掲げています。
セックスって身近なようで遠い存在?
下ネタとかエロい話は飲みの場であったとしても
真剣に、真面目に話すことは少ないトピックかもしれない。
それは恥ずかしいからなのか
話すべきじゃないって雰囲気があるせいからなのか。
でも、話さないせいでみんな意外と知らない、セックスのこと。
避妊のこととか病気のこととか自分の体に関することから
単純に自分は何が好きなのか、何を気持ちいいと思うのか、
パートナーは何が好きなのか、何を気持ちいいと思うのか。
そんなことをもっとオープンに話せたら
もっと素敵でヘルシーなセックスが世の中に増えるはず。
第一章で紹介した「BathHaus」の代表でありプロデューサー兼デザイナーのroseさんは、デザイン性の高いコンドームなどを扱うエチケットブランド「shyboi」をスタートしました。ブランドサイトでは背景についてこのように説明しています。
どうしてコンドームやパンツを買う時にほんの少し恥ずかしい気持ちになるんだろう?
どうして部屋の見える場所にそれがあってはいけない気持ちになるんだろう?
ぼくたちの身体に1番密着して、毎日顔を合わせるものなのに。
ましてやコンドームは、世界で1番大切な人とだけ使うものなのに。
自分と相手のことを大事に扱いたい気持ちがあるからこそ、手にするものなのに。
大人になったシャイボーイの身だしなみ。
大切なあの子を守るため、自分を大切にするために。
こうした流れは日本にとどまらず、世界中で広がっています。特に若者向けの商品のコンセプト作りやブランディングによるファン獲得が得意とされる韓国では、「BIAS(偏見)」をなくすというコンセプトのコンドームブランド「SAIB(セーブ)」や、コンドーム・月経カップなどを販売するブランド「EVE Condom(イヴ・コンドーム)」など、コンセプチュアルなアイテムが次々と生まれています。
クリエイターエージェントのコルクで漫画編集者を務めた佐伯ポインティさんが2018年末にスタートした会員制の「猥談バー」も非常に話題になりました。「猥談バー」とは「エロ」が好きな人が集まってポジティブな猥談をする場所。オープンに先立って実施したクラウドファンディングでは700万円以上の調達に成功しました。
これまでの日本では「性」をいかがわしいものだと決めつけて一方的に隠匿することが正義だとされてきたわけでですが、世界的にみても日本の性教育が遅れているという意見は多く、正しいことを知り、自分や相手のことを考えるためには、オープンな場での議論、特に正しい情報に触れられる環境が必要だということには、なんら反論の余地がないはずです。

roseさんによるエチケットブランド「shyboi」のおしゃれなコンドーム
暮らす場所さえも固定しない人たち
ここまで「自由化」という観点から結婚や恋愛について考えてきましたが、ライフスタイルの多様化を突き詰めれば「どのように暮らすべきか」という問いに行き着きます。
ここでも新たな価値観が生まれています。それが「アドレスホッパー」と呼ばれる家を持たない人々で、定住する家を持たなかったり、いくつもの拠点を転々とする多拠点生活を送る人々が増えているのです。
インターネットの普及や仕事の多様化によって働く場所が自由になり、家賃や公共料金を払ってまで一定箇所に定住する必要がなくなったことが背景にあるよう(WWDジャパン「家を持たないミレニアル世代が増加、働き方改革の先にある“アドレスホッパー”の実態」)で、彼らは「Airbnb」で住む場所を探したり、実家や友人宅を利用することで生活をしているそう。これってある種の「ポジティブなホームレス」なわけで、もちろんまだまだ少数ではあるものの、住宅ローンを組んで家を買うことが人生の目標とされた時代から比べると、衝撃的な事象かもしれません。でも、いつ何が起こるかわからない時代に、一カ所に定住することを決めて土地を買い、生涯定額の対価を支払い続けることよりも、定住せずに生活や時代の流れに合わせて流動的に暮らす方が合理的だとも考えられるわけです。
最近では荷物の預け入れサービスや月額定額制の「住み放題」サービスができるなど、多様な住み方に対応できる制度も登場。ソーシャルメディア事業のガイアックス出身で現在はシェアリングエコノミー協会事務局長などを務める佐別当隆志さんは、2018年12月に多拠点コリビング(co-living)サービス「ADDress」を発表しました。家具やwi-fi、光熱費、アメニティー、共有スペースの清掃費用を含めて月額4万円で、好きなシェアハウスを借りられるサービスで、すでにガイアックスや「東京R不動産」を運営するR不動産、「住所不定」をテーマにしたブランド「ONFAdd」を展開するニューピースなどから資金調達を実施していることからも、注目度の高さが伺えます。
東京で一級建築士として設計事務所に勤めていた木津歩さんも、アドレスホッパーの一人。2018年3月末に事務所を退職して以降、家賃がないために千葉の実家をはじめ国内外を転々とするようになったそうですが、そんな生活を通して「自分が一定期間住んだ地域について、客観的な関係性で地域の面白さを発信できるのではないか」ということを考えつきます。彼は現在、兵庫県香美(かみ)町に拠点をおくNPO法人TUKULUから契約料をもらう形で「関係人口契約」を締結。移住と観光の間にいる関係性として、定期的なオンライン会議や企画立案などを行っています。また「関係人口契約」締結に並行して、クリエイティブ面を担う創作ユニットhyphen,を立ち上げ、青森県十和田市や北海道下川町など、宿泊費・旅費を負担してもらう形で地域に移住し、コンテンツを制作発信しています。家を持たないことを肯定的に捉え、新しい仕組みを生み出したというのは、いかにも「ゆとり」らしいアイデアだなと感じたのです。
このような多様性の先にあるのは、一人ひとりが自分の趣味嗜好や暮らし方を自由に選択できる世界で、(もちろん人に迷惑をかけない範囲で)何にも縛られずに生きることができる環境が整ってきたということでしょう。
コミュニティからタマリバへ
少しずつ範囲を広げて考えてみます。暮らし方、つまりは住む場所に対する価値観が変わると、必然と彼らが属する地域や人のつながり、すなわちコミュニティも変わりはじめます。次は、このコミュニティについて考えてみたいと思います。
インスタグラムで「古着女子」というアカウントを立ち上げ、開設から5カ月でフォロワー10万人を突破して話題となったyutoriのCEO(チーフ・エモ・オフィサー)片石貴展さんは、2018年に「pool」というコミュニティスペースを作りました。「pool」はイベントやポップアップショップ、クリエイターの共創などを行う「『好き』の溜まり場」で、2018年12月に行われたフリマイベントは入場チケットが発売後約2分で完売するほど盛況だったそう。そんな片石さん、実はIT業界出身。前述のIT業界出身デザイナーroseさんとの対談で、「なんでもレコメンドされてしまい多様性を失ってしまったインターネットよりも今のリアルは『インターネット的』なのかもしれない」という話をしていたのがとても印象的でした。かつて知らないものとどんどんつながる魅力にあふれたインターネットが大衆化し、一方で価値観によってつながれる場所をリアルに求めているのではないかと。この記事にもありますが、若者は「約束をしてまで会うほどじゃないけれど、ふらっと立ち寄れば誰かがいるようなゆるい場所」つまり「放課後の教室」のようなタマリバを求めているんじゃないかというのです。最近シーシャ(水タバコ)のあるカフェなどが人気ですが、これも、ゆるく集まってみんなでダラダラできる、いわば放課後の教室的な感覚なのかもしれません。コワーキングスペースやカフェなどの「サードプレイス」は増えつつありますが、こうした目的もなく集まれる場所って意外と少ないんです。
そんなタマリバ最大のメリットは「気軽に知らないものに出合える」こと。かつてのインターネット的な場所です。前述の定額コリビングサービス「ADDress」のトークイベントで同社に出資するニューピースの代表・高木新平さんは、「自分の趣味嗜好に合わせてリコメンドされる現代において、自分が知らないことに出合うのは案外難しい。そんな時に地域はもっとも簡単に新しいものに出合える場所になりうる」とその魅力を伝えました。人や情報の交流が生まれるソーシャルホテルを作るホテルプロデューサー龍崎さんは、こうした偶然の出合いを「ポジティブな予定不調和」と呼び、「偶然の出会いや、そこで手に入る情報が、お客様にとっての刺激になって新しい世界へのきっかけとなる」(「トレンドカルチャーを発信するメディアとしてのホテルが人気」(2018年6月8日))と語っています。もちろん、オンラインでもリアル同様の情報交流やコミュニティの形成はさかんに行われています。好きなテーマでゆるくつながる、そこには年齢も性別も肩書きも関係ありません。「タマリバ」は、今やオンライン・オフラインに関わらず存在するのです。記憶を遡れば、mixiにおけるコミュニティがその源流だったのかもしれません。
オンラインから生まれたコミュニティの実例として「喫煙女子」を紹介します。「喫煙女子」はCHOCOLATE Inc.というクリエイター集団に所属する1996年生まれの企画作家・大澤創太さんが、2018年7月にスタートした企画。タブー観によって喫煙していることを公言できずにいる女の子たちにとって「ありのままでいられる喫煙所」のような居場所を作りたいと考え、時代の流れとは逆行する「煙草を吸っている美しい女性」を連続的なクリエイティブに落とし込むことでそれを体現したのです。仕組みとしては「喫煙女子」を通して自己発信を行いたいモデル(9割近くが被写体未経験)と、コミュニティの理念に賛同するカメラマンをマッチングし、完成した作品をTwitterアカウントに掲載するというきわめてシンプルなもの。にもかかわらず、熱量ある人々が集まることで自然と作品が増え、さらなるファンや候補者が増えるという好循環が生まれました。ランジェリーブランド「Tiger Lily Tokyo」とのコラボで実現した期間限定ECサイトや、アーティストとのコラボMVの製作・公開を経て、さまざまな領域への波及効果も証明されつつあります。

Model (@Rabcantara) / Photo (@muller_2926) / Tobacco「メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8」
(https://twitter.com/smoking__girls/status/1041310736285421569)
このように「思想」でつながるコミュニティがビジネスになる事例として、「D2C」(Direct to Consumer)という概念を取り上げたいと思います。「D2C」はよく「中間マージンを抜いて質の良いものを安く提供するブランド」と説明されますが、これでは本質を掴めないように感じています。思想をファンに齟齬なく伝えるためのダイレクト・コミュニケーションこそD2Cの本質であり、思想があるからこそ共感してくれる消費者と生産者がコミュニティのような「共創関係」をつくりだす。こう考えれば、小売業界の構造を覆すようなヒットブランドが生まれていることも納得ができます。質の良いものを安く提供できることは大事な副産物でしかないのです。
少し余談ですが、僕の中で「ブランドの思想が伝わっているかどうか」を見る一つの指標があります。それは、Instagramのブランド公式アカウントのタグが付けられた投稿一覧を見ることです。「今日のコーディネート」や「最近買ったもの」などと、自分の写真にブランドの公式アカウントをタグ付けして投稿することは、誰にでもできること。だからこそ、ブランドのファンである生の消費者の声を見ることができるのですが、ブランドによっては、この投稿一覧が驚くほど統一された世界観であることがあります。それはつまり、ブランドが提案する思想に共感する同じ価値観の人々が集まっていることを示すのではないでしょうか。誰もが自由に発信できるこの時代に、共感できる消費者を集められることはすごく価値のあることで、こうした統一された世界観をファンが発信するということはすなわちブランドと顧客による「共創関係」があるといえるでしょう。世界観を顧客が勝手に発信してくれることで、二次的な拡散が起こる。それは思想あるブランドにとって最良の波及効果だなと思うのです。
お金ってダルいときない?
ライフスタイルの変容・多様化とともに「お金」に対する価値観も大きく変わりはじめています。前述のアドレスホッパーのような人びとは家賃などの固定費がかからないため、食費や移動費など日常生活ができる範囲のお金さえあれば、いかようにでも生きていくことが可能になったわけで、「最低限生きていけるためのお金を稼げばいいんじゃないか」という意見も存在します。
これまでモノやサービスの対価としてお金があったわけですが、今やゆとり世代が求めるのはそれらだけではありません。ファストファッションのような大量生産に対するアンチテーゼとしてブランドの背景にあるストーリーに共感したり、フェスなどの瞬間的な消費に夢中になったり、友だちやコミュニティとのつながりを大切にしたり。一言でいえば、僕たちは「感情体験」に価値を感じるようになりました。
ただ、「感情体験」やストーリーに対して「お金を払う」ことが当然なのかといえば、そうとも限らない。というのも、友だちとコミュニケーションをとることも、映像や音楽、漫画を楽しむのも、今やなんでもタダでできてしまう時代。大前提として「お金をかけなくてもできるかどうか」という指標を誰もが無意識に持っています。
一方で「これに対してお金を払う」という「ギブアンドテイク」の関係ではなく、「見返りはいらないけれど、お金を払ってあげたい」という「一方的なギブ」にあたる行動も増えています。クラウドファンディングで気軽にお金を集められる時代だからこその価値観なのかもしれませんが、見返りを求めずに応援するという姿勢も見受けられるわけです。
国内最大のクラウドファンディングプラットフォームCAMPFIREで「愛する彼女に会うためのファッションプロジェクトで #ルースニアイタイ !!」という企画がありました。MIKKE(※詳細後述)共同創業者の小川大暉さんが、愛する彼女(ルースさん)に会うためにフランスへの渡航資金を集めるというもので、このひたむきな感情に後押しされて、僕も支援をしました。海外にいる彼女に会いにいくことを「 #ルースニアイタイ」というキャッチコピーとともにイベントにしてしまうあたりの企画力はさすがだなと思いますが、どうしても会いたいからクラウドファンディングでお金を集めるという行為自体が、愛おしく感じてしまったのです。最近では、クラウドファンディングよりも手軽に利用できるフレンドファンディング「polca」というサービスや、アーティスト・タレントへのバーチャルギフト(投げ銭など)ができるライブストリーミングサービス「SHOWROOM」などもあって、お年玉のような感覚で、誰かにお金を送金できるようになりました。
こうしたベクトルの変化の背景に「性善説」という考え方があると思います。一方的なギブは相手を全力で信頼するからこそできることでもあって、「STORES.jp」創業者の光本勇介さんによる不用品買取サービス「CASH」も、商品発送前に査定金額を振り込むという大胆な発想によってサービス開始16時間で3億6000万円のアイテムが現金化されるという事態が起き、議論を呼びました。
「お金」を気軽にオンライン送金したり、ネット上でお年玉を完結させたり、少しお金を軽く扱いすぎなのではないか、とお思いの方もいるでしょう。でも、こればかりは実際にやってみるとわかるのですが、特定の相手から何らかの信頼をもって、お金をいただくということは、少なからず責任を感じるものです。本書も制作のためにクラウドファンディングを実施し、150人を超える方から支援をいただいたわけですが、それだけの期待に対してきちんといいものを提供しようと考えるのは当然です。むしろお金も相手も見える化されたことで、その責任感は増しているようにも感じます。
見出しの「お金ってダルいときない?」という言葉は、コワーキングスペースChat Baseを運営するMIKKEの井上拓美さんが提唱する考えから引用させてもらいました。彼自身一度企業に就職するもすぐに辞めてしまい、お金がなくなった末にやむなく起業という道を選びました。そんな井上さんは「お金がなくても生きていける環境」を作ろうとChat Baseという場所を考案します。Chat Baseは24時間365日無料で使用できるコワーキングスペース。生活を保証されることで生きていくために無理をしてお金を稼ぐ必要がなくなり、クリエイティビティーに集中できる、いわば「クリエイターのためのベーシックインカム」なのです。井上さんは「NEUT Magazine」の取材(NEUT Magazine「『お金ってダルいときない?』起業や大企業への就職を経てクリエイターのベーシックインカムを始めた23歳」)でこのように述べています。
お金は“価値交換の手段”としては世界史に残る最大の成功事例だけど、その反面、お金があらゆることをする上で一番便利なものになってしまったのが最大の弊害。昔は経済も成長してて、同時にモノがなかったから、モノを買って持つことが豊かさの象徴で、経済活動と幸福度の関係が近かった。
でも今はもう違う。モノが溢れてるから。頑張ってお金を稼いでモノを買っても幸福度が満たされにくくなってきた。だから今は無理やり“体験”を経済活動と結びつけて、なんとか幸福度に絡めようとしてる。でも、体験もお金と交換しちゃったら真の価値を得られないと僕は思う。

MIKKEが運営するコワーキンスペースchatbaseで開催された同社の2周年パーティ(PHOTO BY 安東 佳介)
僕らにとって仕事ってなんだ?
お金と切っても切れない関係にあるのは「仕事」です。第二章の最後に「仕事」について考えてみたいと思います。
近年の仕事に関する大きな流れの一つに「終身雇用に対する疑念」がありますが、これはゆとり世代だからというわけではなく、社会全体の議題となっています。大学を出て企業に入社し定年まで働くことを美徳としてきた日本独特の風潮はすでに失われつつあり、いつか潰れるかもしれない会社に属するよりも、起業したりフリーランスとして仕事をする方が実はリスクが少ないという論調まで出てきました。クリエイター集団THE GUILDやデジタルコンテンツの企画・制作のブルーパドルのように、フリーランスの集まり(=ギルド)として会社を組織するケースも増えています。もちろん、それだけの才能あるクリエイターが集まることで革新的なアイデアが生まれることは素晴らしいですし、こうした最先端の会社のあり方にも一理あるとは思います。僕としては、好きを仕事にしようがしまいが、フリーランスだろうが会社員だろうが、自分がベターだと感じた選択肢を選ぶことが大切なのであって、あまり深く考えず周りに流されることが一番のリスクだと思っています。
副業解禁という潮流もありますが、誰もがパラレルワークを実現できるわけではないし、ましてや職場が必要ないリモートワークも、可能かどうかは職種次第でしょう。事実、パラレルワークの事例としても「副業可能な組織に属しながら可能な範囲で複業をする」というケースが増えています。無理して稼ぐためにいくつかの仕事をするのではなく、自分がやりたいことをやりたい範囲で無理なく実現するためのパラレルワークだと考えれば、すごく納得がいきます。もちろん、働き方については世代間で認識の違いが多い部分でもあり、必ずしも全てがうまくいくとは限りません。写真売買プラットフォームSnapmartに務める川北啓加(もろんのん)さんは、かつて新卒第一号として同社へ入社。入社前からカメラマンとしてなど、個人の仕事をしていたこともあり、入社後に複業を続けるかどうかはかなり議論になったといいます。川北さんが「本業に支障のない範囲で自由に別の仕事をするべきだ」と考える一方、伸び盛りの会社としては「その労力を本業のために使ってほしい」という意見。結果として、お互いが理解するまで話し合うことで複業は認められたそうで、このように(努力をともないますが)若者が起点となって組織体制が変わるような事例もあるようです。
同じゆとり世代といえども、キャリア像についての意見はさまざま。前述の企画作家・大澤さんが「将来のことはあまり考えない。10年後に食っていられるかより、来年どんなポートフォリオを作れているかを考えている」と話す一方で、新卒で入社した博報堂から独立・起業した阿部成美さんは「29歳で子どもがほしくて、そこに向かって起業などのライフステージを考えたしたたかなタイプです」と語ります。この時代にキャリアに関して正解も間違いもありません。仕事についてきちんと考えること、重要なのはそれだけじゃないでしょうか。
一方で、会社が多様な働き方・生き方を実現するための選択肢を用意するということは大切かもしれません。これからの時代、頑なに副業を認めなかったり、明らかに自社で囲い込むための制度を作っているのでは、優秀な人材を逃してしまう可能性もあります。ただ、会社である以上、組織マネジメントや守秘義務があって、さまざまな制約があるのもやむおえません。
そんな会社と社員、もしくは個人の関係性を考える上で重要なことはやはり「制度ではなく思想でつながる」ことだと思います。先立って紹介したように、仕事のタマリバが会社になるのです。制度はあくまで思想によるつながりを支えるための手段でしかありません。会社は自分たちのミッションを明確にして発信し、その思想に共感できる人々を集める。「創業者たるもの思想家であれ」ということかもしれません。例えば、インターネット時代のワークウェアを作る「ALLYOURS」創業者の木村昌史さんはまさに思想家の最たる例で、自身のnote(僕らが売っているのはファッションじゃない。)にこのように書いています。
ファッションに気を使っている場合じゃないくらい、やりたいことがある人へ。ファッションなんかより、大事なことがある人へ。かっこいいのは、あなたの服じゃない。あなたのやっていることだ。それを助けるツールとして、僕たちのプロダクトを提供したい。
これは思想で顧客とブランドがつながるという話ですが、この関係性は顧客も従業員も同じ。そもそも誰もが消費者であり、生産者である時代、思想に共感する人はファンとなり、顧客となり、場合によっては従業員にもなる。会社としても、思想で判断すれば、雇用しやすいはずで、ホテルプロデューサーの龍崎さんはこれを「バイブス採用」と呼びます。職歴や技術はもちろん強みだけれど、自分と同じ「バイブス」を持つかどうか、採用で見るべきはそこだというのです。誰でも簡単にファンクラブを作成できるアプリ「CHIP」をリリースした現役大学生で起業家の小澤昂大さんも従業員との関係性について、「社員というより、友だちから入った方々と案件やプロジェクトに応じてゆるく働いています。もともとお互いをわかっているから細かいことを決めなくても安心して任せられる。だからどのくらい働いてもらうのか、あまり決めないようにしています」と話していました。一見すると「そんな適当な関係で仕事が成り立つものか」と思われるかもしれませんが、経歴書と契約書によって結ばれた形式的なつながりよりも、こうした思想でゆるくつながる関係性の方が、会社と良いシナジーを生み出す可能性は高いのではないでしょうか。
2019年2月に2億円の資金調達を発表して話題となった出張撮影サービス「ラブグラフ」の創業メンバー駒下純兵さんも、かつては戦場を撮影するカメラマンを志していました。彼は創業の経緯について、自身のnote(「便利」や「成長」の先に人の幸せはあるのか)でこのように語っています。
戦場の写真はたくさんあるけど世界中のあらゆる争いはなくらないし、戦地の写真を見た人も実際に自分がどう行動すればいいのかわからないのではないか。考えが変わるだけでなく行動も変わらなければ世界は良くならないと考えるようになりました。そうして辿り着いたテーマが「Love」です。
重要なのは、一人ひとりが自分の身の回りにある小さな幸せに目を向けることです。その感性が身につけば、僕たちは人に優しさを与えることができて、その優しさの連鎖は世界を救うと信じています。
会社を立ち上げて4年が経とうとしています。楽なことばかりではありませんでしたが、4年前から作りたい世界が少しずつ形になってきました。
彼は思想のもとで創業し、自身が描く世界の実現を目指しているのです。インターネットで自由に思想を発信できる時代だけに、こうした代表の思想に共感して仲間になることが気軽に実現できるというのは、とても恵まれた環境ともいえます。
さて、仕事について考えたこの章の最後に、そもそも働くことだけが人生の目的ではない、ということを考えさせらた二つの事例をご紹介したいと思います。愛する「紙」のために仕事辞めて世界旅行へ飛び立つ浪江由唯さんと、陸前高田の海に惚れ込み移住した「漁業女子」こと三浦尚子さんです。
浪江由唯さんは1994年、京都府出身。大学時代に高知県の山奥で見つけた紙作りの現場に感動し、こうした手仕事が残り続けるための方法を模索してきました。大学卒業後は岡山県で雑貨屋に就職し、感性を磨きます。2年間勤めた今年、仕事を辞め、世界中の紙に出合うための旅に出るのです。紙の魅力について浪江さんは「手紙で想いを伝えたり、本の良さに気付いたり。紙の種類があるからこそ、こうした表現ができるんです」と穏やかに語ります。高校時代からやってみたかったという世界一周について「紙の研究資料って少なくて。世界中の紙について知り、見てきたものを残すことでこれからの研究に役立てばうれしいです。また、これまで紙に興味がなかった人々にも届けられるように発信方法について模索しているところです」と浪江さん。ちなみにこうした原動力のきっかけは2015年に岡山で生まれたデニム兄弟による「EVERY DENIM」(※詳細後述)による半年間のスクールに参加したことだそうで、「周りに相談したら引き止められるどころか応援されてしまったので、こういう決断をしていいんだと気付きました。(旅行を決めたのは)好奇心だけ。だからお金のことも考えていない、バカなのかもしれないですね」と笑って教えてくれました。
一方、1991年に神奈川県で生まれた三浦尚子さんが陸前高田を知ることになったきっかけは、東日本大震災でした。それまで編集インターンなどを経て編集業を生業にしようかと思案していたところ、震災ボランティアで漁業アルバイトを経験、その面白さと縁に惹かれて大学卒業後に陸前高田に移住したそうです。現在はマルテン水産の牡蠣漁師として、牡蠣とわかめ養殖に関わる全ての工程を担当。毎日朝から夕方まで、地元住民とともに海へ出るといいます。テレビ電話で話を聞かせてくれた三浦さんに「なぜ陸前高田に移住したの?」と聞くと、「とにかく海が綺麗で。当時少し病んでいたこともあって、稼げるかどうかとかよりも、感動と面白さが先行してしまったんです」と答えてくれました。「震災もあって、漁師人口は減る一方です。私は『浜の編集者』として誰かに知ってもらえるような発信をしながら、自分としても独立を視野に本気で漁業をやっています」。
二人の話を要約するとすれば「好きなものを好きと言える時代がきたのだ」ということでしょうか。普通に考えると止められそうな状況でも、みんなが応援してくれる、そんな時代。働くことも大切だけれど、好きを追求してみる、進み方は進みながら考える。まさに「ゆとり」的思想だと思いますが、好きを応援しあえる社会というのは、すごくポジティブな時代じゃないでしょうか。
三浦さんはいまの時代のキャリアのあり方について「好きのつまみ食い」というキーワードを教えてくれました。「まさに『ゆとり』だなと思うのですが、友人が『つまみ食いの生活』をしたいと近くに移住してきて。一つに決めなくてもいいし、生活できればいいじゃんって。私も発信をきっかけに仕事が決まったこともあるのですが、好きがいっぱいあってもいいんじゃないかと思うんです」。自分の好きを追求し、発信できる時代。SNSなどを通じて、それが仕事につながったり、新しい発見や出合いがあったり。好きなものを探して、深掘りして整理するという作業はまるで編集作業ですから、これからのキャリアに求められるのはもしかすると「好きの編集作業」ではないかと感じるのです。

三浦さんが心打たれたという陸前高田の朝の海。船に乗った初日に見た景色は、夜と朝の境目みたいな海だったそう
第三章 「ゆとり」という思想
ポジティブな逃げと声にならない怒り
いよいよ、最終章。ゆとり世代が生きる今についていろんな事例をもとに考え方を深掘りすることで、かなり具体的な価値観や判断基準が見えてきたところだとは思いますが、最後にこうした時代を生きる人々の「思想」について考えてみたいと思います。まず最初に「逃げ」というキーワードを紹介します。
僕は仕事柄、平成生まれの起業家の人たちに「なぜ起業したの?」という話を聞く機会が多いのですが、「社長になりたかった」「お金持ちになりたかった」という意見はめったに出てきません。「お試しでサービスをはじめてみたらうまくいった」とか「やりたいサービスが企業との提携のために法人登録が必要だった」という答えもありながら、意外に多いのが「就職できなかった」という理由です。
クリエイターのためのコワーキングスペースなどを運営するMIKKE創業者の井上拓美さんは「大学卒業後に就職という選択肢がなく、お金がなくなったから銀行を回ってお金を集めて事業をやるしかなかった」といいます。また、米「Forbes」誌の「アジアを代表する30歳以下の30人」にも選ばれた岡山発のデニムブランド「EVERY DENIM」を立ち上げた山脇耀平さん&島田舜介さん兄弟の兄・山脇さんも、「学生時代の長期インターンで仕事のあり方に疑問を持ち、新橋を行き交うサラリーマンたちを眺めながら僕には無理だなと思った」というのです。
この感覚について、「健康的な消費のために」をテーマにアパレルブランドをはじめた「foufou」のデザイナー高坂マールさんは、「マジョリティーに馴染めなくて。僕はある意味ずっと逃げているのかもしれない。『逃げ』を起点に誰もやっていないことを探しちゃうんです。今も意図せず売れることは怖いし、ある意味でこれ以上成長することから逃げている。だけど、夜の究極が朝であるように、逃げの究極は『向き合う』ことなのかもしれない」(『売れないことより、意図せず売れることが怖い』D2Cアパレルが提示する未来のブランド像)と教えてくれました。
そんな高坂さんは洋服の売り方において「明るい機会損失」というキーワードを掲げています。意図せず売れてしまわぬよう、自分の目の届く範囲で商品を直接顧客に届けられるよう、いくら売り上げが見えていても、無理をして増産をしないということです。自身のnote(明るい機会損失)でもこのように説明をしています。
そもそも新作は月に平均3型しかでない。(中略)多くは1週間前後でなくなってしまう。そして次の新作や再販売があるまではオンラインのお店になにもない。まともなMDさんからすれば機会損失しすぎだから在庫を積んだりしろと言われそうだ。(中略)僕が何より恐れているのは「売れなかった」ことよりも「意図せずたくさん売れてしまうこと」だ。自分が意識的に管理できるスケールで続けていくほうが何かと齟齬がないし正直そこまで売り上げをつくることに意識していない。(中略)目の前では機会損失でも、遠くを見れば全然違ったりしている気がする。何もないからもう買わないと思われたらやはりそれまでだと思う。「何もなくても見ていたいブランドやコンテンツ」を作らなきゃいけない。目先の売上よりその深さのほうがよっっぽど価値がある。
目の前の売り上げから逃げることで、長期的なブランドへのエンゲージメントが得られる。世の中の常識から少し距離を置くことで、本質的な価値を手に入れる。僕はこれを「ポジティブな逃げ」と捉えます。もちろん「会社が嫌だから逃げよう」とか「お金に縛られたくないから逃げよう」とか、何でもかんでも逃げを助長するわけではありません。ただ、一方を選択すれば他方を捨てることになる。これは誰にとっても平等で、必ずしも他の人と同じ選択をする必要はない。もしかしたら一つの選択から逃げるということも、ある意味で大きな意思表示になっているんじゃないかと思うのです。

foufou提供
また、「ポジティブな逃げ」の他に、彼らに特徴的な感情があるとすれば、それは「声にならない怒り」なのではないかと思います。第二章でも少しだけ紹介した、農産物のブランディングに挑戦する阿部成美さんは、博報堂時代に、地方で素晴らしいブランドを作っている人たちにフォーカスした「ブランドたまご」というコンテンツを作ります。その取材を通して、今の時代に合ったブランドを作る背景には「義憤」(世の中に対する大きな怒り)があることに気が付いたといいます。「私たちが生まれた頃にはすでに有名なブランドは出来上がっていて、コンビニに並ぶラインアップもほとんど変わることはありませんでした。だから、ブランドから作る体験をしてる人は少ない。そんな時代になぜブランドを作るのかといえば、世の中に対する大きな怒りがあるから。私は山口県で生まれて『地産地消』が叫ばれる中でなぜまわりにたくさんの畑があるのにそれを生かしきれないのだろうと思ったんです。その後、農学部で実際の作物に触れると、一つひとつがこんなにも尊いのにもかかわらず、規定にしたがって廃棄しなければいけないものが多すぎた。効率的に箱に詰めるためだけの規定もあります。これに違和感を感じ、農作物を素敵に伝える仕事がしたいと考えました」と阿部さん。「大量生産や効率化によってあらゆる判断基準が作られ、無機質で温度感のない経済ができあがった私たちの時代には、怒るポイントが多いのかもしれない」というのです。「古着女子」などを立ち上げた前述の片石さんも、起業の背景には「怒り」や「呪い」などがあったと語っています(詳細は後述の座談会を参照)。これまで機能性ばかりに目を向けてきたために見逃されることの多かった「モノコト」に対する「尊さ」がベースにあって、そんな時代のあり方に対して何らかの「怒り」を感じている人が多いのです。
不安・恐怖からの逃げ、社会に対する怒りなど、ビジネスとは切り離されてきた「感情」に素直になることで、起業するという大きな意思決定に終着する。矛盾しているようにも感じますが、人間が人間らしくあるための理想の追求を経済活動とするならば、むしろ本質的な考え方のように思います。
冷たい時代の感情体験
さて、こうした感覚の言語化を踏まえて、「ゆとり」を取り巻く環境とその思想を可能な範囲で総括してみようと思います。
まず、大前提として僕らは「冷たい時代」を生きています。バブル崩壊後の不景気を見て、東日本大震災による人間の無力さを体感し、ある種の「あきらめ」を心の奥底に抱えた世代です。だからこそ、冷静で客観的な思考を身につけているのかもしれません。また、モノもサービスも急増した供給過多の時代、あらゆるモノゴトに機能性ばかりが付加されてゆく中で、精神的な充足を求めるようになりました。どうすれば心を満たせるのか、それこそが行動の重要なきっかけとなったのです。好きか、嫌いか。楽しいか、楽しくないのか。こうした判断基準が優先されはじめたわけです。
これを「感情の時代」と言い換えましょう。これまでの個性を隠匿することが美徳とされた「謙遜」の文化をベースとしながらも、感情で動くこと、人とは違うことを肯定できる時代に近づいています。統計学的な表現ともいえる「マイノリティー」が「個性」となり、情報にあふれた大航海時代に自分が沈んでしまわないための「フラッグ」となったのです。これまで一つしか持てないとされた肩書きや年齢、性別などの「記号」がフラッグとなって、いくつも好きなだけ持てるようになりました。これこそが「多様性」です。そもそも「個性を大切にしよう」というのは、ゆとり教育の命題でもあったわけです。
いろんな感情に従って身につけたフラッグを目印にゆるやかにつながる場所が、第二章でも紹介した「タマリバ」になるのでしょう。ここでは性別や肩書きなど、他のフラッグは関係ありません。いくつものタマリバに顔を出しても、もちろん突然抜けても構わない。そんな、ゆるくて自由なコミュニティが一般化したのです。こうした価値観によって他人や自分とは違うものを許容することにつながりました。排除・同調性からの解放です。
いろんなフラッグがあるからこそ、僕たちは一歩引いた客観的な視点を持てるようになりました。何かに没入することもできるけれど、自らを制限することもできる、一歩引いてコミュニティを眺めることだってできる。もちろん、その没入具合は人や場所によってまちまちでしょうが、ある程度の判断基準や客観性を少なからず身につけているのも「ゆとり」的だなと感じるのです。あらゆる局面で決断をしなければいけない、決断の精度が求められる時代ともいえるでしょう。だからこそ、間違いなく僕らは無意識に意思決定を鍛錬されています。「絶対」が存在しないとわかってしまったが故に、いついかなる時にもリスクを分散できるようなベターな選択をしたい。そのためには思考が必要です。だからこそ、他人の感情・思想に甲乙をつけるのは間違っている。他人は他人だとある意味冷酷に割り切った上で、その意見を尊重しつつ、自分の意見を持つこと。この習慣における意思決定こそが「ゆとり」という思想の根幹にあるものなのかもしれません。
昨今よく言われる「コト消費」という言葉も、個人的には「感情体験」を意味するんじゃないかと思います。決して「モノ」から「コト」へと消費対象が変遷しているのではなく、そこに語るべきストーリーがあって、そのストーリーが好きかどうか、感情が揺れるのかどうか、それこそが購入にいたる全てなのではないかと。感情は購入したモノコトがなくなったとしても記憶という形で残ると考えれば、一時的な行動を表す「消費」という言葉自体が正しくないような気もします。だから、「感情消費」ではなく、あえて「感情体験」と表現しています。自分がかっこいいと思うモノは高いお金を出してでもほしいし、かっこよくなければほしくならないというのはまさに「感情体験」。その伝達手段としてストーリーがあるし、届けるためのサポート役にテクノロジーを活用すればいい。以前Twitterで「洋服が売れないって嘆くなら、洋服を着て出掛けたくなるような場所をつくればいい」と呟いたところ賛同の声を多く意見をいただいたのですが、本来の「コト消費」とはそういうことだと思いますし、出掛けたくなるようなかっこいいストーリーを提案することこそ企業がなすべき仕事なのではないかなと感じているのです。また、クラウドファンディングで支援をすることだって「感情体験」だなと思うのですが、この場合は自己承認やコミュニティへの参加のためにお金を払うケースも多く、お金を払ってわざわざ「生産」側に回っている。こちらでも「消費」という言葉は似つかわしくないように思います。
結局「ゆとり」とはなんなのか
繰り返しますが、本書で言いたいことは「ゆとり」という思想が存在するということでした。これまで世代で区切って語られてきた「ゆとり」が、世代を超えて存在する一つの思想・価値観であると再定義することで、そこに新たな気付きが生まれると考えたのです。もちろん「ゆとり教育」による典型的な「ゆとり世代」の創出がこうした思想に気が付く大きなきっかけにはなっているのですが、「ゆとり」という思想は決してゆとり世代だけに通ずる概念ではないし、むしろ「逃げてきたがためにゆるくつながり始めた」コミュニティの存在を肯定するための言い訳にすぎないのかもしれません。ゆとり教育を受けてのんびりと育ち、テクノロジーの発展を目の当たりにしながらも、先人たちの作った社会制度に当てはまることができずに逃げてきた人たち。彼らが同じ価値観によって簡単につながり、次第にそのコミュニティが大きくなりました。その結果が第二章で紹介したような「ライフスタイル・価値観の多様化」という一つの特徴ではあるわけですが、その根底にあるものこそ「ゆとり」的な思想で、そこにあるのは自分自身で考える力ではないかと思いました。
事実「ゆとり」という思想に近しい「ゆるくてやさしいつながり」のようなものを感じるのは、「ゆとり世代」の意見ばかりではありません。実は、今回本書を作ろうと考えて参考にしたのは、糸井重里さんの「インターネット的」という本でした。15年以上前に書かれたにも関わらず、この本には「シェア」や「フラット」など現代に通じる思想が出てくる。もちろん、テクノロジーや時代の進化とともに手段や見え方は変わり続けますが、「ゆとり」的思想の本質は時代や世代を越えて普遍的なのではないか、という仮説が執筆の前提にありました。さらに時代をさかのぼれば「ゆとり」の思想は、昨今世界的トレンドにもなりつつある「禅(ZEN)」にも通ずる部分があると思います。「禅」の思想に影響を受けた思想家・西田幾太郎が「純粋経験のみが実体である(ぼくはこれを『刹那的な思考だけは間違いなく存在する』と理解しています)」(「善の研究」(西田幾太郎著)から)と語っていますが、目の前にある日常の儚さやその時の感情に重きを置いて行動する「ゆとり」のルーツは、いくらかここにあるような気もします。
「ゆとり」という思想を端的に言語化することは非常に難しく、「ゆとり」に紐づく具体的なキーワードをあげるとすれば「競争しない」「ありのまま」「執着心がない」「ゆるくつながる」などいろいろとあるのですが、これらは現代(というか現時点)において表出している一部分でしかなく、その奥にこそ言語化できない思想があると思うのです。前述の企画作家・大澤創太さんも「パンクと同じで『ゆとり』も時代ごとにアップデートされるもの。思想を定義してしまった瞬間に陳腐化してしまう。この曖昧さ、ゆるさ自体が『ゆとり』なのかもしれません」と話していたことに妙に納得したのですが、まさにその感覚。冒頭でも述べましたが、思想において形而上の概念を言葉にすれば陳腐になってしまうことはご理解いただけるでしょう。
そもそも、ここで書いてあること自体、絶対的に正しいかといえばそんなことはないでしょうし、統計学的な根拠もありません。本書では「ゆとり」のエッセンスを浮かび上がらせるために、意図的に起業家や珍しいキャリアの人たちを取り上げましたが、「ゆとり」という思想を通釈することで伝えたいのは、起業すべきだとか、好きなことだけをやれとか、決してそんなことではありません。むしろ刹那的な思考を内包した「ゆとり」という概念は、程度の違いこそあれ、世代を超えてあまねく存在するのではないかということでした。本書によって、少しでも自分の心の「ゆとり」について考えたり、自分の感情に素直なれたとすれば、それだけで十分素晴らしいことだと思うのです。
「ゆとり本」特別座談会
「こんな時代になぜ起業するのか」
L&G Global Business龍崎翔子 × MIKKE井上拓美 × yutori片石貴展
2月末に「ゆとり本」のコンテンツを詰めるにあたって、企画段階から関わってもらったL&G Global Businessの龍崎翔子さん、MIKKEの井上拓美さん、yutoriの片石貴展さんという3人の起業家とともに「編集会議」と銘打った座談会をライブ配信をしながら実施しました。たった1時間弱の座談会でしたが、最後にそこに散りばめられた「ゆとり」的思想を感じられるような対談の模様を最後にお届けします。

左から片石貴展さん、龍崎翔子さん、井上拓美さん、すみたたかひろ
―自分が大切にしているもの
すみた:今日は「ゆとり」について改まって話をするというより、3つの質問を通して、自身の思想や価値観を話して、そこから深めていくような感じにしたいなと思います。まずは「自分が大切にしているもの」。スケッチブックに自分が大切にしているものを書いてください。
片石:僕は「ほどほどの背伸び」「見栄を張らない」「居心地良い」。端的にいうと、全部一個にまとめられて、「ありのまま」でいること。今そこにいる人がどんなことを考えているか、どういうことを大事にしているか、みたいなのを大事にしている気がする。だから、シャンパンあけても楽しいとは思わないし、だったらサウナいきたくね?みたいな(笑)。居心地がすごく大事かな。挑戦するのは大事だけど、全く別の自分になろうとするのは違うというか。記号で自分を語らないようにするっていうのが思想としてあるかな。
龍崎:それ聞いて思ったのは「自分のものさし」を見つけている人が幸せになれるのかも。その自分のものさしがどういう形かをみつけるまで、知るまでの期間が「くすぶる期間」なのかなって。
すみた:ここにいるみんなは自分のものさし見つけてそう。
片石:半分くらいかな〜。
井上:自分のことは把握してる気がする。自分がどうしたらじんましんが出るかとか、自分がどうしたら楽しいかみたいなところはなんとなくわかってきたかな。
龍崎:うちはたぶん見つけてるタイプ。自分にとっての直感って、絶対なんらかの行動様式にのっとっているもの。だから、それが何だったかっていうのは、自分の過去の選択とか、過去どう考えたのかを振り返って、共通点を探すとわかる。
すみた:その流れで翔子ちゃんの答えを聞こっか。
龍崎:私は「オルタナティブな選択肢」「歴史へのリスペクト」「グラマラス」。一つは「オルタナティブな選択肢」。なんか、喧嘩したくないんだよね。あなたがいいと思うことを一切否定したくないし、認めたい。認めるってのももはや傲慢で、(相手の意見に対して)めっちゃいいと思いたい。それでいて、うちはこうだよ、って当たり前に提案したい。世の中って選択肢がないシーンが結構多くて、そこに新しい選択肢を提案したい。でも、それは過去のものを否定する形で提案するのではなくて、「好きな人は、こっちきて!」みたいな。二つ目は「歴史へのリスペクト」。選択肢をどうやってつくるか、ってときに「これ売れるやん」「みんなこれ好きやん」みたいな出し方は嫌で。自分がホテルつくるときは、絶対にその街がどういう街なのかを考える。世界中どんなところでも、そこに人がいて、歴史があれば、そこならではの文化があって、空気感ができるから、それを丁寧に手探りして見つけて、それとマーケティング的な要素を組み合わせるっていうのが自分のルールとしてある。最後は「グラマラス」。日本にはエロさが足りない!「エロス」って意味ではなくて、もっと「セクシー」であっていいと思うの。「魅力的」っていうのをもっと本能的に追及していいと思う。例えば、ホテルだとわかりやすくて、もっとプールとかエロくていいじゃんって。なんでこんなハイビスカスの絵ばっかり描いてるの?って思っちゃう(笑)。
井上:僕は「もれ」「じんましん」「さみしい」。自分自身が何かを表現できないから、表現されているものより、表現されていないものに興味がある。人間の奥底にある感情、例えば、イライラとかエロスとか。なんとなく出しちゃいけなさそうだから出せていない感情に興味がある。そこを自分自身も出せるようにしたいし、出せるような環境がほしかったからここ(chat base)をつくったし、他の人も普段社会で出せていない感情をここでは出せると楽しいなって思う。
すみた:「もれる」ってどういうこと?
井上:言葉が漏れるとか、感情が漏れるとか、なんか「ん~~~」っての。その「もれ」が好き。感情がすごい爆発しそうだけど、それがちょろっと出て、あっ、みつけた、みたいな感覚。それで二つ目が「じんましん」。どうしたらじんましんが出るかがわかる、ってのが自分にとっては大事。僕の場合は(会社に就職したときに)じんましんが出たからラッキーだった。自分の異変に気付けた。自分が今変だ、ってことを認識できることが大事。最後は「さみしい」。僕の一番のクリエーションのモチベーションは「さみしさ」。怒りでもなく、もちろん楽しいこともあるけど、さみしさが一番大事。自分の価値観が今共有できないさみしさ。最近は人に感情移入しやすくなっちゃってて、なんなら、横須賀線で酔っ払ってる人見たら、さみしくなっちゃう。
龍崎:わかる。哀愁?みたいな。この人どんな人生だったんだろう、幸せになってほしいなって思う感じ。
井上:その人にとっては究極的にはそれが幸せかもしれないじゃん。でも、なんか、まだ(選択肢が)いっぱいあるし、(たくさんの選択肢があるうえで)それを選んだのであれば美しいと思う。選ばずして、そこにいるってことにさみしさを感じちゃう。これ(大切にしている価値観)をトータルで考えたら、僕自身が価値観を変えまくっている。だからこれ(三つの価値観)は今ホットな価値観。自分の価値観は変わり続けている。でもこれ(=じんましん)があったから、自分の感情に変化がいっぱいあるな、って感じる。僕はいつもさみしい。
―「こんな時代になんで起業したの」
すみた:さみしさの話とかもそうだけど、それぞれみんな、感情が起業のきっかけにつながったのかな。
片石:俺は「怒り」。いろんな感情があるけど、何が一番かっていうと怒り。
龍崎:私は「乾き」。
すみた:乾きに対して、満たしてあげたいみたいな?
龍崎:私は、原体験が、アメリカでカ月間西海岸から東海岸までドライブしたときのことで。一人っ子だったから、親が一日10時間とか運転してるのを一人でずっと座って待っている状態だった。後部座席で変わらない景色をずっと見てて、だから、車を降りる瞬間がとっても楽しみで。でも、実際は全然かわり映えしなかった。めっちゃ期待してるのに、満たされなかった。その幼少期の原体験で抱いた自分の乾きを癒やしたくて、ホテルを作った。
すみた:さっき言ってたエロいプールとかも、まさに乾きに対しての「満たし」だよね。
龍崎:そう。機能性の対極がグラマーさだと思っている。機能だけでつきつめたらエロくなくなって最低限になっちゃう。日本にはそういうのが多い。そうじゃなくて、機能性の上のスパークジョイするなにかがほしくて。
井上:機能性のところでいうと、今ある多くのサービスがリーチまでなんだよね。目的がリーチしてお金を払ってもらうところ。
すみた:服だったら買う。ホテルだったら泊まる。
井上:その先のところを設計しているところはなかなかなくて。服を買うところじゃなくて、服を買って着て行ってくれるところを本気で考えるのがいい。
龍崎:それが、ゆとりとその前の世代の違いかも。イメージだけど、前ゆとり世代って、ひとつのものさしで生きていて、その中でいかに自己実現できるかだった。だからいかに社会的に認められるか、つまり売り上げを上げるかっていうのにフォーカスしていたから、機能性だけになっちゃったのかもね。
すみた:片石くんが言うステイタスっていうのもそうかもね。同じ指標しかなかったから、そこで勝負するしかなかった。
井上:高度経済成長期はみんなモノを持っていなかったから、モノを持っていることが幸福度に直結していたんだよね。
すみた:今はモノにあふれているからね。
片石:けど結構むずいなって思うのが、俺、最近「呪い」という言葉が好きで。(人々は)呪いをかけられているんだなって思ってて。日本にいる限り、そのときの価値観をインストールされるじゃん。だけど、今は何も指標がない。インターネットができて、おびただしい指標や価値観が生まれては消え、消費され。その中で、自分が自分であることをいいと思えるとか、今自分が幸福であるということを感じるのってすげえ難しいよね。
井上:今は会社員でもTwitterとかで翔子ちゃんみたいな人の情報に簡単に触れられるじゃん。それと比べちゃうもんね、インターネット見ていたら。そこのギャップを頑張って埋めようとするじゃん。でも、本来目指すところはそこじゃなくて、自分のものさしを見つけていくプロセスをどう経るかみたいなさ。
片石:それってすげえ自分に自信ないとできないよね。
龍崎:2人は自己肯定感高い?自分のこと、好き?
井上:難しい質問だな…。
片石:好きになろうとしている。否定はしていない。
龍崎:自分は自己肯定感があるタイプで、それって結構教育だなって思う。うちは親が変わってるんだよね(笑)。
井上:それでいうと局所的にないところがある。ないときとある時がある。なんで今自分が嫌な気持ちになっているんだろう。その嫌な気持ちになっている理由を探して、そこに何ができるかな、みたいなことは結構考えている。
すみた:みんな自己分析力すごいよね!
龍崎:自己対話力高いよね(笑)。
すみた:普通はみんな自分のことそんなに考えてないよね。取材とかで聞かれる機会が多いからかな。
井上:なんでだろ。今まで壁が多かったんだよね。お金ないとかさ。高校卒業してから、給料もらって働いたって経験がない。お金がないからお金作んなきゃみたいな。別にやりたいことないし。でも、やりたくないことはガンガンやめて。でも、じんましん出やすいタイプだから、たぶん違和感に対する感度が高い。誰かにとっては壁じゃなくても、自分にとっては壁だと感じる瞬間が多かった。だから、ひたすら目の前にある壁を乗り越え続けるしかなかった。課題がこんなに目の前にあるってことは、ありがたいことだった。ラッキーだったと思う。その課題をクリアしていく段階で、結果自分と向き合う必要があったから。
すみた:片石くんはなんで起業したの?
片石:俺は親が起業家で、老人ホームとか病院とかやってて。起業かそれ以外かっていう分け方が自分の人生にはなくて。おやじみたいにやってたら昼までWOWOW見られるじゃんみたいな(笑)。逆に土日いないこともあるし、自由とは何かっていうことが体感としてあった。だから自分はそれ以外無理なんだよね。2年働いたアカツキでは自分のスキルをインプットするっていう目的があったけど、これからは無理かも、自由に生きたい(笑)。
井上:僕は会社員なれるならやりたいけどね。入れてほしい(笑)。
片石:じゃあ明日から来て(笑)
すみた:取材でいろんな人に話聞いてたら、それ、めっちゃ出てきた。「ポジティブな逃げ」って僕は呼んでるんだけど、それしかなかったとか、単純に合わなかったとか。
片石:「逃げ」って難しいと思っていて、今、安易に逃げを誇張する価値観があるんだけど、それってすごく無責任で。ただ単に逃げるのは違う。絶対に頑張らないといけないときもある。辞めていいときとそうじゃないときは絶対あって。すごい難しいテーマだよね。
すみた:辞めどきってのは難しいよね。
龍崎:私がホテルはじめたときもAirbnbで試しにやってみたらできましたってところからスタート感じだったんだよね。雪だるまと一緒で一番最初の雪玉作ってみて、これ転がせるじゃん、みたいな感覚があって。これを転がしたらどうなるんだろうみたいな見通しが立ってやっと本格化した。雪がさらさらのままだと雪だるまができないのと同じ。
井上:僕は無理せずちっちゃく始められる環境が作りたかった。ここに来る人となにか一緒にプロジェクトを作るときにも絶対にお金をかけず、時間もそんなにかけず、趣味から始めるんだよね。でも、ただの趣味になっちゃうと、辞めるかもしれない。だから赤字にはならないようにしたい。それを考えながら、趣味をまじめにやるみたいな。だからここ(chat base)に集まる人は、ここに来る瞬間だけ部活みたいな、自分のやりたいことだけをやれる環境にしたい。自分がそういう環境がなくて苦しかったから、部室みたいな場所を作りたかった。しかも、みんな「やりたい」っていうポジティブな欲求を抱いて集まると楽しいじゃん。自分が1回、自分のやりたいことをやって、誰かに価値として感じてもらえる成功体験をすると、見違えるように人って変わる。その体験を味わえるだけで全然違う。
―「ゆとりあるある」
すみた:最後に「ゆとりあるある」を書いてみよう。みんなの中の「ゆとり」ってなんなんだろう。これはできた人からいこうかな。
龍崎:じゃあ私から、「心にギャルを」。最近「人間にはヤンキータイプとギャルタイプがある」っていう話を聞いておもしろかった。ヤンキータイプは他人との比較で、自己肯定感を作る。トライブを作ってトライブ同士でバトルする。ギャルタイプは自分自身を着飾ったり、踊ったりすることで、自分の自己肯定感を養って、コミュニティを作る。私はギャルだなって思ったんだけど、よく考えたら、ゆとりみんなギャルじゃねって思った(笑)。
井上:僕は「ニュートラルに出会いたい」。これは僕っぽくない言葉かも。でも、大人と会う時もはじめましてのときには銭湯とかシーシャとかがいい。基本全部そうしてる。銭湯はなかなか難しいけど(笑)。理由はさっき話していた感覚に近いかもしれないけど、別にいいも悪いもないし、上下もないじゃん、究極。
すみた:いきなり会議室で会うと、名刺交換だもんね。
井上:そう。出会い方ってすごく大事だなって思っていて。人と会うときに最初から上下がある状態だとしんどい。だから、いかにしてニュートラルな状態で会えるか。同じ立場っていうか、裸になって会いたい。心が。そっから会う方が仲良くなれる。だから、飲みにケーションとかいうけど、結局はそれもニュートラルに出会える手段で、お酒飲んだら単純にハッピーになるし。
すみた:これ、ゆとりあるあるなのかな。
龍崎:でも、私のポリシーも同じ!私は人に会うときに、自分から「お願いします、会いたいです」っていうのは絶対にしない。向こうから「気になる、会いたい」って言ってくれないと会わない、ってのがポリシーとしてある。じゃないと、はじめのスタート地点がアンフェアになってしまって、一生その関係が続いちゃう。向こうが会いたいって思ってくれない限り、まだ会う立場じゃないって思ってる。
井上:友達になったら、価値交換じゃなくなるよね。価値交換じゃなくてギフトなの。好き、みたいな。そういう出会いをしたいし、そういう関係性になりたい。仕事仲間も全員友達から。
片石:最後に俺は「目」にした。自分が何かとの比較によって捉えられてるって感じる瞬間があって。はかられてるっていうか、こいつはこのクラスだな、これくらいねって思われてる瞬間。人を人として見ていない瞬間がある。そういう意味で、ニュートラルとかギャルとかは近い気がしてる。上下ってよりは「その人だよ」みたいな。そういう目をしてる人には、自分がいいときはいいかもしれないけど、自分にとって悪い時は相手を裏切るし、あんまり一緒に過ごしたくないなって思っちゃう。
すみた:なるほど。そろそろ時間ですね、おもしろかった。一生続けられそう(笑)。ありがとうございました!
「ゆとり」思想をひもとくキーワードたち
最後に「ゆとり」思想をひもとくためのいくつかのキーワードを掲出ページとともにまとめます。もしも、この中で気になったキーワードがあれば、そのページを見てください。本来は最初から読むことをオススメしますが、突然開いたページでどんな価値観に出合えるのか、そんな『ポジティブな予定不調和』を楽しんでください。
ゆとり世代
ゆとり教育
ゆとりの時間
東日本大震災
ミレニアル世代
別アカウント
フリマアプリ
主客混合
NEUT Magazine
BAMP
soar
She is
BathHaus
平成最後の夏
エモい
ラブグラフ
平成ラストサマー
平成が終わルンです
ソーシャルホテル
多様性(ダイバーシティ)
LGBTQ+
グラデーション
Palette
SOGI
マッチング
#結婚式に自由を
拡張家族
健全な性のオープン化
猥談バー
アドレスホッパー
関係人口契約
古着女子
タマリバ
シーシャ
ポジティブな予定不調和
喫煙女子
D2C
共創関係
感情体験
クラウドファンディング
Chat Base
ギルド
ALLYOURS
バイブス採用
好きのつまみ食い
foufou
明るい機会損失
ポジティブな逃げ
声にならない怒り
尊さ
冷たい時代
フラッグ
インターネット的
禅
儚さ
あとがき
企画からたったの3カ月。「ゆとりの思想」を紐解こうと、とにかくいろんな人に会ってきました。いよいよ本格的にコンンテンツを作らなきゃいけないと1月末には業務委託をしていた仕事を辞めてまで、この書籍と向き合ってきたのです。原稿は案外すんなり進みました。そうして、書き終えてみて、これは自分自身の生き方を肯定するための時間だったんだなと気付いたのです。
僕はこれまで、どこかに属するということが苦手なタイプでした。だから、いつどんな仕事をしていても、どんなグループに紛れていても「ここは僕の居場所じゃない」と客観視をする癖がありました。来る日も来る日も、まだ見ぬ居場所を探していたのです。
でも、別に居場所なんてなくてもいいんだと思えたことは、今回の書籍制作を通じて僕が享受した最大の成果だったのかもしれない。ゆるくつながれる場所があれば、ただいまと言える場所があれば、それでいい。そう思った僕にはやはり「ゆとり」という言葉がぴったりなのかもしれません。
本書は「90%の読後感」を意識して制作しました。だから、意見を述べるのは最小限とし、読んでくださる方々の自由な感想をもって完成となるわけです。そんな、僕のわがままをつめこんだ今回の制作に関わってくださった若尾さん率いる編集チーム、取材させていただいた方々、そして何よりクラウドファンディングを通じて支援をいただきましたみなさまに、この場を通じて感謝の意を伝えさせてください。本当にありがとうございました。僕は、今とても幸せな心地です。
1年後のあとがき
すごい時代になりました。平成が終わり、平穏な令和元年が過ぎ去り、こんな日々がやってくるなんて当然誰も予想だにしなかったでしょう。移動が制限され、人と会うことも難しくなりました。経済は停滞し、人々は見えないウイルスに怯え、いつ終わるともわからないトンネルの中をただ歩いているかのごとく日々を過ごしているわけです。
一方で、これまでの常識が全て無に帰せられたこの状況が、次の時代に向けた大きな転換期であることは間違いありません。全ての常識を捨てて、新しい日常を作る。これまでも人々はそうやって進化をしてきたわけです。
ちょうど一年前、みなさんのご協力あって、「ゆとり本」を上梓できました。あの時に話を聞いた人々はみな、あの日とは全く異なる日常のなかで、新しい今を生きています。出発前だったあの子が世界一周を終えたり、自らが創業した会社を退任した代表がいたり、新しい命を授かったり。とにかくみんな昨日とは違う、予想だにしなかった今日を活発に生きています。
あらためて考えてみると、適度な距離をとること、合理性以外のものでつながること、そして、死を思うこと。じつはウィズコロナの時代に求められるのは、本質的なウェルビーイング的思想なのではないかと思います。僕たちはただ本質に近づいているのです。
明日が来るかどうかなんて誰にもわかりません。一年後の未来など想像つくはずがありません。それはこの一年で明確になったでしょう。だから、今を生きて、楽しんで、また来年笑えるように、今こそゆとりの精神を広く持つべきではないでしょうか。
僕はいま、本文にも登場した龍崎さん率いるL&Gのお手伝いをしています。旅行に行けない時代のホテルのありかたを模索し、見えないトンネルの出口を目指して必死に走っている最中です。この本に登場してくれたみんなも、読んでくれたみんなも、同じようにそれぞれの道を走っているでしょう。
学生時代に大震災を経験し、なんにもできない無力感に苛まれたゆとり世代はもう子どもではありません。新しい時代を作る力を持っているはずです。さあ、今こそ、みんなでゆとり世代の逆襲を始めましょう。
著者:すみたたかひろ
編集:若尾真実
デザイン:檜山加奈
表紙イラスト:わかる
企画協力:龍崎翔子、金井塚悠生、片石貴展、中沢渉、井上拓美、高彦祐紀、松下裕美子、なかむらしんたろう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
