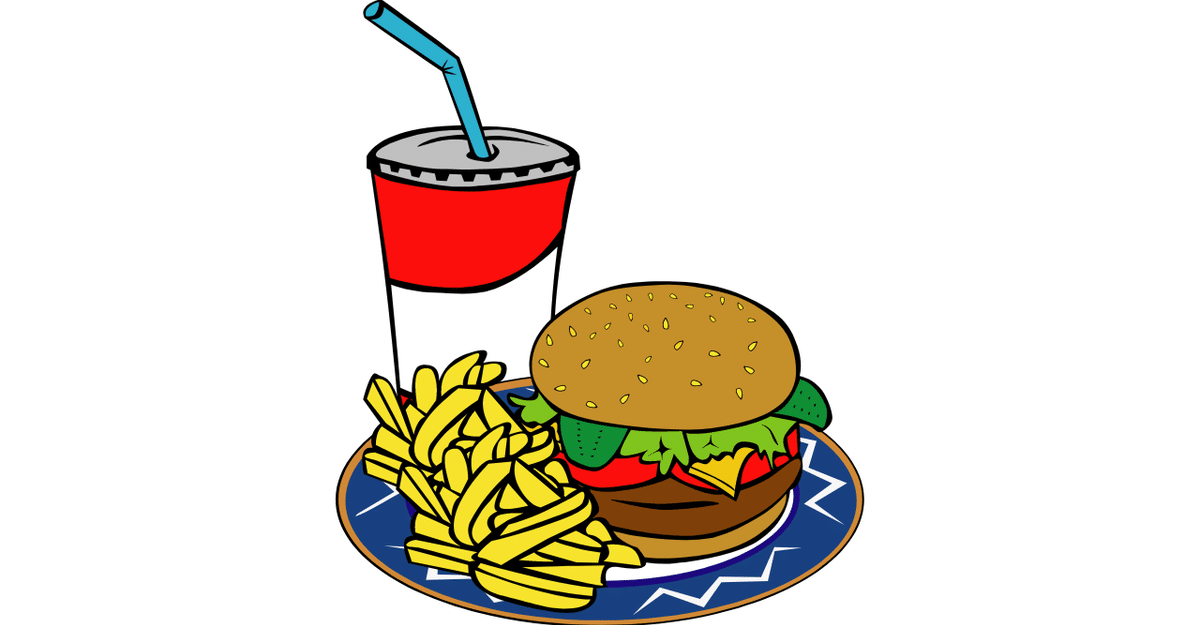
#028 祖母の食べたかったハンバーガー
中学生の時に両親が離婚した。父の元で生活することになり、家事の多くは祖母がこなしてくれていた。とても優しい祖母だった。
15歳の僕にはそれが少し鬱陶しく、面倒だった。世話焼きの多くは食べ物に関することで、なにかにつけて「お腹すいてない?」と聞く。もちろんすいている。15歳なんだから。
だけど、祖母の味付けは田舎の、そして年寄りのそれだ。ちょっとしょっぱくて、ちょっと辛くて、色は黒っぽくて茶色っぽい。こういうんじゃないんだよなぁ、とは思いつつも、他に選択肢がないので流し込むように食べた。食べるのが早いとよく言われる。たぶんこの頃にそうなったんだと思う。
高校生になると家にいる時間はぐっと減った。アルバイトもしていたし、なにもなければ友達の家に入り浸っていた。みんなが興じるテレビゲームの類は好きではなかった。たばこの煙も苦手だったけれど自分ちよりは遥かにいい。そうじゃなければスクーターであてもなく(でも距離はたかがしれているけれど)ひたすら走っていた。
ある日、祖母が「ハンバーガーっていうの? あれ、食べてみたいわねぇ」と言った。僕の住んでいた町は田舎だったとはいえ、ハンバーガーを食べられるところなんていくらでもあった。十代だったから1度の食事でハンバーガーを2個食べるなんて当たり前だったし、昼にマクドナルド、夜がロッテリアだったとして全然問題なし。むしろ歓迎。なんてことはない日常だった。
だから、祖母の言うことは聞き流していた。聞こえないふりをしていた。そんなものいつでもいくらでも食べられる。祖母のために買いに行くなんて面倒くさい。
高校を出ると同時に家も出て、いよいよ本格的に帰らなくなったある日のこと。父から電話があった。婆さんが死んだから帰ってこい。
風呂から上がって倒れ、そのまま意識が戻ることなく逝ってしまった。ハンバーガーくらい買いに行ってあげればよかった。スクーターでひとっ走りじゃないか。
ハンバーガー。あの時、祖母は本当に食べたかったのだろうか。それとも、なんとなくギクシャクとした孫との時間を繕うとしていたのだろうか。
大正に生まれ、昭和の戦争を生き抜き、平成になって余生をゆっくりできるかと思えば、再び家事に追われる毎日。たまには献立から解放されて、たまにはハンバーガーくらい食べたっていいじゃないか。でも、僕はそんな風に思いやってあげられなかった。
ハンバーガーを買ってくる。たったそれだけのことだったのに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
