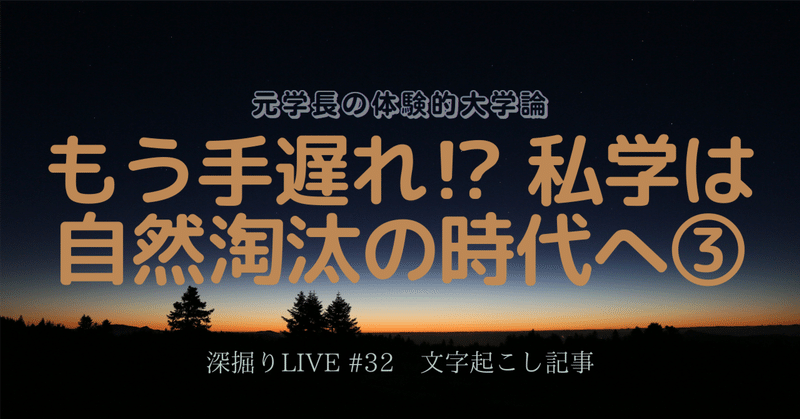
もう手遅れ⁉︎ 私学は自然淘汰の時代へ③(深掘りLIVE #32 文字起こし記事)
LISTENで聴く、LISTENで読む
深掘りLIVE #32 もう手遅れ⁉︎ 私学は自然淘汰の時代へ③
深堀ライブの32個目。「もう手遅れ⁉︎私学は自然淘汰の時代へ」のその3をやりたいと思います。
深堀ライブの配信について
これでこのシリーズは完結しようかなと思っているんですが、まずこの深堀ライブですけれども、現在はLISTENというプラットフォームから音声配信をし、そこで試し聞きができます。さらにそこで文字起こし記事ですね、有料エピソードとして購入すると文字起こし記事を読むことができます。
このLISTENをホストに配信した音声を、noteというプラットフォームに音声記事として同じものを配信しています。さらにLISTENで文字起こしされた文字データを元に、noteにより読みやすい形で文字起こし記事を書いているというのが、この深堀ライブということになります。それも32回目になりました。
社会淘汰ではない、自然淘汰という意味
この「もう手遅れ⁉︎私学は自然淘汰の時代へ」ということで、この自然淘汰の意味なんですが、これは結局、社会淘汰に対比して自然淘汰と言ってるわけですね。これまで日本の大学っていうのは、ある意味、社会的な淘汰にさらされてきた。これからの10年は自然淘汰にさらされるっていうことなんですね。
今日はこのことの意味、それからじゃあどうすんのかという話で、これまでその1その2でも語ってきたわけですけれども、まずは現実を直視することから始めるしかない。さらに目先の1、2年ではなく、次の10年後ですね。
10年後を考えて今行動しないと間に合わない
10年後を考えて今、行動しないともう間に合わないということです。10年後を考えて今行動しても間に合わないかもしれないと私は思ってるんですが、まあそういったことですね。
それからじゃあその場合にどうするかっていう話で、今日は2つほど言おうかなと思ってます。
自然淘汰の時代へ(その1振り返り)
ちょっと過去の振り返りですけど、その1では、これは4月1日に配信しましたけれども、人口減少ですね。18歳人口の減の中で今どういう時期に入ったのかと。実はこの10年、過去10年は平和な10年だったと。これからの10年はまさに自然淘汰の10年だと。過去10年は平和な10年だったんだけど、そこで大学はやっぱり社会的な淘汰に晒されて結構厳しかったわけですが、これからはその比ではない自然淘汰の時代に入るんだという話をしました。
もう1つは、じゃあその時どうするかっていう時に、1つはオンデマンド教育。そしてもう1つは、収容定員のさらなる縮小。これはもう最低限やらないとダメだという話ですね。そしてもう1つは、壁を壊す。1学部1学科、究極的には1学部1学科の導入も考えるべきだと。特に小規模大学は、下手に学科の壁を増やすべきではないし、減らすべきだという話をしています。
イノベーションなしには生き残れない(その2振り返り)
そして、その2、4月22日に配信しましたが、その1を踏まえながら、自然淘汰に近い淘汰圧がかかるということで、その時に生き残るためにはイノベーションが必要だと。大胆なイノベーションがね。イノベーションなしで生き残ることは難しいという話ですね。
さらにオンライン・オンデマンド教育の効用というか、なぜそれを導入すべきかという話。そして学部・学科の壁をなぜ壊すべきか。これはイノベーション戦略として重要なんだという。基本的な発想として、イノベーションの基本的な発想として、これはもう最低限必要なんだという話をしてきました。
社会淘汰を勝ち抜いても、自然淘汰に負ける時代
今日その3ですけれども、最初に言いましたが、自然淘汰の時代に入るっていうことは、これまでの社会的な淘汰の比ではない淘汰圧がかかるということなんですが、その意味は、これまでは競合校、競合大学との競争関係があって、その競争関係の中で勝ち負けがやっぱりあったわけですよね。そこで負けると厳しくなると。そこで勝てば何とか生きながらえると。
ところが自然淘汰の時代においては、社会的な競争、つまり競合大学、競合校との競争に勝っても、滅びる可能性があるという。これが自然淘汰の恐ろしさですね。つまり、競合校との競争、社会的な淘汰を生き抜いたとしても、自然淘汰の淘汰圧には負けてしまう可能性が高いという。ここをちゃんと理解できるかどうかは、とても重要だというふうに思っています。
10年後の現実を直視する
ところが、これまでの日本の特に中小の私学ですね、目先の1,2年のことだけを考えて動いてきた部分が大きいわけですね。これ自体、大きな問題なんですが、やっぱりせめて10年単位で考えないと、最低でもですね。本当は大学はもっと長いスパンで、30年単位ぐらいで考えるべきなんですが、とにかくせめて10年後のビジョンが持ててないと、これはやっぱり目先の1,2年だけで生き残れるほど甘くはないということです。
それでどうするかということで、一応、私なりの処方箋。大胆なイノベーション。基本は壁を壊すという話をこれまでしてきたんですが、そこでやっぱり一番重要なのは、現実を直視するということですね。どうしても目先の1,2年にとらわれるということは、現実を見たくないという、あるいは見ていないと。やっぱり10年後の現実をしっかりと、18歳人口の問題を含めてね、直視すると。ここからしか始まらない。
考え抜いて決断するしかない
現実を直視した上で、もう悩んで考え抜くと。その場合の選択肢としては、その1その2で述べたようなイノベーションに取り組むのか、それとも早々と募集停止を学生に被害が出ないうちに打ち出すのか、それとも統合再編ですね、他大学との。他大学との統合再編に踏み出すのか。もうこれしかないと思っています。
そのときに重要なのがもう1つ。自然淘汰の時代を生き残る上で重要なのは、イノベーションとともに、強みを最大化するということです。それぞれの大学はそれぞれの強みを持ってるわけです。これを新しいこと、これまでやってないことにチャレンジしてる余力も余裕もこれからの時代はないと。むしろこれまで持ってきた中でも、特に自分たちの大学の強みだと思われるものに特化していくということが重要だと思います。
強みを売りにしてイノベーションするか、それとも他大学に売り込むか
ここから先は
おだちんちょうだい!頑張って書いたよ! お駄賃文化を復活させよう! ODACHINを国際語に! オダチン文化がSNSを救う! よいと思ったらサポートをお願いします!

